 とんでもニャ~Mの推測2-10
とんでもニャ~Mの推測2-10※役にたたない推測ばかりの駄文です。(爆)
 とんでもニャ~Mの推測2-10
とんでもニャ~Mの推測2-10| ●2009.06.02(Tue.) |
先日の「妙義神社」の円空仏が気になり、検索してみたところ、大間々博物館(コノドント館)のコラムがヒットしまして。
(http://www.city.midori.gunma.jp/conodont/column/others/enku2.htm)
拝見していると、どうも日光との関連が強いように思われ、また、埼玉に円空仏が多いというあたりも、行基や太子ゆかりの場所が埼玉に多くみられるのと関連がありそうで。長野も、かな。
「大間々」と行基で検索すると、空海も絡んできて、「関東八十八ヵ所」の群馬の霊場を巡拝された方のブログに、「謎の弘法伝説を秘めた袈裟丸山の出発地点・大間々町へと向かうことにします。」とあり、興味深いなと。
リンク先のお話によると、「赤城の神は仏の地になることを嫌い、谷を一つ隠し」たことにより道場が作れず、袈裟を丸めて下山したそうで、榛名山にも同じような伝説があるとか。
(http://bany.bz/qukai/entry_18605.php)
で、「赤城の神は日光の男体山とも戦ったほどの勇敢さを持っていることから・・・」とあり、検索でヒットした「二荒山神社の縁起」によると、「赤城神」は「ムカデ」のようで、うーん・・・と。
(http://www.genbu.net/data/kouzuke/akagi_title.htm)
ムカデというと「信貴山朝護孫子寺」を思い出し、太子を思い出すんだが・・・太子のヨメとなる前に蘇我氏の刀自古郎女が、物部氏の母とともに戻ったのが「伊香郷」(滋賀?)とされていて。
「神道集」にあるという「赤城大明神」の説話にある「伊香保姫」、守られたという「伊香保太夫の居城」は、「伊香保神社」のあたりかと思われるが、その神社にあるという「北辰鎮宅霊符尊」は、以前書いたことのある「太上神仙鎮宅七十二霊符尊神」と同じではないかと思われ、だとすると、太子が四天王寺の守護として置いた七宮の一社「堀越神社」との繋がりが伺えるわけで。
(伊香保神社:http://www.genbu.net/data/kouzuke/ikaho_title.htm)
(堀越神社:http://www.horikoshijinja.or.jp/)
「鎮宅霊符」は、「推古天皇の時代に百済の聖明王の第三王子の琳聖太子が来日して持って来た」とされているそうで。
(http://www5b.biglobe.ne.jp/%7Eryumyoin/sub46.html)
あ、大阪・交野市の「星田神社」の御祭神:天之御中主大神が、「仏教では北辰妙見大菩薩、道教・陰陽道では太上神仙鎮宅霊符神」とありますね。
(http://kamnavi.jp/mn/osaka/hosida.htm)
で、「貫前神社」は「抜鉾」「貫前」の二神を祀る神社だった。」とあり、御祭神は経津主神、比賣大神で、物部氏によって祀られたニギハヤヒ・瀬織津姫だったのでは、と。
(http://www.genbu.net/data/kouzuke/nukisaki_title.htm)
だから、円空も足跡を残したのかも・・・。
蘇我氏の刀自古郎女・・・なぜ出家して尊光上人として善光寺の尼僧となったのか、ずっと気になってるんですよね。
太子や蘇我氏の意向によるものだと思うけど、立場的に深い意味がありそうで、それが何かが気になるわけで。
日本最初の尼僧の一人に、司馬達等の娘・善信尼がいて、
| 584年、蘇我馬子が邸宅内に百済から将来した弥勒仏の石像を安置した際、弟子となった恵善尼・禅蔵尼とともに斎会を行ったと伝えられる。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E4%BF%A1%E5%B0%BC) |
とのことで、「刀自古郎女」はその名から、蘇我家の主となる立場にあると思われるのに出家した、ということで、「斎宮」のような重要な役割を担っていたのかも、と。
「刀自古郎女」の母は、日本書紀などでは物部守屋の妹とされているが、『先代旧事本紀』天孫本紀では守屋の妹は、
| 同母妹の布都姫といい、物部守屋の異母弟の石上贄古大連と結婚し、物部鎌足姫大刀自(蘇我馬子の妻)の母である。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E5%AE%88%E5%B1%8B) |
とされていることから、「物部鎌足姫大刀自」の娘にしかできない役割だった、とも言えそうな・・・。
「善光寺式阿弥陀三尊」が献呈されたのが552年、本田善光が難波の堀で仏像を見つけたとされるのが602年、現在地に遷座したのが642年、2年後に本堂が創建され、654年に秘仏とされた、とのことで、本堂が創建されたあたりの開山かと思われるが、馬子はもういない頃なので、太子の意向が強かったのかな、と。
守屋の次男・真福を願主とし、太子が創建したとされる岡崎市の「真福寺」は594年とされており、守屋が滅ぼされたとされる587年から7年しか経ってなく、守屋が排仏派だったとは思えず・・・。
それにしても、善光寺大本願の「菊の裏紋」、「桜」が真ん中にあって興味深いですね。
(http://tamruns28.seesaa.net/article/107486090.html)
| ●2009.06.07(Sun.) |
コミック「日出処の天子」と同じ頃から、長岡良子さんのコミックもよく読んでまして、先日新作が出たのを知ったので購入しまして。
永久保氏の「真カルラ舞う」同様に、「ミステリー」になるんですよね、アヤカシとかが絡んでくるものは・・・「眉月の誓」に行基も出てくるんで、行基もその一員のようで。(爆)
購入したコミック「夜のこだま」の中の一話の「闇に鳴く鳥」に、「体身香」という服用すると体からいい匂いがするというお香のことが描かれていて。
それを見て、行基ゆかりのお寺の縁起に「香木」がよく出てきてたし、仏教には欠かせないもので、そこに「魔多羅神」を見出せるのかも、と。
行基の祖父は薬草採取を生業としていたとされているし、小角の名の「役」というのも薬に関連する職種だし・・・。
そして「不思議空間 遠野」さんのサイトの「遠野物語拾遺121(タイマグラ)」に、
| 下村の某という男が岩女釣りに行った処が、山奥の岩窟の蔭に、赤い顔をした翁と若い娘とがいた。いずれも見慣れぬ風俗の人達であったそうである。このタイマグラの土地には、谷川を挟んで石垣の畳を廻らした人の住居のようなものが幾箇所も並んである。 「遠野物語拾遺121」 (http://dostoev.exblog.jp/8994608/) |
とあり、「魔多羅神」「瀬織津姫」に繋がりそうで、「香十徳」という香道に関する十の得が、
| 感格鬼神 感は鬼神に格(いた)る - 感覚が鬼や神のように研ぎ澄まされる 清淨心身 心身を清浄にす - 心身を清く浄化する 能除汚穢 よく汚穢(おわい)を除く - 穢(けが)れをとりのぞく 能覺睡眠 よく睡眠を覚ます - 眠気を覚ます 静中成友 静中に友と成る - 孤独感を拭う 塵裏偸閑 塵裏に閑(ひま)をぬすむ - 忙しいときも和ませる 多而不厭 多くして厭(いと)わず - 多くあっても邪魔にならない 寡而為足 少なくて足れりと為す - 少なくても十分香りを放つ 久蔵不朽 久しく蔵(たくわ)えて朽ちず - 長い間保存しても朽ちない 常用無障 常に用いて障(さわり)無し - 常用しても無害 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E9%81%93) |
とのことから、香りによって変化をもたらすこと(香木信仰?)と「魔多羅神」が、「古代インド医学」と習合し、仏教に取り入れられたのではないかと思われるわけで。
それが神社での祭りという形で残っているのが、「大山祇宮・生土祭」(愛媛県今治市)かと。
(http://mryanagi.hp.infoseek.co.jp/new_page_36.htm)
(http://djv.libnet.pref.okayama.jp/mmhp/kyodo/kenmin/eyo/eyo-jisya-ehime01.htm)
コミックに「虚空蔵菩薩の仏国土を香集世界というじゃないの」とあり、検索してみたけど詳しくはわからず、「虚空蔵」といえば行基ゆかりの京都の「法輪寺」や、「虚空蔵求聞持法」「天御中主」などを思い出すしかなかったが・・・。
ただ、指宿の「枚聞神社」の「天井宮(乙姫宮)」がの本地が「虚空蔵」で、「豊玉姫妹君也。」というあたりが気になるなぁ、と。
(http://www.lares.dti.ne.jp/~hisadome/honji/files/KAIMON.html)
| ●2009.07.22(Wed.) |
昨日から読み始めたのが、「善光寺の謎」「日光東照宮 隠された真実」という宮元健次氏の著書で、目次を見ると、今までランダムに調べて繋ぎあぐねている事柄と重なりそうで、興味津々で読み始めた。
が、どうも違うような気がして・・・調べ損ねている部分があったりして、それらはとても参考になったけど。
その一例を挙げると、
| 『神長守矢氏系譜』によれば、物部守屋の次男である武麿が守屋滅亡後、諏訪に逃亡したという。 |
とあるが、守屋の次男は岡崎市の「真福寺」によれば、名は「真福」で、日頃薬師如来を信仰していたようなので、諏訪に「逃げる」ということはなかったのではないかと思われるわけで。
(http://www.shinpukuji.com/jiin/index.htm#engi)
守屋あるいはその子の関係者が善光寺を創建となると、なぜ太子ゆかりの四天王寺との繋がりが見られるのかな、と。
そのあたりについて著書は、「守屋の鎮魂」のための創建とされていて、四天王寺には願成就宮(守屋祠)があることから、四天王寺もまた「守屋の鎮魂」のための創建ということだが・・・。
(http://kamnavi.jp/mn/osaka/sitenouji.htm)
上記の神奈備さんのページに、
| 太子堂の後ろにあり。今参詣の者、守屋の名をにくむや、礫を投げて祠を破壊す。寺僧これを傷んで熊野権現と表をうつ。 |
とあることと、先日拝見した本坊庭園「極楽浄土の庭」の「一心大神」から、ふと頭に浮かんだのが「瀬織津姫」であり、「魔多羅神」なんだが・・・。
同じく神奈備さんのサイトの「坐摩神社」に書かれている、元四天王寺の地の「祖神饒速日命を祀る磐船神社が祀られていたとの説」について、著書にもあったけど、それならなぜ現在地に遷ったのか、私には謎なんだが・・・。
(http://kamnavi.jp/ym/osaka/ikasuri.htm)
あと、「法隆寺」も同じく「守屋の鎮魂」のためとされていて、行基が建立したと伝えられている「西円堂」について、
と書かれていた。
そのことにより、太子と行基の繋がりがあることを証明されたようにも思えるが、西円堂は「橘夫人の発願によって行基菩薩が建立」とされていて、それならば「橘夫人の発願」が「守屋の鎮魂」だった、ということになるのでは、と。
諸兄の母であり、のちに不比等の妻となった「県犬養宿禰三千代」が、なぜ「守屋の鎮魂」のために行基に「西円堂」を造らせたのか・・・。
不比等の罪を、中臣氏の陰謀のツケを背負わされた?と思えたりして。
あと気になったのは、「鹿島神宮」と「出雲大社」の御神体の向きが、東と西で「正反対」となっている、とされていて。
それの元(?)となったのが、タケミカヅチと大国主の立場で、タケミカヅチの祀られる常陸が「再生の地」、タケミナカタが逃げた諏訪が「黄泉の地」ということからも、善光寺の「守屋鎮魂」を裏付けておられる感じで。
でも、それは逆に、「再生の地」に祀られる神を「タケミカヅチ」で定着させ、そういう地に元々祀られていた神を乗っ取ろうとしたのではないか・・・中臣氏は、と思った次第で。
その後には、「黄泉の地」もセットで祀られるべき場所だからと、乗っ取る算段でいたのではないか、とも・・・。
うーん、それで言うならば、「日本書紀」が正史とされている今、瀬織津姫のことを明かせば明かすほどに、中臣氏の正当性を証明することになりかねないことになりそうだな、と。
そうなってしまえば、中臣氏の、というよりも、不比等の思うツボ、と言えそうな・・・。
「日本書記」が正史と見做されている限り、瀬織津姫は隠された神でいるしかない、ということになるというのは・・・。
つまりは、行基たちの働きも、闇の中に存在するしかない、ということになりそうで・・・。
ただ、守屋の鎮魂のために善光寺を建立したのであれば、そこに蘇我馬子と物部氏のヨメとの娘で太子のヨメである「刀自古郎子」を行かせたのは、「鎮魂」だけでは言い切れないものがあるのではないかと思われるわけで。
だからこそ、太子には物部氏の血が流れているのではと思えるわけで・・・。
| ●2009.07.24(Fri.) |
 「善光寺の謎」を読み終え、「守屋柱」が中央にあることなどから、「守屋鎮魂の寺」とされていて、太子ゆかりの四天王寺や法隆寺なども同様、という見解のようだが・・・。
「善光寺の謎」を読み終え、「守屋柱」が中央にあることなどから、「守屋鎮魂の寺」とされていて、太子ゆかりの四天王寺や法隆寺なども同様、という見解のようだが・・・。
ま、私自身も確実に言えることがなく、推測の域での違和感をどうのこうのと言えないわけで、とりあえず気になっていることを書きますと、「法隆寺」の金堂の「釈迦三尊像」が、「実は『阿弥陀如来三尊像』であったといえるのではないだろうか。」とされていることで・・・。
それはかつて、「とはずがたり」で二条が「浅草寺」の御本尊・聖観音を「十一面観音」と間違って書かれている、ということ、行基ゆかりとされた「極楽寺」の石仏が、「阿弥陀如来」とされているが印からは「大日如来」ではないか、とされていることに共通する何かがあるのでないかと思えて。
(とはずがたり巻4.「浅草寺詣で、秋月の述懐」:
http://www015.upp.so-net.ne.jp/gofukakusa/genbun-towa4-10-sensoji.htm)
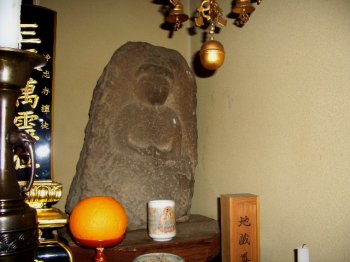
「法隆寺」金堂の「釈迦三尊像」の脇侍が、「文殊菩薩・普賢菩薩」ではなく、「薬王菩薩・薬上菩薩」とされているのも気になり、奈良の「興福寺」中金堂の釈迦如来の脇侍も同様のようだが、著書では「興福寺」での守屋鎮魂についての記述がないあたりに、「法隆寺」の像を作成した「止利」が、太子の意思を反映させた独自の形式かと思われて。
外陣壁画・釈迦浄土図の説明によると、薬王・薬上菩薩は「法華経寿量品」に説かれているそうで。
(法隆寺金堂壁画・1号壁:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E9%9A%86%E5%AF%BA%E9%87%91%E5%A0%82%E5%A3%81%E7%94%BB)
薬王菩薩の前世は「カグツチ」を思い出すような・・・。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E7%8E%8B%E8%8F%A9%E8%96%A9)
「大江親通は壁画を「鞍作鳥」すなわち、法隆寺金堂本尊の作者である止利仏師の筆としており・・・」とのことで、壁画にもある「薬王・薬上菩薩」に、やはりメッセージがあるように思えるわけで。
うーん、ちらっと「興福寺」の釈迦三尊像の脇侍「薬王菩薩・薬上菩薩」を調べてみたら、「本来は廃絶した西金堂本尊・釈迦如来像の脇侍として、鎌倉時代の建仁2年(1202年)造立されたもの。」とあり、「西金堂」は「天平6年(734年)、光明皇后が母・橘三千代の一周忌に際し、釈迦三尊を安置する堂として創建した。」とのことで、興味深いですね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%88%E7%A6%8F%E5%AF%BA)

先日書きましたように「法隆寺」の「西円堂」は、「橘夫人の発願によって行基菩薩が建立」とされているし、著書によると、「法隆寺」の金堂にはかつて橘夫人念持仏「一光三尊形式の金銅阿弥陀如来像」があったそうで。
ということで、守屋鎮魂から離れてしまいましたが、今まで調べてきたことから、「守屋」を「瀬織津姫」に置き換えれば納得できそうなんだが・・・。
| ●2009.07.28(Tue.) |
風琳堂さんのブログ「隼人の乱と瀬織津姫神【Ⅲ】──中臣氏が奉祭する神」で、「中臣氏の遠祖」とされる「天種子命」が出てきて。
(http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2009/7/26)
かつて見たことのある神名だなと、読み返してみたところ、「天太玉命」や「豊石窓命・櫛石窓命」を追ってた時に出てきたんですね、孫の「天富命」とともに、「神武天皇に仕えて祭祀を担当して橿原宮の造営にも当った・・・」と。
(http://www.7kamado.net/futo-i.html)
上記URLを拝見した時、藤原氏の祖とされる「天児屋根命」も出てきたけど、「斉部氏」が出てきたのには首をかしげてて。
「斉部氏」は「忌部氏」で、「荒妙御衣を貢上して御衣御殿人と呼ばれ」たということで、2008.11.08に書いた「神麻続機殿神社」を思い出して。
(忌部神社・http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/south/s_inbe.html)
(神麻続機殿神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E6%AE%BF%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
善光寺阿弥陀如来が最初に祭られたのは「麻績郷」で、荒衣を織っていた地で、物部氏との繋がりが強かったのではと思われるわけで。ま、他の氏族も、だけど。
ということで、物部氏を思い出さずにはいられないんだが、天児屋根命の祖が津速産霊尊とされていて、その子が「市千魂命」「武乳速命」とあり、「武乳速命」(添の御県地の祖神)が「乳速日命」と同一人物なら、「広湍神麻続連等」の祖で上記とも繋がるわけで。
(中臣氏:http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/02/021/02109.htm)
極めつけは、神奈備さんのサイトの「中臣須牟地神社」が、「虚空見つ日本国の王 物部氏」に分類されていることで。
(http://kamnavi.jp/mn/index.htm)
ゆえに、「市千魂命」あたりを不比等が創作し、「天児屋根命」を祖として乗っ取ったのではないかと推測しているわけで。
そして、物部氏を乗っ取ったのでは、と・・・そして、中臣氏の「比売神」を、「瀬織津姫」にしたかったのではないか、と。
(http://www17.ocn.ne.jp/%7Ekanada/1234-7-23.html)
| ●2009.07.31(Fri.) |
「善光寺七宮」を改めて拝見してて、読み落としてたか、最近調べたばかりなのに忘れてたかで、「加茂神社」で「え?」と。
「善光寺大本願上人が京都から勧請したとされる神社」ということは、太子のヨメで馬子の娘である刀自古郎女が勧請した神社、ということで、さらに検索してみた。
(http://homepage3.nifty.com/himegappa/jisha/kamo/kamo.html)
すると、「日頃信仰していた京都賀茂御祖神社(下鴨社)の御神霊を奉持し祀ったと伝えられています。」とあった。
(http://www.zenkoji.jp/zenkojikai/shinetsu/s-183.html)
蘇我氏と葛城氏は奈良・御所近辺で繋がりが見られるようだが、それ以外にも何かありそうな・・・。
廃仏派とされた物部氏の、守屋の次男が「薬師如来」を信仰していたことと同様、崇仏派とされた蘇我氏の、馬子の娘で初代大本願上人が、信仰していた「玉依姫命」を「奉持し祀った」というのは興味深いことで。
ま、私は「瀬織津姫」が「薬師如来」であり「玉依姫命」ではないか、と。
「牛にひかれて善光寺まいり」の、「牛」であり「善光寺観音」でもある「阿弥陀如来」も、太子作とされる「布引観音」の「聖観世音菩薩」も・・・。
ところで、「牛にひかれて善光寺参り」が「信濃四大伝説」の1つとされていたんだけど、他の3つは?
(http://kusabue.jp/nunobiki1.html)
ん?上記サイトで幸村のところを見たんだけど、ルーツの「滋野氏」ってたしか「九曜紋」を調べている時に出てきて・・・「紀氏」についてもその近辺で見たような・・・真田氏は高野山にも縁があって・・・。
で、「滋野氏の氏神白鳥神社はオシラサマ・・・」とあるあたり、やはり「瀬織津姫」に繋がりそうな。
(http://kusabue.jp/unno1.html)
うーん、行基ゆかりの「布引観音」、太子ゆかりの「牛伏寺」も気になる・・・というか、「信濃三十三観音霊場」を巡ってみたい。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%BF%83%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E9%9C%8A%E5%A0%B4)
行かれた方のサイトはあったけど・・・。
(http://siyuin.shikisokuzekuu.net/sinano33kannon/sinano33-1.htm)
でも、埼玉の行基や太子ゆかりのお寺も興味深いんですよね・・・って、どちらも遠くて簡単に行ける場所ではないんだなぁ・・・。
いや、嘆いてないで、ここにいながらにしてできることを探さねば。
それにしても、「善光寺」にも、「法隆寺」の「救世観音」のような、太子鎮魂の像があるんでしょうかね?
あと、刀自古郎女と太子の子・山背鎮魂のための像や、刀自古郎女の兄・蝦夷や甥・入鹿のも。
ないのであれば、「法隆寺」の「救世観音」は太子鎮魂の像ではないのかも・・・。
追記:守屋の次男が「武麿」という名で、諏訪の宮司の祖とされていたり、守屋の次男が「真福」という名で、岡崎の「真福寺」に信仰していた薬師如来を祀ることを太子に願い出たとされているが、「物部文書」には「物部守屋の戦死後、守屋の一子、那加世が鳥取男速という臣下に守られ、蝦夷の地へと落ちのびたことを伝える。」とされているようで。
(http://www.mars.dti.ne.jp/~techno/column/text6.htm)
はて・・・・・。
| ●2009.08.05(Wed.) |
これといった用事もなく過ごした昨日、久々に「カルラ舞う」の飛騨編を読んでまして。
先日「救世観音」がどうのって書いてて、たしかコミックに出てきたなぁと探したら、初期の「カルラ舞う」にありまして、法隆寺の「救世観音」は、太子を含めた「蘇我氏鎮魂の像」とされてました、はい。
で、気になったのが、藤原氏と「両面宿儺」の繋がりで、そのウラ(?)には流された新羅の僧・行心の存在があるように思われるが、私自身はまだよくわからず・・・。
(懐風藻:http://www.e-net.or.jp/user/stako/NI/N01-04ka.html)
| 皇子大津の謀反、発覚す。皇子大津を逮捕す。併せて皇子大津が為にあざむかれたる直広肆八口朝臣音橿、小山下壱伎連博徳、大舎人中臣朝臣臣麻呂、巨勢朝臣多益須、新羅沙門行心と張内礪杵道作等、三十余人を捕む。 (『日本書紀』持統称制前紀、朱鳥元年10月2日条) (http://funabenkei.daa.jp/yononaka/ohku/686.html) |
というのが、関連の1つかとも思われるが、このあたりに何かカラクリがあるような・・・。
「両面宿儺」が、「我は救世観音の使現なり。驚くこと無かれ。」と、洞窟から現れ村人に伝えたというあたり、気になりますね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E5%85%89%E5%AF%BA_(%E9%AB%98%E5%B1%B1%E5%B8%82))
上記URLの「千光寺」が、
| 720年(養老4年)、泰澄により白山神社が開かれ、850年(嘉祥3年)頃、真如親王(弘法大師十大弟子の一人。俗名高岳親王。平城天皇第3皇子、嵯峨天皇皇太子)が開基する。 |
とあるのも興味深く、「真如親王」の甥が「業平」というあたりも、「千光寺」にある何かを言わんとしているようで・・・推測としては、善光寺の初代上人となった「刀自古郎女」と近いような・・・。
「千光寺」に「おびんづるさま」があるんですね・・・円空?
(http://daien.senkouji.com/?eid=47521)
「おびんづるさま」は「東大寺」の大仏殿のが有名だが、他で知ってるのは「四天王寺」の六時堂・紙衣堂、京都の「六角堂」、奈良の行基ゆかりの「浄願寺」・・・あ、京都の「興福寺」にもあったけど、ここだけ金網に囲まれていて触れなくて。
検索で真っ先に出てくるのは「善光寺」だけど、あとは奈良の「法楽寺」や、大阪の「三津寺」が多く、いずれも行基ゆかりのお寺で。
(法楽寺:http://www.city.ikoma.lg.jp/dm/07/0704horakuji/070406binzuru/070406binzuru.php)
(三津寺:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%93%E5%BA%A6%E7%BE%85%E8%B7%8B%E5%9B%89%E6%83%B0%E9%97%8D)
知多の「光明山 安徳寺」は行基との繋がりはなさそうですが、「知多四国八十八箇所は、愛知県の知多半島にある88ヶ所の弘法大師(空海)ゆかりの札所の総称。」とあり、何らかの関連はありそうで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E5%A4%9A%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%85%AB%E5%8D%81%E5%85%AB%E3%83%B6%E6%89%80%E9%9C%8A%E5%A0%B4)
浦安の「宝城院」、今治の「泰山寺」、長岡京市の「勝龍寺」も空海ゆかりか真言宗の寺院ですね。
(宝城院:http://members3.jcom.home.ne.jp/urayasucity/shiseki/shiseki01.htm)
(泰山寺:http://45988.web.fc2.com/junrei/56/56z.htm)
(勝龍寺:http://www.city.nagaokakyo.kyoto.jp/contents/03040009.html)
東京の「深大寺」にもあるようで、ご本尊が「恵心僧都」作の「阿弥陀如来」像というのが気になるし、天台宗が絡んでくるあたりも・・・。
(http://peaceman.jugem.jp/?month=200704)
(http://jindaiji.co.jp/jindaiji.html)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA)
「恵心僧都」は京都の「広隆寺」の「阿弥陀如来」「魔多羅神」に絡んでくるし、行基ゆかりの岐阜の「行基寺」のご本尊が、「深大寺」と同じく「恵心僧都」作の「阿弥陀如来」で。
(http://www.geocities.jp/easyclub_choro/agy7.htm)
だんだん話がそれてきてますが、いずれにも「瀬織津姫」が見え隠れしているようで・・・。
あ、兵庫の「清荒神 清澄寺」にも「おびんづるさま」がありましたね。こちらも「瀬織津姫」が感じられるお寺で。
ん?風琳堂さんのブログ「隼人の乱と瀬織津姫神【Ⅴ】──宇佐氏が奉祭する神【上】」のトップの御由緒の写真に、「菅原神 大物主神」とある。
(http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2009/8/4)
「菅原神」は道真のことと思われ、天満宮で祀られる道真の背後には、祖である「天穂日命」がいるように思われ、さらに「瀬織津姫」も見えるように思っていたが、「菅原神 大物主神」とあるならば、「天穂日命」と「瀬織津姫」も道真によって繋がる、ということかな、と。
ま、明治18年の合祀、というあたりも、考慮に入れなきゃいけないと思われるが・・・。
| ●2009.08.13(Thu.) |
昨日、内科の待ち時間に「伊勢神宮の衣食住」という本を読んでいると、「神宮の神職は心の御柱について語るべからず」とされていた、という古い言い伝えがあったそうで、古い神社・仏閣はどこもそうなのかも、と。
そういうのに加え、先日の誓玉上人の著書によると、善光寺は何度も火災に遭い、史料が焼けてしまって論文を書くのをやめたそうなので、せめて他の手がかりはないかと、検索してみたんだけど・・・難しいなぁ。
かつて「日本三上人」と総称されたのが、善光寺、熱田の「誓願寺」、伊勢の「慶光院」だそうだが、
| 今なお昔の伝統格式を持って、実質的に宗教活動を行っているのは、善光寺大本願のみになってしまいました。 |
とあり、ネットで繋がりを見出すには、どう調べればよいやら、と。
2冊で共通すると思われるのが「麻績」という地名で、三重のいなべ市には「麻績塚古墳群」があるようで、「古代にこの地方を支配した豪族麻績氏の墓という伝承から名付けられ・・・」とあった。
(http://www5c.biglobe.ne.jp/~ito/arcomizuka.htm)
たぶん、「神麻続機殿神社」(松阪市井口中町)との繋がりがあると思われるが、信州の「麻績」との繋がりは探せず・・・。
(http://www.isejingu.or.jp/ryouti/ryouti4.htm)
ただ、信州の「麻績宿」は、「戦国時代には麻績服部氏の城下町として発展しました。」とあることから、秦氏か物部氏の支族ではないかと思われ、「麻績神明宮」が「平安末期から麻績御厨として伊勢神宮の荘園でした。」とのことから、古くから伊勢との繋がりがあるようで。
(http://omigoto.vill.omi.nagano.jp/zenkojimiti/route01_02.html)
そういえば・・・以前調べたことがあったなぁ、麻績駅のある「上水内郡」について。
あ、「坐摩神」の1柱「阿須波神」と「須波神」が同神かどうかを調べてて、2006.11.24(Fri.)分に、「日本書紀」に「持統天皇の五年(691)八月、降雨の多い災難のとき、使者を遣わして、龍田の風神、信濃の須波・水内等の神を祭らせた。」を引用させていただいてて。
(http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/middle/s_suwa.html)
「水内神」は最近「善光寺七宮」の1社「妻科神社」に祀られているのを拝見していて、「善光寺鎮座以前の水内神として諏訪大社の県内に最も古い分社のひとつです。」と。
(http://www.zenkoji.jp/zenkojikai/shinetsu/s-182.html)
「龍田」の風神とともに祀られるのなら「瀬織津姫」であろうと思われ、「妻科神社」の御祭神・八坂刀売命は同神かと思われるが、さらに刀自古郎女が善光寺に入る際、「加茂神社」に同神と思われる「京都賀茂御祖神社(下鴨社)の御神霊を奉持し祀った」のは何故なんだろ・・・。
(http://www.zenkoji.jp/zenkojikai/shinetsu/s-183.html)
あ、「八坂刀売命は,伊勢国多気郡麻積の豪族;天八坂彦命の子孫であると伝えられている。」とあった。
(http://www.geocities.jp/jp_kozoku_ken/Suwa-shinnkoh.html)
「天八坂彦命」は神麻續機殿鎮守神で、伊勢神麻續連等の祖、でしたね。
うーん、「天八坂彦命」についてを引用させていただいたサイトに、しばらくハマってた・・・三種の神器のうち、「八咫鏡」が伊勢、「草薙剣」が熱田なら、「八坂瓊の曲玉」は善光寺?と。
(http://www.geocities.jp/jp_kozoku_ken/Kennkyuh-yohshi.htm)
いや、「堂童子考」に書かれているように、「善光寺集団は,北信濃において,諏訪に象徴される小倭国残存勢力に対抗意識を燃やしていたと考えられる。」のなら、「八坂瓊の曲玉」は剣璽の間?でも、太子の預言書には、なぜか将来の宗派に対する批判があったので、「八坂瓊の曲玉」がどこかに移されたあと、ミシャグチ&諏訪神を乗っ取った?
うーん、藤原氏でも北家は物部氏との繋がりを感じられるから、さらに奪回して密かに守っている、とも考えられなくもないが・・・戦国時代に、こぞって善光寺の阿弥陀如来像を手元に置きたがってた様子から想像するに、そういう背景もあったから、とも推測できるのでは、と。
上記URLの下の方に、「国造本紀」に「吉備中県」が「橘氏は倭王を誅する倭本族」とされていて、「倭族を誅罰する武家としての橘氏」とあるが、橘氏も県犬養美千代が不比等に丸め込まれ(?)たことにより、氏神を祀っていた「梅宮大社」に藤原氏が入り込んでいたりするので、諸兄のように屈せずに行基たちと行動をともにした、とも推測しているので、「倭本族」、「倭本族離反者」、「午族」に飲み込まれてしまった「倭本族」や「倭支族」の線引きが難しいように思われて。
それは、ニギハヤヒがナガスネヒコを殺したとされるあたりが、実はニギハヤヒが人質になる代わりにナガスネヒコを東国に逃したことをそのまま書けないから、著者側の都合のいいように「殺した」という表現をしたのかもしれない、というようにも考えられるように・・・。
あ、すみません、話を「麻績」に戻しますと、熱田方面との繋がりはというと、稲沢市に「麻績」という地名があるようで・・・稲沢市って「善光寺東海別院」のあるところですよね。
(http://baba72885.exblog.jp/9739433/)
ほぉ~、稲沢市には「富士社」(御祭神・木花佐久夜比売命)がけっこうあるんですね。
(http://homepage3.nifty.com/fujii-hi/fujizuka/kaiin-corner/kinugasa.html#inazawa)
いなべ市の「麻績氏」との繋がりはわかりませんが、千葉市に麻績氏が開発したという「大百池(おおどいけ)」があるそうで。
(http://www.geocities.jp/chiba_bunka/odo.html)
栃木県佐野市の「小見」も、「麻績」との関連がある?
(http://www.city.sano.lg.jp/profile/chimei/omi.html)
「古代には「麻績村」と呼ばれ、琴平山周辺には忌部氏が住みついて麻の栽培が盛んであったが、麻を紡ぐ「麻績」から「あ」が除かれて佐文となった」という、香川県仲多度郡まんのう町に、「加茂神社」があるんですね。
(http://www.town.manno.lg.jp/kanko/ayako.php)
あ、「麻績王」が出てきて・・・かつて「和布刈神事」について調べていて、このサイトに辿り着いたっけ。
(http://homepage2.nifty.com/amanokuni/ominoookimi.htm)
で、息長真手王の娘が「麻績皇女」といい、「麻績皇女」と継体天皇との子「ササゲ皇女(記は佐佐宣郎女)」が、「伊勢大神(伊勢神宮)の祠を祀るとある」とされているそうで。
(http://www.mctv.ne.jp/~kawai/vtec/)
ん?継体天皇って「男大迹天皇(おおどのすめらみこと)」でしたよね・・・千葉の麻績氏が開発したという「大百池(おおどいけ)」との関連はあるんだろうか・・・?
こちらのサイトも興味深いが、ちと疲れました・・・結局、寄り道ばかりで肝心なことを調べるに至ってなくて。物部氏がかなり絡んでいて、だからこそ太子も絡んで、行基をはじめ、太子の足跡を追った人々が絡んでると思うんだが・・・。
うーん・・・あ、神奈備さんの「韓国の伊太氏の神」が気になりますね。
(http://kamnavi.jp/itakiso/sasatani.htm)
あ、麻績氏について調べるの、忘れてた。
| 平姓小見氏: 下総国香取郡小見郷(現・千葉県香取市小見)発祥の小見(小海)氏は房総平氏の氏族で、以下の流れがある。 ・匝瑳党小見氏と呼ばれる上総氏の流れ ・千葉常胤の弟胤隆の流れ ・椎名胤光の子胤澄の流れ ・東胤頼の子木内胤朝の孫胤直の流れ 鎌倉時代以降、千葉氏のもとで歴史に名を残した。 源姓麻績氏: 藤原姓小見氏: |
とのことで、祖を辿れば物部氏かと思われるが、証拠はないわけで・・・。
追記:「妻科神社」で「聖徳宮の祭り」があり、太子像が安置されるようで。
(http://www.azumino.matsumoto.nagano.jp/meditation/nagano/indexf-5.html)
| ●2009.08.16(Sun.) |
夜が明けてちょろぷ~に起こされ、テレビをつけると、ニュースの合間に各地の情報があり、そのうちの1つが埼玉の長瀞町のお祭りで、2艘つないだ船にやぐらのようなものが組まれ、灯篭が取り付けられているのを見て、これって「瀬織津姫」に関するお祭りとちゃうのん?と、PCを立ち上げて。
(http://www.nagatoro.or.jp/)
あるサイトを拝見すると、「船玉まつりは、大正年間長瀞の船頭達が川の神様をお祭りしたのに由来する。」とあり、また別のサイトでは、「明治の末頃遊船の船頭が水神様を祀り、水上安全と水難供養を行ったのがこの祭りの起源であるといわれている。」と・・・。
(http://www.syokoukai.or.jp/event/funatama.htm)
(http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=80729)
瀬織津姫との関連ははっきりわからず・・・。
上記URLに「岩畳と並ぶ『観光地 長瀞』のシンボル」として「宝登山神社」の写真があり、検索すると、御祭神が神武天皇、大山祇神、火産霊神とあり、「ご由緒物語」というのを拝見すると、ヤマトタケルが禊してて・・・。
(http://www.hodosan-jinja.or.jp/yuisho/index.htm#yuisho)
そのヤマトタケルを助けたという「お犬さま」(大口真神)が、奥宮に祀られているそうで、「お炊き上げ」の神事で「神饌として奉献致します。」とのことで、このあたりに何かありそうな気が・・・。
「犬」というと、高野山を思い出すんだが、拝殿の北東に「玉泉寺」という真言宗寺院があり、地蔵菩薩が安置されており、護摩堂には不動明王が安置されているので、高野聖が絡んでるのかも、と。
「長瀞のお宮」を拝見すると、「石上神社」や貴船神を祀る神社があったりして、瀬織津姫が見えてきそうだが・・・。
(http://www.hodosan-jinja.or.jp/koutsu/omiya.htm)
| ●2009.08.20(Thu.) |
まだちょこっとしか読んでないんですが、森氏の著書によると、「延喜式」で「粟」が多く取れたところとして、京都の山城と四国の阿波が挙げられているそうで。
山城で真っ先に思い出すのが秦氏で、阿波と言えば「麻」を思い出し、その両者が「粟」で繋がるのは、当然のことのように思えるわけで。
読み進んでいくうちに、秦氏と物部氏の接点が見出せるかどうかはわからないですが、最初のこのあたりだけでも、善光寺と四天王寺のみならず、大阪と埼玉との繋がりも見えたような気がして・・・。
粟も稲も、人が生きていく上で欠かさせないものであり、「陸田」と「水田」の違いはあれど、いずれもが「田」で作られるものであるから、後から「稲」を持って日本に来た民族に対し、「粟」を主食としていた民族は受け入れることができたのではないか、と。
それが物部氏と秦氏との関係に相当するように思えて・・・。
うーん、現存する「風土記」を読む必要があるのかも、と、ヒントをいただいたように思えるのだが、まずは読み進んでから考えてみようかな、と・・・。
| ●2009.08.21(Fri.) |
昨日著書名を書くのを忘れましたが、「日本の深層文化」という本で、3分の1を読んだ時点で付箋が10ヶ所・・・ほぼ2~3ページに1枚の割合でして。
かつて調べたことのある事柄がいくつか出てきており、推測されている部分に共通点があったりするが、確証となると森氏も「宿題」とされているところもあるけど、共通点があったということだけでも心強く思えて・・・。
で、「倭人伝」にある「種禾稲紵麻」について、「禾稲」を「いね」と読まず、「禾(粟)と稲」とされており、さらに「種えている」のが「紵と麻」で、
| これは同じ人間が禾と稲やさらに織物の原料となる植物をも栽培していたと中国人の目には映っていたのであろう。倭人の広義の農耕の実態にせまる文章であろう。 |
とあり、後から「稲」を持って日本に来た民族と、「粟」を主食としていた民族が融合した「倭人」たちは、移住先でも同じように栽培を続けていたのではないか、と思われるわけで。
そのあと「野」とつく場所が「豊かさ」を表し、「聖地」であったのではないかとされており、「武蔵野」も出てきて、「防人の歌」を詠んだ武蔵野の人の名には「物部氏」もあって。
また、麻で作った布を川の水で晒しながら詠んだ歌も載っていたんだが、それを見て、「牛に引かれて善光寺まいり」は、ひょっとしたら「布引観音」から「善光寺」に至る地域での産業を意味し、「とはずがたり」にあった「浅草寺」から「善光寺」の道のりは「麻の道」を示し、移民の足跡を伝えているのかも、と。
その「麻の道」には、「防人の歌」で出てくる氏名が示すように、物部氏らが関与している、ということではないか、と・・・。
そして産業を支えていた1つに「信仰」があり、「牛に引かれて善光寺まいり」からは「阿弥陀如来」「観音様」や「牛」が連想でき、それが「瀬織津姫」や「天穂日命」などに繋がるのでは、と。
それらに太子が絡み、行基たちが絡み、家康などの武将が絡んでいるように感じられるわけで。
追記:「阿波」と「安房」との繋がりについては2008.11.08分に、「紵(苧(からむし))」については2008.11.17分に、「青麻神社」については2009.03.25分に書いていて、これからそのあたりについて書くことになるかも、と思い、覚え書きしておこうかな、と。
著書に行基の出身地の異説ついてふれておられ、そういえば「日本霊異記」で行基が「頸城郡の人」とされてたこと、けっこう前に疑問に思って書いたものの、そのあと調べることなく過ごしているなぁ、と。
あと、「蜂岡寺」と「蜂田寺」の共通点は「秦氏」ではないかという推測も以前書いていて、さらに「蜂田皇子」との関連もありそうに思いつつも、結局調べきれてなくて・・・。
森氏からの「ちゃんと調べるように!」というご指導かと思いながら、やはりどう調べたらいいのかを再度考えあぐねていて・・・横道にそれてしまった。(爆)
で、「蜂」といえばネットのニュースから「蜂蜜」について調べたことがあって・・・「栃木」だったかな?あ、2008.05.01(Thu.)分ですね。
著書によると、蜂蜜は固形で納められていたようで、正倉院に残っているその塊の写真があったが、その使い方は不明なようで。
現代でも、大根を蜂蜜につけたものが風邪にいいと言われてたりするので、いろんな用途があったのかもしれませんね。
| ●2009.08.22(Sat.) |
森氏の「日本の深層文化」に、「野の持つ潜在的な力」について書いておられたことは、昨日ちょこっと書きましたが、もう少し詳しく調べていこうかと思いまして。
読み進もうとしても、気になって読み返していて、ほとんど進んでないということになっているので、先に調べた方がいいですよね。(苦笑)
まず、京都の「七野」に「櫟谷七野神社」があることが書かれていて、検索したところ、「春日神社と呼び親しんでいる」と書かれているサイトがあった。
(http://www5e.biglobe.ne.jp/~hidesan/ichiidani_nanano-jinjya.htm)
御祭神は春日明神・天児屋根命・武甕槌命・斎主命だそうで、「賀茂斎院跡」にあるというあたり、「聖地」であることを示しているようだが、ちょっとひっかかるものがあったりするんだが・・・。
(http://kaiyu.omiki.com/nanano/nanano.html)
「斎院」は身を清める場所であったこと、「櫟」という文字が使われていること、「山王七社」を勧請したとされている史料があること、隣接して建てられていた「廬山寺」の御本尊が太子作とされる薬師如来坐像であることなどから、そこに「瀬織津姫」の存在があるように思われて。
だから、「春日神社」という呼び方であることが気になるんだが・・・。
で、「七野」は「内野・北野・萩野・蓮台野・紫野・上野・平野」とあり、このあたりについては森氏の著書に沿って2009.04.29あたりで調べたことがあったと思うので、割愛させていただきます。(嵯峨野も同様)
で、次にあった「印南野」は調べたことがなく、聖武天皇が行幸するために頓宮を作っていたというのを初めて知りまして。
726年に行幸しているということは、行基との繋がりができてからのことだと思われるが、行基絡みでは出てこなかったと思うんですよね。
ただ、西国街道にあることや、大輪田の泊を改修していることから、行基はよく知っていた地であると思われるが。
で、その「印南野」ですが、著書によると、ヤマトタケルの母・印南別媛(日本書紀では播磨稲日大郎姫)の居住地で、印南別媛はそこから出ずに景行天皇が通っていたことから、印南別媛の優位性の中に、森氏は「野」の持つ潜在的な力を見出しておられて。
では、景行天皇が通うほどの「野」の力とは何か・・・著書では印南別媛と同じような例として「沼河比売」を挙げておられ、「沼河比売」といえば「ヒスイ」を思い出し、そこで連想したのが、周辺からの「産物」なのかも、と。
印南別媛の母が「吉備氏」ということや、「赤石」という地名から、産物は「鉄」かな、と。
検索した中に、
| 丹波の鹿が鵯越から蟻の戸を伝って降りた山の手の陣は播磨の印南野と呼ばれ、聖武天皇があり通いされた有名な土地であり、「赤石櫛渕」と呼ばれた有名な国境の土地・・・。(後略) (http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E5%8D%B0%E5%8D%97%E9%87%8E%E3%80%80%E7%94%A3%E7%89%A9&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt&meta=vc%3D&u=www.geocities.jp/myenglishwords/182.doc&w=%E5%8D%B0%E5%8D%97%E9%87%8E+%E7%94%A3%E7%89%A9&d=P5GkyBlMTRCE&icp=1&.intl=jp) |
とあって、足しげく聖武天皇も通ってたようだが、それもまた「野」の持つ潜在的な力によるものなんでしょうね。
で、「赤石櫛渕」が気になったので調べてみたら、「鉢伏山の断崖が海に突き出し櫛の目のようになっていた難所であった」ことから、「赤石櫛渕」と言われたようで。
(http://www.kcc.zaq.ne.jp/tsubosango/TS163.html)
上記URLで、石碑に「巳之日祓社上野岡道」とあり、「巳之日祓社は関守神社のことで、岡上の道にあることを示す」とされていて、「岡上」とは「上岡」のことなのかな?と。
「上岡」について著書に、香具山と耳成山が争った時、出雲の阿菩の大神が印南野まできたら争いが止まったと聞いたので、乗っていた船を覆してそこにいることにしたので、「神岡」と名づけた、と、「播磨国風土記」から引用されていて。
その争いについての解釈は、「不定期便823」というページにあり、なるほどと思ったんだが、「阿菩の大神」とは?と、
(http://www3.kitanet.ne.jp/~nihirata/20070707.html)
検索すると簸川郡の「伊佐賀神社」がヒットし、播磨国風土記についてもふれておられ、「阿菩大神の「阿菩」が「伊菩」に、さらに「伊保」となり、その大神のお宮も「伊菩神社」といわれるようになりました。」とのことで。
(http://www.town.hikawa.shimane.jp/yu/cont/kihon/isa.htm)
「イボ取りの神さま」ってことですよね・・・真っ先に思い出すのは、ニギハヤヒの祀られている東大阪市の「石切神社」で、かつて「牛神社」や「野槌社」でも、「イボ取りの神さま」が出てきてたんですよね。
(http://www.ishikiri.or.jp/top.html)
(http://www.iz2.co.jp/matsurijoho/7/ishi_kengyu.html)
(http://kamnavi.jp/ki/tuhata.htm)
あ・・・うろ覚えだけど、「香具山」はニギハヤヒと関連があったような・・・天香山命はニギハヤヒの子でしたっけ。
「関守神社」に話を戻しますが、ウィキペディアに「須磨の関があったとされる場所に神社を建てたことから来ている。」とあり、その脚注に「伝説地の一つ。他に現光寺、多井畑厄除八幡宮と諸説がある。」とされていた。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%AE%88%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(http://www.kcc.zaq.ne.jp/tsubosango/TS66.html)
「多井畑厄除八幡宮」は、聖武天皇の子・称徳天皇が勅により疫神祓いを行わせ、高倉天皇が「石清水八幡宮」を勧請した、と。
(http://www.tainohatayakuyokehachimangu.or.jp/history.html)
つまり、ここも「聖地」であることを示しているようで、瀬織津姫に繋がるように思われ、地名・神社名から秦氏のテリトリーのように思われるんだが・・・。
で、「巳之日祓社」について、検索してヒットしたのが千葉の「橘樹神社」で、ヤマトタケルや「櫛」が出てくるあたりは気になるところだが、御由緒の「春季祭旧暦2月上巳之日」と「古來火難水難兵難祓除の神として諸人の崇敬厚く霊験顯著なり」でヒットしたようで・・・。
「巳之日祓社」との直接的な関連がないにしても、「走水」が出てくることや「相模國穂積氏忍山宿禰の女たる弟橘比売命」というのが気になりますね。
(http://www.geocities.jp/engisiki02/kazusa/bun/kaz190201-01.html)
上総も相模も著書に出てきましたし、「忍山宿禰」が「穂積氏」ということは「物部氏」では?
著書ではこのあと「交野」について書かれていて、ニギハヤヒ降臨の伝承があり、「聖地」だった、と。
次の「宮城野」では、かつて森氏の著書から「嵯峨野」で調べていた源融の「塩焼き」のことがあり、とんでもニャ~其の19(2001/05/27)に書いた、橘為仲のことが書かれていて。
仙台銘菓と言えば「萩の月」が有名で、行基ゆかりのお寺に「萩」のつくお寺があったりして、「萩」に何かあるのかなと調べてみたものの、気になったのは「荒れ地に生えるパイオニア植物で、放牧地や山火事跡などに一面に生えることがある。」のあたりだけで・・・。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%AE)
ただ、日本のほぼ全域でみられるという花なのに、なぜ橘為仲は「宮城野の萩」を持ち帰ったのかが疑問ではあるが。
「秋ハギと牡鹿のペアの歌が多い」とあることから推測するなら、宮城野の萩とその他の地域の萩とは異なる点があり、「牡鹿」とのペアで詠まれることにこだわれば、「牡鹿」もまた宮城野では他とは異なるのか、「萩」が何かを例えて伝えようとしているのか・・・。
今まででの感触から言えば、「牡鹿」の本質(?)が変わっているという風に感じられ、「萩」も姿を変えた瀬織津姫という推測に至るのだが・・・。
ということで、時間がなくなってきたので、他の「野」については後日・・・。
| ●2009.08.23(Sun.) |
金曜に、森氏の著書に「武蔵野」について書かれていることを少し書きましたが、関東方面での出土品の傾向などから、「野」での布の材料となる「紵」や「麻」の栽培がさかんだったのであろう、とあって。
奈良~平安時代の史料に「商布」や「商旅」という言葉がよく出てくるそうで、税金として納める「調布」や「庸布」よりも多くの「商布」が、「商業活動によって国や郡などの役所が入手し都へ送った」ということ、その記録のある人物として「漆部伊波」について書かれていて。
「漆部伊波」は相模国の人とされており、東大寺の大仏建立の際、「10名の大量商布献上者の一人」として寄進しており、「この事実から、伊波が相模国において相当な経済力を保有するとともに、中央との密接な関係を保有する人物であったと推考して誤りないと思う。」とされる人物で。
(http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/0219/publication/kiyou/kiyou06/kiyou0608/kiyou0608.html)
難波の堀江近く・・・たぶん善光寺の阿弥陀如来が引き上げられたあたり・・・に家を持っていたそうだが、そうした背景には秦氏が大きく関与しているのでは、と、私は推測しているわけで。
上記URLである「神奈川県立公文書館紀要 第6号」には、「大山寺」について書かれているのだが、以前調べた時に「良弁」による創建であることが、行基による「日向薬師」の開山や「白髭神社」の創建に、何らかの形で関わっているのかもしれないなと思って。
また、良弁の父が「染谷太郎時忠」で、行基と良弁の繋がりから、行基創建の「甘縄神明神社」の社殿を染谷太郎時忠が整えたのだろう、とも。
「大山寺」の近くに秦野市があり、秦氏関連の氏族がいたと思われ、染谷太郎時忠との繋がりもあったことから、行基や良弁の活動がスムーズに行われたのではないかと思われるわけで。
だが、ずっと「染谷太郎時忠」については謎だったんだが、上記URLによると、「染谷太郎時忠」は「漆部伊波」ではないか、とのことで。
「染谷太郎時忠」が「漆部伊波」であれば、行基が輪島塗を伝えたという伝承も、可能性がなくはないのかも、と。
(http://www17.ocn.ne.jp/~verdure/yogo/yogo_wa.html)
あと、「大山寺」のある伊勢原市が、「相模国大住郡」とあることから、ひょっとしたら移住していた「隼人」の力添えもあってのことかとも思われて。
ただ・・・染谷太郎時忠が「鎌足」の玄孫とされているようなので、うーん、と。
(http://www7a.biglobe.ne.jp/~tomlife/sub20kamakura_04_kyukamakura.html)
著書に、愛知の「漆部神社」は「漆部伊波」と関係があるのかどうか、疑問に思っておられ、私も気になったので調べてみたところ、「漆部は漆器具の製作を行った人々の集団で、その祖神は三見宿禰(ミツミノスクネ)とされている。」とあった。
さらに、三見宿禰は「出雲醜命」の子とあり、
| 『神社名鑑〈愛知県〉』に、ずばり漆部を冠した漆部(ぬるべ)神社が収載されており、祭神は三見宿禰命、木花咲耶姫命等であるが、相模国とはかなり離れた尾張国だから、参考にはしがたいが、しかし、同族であった可能性は否定できまい。 (http://news.onekoreanews.net/print_paper.php?number=48739) |
とされていて。
(漆部神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%86%E9%83%A8%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
「出雲醜命」を検索すると、「物部氏」に辿りついた。
(http://www.max.hi-ho.ne.jp/m-kat/nihon/13-3mononobe-2.htm)
島根の「物部神社」の境内社「乙見神社」に「三見宿禰命」が祀られているが、境外摂社の「漢女神社」の御祭神が栲幡千々姫命・市杵島姫神・抓津姫命で、な~んとなく気になって・・・「天香具山命」が祀られているのが「伊夜彦神社」というのも。
(http://www.genbu.net/data/iwami/mononobe_title.htm)
あ、「栲幡千々姫命」は「旧事本紀」によると、饒速日命の母、宇摩志麻遅命の祖母、でしたね。
で、「物部神社」のホームページによると、「鎮魂」とは「活力を与える・復活を促す・甦る・悪影響をもたらすものを払拭するなど総ての好転的な意味を持つものである。」というのがあり、興味深いな、と。
(http://www7.ocn.ne.jp/~mononobe/chinkon.html)
その意味での「鎮魂」なら、「善光寺」の「守屋柱」の存在が納得できるように思える。
うーん、「漆部神社」の「八大明神」が「稲荷神社、賀茂神社、春日神社、住吉神社、祇園神社、貴船神社、平野神社、松尾神社の祭神の総称」で、先日の「櫟谷七野神社」は春日・伊勢・賀茂・石清水八幡・平野・松尾・稲荷で「七ノ社」ですか・・・。
「漆部神社」のおとなりの「甚目寺」は、真言宗智山派の寺院で、御本尊は聖観音(秘仏)で、御前立である十一面観音の胎内仏、とのことで、
| 伝承によれば、推古天皇5年(597年)、伊勢国の漁師である甚目龍磨(甚目龍麻呂)が漁をしていたところ、当時海であったこの地付近で観音様が網にかかり、その観音像を近くの砂浜にお堂をたてお祀りしたのが最初という。この観音像は、敏達天皇14年(585年)に、物部守屋、中臣勝海の手によって海に投げられた3体の仏像のうち1体(聖観音)といわれている。残りの2体のうち、阿弥陀如来は善光寺、勢至菩薩は安楽寺(太宰府天満宮)にあるという。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9A%E7%9B%AE%E5%AF%BA) |
興味深いですね。甚目龍磨(甚目龍麻呂)も「漆部連」の一族らしく、「御前立である十一面観世音菩薩象が尾張国唯一の乾漆像」とのことで。
(http://kamnavi.jp/en/owari.htm)
そこに「漆山神社」のことも書かれていたので検索すると、御祭神が雷神・龍神・大山祇神とあった。
(http://www.genbu.net/data/etigo/urusiyama_title.htm)
「漆部神社」には「木花咲耶姫命」も祀られており、物部氏と「瀬織津姫」には深い繋がりがあるようだな、と・・・。
話がそれますが、「漆部伊波」で検索していて「杜本神社」を知り、「一説には、崇神天皇の時代、経津主命の14世の孫の伊波別命が、祖神・経津主神の陵墓のある地に住み、経津主神を祀ったのが起源であるという。」とあり、ちょっと気になって。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%9C%E6%9C%AC%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
| 祭神 経津主命と経津主姫命の夫婦神を祀るとしているが、『神社明細帳』では事代主命・経津主命、『河内国式神私考』では句々廼智命・氷谷坐彌豆波乃売神、『地名辞典』『神祇志料』『地理志料』では「当宗忌寸の祖神」としている。 |
とあり、木の神「句々廼智命」の次に、山の神「大山津見神」、野の神「鹿屋野比売」が産まれている・・・あ、そうか、「野」が神聖な場所であるのは、「鹿屋野比売」すなわち「瀬織津姫」なんだな・・・。
(樽前山神社:http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo)
「鹿屋野比売」は「漆部神社」の近くと思われる「萱津神社」で、「日本唯一の漬物の神」として祀られているんですね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%B1%E6%B4%A5%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
「阿波手の杜」とも呼ばれたというあたり、何かありそうだけど、かつての御神木は「連理の榊」ということで、貴船奥宮の御神木「連理の杉」を思い出した。

あ、話がそれましたが、「当宗忌寸」を検索すると「誉田八幡宮」の摂社「当宗神社」がヒットし、
| 当地は景行天皇の皇子で成務天皇の弟である五百城入彦命一族の土地であるとともに、五世紀頃の楽浪郡からの渡来人である当宗直一族の居住地であったとしている。
(http://kamnavi.jp/en/kawati/konda8.htm) |
とあり・・・五百城入彦って景行天皇の子ですよね。で、「印南野」の印南別媛と景行天皇の子がヤマトタケルで。
五百城入彦の母が「八坂入媛命」で、五百城入彦の子に「品陀真若王」がいて、その娘が応神天皇の皇后・仲姫命・・・仁徳天皇の母ですね。
「八坂入媛命」の父が「八坂入彦命」ということは、諏訪や「麻積」と繋がりますよね・・・。
(八坂入媛命:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%9D%82%E5%85%A5%E5%AA%9B%E5%91%BD)
「当宗神社」について他のサイトでは、「当宗忌寸氏は百済系渡来氏族で東漢氏の一族」とあった。
(http://www.oct.zaq.ne.jp/yasuo26/masamunejinjya.html)
ただ、「杜本神社」に「平安時代には「矢作忌寸」を称したという。」とあり、「矢作」で追うならば物部氏に繋がるが・・・。
(矢作神社:http://kamnavi.jp/mn/osaka/monoyao.htm)
(矢作神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E4%BD%9C%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E5%B8%82))
URLの後者の矢作神社、ヤマトタケルが絡んでいることや、守屋の次男が太子に申し出て「薬師如来」を祀ったとされる「真福寺」と同じ岡崎市というあたり、気になるところで。
ん?かつて調べてた「五十瓊敷入彦命」は「弓矢」を望み、弟の「景行天皇」が皇位を継いだんですね・・・だから「五十瓊敷入彦命」は物部氏ゆかりの神社に祀られているのか・・・でもなぜ?
あ、崇神天皇・御間城姫命の母が「伊香色謎命」で、「父方の祖父:大水口宿禰命(饒速日命の4世孫乃至5世孫)」とあるから、その縁でしょうか。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%A6%99%E8%89%B2%E8%AC%8E%E5%91%BD)
大水口宿禰命が、
| 『日本書紀』によれば、崇神天皇7年8月、倭迹速神浅茅原目妙姫・伊勢麻績君とともに同じ夢を見て、一貴人が「大田田根子を大物主大神を祭る主とし、市磯長尾市を倭大国魂神を祭る主とすれば、必ず天下太平となろう」と告げた旨を天皇に奏上し、また垂仁天皇25年3月条の「一云」にも、倭大神(倭大国魂神)が大水口宿禰に神憑りして、倭大神を祭るべきことを教えたと載せるなど、奈良県天理市にある大和神社の創祀に関係したことが見える。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B0%B4%E5%8F%A3%E5%AE%BF%E7%A6%B0) |
とあるのも興味深いですね。「倭大国魂神」は「『大倭神社注進状』では、大己貴神(大国主神)の荒魂であるとしている。」とあって。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AD%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E9%AD%82%E7%A5%9E)
「長尾市宿禰」は「宇豆毘古(椎根津彦)の7世孫」だそうで。
(http://homepage2.nifty.com/amanokuni/yamato.htm)
大水口宿禰・倭迹速神浅茅原目妙姫(倭迹迹日百襲媛命:大物主神の妻)・伊勢麻績君の3人が同じ夢を見たというウラに、何があったのだろう・・・。
いや、事実?倭迹速神浅茅原目妙姫のシットで、大物主神の別の妻である「倭大神(倭大国魂神)」を追い出したのを、カムフラージュするため(言い訳するため?)に、大水口宿禰・伊勢麻績君も同じ夢を見た、ということにしたのかも?
何だか、倭迹速神浅茅原目妙姫が神功皇后に、倭大神が大中姫に見えてくるような・・・それで太子は忍熊皇子の鎮魂供養したのか・・・。
(http://kamnavi.jp/mn/kinki/nitiyoubi.htm)
で、「杜本神社」にある「隼人石」や、神宮寺だった「金剛輪寺」が太子の開基、反正天皇がこの地に一夜行在されて禊された旧蹟地、藤原長手の墓がある、というあたり、気になりますね。
(http://www12.plala.or.jp/HOUJI/jinja-1/newpage254.htm)
(http://www.geocities.jp/engishiki01/kawachi/html/040301-01.html)
「藤原長手」は「藤原永手」ですよね、藤原「北家」の祖・房前の次男の。ということは、物部氏との繋がりを示しているのでは、と・・・。
追記:「五十瓊敷入彦命」は岐阜市の「伊奈波神社」の主祭神で、臣下の物部十千根命が配祀されていることや、「『美濃国神名帳』には「正一位 伊奈波大神」「従五位下 物部明神」と記載されている。」というあたり、気になるところで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%A5%88%E6%B3%A2%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
| ●2009.08.24(Mon.) |
「下野国」が著書で出てくるので、2009.04.25、26分を読み返していたところ、「豊城入彦命」が「ニギハヤヒに繋がるのかも」としていたが、昨日書いてた崇神天皇の母「伊香色謎命」の父方の祖父が、ニギハヤヒの末裔であるから、繋がったんだなぁ、と。
「下野国」についてはあとで書くとして、「甚目寺」の伝承に、海に投げられた3体の仏像のうちの1体が「甚目寺」の御本尊で、「残りの2体のうち、阿弥陀如来は善光寺、勢至菩薩は安楽寺(太宰府天満宮)にあるという。」とあったので、「安楽寺」について検索してみた。
が、「明治の神仏分離で、仏像の幾つかは近隣の寺院に移されものもあり・・・」とのことで、廃寺になるまでのことは書かれていたが、「勢至菩薩」のことはわからず・・・。
(http://www.d1.dion.ne.jp/~s_minaga/ato_anrakuji_t.htm)
「菅原道真御神忌1100年大祭に伴い、百数十年ぶりにその仏像を太宰府天満宮に集め、天台宗僧侶による舞楽法要が行われ たと云うことのようです。」と書かれていたが、検索では見出せず・・・。
太宰府天満宮の年表には947年に道真の孫・僧平忠が安楽寺別当になることと、933年に2度勅使が安楽寺に下向したことは書かれているが、それ以上はわからず・・・。
(http://www.dazaifutenmangu.or.jp/shiru/nenpyo.htm)
あ、太宰府天満宮の本殿が「安楽寺」だったようですね。
(http://www.kyuhaku-db.jp/dazaifu/historic/44.html)
「九州国立博物館」で行われた「国宝 天神さまー菅原道真の時代と天満宮の至宝ー」 にもないようなので、ひょっとして秘仏となっていたのを、廃寺となってからは存在自体を公表しなくなり、今でも本殿にこっそり安置されてるとか・・・?
(http://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s13.html)
ということで、結局見つけることができず、中途半端ですが時間切れで・・・すみません。
| ●2009.08.25(Tue.) |
「下野国」が著書で出てくるので、と昨日書きましたが、「上野国」が主でして、かつて「毛野国」として1つの勢力だった頃のことについて書かれてまして。
著書によると、発掘された古墳の様子から、群馬県太田市の「太田天神山」という5世紀後半の前方後円墳が東日本最大規模だそうで、継体天皇陵と思われる「今城塚古墳」より墳丘が長いそうで、「大王墓」に匹敵する規模である、と。
そしてそのあとに書かれているのが、昨日書いてた「豊城入彦命」の話で、「日本書紀」の景行天皇55年に、東国の人の手によって「上野国」に葬られたことがあるそうで、「この話は古墳にはどんなものがあるかを考えるさいの参考になる。」とされていて。
ま、はっきり「豊城入彦命」のお墓とは書いておられず、豊城入彦命の孫「彦狭嶋王」の古墳の候補がいくつかあるそうで、「太田天神山」もその候補になるとみている、と・・・。
私としては「豊城入彦命」のお墓と思えたりするんだが、孫の「彦狭嶋王」であっても、「物部氏」の血筋であることが重要な意味を持っているのでは、と。
そういえば、「武蔵野」になると思いますが、かつて行田市に太子の舎人のお墓(古墳)がお寺の裏にあって、その舎人が「物部氏」だったような・・・あ、「八幡山古墳」で「物部連兄麻呂」ですね。「漆塗り木棺」というあたり、「漆部伊波」との繋がりが考えられそうな感じがしますね。
(http://www.bell.jp/pancho/travel/saitama/hatimanyama%20kofun.htm)
あ、検索してたら「太子にまつわる伝説」というのがあり、太子の遺骨を納めて堂を建て、「地蔵院」という名にしたそうだが、のちに太子の子・「山背大兄王」の遺骨を太子の墓に一緒に埋葬して「西行寺」と改めたとか・・・。
(http://www.kodaihasu.com/gr/anc/3th/index.htm)
麓にそのお寺があったという「丸墓山古墳」は、「全国でも最大規模の円墳」だそうで、「太田天神山」と時代のズレがあるかもしれませんが、太子、というか、太子を含めた「物部氏」の勢力があったことを表しているようで。
(http://blog.goo.ne.jp/kuni-furutone118/d/20060514)
あれ?「丸墓山古墳」だけど、「聖徳太子の侍臣“蘇我調子麿”の墓」とあった・・・蘇我氏?
(http://blog.goo.ne.jp/kuni-furutone118/e/2db5e43cdd110621238cd3633936c852)
コミック「日出処の天子」では、調子麿は百済の妻妾の子になってたと思うんだが。で、守屋を射たとされる「トミノイチイ」は、種違いの兄になってて・・・。
へぇ~、先日調べた「宝登山神社」って、長瀞だけでなく「羽生」にもあるんですね。え!?中手子林の「文殊院」が「徳川御三卿“田安家”の祈願寺」って、行基の生家である「家原寺」と繋がるじゃないですか。
(http://blog.goo.ne.jp/kuni-furutone118/c/403ed9ebce8d92bc420341c9a69e9e68)
で、「八幡山古墳」の話に戻りますが、
| この伝記(聖徳太子伝暦)によれば、物部連兄麻呂は聖徳太子の舎人として活躍した人物である。仏教に惹かれて身を慎み、のちに在俗の信者となって太子に仕えた。太子の死後、舒明天皇5年(633)に武蔵国造に任命され、のちに小仁(しょうにん)の位(聖徳太子が定めた冠位12階の第4位)を賜ったという。 |
ここでの太子と「物部連兄麻呂」の関係は、岡崎市にある守屋の次男による「真福寺」と通ずるものがあるように思われて。
| 天皇家や豪族が武蔵国に進出してきた中でも特に物部氏(入間郡の物部天神社をはじめとす)の活躍が目立つ(秩父地方は大伴氏、埼玉東部は中臣氏か?)。 (http://skyimpulse.s26.xrea.com/musasi-saisi.html) |
とされているあたりも、関連がありそうですね。
話がそれてしまいましたが、上記のように東国での仏教が盛んだったことは、著書にも書かれており、京都「高山寺」に、「上野国」の「緑野寺」に空海が写経を依頼した旨が記された経本があるそうで。
(緑野寺にあったという相輪とう:http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_bunkazai/sourintou.htm)
「相輪とう」は最澄の発願により建てられたものだそうで、著書によると、北の守りとして下野国「大慈寺(小野寺)」、東の守りと思われる上記URLの「緑野寺」、南の守りの豊前国宇佐郡「宝塔院」、西の守りの筑前国「宝塔院」、中央の守りとして山城国と近江国に「宝塔院」をつくり、比叡山の東塔、西塔も同様のようで。
北の守りの下野国「大慈寺(小野寺)」は、「天平9年(737)に行基が建立したと伝えられ、奈良時代や平安時代の瓦が出土している。」とのことで、行基菩薩千二百五十年御遠忌記念誌「行基菩薩」記載の行基ゆかりの寺院。
小野氏と秦氏の繋がりから建てられたのではないかと思われるのだが・・・武蔵国一宮はかつて「小野神社」(多摩)で、御祭神は「江戸名所図会」では「瀬織津姫」とされていて、現在は「天下春命」もともに祀られているようで。
厚木市の「小野神社」では、ヤマトタケルと「天下春命」が祀られているが、「社伝によると、716年僧行基が薬師如来を刻み奉安したという。」とのことで、上記の繋がりを示すことになるのでは、と。
で、「上野国」のところで森氏は「多胡碑」について書かれていて、「羊太夫伝説」は「乗馬」の風習の発達をあらわし、「上野国」が東西南北の地に行きやすい、交通の要衝だったことを物語っている、とされていて。
後者の「交通の要衝」については、2008.11.14分で引用させていただいたように、「「仁叟寺」(http://jinsouji.net/)の「末寺」だった「八束観音寺」には、「羊太夫」の守本尊「千手観世音」(伝、行基作)が祀られていた」ことと、行基がそういう場所に寺院を建てたりしていることからも繋がるかと。
(http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/simin10/hitujika.html)
また、前者についても上記URLに、吉井町馬庭の「龍馬観世音」に、「堂内に八束小脛の像がある。そばの神馬橋は、羊太夫の白馬が倒れた所。羊太夫が乗馬の調教をした所を馬庭という。」と、羊太夫に関する伝承が書かれていて。
うーん、伝承の30に、「服部連は、百済から伝わった仏像を難波の堀に投げ込んだ罪で、那佐郷(南蛇井)に流された。この地で服部連と妻玉照姫との間に生まれた菊連の子が羊太夫である。」とあった・・・が、36の
| 羊太夫の墓がある。中臣羽鳥連・妻玉照姫・子菊野連は、守屋大連の一味同心として、蒼海(元総社)に流罪となる。後、大赦を受け、菊野連の子青海(中臣)羊太夫は、玉照姫が聖徳太子から譲り受けた釈迦牟尼仏の安置所として、釈迦尊寺を建立した。 |
を含めて考えると、不比等によって歪められた伝承である気がして・・・。
それらの下の段(3)の、「羊太夫伝説の中にも「神代か人皇の代かはっきりしないほど昔、羊の大夫という人があって、この方は天下を総べられる王様の血統をひく尊いご身分であられたが、何かわけがあって都からはなれたこちらの地方へお下りになり」というものがある。」からすれば、「羊大夫」は「物部氏」のように思われて。
まだまだ謎だらけだけど、氏族の繋がりは移住しても強く、田村麻呂や安部氏の「東征」は、関連氏族に「朝廷」の名のもとに折衝を言い渡されたものと思われ、2009.05.01分に書いた葛井親王や阿保親王が「上野太守」になったことも、2001/05/27分で書いた橘為仲が「陸奥守」になったことも同様かと。
あ、「豊城入彦命」もそうかもしれませんね。
ということで、今日もまた寄り道が多くなってすみませんでした・・・。
| ●2009.08.26(Wed.) |
「野」の最後はうちのご近所の「百舌鳥野」だったんですが、行基のことが多々書かれていて嬉しくなり、21日に書いたものの、かなりはしょってたりして、調べてから再度書こうと思ったけど、やはり調べきれずにいまして。
ただ、仁徳天皇が自分の陵地を定めたことが「日本書紀」にあるそうで、そこには「鹿」が関係しており、次の章の「鹿と人」に関連がありそうで、そのあたりに何かありそうで。
「日本書紀」の記述は、野のなかから走り出してきた鹿が役民のなかで死に、調べてみたところ、耳から百舌鳥が飛び出し、耳の中を食い割いていた、とのことで。
それについて森氏は、鹿は土地を象徴する動物で、「鹿が倒れたということはその土地の占有者がいなくなったことを意味するとみられる。」とされていて。
「鹿と人」の章では「豊後国風土記」の速見郡頸峯の伝承を引用しておられ、水田の苗を食べた先住動物の「鹿」との間には、「葛藤はあったが武器をもった人のほうが優位になり、鹿を服従させたというストーリーである。」と。
また「播磨国風土記」からは、伊和の大神が「巡狩」した際に出会った「鹿」のことを引用されてて、文章から推測するに、伊和の大神が鹿を倒して服従させたのだろう、と。
他にも各地の遺跡からの出土品に「鹿」が描かれている例をあげておられ、それらも「服従」を表しているように思えて。
「鹿」というと「春日大社」を思い出し、先住民であった「春日氏」が上記のような過程で5世紀に渡来してきた人々に「服従」あるいは「融合」したのでは、と。
それは春日氏のみならず、初めの章に書かれていた、春日氏と同じ「和珥系氏族」である粟田氏、大宅氏、小野氏、柿本氏らも同じ道を辿ったのではないか、と。
(和邇氏考:http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-10.html)
上記URLによると、天皇家の妃を輩出している氏族で、「稀な「高貴」な氏族といえる」とされているあたり、昨日の「羊太夫」にも関連するのかも。
「彦坐王」は謎の重要人物である、とされているあたり、気になりますね、2008.08.02に堺市の「日部神社」「菱木神社」について書いていて、「日部神社」の御祭神が「彦坐王」で日下部氏の祖神、「日部神社」と「家原寺」とは2キロほどの距離で、「日下部首」と行基には繋がりがあったように思われて。
「菱木神社」の御祭神はスサノオとされているが、「日部神社」の御祭神「彦坐王」の甥「菱木造」、つまり「豊城入彦命の可能性が高いと個人的に考えます。」とされているサイトがあって。
(http://www.sakai.zaq.ne.jp/dudrs406/newpage7.html)
(http://www.sakai.zaq.ne.jp/dudrs406/newpage18.html)
「豊城入彦命」だとしたら、「上野国」やニギハヤヒに繋がりますよね・・・。
「彦坐王」は岐阜市の「伊波乃西神社」にも祀られているようで、神社名がちょっと気になった。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%B3%A2%E4%B9%83%E8%A5%BF%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
「『先代旧事本紀』国造本紀因幡国造条に「彦坐王児彦多都彦命」と見えるが、不詳である。」というのも関連がありそうで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A6%E5%9D%90%E7%8E%8B)
また、「日下部には『新撰姓氏録』に“日下部“は”阿多御手犬養同祖。火闌降命之後也”との伝承もある。」というのも気になる。
(http://www.sysken.or.jp/Ushijima/Den-kamigami.html#ひこ坐王)
「コノハナサクヤ姫(神阿田津姫)を祭神とする式内都萬神社」を奉祀してきた有力な氏族、とされるあたりも同様に。
(http://www.sysken.or.jp/Ushijima/Den-hyuga.htm#コノハナ吾田日下部)
(都萬神社:http://www.genbu.net/data/hyuga/tuma_title.htm)
「火闌降命」は「隼人の祖」とされているが、「(日本書紀の)第八の一書では、古事記で火照命の事績とされていることが火闌降命の事績として書かれている。」とあって。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E9%A0%88%E5%8B%A2%E7%90%86%E5%91%BD)
「都萬神社」の「都萬」は「妻」で、木花開耶姫命は瀬織津姫と思われるので、ニギハヤヒと日下部氏の繋がりもあらわしているように思えて。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E8%90%AC%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
上記URLに「一説には柧津比売命という説もある。」とあり、「柧津比売命」は23日に書いた島根の「物部神社」の、境外摂社「漢女神社」の御祭神の1柱で、ここでも日下部氏との繋がりが見えたようで。
「都農神社」に、古文書類を焼失しているため、「都萬神社との政治的・宗教的対立を生じたとされるが・・・」の詳細は不明とされているが、氏族間の何かがありそうですね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E8%BE%B2%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
うーん、それにしても、「豊城入彦命」「五十瓊敷入彦命」「五百城入彦命」についての記憶がごっちゃになってくるし、「伊波別命」「伊波例命」「伊波久良別命」なども、「伊和大神(大己貴神)」「漆部伊波」と混ざってごちゃっと・・・話を戻そう。
「鹿」での著書からの引用のように、その手段を真似て借りた軒先から母屋を取るだけでなく、氏神も乗っ取ったのが不比等かと・・・。
そうそう、2003/02/02分に森氏の著書から「動物埴輪」について、「宮中の祈念祭でウマ・イノシシ・ニワトリをたてまつっていた。」とされ、「この3者が動物埴輪のベスト3であるのは示唆深い。」とあり、それらの動物は「飼育されていた」と書かれていたのを引用させていただいて。
今回の著書には、埴輪や土師器などには「鹿」や「猪」が多く描かれているが、「壁画」はそれらに比べて描かれることは少ないとあり、5世紀後半から「刀」の装具に「鹿角」が使われるようになったことを指摘されていて。
これらには関連があると思われるんだが、私にはそれを読み取るだけのちからがなくて・・・。
ただ、「鹿」が「恭順」を示すのであれば、「光明皇后」の母が「女鹿」という和泉国分寺近くの伝承は、「橘三千代」が「恭順」を示した、というか、不比等に従わざるをえなかったことを表しているようで。
(http://www.geocities.jp/easyclub_choro/ajno31.htm)
で、著書に、鹿の頭や鹿の角を奉納している例として、長野の「諏訪大社」、福岡の「志賀海神社」と、鹿の頭の奉納が絵馬の奉納になったのだろうとされている埼玉県秩父市の「森のおすわさま」で、何か共通点があるのだろうか、と。
埼玉県秩父市の「森のおすわさま」は、長野の「諏訪大社」と同じく主祭神が建御名方命、八坂刀売命と思われ、福岡の「志賀海神社」を検索すると、
| 龍の都とも呼ばれ、伊邪那岐命の禊祓によって出生した底津綿津見神・仲津綿津見神・表津綿津見神の三柱(綿津見三神)を祀る。全国の綿津見神社の総本宮(海神の総本社)である。代々阿曇氏が祭祀を司る。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E8%B3%80%E6%B5%B7%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
とあり、拝殿前の「鹿角堂」に奉納された鹿の角があるそうで。
「玉依姫命」は「綿津見大神」の子で神武天皇の母だが、タマヨリビメは善光寺大本願上人(刀自古郎女)が勧請して祀ったとされる「京都賀茂御祖神社」の御祭神と同じ名だし、大物主命のヨメ・活玉依毘売も近い名だし、「龍の都」ということで「瀬織津姫」が浮かんでくるんだが・・・。
祭祀を司る「阿曇氏」の祖神が阿曇磯良」とあり、「宮中に伝わる神楽の一つ「阿知女作法」の「阿知女]は阿曇または阿度部のことである。」とのことで「阿知女作法」を見ると、「物部氏」に繋がっていくようだが・・・。
(阿曇磯良:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%9B%87%E7%A3%AF%E8%89%AF)
(阿知女作法:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E7%9F%A5%E5%A5%B3%E4%BD%9C%E6%B3%95)
阿曇磯良について、2003/04/27分で少し書いていて、そこに玄松子さんのサイトのURLを書いてたので拝見すると、「建御名方の妃・八坂刀売は安曇の女らしい。」とあった。
(http://www.genbu.net/data/tikuzen/sikakai_title.htm)
八坂刀売命・・・父は天八坂彦命であり妹に八坂入姫命がいるとされる、という伝承や、綿津見命の娘であり穂高見命の妹とする、という伝承もあるようで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%9D%82%E5%88%80%E5%A3%B2%E7%A5%9E)
前者の伝承なら、「天八坂彦命」は伊勢神麻續連等の祖であり、「八坂入媛命」は「五百城入彦」の母だったと思うが、「八坂入媛命」の母が物部氏?
後者の伝承の「綿津見大神」の子は上記のように「玉依姫命」で、「穂高見命」は「信州安曇野の開拓者」とありますね・・・「穂高見命の弟の振魂命は、倭氏・津守氏・尾張氏の遠祖にあたり、同族といえるだろう。」ということは、物部氏との繋がりが伺えるわけで。
(http://homepage2.nifty.com/amanokuni/azumi.htm)
阿曇氏も不比等が消した?
森氏の著書の最終章が「鯨と日本人」で、「常陸国風土記」に、クジラに似た丘があるのを見たヤマトタケルが「久慈」と名づけた、と、久慈郡の地名説話を引用されていて、「クジラ」を知っているということは「海」について知っていることをあらわしている、というような内容があった。
それは古墳にも見られる傾向のようで、「濠」のある古墳は、「大海」に浮かぶ不老不死の理想郷「蓬莱山」などの信仰によるものではないかとされており、5世紀の巨大古墳のうち「濠」があるのは、大阪・奈良のほか、兵庫・岡山に少しあるだけだそうで、濠のある古墳からはタコやイカと思われる遺物が出ていることもあるそうで。
いくつか書かれている順を変えて書いてたりしてたんだけど、もう1つ、わからずにいて書きあぐねてたのが、「天武天皇」の「信濃遷都」に関することで。
未だに692年に「持統天皇」の伊勢行幸を諫めた「三輪高市麻呂」について謎のままだが、「天武天皇」が「大海人皇子」で「海」を熟知したルーツが信濃にいるから、という推測が。
「天智天皇」もルーツの里に遷都して「大津宮」としたのではないかとも想像でき、琵琶湖と諏訪湖が繋がっているという伝承を聞いたことがあり、そこに「天智天皇」と「天武天皇」の繋がりも見えるようで。
「持統天皇」の伊勢行幸を、「三輪高市麻呂」が「信濃遷都の布石」と捉えて反対したのだろう、とされてましたが、果たして「持統天皇」に夫の意思を継ぐ気持ちがあったのかな?という疑問があって。
それもまだわかってないのですが、柿本人麻呂の歌から想像するに、三河にも行ったのではないかとされていて、もしそうだとしたらそれもまた疑問で。
いや、柿本人麻呂自体も謎で、今まで石見で調べてた時にもよく見かけたし、2008.10.12分で引用させていただいた中に、「柿本人麻呂とは三輪高市麻呂(692年持統天皇の伊勢行幸を諫めた)に他ならないことになる。」と・・・。(http://www.geocities.jp/yasuko8787/0q-5.htm)
引用しておられた柿本人麻呂の歌に、「麻積王」が流されたという「五十等児乃嶋(伊良湖)」が出てきており、柿本人麻呂は「三河」に行ったこと以外にも、何か言わんとしているような・・・。
ふと思いだしたのは、守屋の次男が創建したという「真福寺」が三河にあること、今までのことから「麻積」の背後に「物部氏」が見えるように思えること・・・。
柿本人麻呂は、「持統天皇」が不比等に操られてさまざまなことが改竄されていくのを見越し、伊勢行幸を、そこから三河に行くことを「諫めた」のかも、と・・・。
追記:「麻績王」については2008.10.28に少し書いており、「麻績王」が「聖武天皇」「柿本人麻呂」「美努王」など、諸説あるそうで、
| 「麻績王」というからには、麻績連が壬生(乳部)、又は母親の出身氏族ということだろうか。」と、「斎部氏説」の初めにあるが、4つ書かれている説のどれにも当てはまりそうで・・・。 (http://homepage2.nifty.com/amanokuni/ominoookimi.htm) |
としており、
| もし、武乳速命=乳速日命で広湍神麻續連等の祖だとしたら、麻續(麻(お)を細く裂いて、より合わせて糸にすること)に携わる人のトップが「添県主」だとしたら、と仮定して探してみた。 技術的には変化はあると思われるが、旧添上郡月ヶ瀬村では今でも、麻生地を晒して純白にした「奈良晒し」が織られているそうで。(http://www.h5.dion.ne.jp/~tarering/nihon4.htm) |
とも。
また、「籠名神社祝部海部直等之氏系図」によると、
大神神社の古文書(饒速日大王の陵墓、三輪山を御神体として祀る) 以下系図 (十六氏)
(http://www1.kcn.ne.jp/~kikujo/11.html) |
とのことで、藤原氏は北家に限られると推測しているが、関連性がありそうで。
| ●2009.08.28(Fri.) |
森氏の著書を読み終え、一緒に購入してた「伊勢神宮 知られざる杜のうち」の目次を見て、2009.08.13に書いてた、「日本三上人」のうちの伊勢の「慶光院」について、少し書かれてまして。
100年以上途絶えていた「式年遷宮」を復興させたのが、「慶光院」の勧進聖だったんですね。神宮寺の一つとなったが、「式年遷宮」が正式に行われるようになったことや、廃仏毀釈によって廃寺になったようで。
(http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E6%B8%85%E9%A0%86%E3%80%80%E6%85%B6%E5%85%89%E9%99%A2&search_x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&u=www.jingukaikan.jp/sukeikai/imgs_mimosuso/49.pdf&w=%E6%B8%85%E9%A0%86+%22%E6%85%B6%E5%85%89+%E9%99%A2%22&d=HJ6IYBlMTS6Q&icp=1&.intl=jp)
「慶光院」について書かれているページの少し前に、「朝熊山スカイライン」の登り口に「西行谷」と呼ばれるところがあり、かつて「西行」が庵を結んでいたことが書かれていて、それが、聖武天皇の勅による行基創建とされる「菩提山神宮寺」だったようで。
検索で見ると、違う場所のような感じもするんだが、土地勘がないのでよくわからず・・・。
(http://www.kankomie.or.jp/kataribe/course.php?id=6462)
その「菩提山神宮寺」にあった御本尊が、愛知県碧南市音羽町「海徳寺」の御本尊「大浜大仏」だそうで。
(http://asai.vis.ne.jp/mikawa/useful-link/koikigyosei.shtml)
(http://e-tera.net/Entry/185/)
「大浜大仏」について書かれている項の最後に、「神宮鎮座の聖地なるがゆえに伊勢にはほかの宗教が押し込んでくるのである。」とされていて、私にはその要因として「瀬織津姫」などのことがあるからだと思うのだが。
それらのことや、内宮と外宮の争い、「式年遷宮」が途絶えたことなど、詳しく知っていたであろうと思われるのが、上記の出来事の間に書かれていた「荒木田守武」ではないだろうか、と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%92%E6%9C%A8%E7%94%B0%E5%AE%88%E6%AD%A6)
荒木田守武が、「三禰宜になる四十四歳のとき、「両大神宮」という御神号の軸を書いている。」とあり、そのことについて「両方を書くなら「皇太神宮 豊受神宮」と書いたはず。」とされていて。
書かれているように、「内宮と外宮の両方が仲良くなってほしいという思いが込められているのだと私は思う。」というのもあると思うが、何か他にもありそうな、というか、両宮のみならず、御祭神に対する人々の思いがあるように思うんですよね・・・。
同じページに、「卜部兼倶によって流された京都の吉田山へ大神宮が飛び移ったというデマ・・・」というのがよくわからなくて・・・。
(卜部兼倶:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9C%E9%83%A8%E5%85%BC%E5%80%B6)
うーん、京都の「吉田神社」に何かあるような・・・。
(http://www5e.biglobe.ne.jp/~hidesan/urochoro-yoshida-jinjya.htm)
このあたりはかつて森氏の著書で「吉田兼好」が出てきた時、調べていたと思うんだが・・・あ、「吉田兼好」は「とはずがたり」でも絡んでたと思い・・・やはり瀬織津姫に繋がるように思えて。
「奉幣の儀」では、「中臣が宣命を奏し、忌部は幣帛を奉り、卜部は祓いを司る役柄であった。」ということから、「デマ」とされる部分に当時の状況を垣間見ることができるような・・・。
追記:神宮式年遷宮で調製される伊勢神宮内宮の神宝の1つに「須賀利御太刀」があり、「須賀利」とは「蜂」のこと、ということで気になりまして。
「須賀利」で検索すると、尾鷲市に須賀利町があったが、その上にあった梶賀町の「ハラソ祭り」に、「「ハラソ」は「羽刺」が転化した、或は中国から漂着した「秦氏」に由来するともいわれ、捕鯨の習俗を今に伝える祭りです。」とあり、秦氏のテリトリーだったのかも?と。
(http://owase-kb.jp/kankou/maturi.html)
江戸時代の捕鯨の習俗のようであるが、それ以上の情報はわからず・・・。
(http://www.kumadoco.net/dictionary/report.php?no=28)
で、「日本三上人」の熱田の「誓願寺」について、日秀妙光という尼僧が建立したお寺で、「熱田神宮の社殿修造に際して,勧進活動に従事する存在であったかと推察される。」とのことで、善光寺で出家したので「善光尼」とも言われたそうで。
「正親町天皇より天下泰平、宝祚延長の祈祷を命じ」られ、「紫衣の着用と上人号の使用を認可」されて以来、代々「熱田上人」と通称された、とのことで。
(http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E7%A7%80%E5%A6%99%E5%85%89)
勧進活動の内容については検索では見出せず・・・。
で、「慶光院」について、
| 初代慶光院院主である守悦(しゅえつ)上人が流失していた宇治大橋を勧進により架けたことから、遷宮のために諸国を巡って金品を集めたいわゆる「慶光院勧進」が始められたと言われています。その後、三代院主の清順(せいじゅん)上人が外宮の式年遷宮を、四代院主の周養(しゅよう)上人と五代院主の周清(しゅせい)上人が両宮の式年遷宮を遂げたため、「伊勢上人」「遷宮上人」とも呼ばれました。 (http://www.samenotare.jp/oharaimachi/link_index.html) |
とされるサイトがありました。
| ●2009.08.30(Sun.) |
「伊勢神宮 知られざる杜のうち」を読み終えて・・・神事の内容や経緯などを拝見し、いろいろと思うところはあるとしても、お伊勢さんはすごいところだな、と。
何て表現したらいいのかなぁ・・・たぶん、神事に関わっている方々の中に、「不思議」に思えることがあるような感じがするが、それは「不思議」ではないということも感じ取っておられるのでは、と。
いちばん大切なことは、すべての神、すなわち、大自然に対する感謝の気持ちで、その空間におられる神々に合ったお祭りをされているように、本を読んでて思ったわけで。
それはお伊勢さんでしかできないことと思え、それが西行の
の歌にあらわれているようで。西行が祀られている神のこと、知らないはずはないですから・・・。
ただ、神宮内が神のおられる聖域であっても、祀るのは人間であり、神宮内では負いきれない人間的(?)な部分を、西行や行基たちは「菩提山神宮寺」で瀬織津姫(阿弥陀如来)を祀ることによって、バランスを取っていたように思われて。
それが「菩提山神宮寺」のあたりで芭蕉が詠んだ、
という歌に込められているのでは、と。(参照・http://www.ict.ne.jp/~sasa-mi/miekuhi85.htm)
明言はされてないけど、上の2首を引用されているあたりに、「不思議」に思えることも気づいておられるように思われ、それは神事に関わるすべての人がそうであるように思えて。
「善光寺」もお伊勢さん同様、再建には「勧進」による部分が大きかったように思われるので、伊勢上人の思いを同じように感じておられたのでは・・・。
ということで、今度は「熱田神宮」が気になってきたので、その方面の本を読んでみようかなと思っています。