 とんでもニャ~Mの推測2-13
とんでもニャ~Mの推測2-13※役にたたない推測ばかりの駄文です。(爆)
 とんでもニャ~Mの推測2-13
とんでもニャ~Mの推測2-13| ●2010.01.05(Tue.) |
2009.12.23分に、「京都の歴史を足元からさぐる」p33で「万葉集3236」が引用されていて、「皇神」(須馬神)について調べたあと、「須賣神」とも書くことから、「天宇須賣神」の略のように思えたり・・・と。
そのあと、「佐那神社」で「天宇須賣神」に「和魂」「荒魂」があることを知り、それからちょっと気になってた。
(http://kamnavi.jp/en/mie/sana.htm)
すると「笠沙路探訪」さんの2010年正月号で、「『赤い衣』は、『践祚大嘗祭」で『天鈿女命』の系譜である『猿女』が着用することになっている。」とあり、上記のことに繋がるかも、と。
(http://www4.synapse.ne.jp/yatusiro/newpage32.html)
となると、瀬織津姫に繋がるように思われ、ならば「天穂日命」はやはり瀬織津姫かと。
以前、行基ゆかりの堺市東区「萩原天神」で、日置氏(吉村家)が氏神「天櫛玉命」よりも、「天穂日命・菅原道真公」を主に祀ったことが、瀬織津姫に繋がるのではと考えていたので。
で、「『三河赤引の糸』が『天照大神の御衣』・・・」とありましたが、このあたりも以前「機殿神社」を見て瀬織津姫を連想し、まだはっきりしていない部分はありつつも、「服部」と「麻績」で秦氏と物部氏は絡んでいる、と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E6%AE%BF%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
すなわち「隼人」が絡んでいる、と・・・。
まだ長時間は座っていられないので、気になってるもののあまり検索できず、ここまでしか書けなくて・・・すみません。
| ●2010.01.06(Thu.) |
昨日あまり検索できなかったので、「天宇須賣神」のみ調べてみた。(アメノウズメ、天鈿女命はまだです。)
まずヒットしたのが、富山県中新川郡の「雄山神社」で、「八幡宮」に合祀された「櫻文社」の御祭神が「天宇受賣命」で。
(http://www.oyamajinja.org/iwakura/index.html)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%84%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
「雄山神社」の境内社に「刀尾社」があり、祀られている「伊佐布魂命」は2009.12.30分に引用させていただいたように、倭文連の祖神で物部氏。
で、「雄山神社」はイザナギと天手力雄神(太刀尾天神剱岳神・本地不動明王)が祀られているが、
| そして天孫降臨の際、天宇受賣(アメノウズメ)は案内にきた国津神の猿田毘古(サルタヒコ)に会い、名前をもらって猿女となるのだがどういうわけかとってつけたように、「さて、その猿田毘古神が阿邪訶(あざか)にいる時、漁をして比良夫貝(ひらぶがひ)にその手を挟まれて、海水に沈み溺れた。」という不自然な猿田毘古のエピソードが続く。普通に読んではなんのことかわからないけれどこれが猿田毘古の出自を仄めかしている文章であった。「比良夫貝(ひらぶがひ)にその手を挟まれて、海に沈んだ」の中に「平(ヒラ)」と「手」「海」を暗号として盛り込んである。海はアマで天、「平」は岩戸で「手」とくれば「タヂカラオ」。かれは天では「タヂカラオ」としてウズメとともに岩戸開きに働いたのであった。 (日女:http://blog.goo.ne.jp/fumioyamashita/e/41244eef5edf2dca58b0e464c4328250) |
とあり、また別のサイトには「早松佐羅神社は「佐羅宮」と呼ばれた白山宮のひとつで、佐羅大明神を祀る社とククリ姫を祀る社がある。佐羅大明神は以前ブログに書いたように、瀬織津姫の息子 佐羅皇子 = サルタヒコのことだ」と。
(http://hakusan1.jugem.jp/?page=1&month=200907)
(早松佐羅神社:http://www.genbu.net/data/kaga/sara_title.htm)
「佐羅皇子」とは、「下白山の女体后が近江の志賀の都で唐崎明神に見そめられ、妊娠して加賀に帰る途中、愛発山で誕生したのが佐羅王子。」とあった。
(大野湊神社:http://kamnavi.jp/it/higasi/isikawa.htm#oonominato)
「唐崎明神」は去年の夏、貴船の帰りに太子ゆかりの「頂法寺(六角堂)」でお参りしましたっけ・・・大津市唐崎の「唐崎神社」は「祓所」で。
(http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/bunka/data/bz_423.html)

「下白山の女体后」は「龍宮の宮」にいるようで、瀬織津姫と思ったんだが、サルタヒコが息子なら瀬織津姫は天宇受賣の姑になりますよねぇ。
(義経記・愛発山の事:http://www.st.rim.or.jp/~success/gikeiki_07.html)
うーん・・・とりあえず検索にあった天受賣受命を祀る神社を書いておきます。
| ■戸隠神社[火之御子社] 長野県長野市戸隠 御祭神:天宇受賣命、天之忍穂耳命、栲幡千千姫、高御産巣日神 主祭神の天宇受賣命さまは古事記の天岩戸段と、天孫降臨段、猿女君段でご活躍されており、歴史的にみても戸隠神社の他の御社とちがって、創建から今日までずっと御社の形で通した、ご由緒ある御社で、神社の御神楽に深いかかわりをもっています。ご社名の火は過去において日と混用されてきましたが、現在は火に統一されています。 ■和田神社[秋葉神社] ■佐地神社 ■篠神社 ■赤國神社 ■桑津天神社 ■門僕神社 ■千代神社 ■別浦海神社(ワダツミジンジャ) ■諏訪神社 ■石清尾八幡宮[御先社] ■椿大神宮[別宮 椿岸神社] ■小許(古)曽神社 ■白川神社 ■糟目春日神社 ■月見里神社 ■太平山神社 (http://www.genbu.net/data/simotuke/taihei_title.htm) ■箱根神社(九頭龍神社)[攝社 高根神社] ■子之神社 ■熱田神宮[笹社] ■大國魂神社[宮乃咩神社] |
戸隠神社と和田神社[秋葉神社]では、「火」か「日」とされているようで、佐地神社も近いような。
篠神社では、天照大神・天宇受賣命が天鈿女命・天穂比命とあるならば、天照大神は天穂比命ということかと。
桑津天神社の向かいに京善寺があり、御本尊の不動明王は和歌山の根来寺の不動明王像と同木同作のものとされていて、瀬織津姫と繋がりそうで。
門僕神社が隼人と繋がり、漆部と繋がるということは、物部氏とも繋がるということで、御祭神が不比等によって変えられてしまったことを、藤原氏に乗っ取られたことを証明しているようで。子之神社も物部氏系ですね。
岡山の別浦海神社・諏訪神社は、上記同様、海人すなわち物部氏との繋がりを示しているようで、勧請元の信濃の諏訪神社も同様、ということかと。
小許(古)曽神社は比売許曽神社などとの関連がありそうで、京都の許波多神社(木幡・コハタ)など、「許」(高句麗?)などとの関連が気になるところで・・・白川神社は新羅を思わせるようだし。
で、関連がありそうに思うこととして、
| ●ヨーロッパでは、なぜかこのシダは大昔から霊草として知られていて、シャーマンは月夜に摘んだこのシダを呪術に使った。その根拠は例の外徴説で、半月形の羽片が月の支配下にあることを示しているからというのだ。錬金術ではこのシダが水銀を月の色をした本物の銀に変える力を持つとされていた。 一方、この草には鉄を引き寄せる力があって、これがたくさん生えている草原に馬が踏み込むと、その蹄鉄が抜け落ちると信じられていた。そのため、Unshoe-the-horse という呼び名も残っている。この力はまた錠前をも壊すので、鍵がなくてもこの草を鍵穴に差込さえすれば開けることができるともいわれていた。この草で嘴を研いだキツツキは鉄板にも穴が開けられるとか、妖精が馬代わりにこの草を乗り回すなどという言い伝えもあった。 (ヒメハナワラビ:http://www5e.biglobe.ne.jp/~lycoris/ferns-zokushin.densetu.html) ●古事記の中でも有名な「天の岩戸」のシーンで天宇受賣命が身につける「天の真折(あまのまさき)」がテイカカズラだと伝えられています。 ●召天兒屋命 布刀玉命而 内拔天香山之眞男鹿之肩拔而 取天香山之天波波迦而 令占合麻迦那波而 天波波迦(原文は異体字): 葉の葉脈が整然として、理想的な方眼紙状になっている、ある香木の葉。天とは、理想的な。波とは、水面の高低運動によって生じる筋状の罫線のようなものの意。迦とは、歩いて行って出会う意。波波迦とは、罫線が縦と横に組み合わさって、方眼紙状になったものの意。 占合: 「うらへ」は「うらあへ」で、「うら」は心であり、「あへ」は合致である。心と心、霊と霊を合致させる作法・行法のことであります。 天香山之五百津眞賢木矣 根許士爾許士而 於上枝 取著八尺勾瑰之五百津之御須麻流之玉 於中枝 取繋八尺鏡 於下枝 取垂白丹寸手青丹寸手而 眞賢木: 永遠不滅の宇宙大生命を樹に譬えているのである。それを象徴する為の、芳香のある常緑樹。月桂樹、楠木、榊。眞(ま)とは真実の、自然のままの、正しい、永遠不滅の義。賢木(さかあき)のサカアとは、無限伸展・無限の栄え(イヤサカア)の義。 天宇受賣命 手次繋天香山之天之日影而 爲鬘天之眞拆而 手草結天香山之小竹葉而 於天之石屋戸伏汗氣而 蹈登杼呂許志 爲神懸而 掛出胸乳 裳緒忍垂於番登也 天宇受賣命:天照大御神の本化神。高御産巣日神の御子。宇(空間・全ての現れ)をそのままに受ける意義から、虚心坦懐・無我・無心・謙虚・素直・従順・無邪気・無畏怖・無為・神任せ・・・等の神性を保持する最高に素晴らしい女神。髻華(うず):古代、木の枝・葉・花等を冠や髪にさして飾りとしたもの。神楽に髻華(うず)をかざして舞った〔自然のものを身に付けて、天真爛漫に神楽舞いを舞った)ところから、この名が在る。 渦(うず):流体の中で、こまのように自転している部分。速度の違う二つの流れが合わさるとき、流れが鋭い角を曲がるときなとに生ずる。煙草の煙の環や竜巻・台風の類も渦の一種。大きく渦に巻き込む働きを示す。 ●ML西行辞典vol・103 正木:初冬にも紅葉するけど初夏にも紅葉するカズラのようです。テイカカズラなど諸説ありますが、サンカクヅルのようです。 ここ葛城山ではまさきのかずらの色は秋に似て紅葉し、他の木の梢は緑であることよ。 (新潮日本古典集成山家集から抜粋) |
たしか「波波迦」は「桜」で、「占合:うらへ」は「うらみ」と、「眞賢木」は瀬織津姫の名「撞賢木厳之御魂天疎向津媛命」と繋がりそうで、総体的に考えてみようと思いつつ、やはりまだあちこち絡まったままでして・・・。
| ●2010.01.09(Sat.) |
森氏の「京都の歴史を足元からさぐる」の嵐山編で、調べても関連がいまいちよくわからなかった「後水尾天皇」がずっと気になってた、先月読んだ宇治編での「当尾」や、以前調べてた「塔尾」なども同様に。
とりあえず「後水尾天皇」について検索すると、行基作といわれる十一面観音が安置されている「観空寺」は、嵯峨天皇創建で後水尾天皇が再建されたそうで。
(http://sagano.koichaya.jp/?eid=134008)
| [後水尾天皇] 慶長元年6月4日(1596年6月29日) - 延宝8年8月19日(1680年9月11日)。第108代天皇。後陽成天皇の第三皇子。 遺諡により後水尾と追号された。水尾とは清和天皇の異称である。後水尾天皇は、不和であった父後陽成天皇に、乱行があるとして退位に追い込まれた陽成天皇の「陽成」の加後号を贈り、自らは陽成天皇の父であった清和天皇の異称「水尾」の加後号を名乗るという意志を持っていたことになる。このような父子逆転の加後号は他に例がない。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%B0%B4%E5%B0%BE%E5%A4%A9%E7%9A%87) |
ウィキペディアから気になる部分を抜粋しましたが、「父子逆転の加後号」だけを意識しての追号なのか、それとも「清和天皇」が「水尾」という地を好んだ理由に関連してのことなのか、両方ともなのか・・・。
「水尾」は交通の要衝だったようで、秦氏のテリトリーと思われることから、その勢力が清和天皇の背景にあったことを想像していたが、「水尾の女性が身につける、榛の木染の三巾の赤前垂れは、天皇に仕えた女官の緋の袴の遺風であるとも伝えられている。」というあたり、気になりますね。
(http://inoues.net/tenno/seiwa_tenno.html)
「赤前垂」で検索すると、泉鏡花の「夜叉ヶ池」に「峰の茶店に茶汲女が赤前垂というのが事実なら、疱瘡の神の建場でも差支えん。湯の尾峠を越そうとも思います。」とあり、疱瘡の神?湯の尾峠?と。
(http://www.aozora.gr.jp/cards/000050/files/3407_19566.html)
さらに、「右に、湯尾峠の万年姥。針のごとき白髪、朽葉色の帷子、赤前垂。」とあり、あらすじを読まないとわからないが興味深いな、と。
まず、タイトルの「夜叉ヶ池」に伝説があるようで、その伝説に出てくる「安八郡」も、「海人たちの世界」を読んでて気になってた場所で。
「夜叉ヶ池の伝説」の「小蛇(=龍神)」が瀬織津姫に繋がるように思われ、「今、織りかけの麻布がありますから、これを嫁入り道具にいたします。」というあたりに、物部氏との繋がりを感じるわけで。
うーん、「泉鏡花」の名前だけは知ってたが、読んだことがなかったので、ちと検索で調べてみたけど、この人も瀬織津姫などについて気づいていたような気がする。
ん?上記のサイトの「夜叉ヶ池」を読んでたんだけど、これってレンタルDVDで見たことがある・・・武田真治さんや田畑智子さん等が出ておられたような・・・住吉区にいた頃かな。
で、「湯尾峠」を検索すると、やはり交通の要衝だったようで、晴明が絡んでいるようですね。そして芭蕉が「月に名を包みかねてや痘瘡の神」を詠んでいて・・・「十五夜の月、別名 疱瘡<=芋=いも>の月」ですか。
(湯尾峠:http://www.fuku-e.com/theme/03/03/01/3-3-1-1b.html)
(http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/imokami.htm)
(おくすり博物館:http://www.tpa-kitatama.jp/museum/museum_12.html)
うーん、かつて家康や道灌を調べてて出てきた「太田姫稲荷神社」は、京都・山城の「一口(いもあらい)稲荷神社」を勧請したとあったけど、こういう繋がりがあったとは・・・「月」の信仰、すなわち隼人が絡んでいるようですね。
「ツキヨミはローマ字ではtukiyomiで逆にするとimoyikutとなる。それで昔は月見にニギハヤヒゆかりの稲を飾り、芋(imo)を供えたのだ。」とされるサイトがあり、(旧暦8月の)十五夜の月=疱瘡=芋=ニギハヤヒ、ということなのかな、と。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki26.htm)
旧暦の8月の十五夜は「中秋の名月」で、やはり芭蕉も気づいていた、ということなのか、それとも「松尾」だから知っていて当然だったのか・・・。
そのサイトには神話についても書かれていて、「出雲は「赤土(はに)」に象徴化している。もうおわかりのようにヨミの国は赤という思想とハニは八と二で出雲のことになる。」とあり、「赤前垂」や「赤引の糸」なども「出雲」を表し、天皇のルーツを示すのかも?と思い、「白」が「この世」とされているのなら、「聖神社」や「布引観音」のように「白」い布を用いたのは、ヨミの国からこの世への導きを意味しているのかも、と。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki23.htm)
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki28.htm)
上記URLの下の方では「天津祝詞(祓い詞)」について、「黄泉(出雲)の國の穢れを禊ぎ祓うことで出雲と訣別した日向族の祝詞になってしまっているのである。」とあり、不比等のしわざかと。
気になって続きを読んでいると、調べたことのある「子の権現」や「青麻神社」が出てきて、どうやらニギハヤヒに繋がるようだが、ここでも「子ノ聖( ねのひじり )が祀ったという十一面観音とは実はニギハヤヒのかぶるもう一つの仮面で素顔はやはりニギハヤヒなのだ。」とあり、また、大歳神=宇迦之御魂神とされているようで、うーん、と。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki30.htm)
ま、「「ホホデミ」の姉が、「天火明」=「大吉備モロスス」=「モロスク」ということ。(※女性)」とされるサイトもあったし、私は「天穂日命」は女性だと思ってはいるが・・・。
(http://www.platz.jp/~hvhy/gen/g203.html)
あちこち寄り道しましたが、「後水尾天皇」の指示で造営されたという「修学院離宮」の庭園に、巨大な人工池の「浴龍池」があるそうで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E9%99%A2%E9%9B%A2%E5%AE%AE)
また、後水尾上皇のために造営されたという「仙洞御所」は、正式名称は「桜町殿」だそうで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E6%B4%9E%E5%BE%A1%E6%89%80)
「その地が桜を愛し桜町中納言と呼ばれた藤原成範(1135-87)の屋敷跡であったこと」から、「桜町殿」と呼ばれた、と。
(http://jpimg.digital.archives.go.jp/kouseisai/category/emaki/sakuramachi.html)
藤原成範の父は南家で、母は「紀伊局」こと「藤原朝子」だそうで、世阿弥の「泰山府君」に登場するくらいだから、父母のいずれか、あるいは歌人の繋がりから、瀬織津姫のことを伝え聞いて桜を愛でたと思われるが・・・。
(http://junseikai.cool.ne.jp/taisanpukun.htm)
(http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sigenori.html)
藤原成範の娘にまつわる「水」の話があるようで、その「霊水」があるとされるのが知多の「恋の水神社」だそうだが、書かれている歌の「尾張」「野間」がちと気になった。
(http://enmusubida.com/spot/04tokai/aichi004.html)
「恋の水神社」の御祭神が「美都波能女命」ということで、「お告げ」のあった「三輪大神」も「熱田」の神もその「水」の神威を知っていた、ということかと・・・あと、玄ぼうも。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%8B%E3%81%AE%E6%B0%B4%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
さて、これらのことを知っていて後水尾天皇はその地を選んだのだろうか?
それにしても、「尾」は何を表しているんだろ?ギリシャ神話の「ケルベロス」は「龍の尾」をもつ、ということで少し興味を持ったが・・・。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AD%E3%82%B9)
「水尾」はかつて「みずのお」あるいは「みのお」と呼ばれていたそうで、大阪の「箕面」も関連があるのかも。
(http://www.linkclub.or.jp/~mcyy/kyo/akechi/02.html)
「豹尾神」は、「陰陽道における8人の方位神(八将神)の一人」で、「本地は三宝荒神とされ、豹尾神は、天宮神という女神を伴う。」とされ、「計都星の精」とのことだが、「計都星(ケートゥ)」は「月の降交点(西洋占星術ではドラゴンテール)に存在するとされた天体」とあり、「月」の信仰と繋がりそうで。
(豹尾神:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%B9%E5%B0%BE%E7%A5%9E)
(ケートゥ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%83%BD%E6%98%9F)
スサノオは「スサの尾・穂」とされるサイトがあった。
(http://green.ap.teacup.com/20060818/616.html)
「云」という字が「雲」であり、「竜のしっぽ、すなわち竜尾をかたちどったもの」とされていたようで、そうすると「出雲」は「龍の尾が出たところ」となりますね・・・ヤマタノオロチ?
(http://i.mbs.jp/tv/ayakashi/ayagami/06.html)
ニギハヤヒ関連で、「(高橋郷)日尾社 祭神 天日尾神、国日尾神、天月尾神、国月尾神」とあり、検索したところ、舞鶴市の「日尾池姫神社」と「彌伽宜神社」がヒットし、龍の頭・胴・尾がバラバラに祀られるというのは行基ゆかりのお寺にもあったし、他にもありましたね。
(丹後風土記残欠:http://www.dai3gen.net/tango.htm)
(日尾池姫神社:http://www.geocities.jp/k_saito_site/doc/tango/hioikehimejj.html)
(彌伽宜神社:http://www.takaden.info/Mkagezinzya6.htm)
「日尾八幡神社」が松山市にあるようで、主祭神は品陀和気命、帯仲日子命、大帯姫命のようですが、中玉殿には伊予比売命とともにニギハヤヒが祀られているようで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%B0%BE%E5%85%AB%E5%B9%A1%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
「日尾とは日向の反対語で朝日の当たらない西側を言う。」と、富山市八尾町の「日尾御前山」について書かれていたサイトにあった。
(http://www.fitweb.or.jp/~ike/nissi2008/hiogozenyama080628/080628.html)
氷見市福岡町の「日尾神社」では、天押日命・ 底土神・ 赤土神・ 磐土神・ 伊邪那伎命が祀られているそうで、「大伴家持当国に司となる時、国内諸神社参拝の節、 本社は大伴家の祖神なりとて祭文を捧げられた。」というあたりが気になりますね。
(http://www.ariso.jp/jinjya/index.html#日尾・福岡)
津山市綾部の「綾部神社」に、「日尾神社」が合祀されているようだが、詳細は不明で。
(http://www.okayama-jinjacho.or.jp/cgi-bin/jsearch.cgi?mode=detail&jcode=03067)
美馬市穴吹町の「尾山」と呼ばれる山の上にあるという「十二所神社」は、「大正二年五月十五日尾山神社を合祀」とのことで。
(http://www.genbu.net/data/awa2/jyuni_title.htm)
「神戸市灘区日尾町」について、「字名の由来は不明。文明元年(1469年)11月の「都賀荘寺庵帳」に「壱反 八幡 日尾」と見える。『神戸の町名 改訂版』では「日尾は六甲八幡の末社か。あるいはヒエ(日枝)と関連するのだろうか」と推測されている。」とあり、「都賀荘」と日置氏との関連が気になるところで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%B0%BE%E7%94%BA)
秩父郡小鹿野町には「日尾城跡」があるようで、同住所に真言宗豊山派の「菩薩寺」、曹洞宗の「光西寺」があるようだが、詳細はわからず・・・。
(http://www.chichibu.ne.jp/~keig/index24.htm)
(http://www.e-sougi.jp/tera/saitama/chichibugun.html)
大里郡寄居町の「諏訪神社」は、「武州日尾城主(小鹿野町)諏訪部遠江守が鉢形城の家老となって出仕したとき、信州にある諏訪神社を守護氏神として分祀奉斎しました。」とのことで、気になりますね。
(http://www.geocities.jp/f_travel2000/yorii_town13.html)
諏訪部遠江守とは「諏訪部主水助定勝」だそうで、日尾城ができた頃の「日尾村の初期名主」が「和田家」で、「先祖和田隼人は日尾城に仕えたという伝承が残っている。」とあり、「日尾城に仕えた武士の霊を弔うために、この地に菩薩寺が建立された」とのことで・・・「和田家」は秦氏かと。
(http://www.water.sannet.ne.jp/u-takuo/kamosita-hiozyo.htm)
桜井市の「等彌神社」には、「上津尾社」「下津尾社」があるようで、ここもニギハヤヒに繋がりそうな。
(http://www.norichan.jp/jinja/hitokoto/tomi.htm)
(http://www.ten-f.com/tomi-no-shinpou.htm)
「神武東征の際、光のある井戸から出てきた尾を生やした国つ神」に「井氷鹿」がいたようで、水銀が関係してる?それとも雨乞い?
(http://www.zb.em-net.ne.jp/~kiokunomori/html/mukashi/shinnmei/shinnmei-11.html)
(井光神社八幡宮:http://kamnavi.jp/as/yosino/yosino8b.htm)
相模原市藤野町に「石楯尾神社」があり、「何か天地の自然現象を司り給う大歳神の御鎮座と不思議な関連がある様に思はれてならない」とあることから、御祭神「石楯尾大神」は大歳神?「菊理姫神 (幽産土神=速玉男神 事解男神)」とあるのが興味深いですね。
(http://www.kanagawa-jinja.or.jp/search_dtl.php4?jid=1087&cd=1208227&scd=&npg=0)
「時空捜査局」さんのサイトでは事解男神について、「事(コト)が逆さになって地(トコ)になり地の主の意味を含んでいる。即ちオオモノヌシの本名、天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊の国照の部分を示している。」とあったが・・・。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki14.htm)
ん?石楯尾神社の「石楯尾大神」は「石村石楯は当地の住人で高座郡の県主」で、「景行天皇の御代、日本武尊が東征の折、持ってきた天磐楯(あめのいわたて)を東国鎮護のため此処に鎮め、神武天皇を祀ったのが始まりとされる。」とあり、「藤木姫」が御祭神にありますが、詳細は書かれてないですね・・・。
(http://www.geocities.jp/engisiki/sagami/bun/sag160506-01.html)
「藤木社(瀬織津姫神)」が「上賀茂神社」にあり、「川尾社(罔象女神)」「棚尾社(豊石窓神、櫛石窓神)」「杉尾社(杉尾神)」「土師尾社(建玉依比古命)」「山尾社(大山津見神)」もあって、「本殿周囲の社名は「~尾社」というのは、何か意味があるのだろうか。」とされてますね。
(http://www.genbu.net/data/yamasiro/kamigamo_body.htm)
あと、気になった場所として「千尾の峯(熊野)」がありましたが、いずれも「スサノオ」「ニギハヤヒ」「瀬織津姫」「出雲」で繋がりそうですね。
(http://ryuso.info/n/n293_307.htm)
| ●2010.01.10(Sun.) |
昨日「尾」について検索しましたが、かつて「石上神宮」の「桃尾の滝」の「ももお」は、「とび」とも「とみ」とも読めるのではないかと思い、「トミノナガスネヒコ」すなわち「長髄彦」に繋がるのかと思ってた。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%AB%84%E5%BD%A6)
長髄彦は奈良市富雄のあたりの豪族だったという説もあったそうなので、「尾」「雄」の使われ方によって「び」とも「お」とも読むのかな、と。
で、もしそれらが物部氏やニギハヤヒと繋がるのであれば、「水尾」「当尾」「塔尾」「八尾」や、「尾」がつくお社や神名、倭直の祖「市磯長尾市」なども繋がることになるだろうし、「水尾」が「みのお」だったことから、「箕面」のように変形していった地名も繋がるのでは、と。
「阿保親王」も「あおしんのう」とも読むようだから、「保」も同様かと・・・昨日の、スサノオは「スサの尾・穂」にも繋がりそうだし。
とすると、2009.12.30分の長崎の「安保地区」も当てはまるだろうし、「日見峠」も元は「日尾」だった可能性も・・・。
あ、長崎といえば、「時空捜査局」さんのサイトで、行基ゆかりとされる「四面宮(温泉神社)」について、
| なんと建日向日豊久士比泥別命という日向神がオオクニヌシのことであることに驚愕した行基は自身が佛教者であることを超えてやむにやまれぬ思いに駆られて石祠を作ったのである。だれもが出雲出身と信じて疑うことのないオオクニヌシが雲仙で誕生していたことをその時、感じたのだった。 (http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki16.htm) |
とあり、オオクニヌシの本名は「コト(事あるいは己等と表記)」と・・・。
「古事記」によると、「次に筑紫の島を生みたまひき。この島も身一つにして面四つあり。面ごとに名あり。かれ筑紫の国を白日別といひ、豊の国を豊日別といひ、肥の国を建日向日豊久士比泥別といひ、熊曾の国を建日別といふ。」とのことだが・・・。
(http://hwm2.gyao.ne.jp/seichi/ryokou_kiroku/ryokou_970814-19.html)
「時空捜査局」さんのサイトでは、「白日別命はスサノオあるいはイタケルで豊日別命はニギハヤヒと考えられている。そして建日別命、速日別命も命名法からみれば出雲系の神々らしい。」とあった。
が、「鴨着く島」さんのサイトでは、白日別(筑紫国)は半島由来の箕子系の辰韓王を頭に戴く「大倭」で、豊日別は東海岸に亡命王権を樹立した女王トヨの国「豊国」で、建日別は熊襲の一種である「狗奴国」(肥後国)とされており、速日別は熊襲の投馬国(日向国)でニギハヤヒのようで、建日向日豊久士比泥別(肥前・筑後国)は詳しくは書かれておらず・・・。
(http://kamodoku.dee.cc/kumaso-hayato-4.html)
(http://kamodoku.dee.cc/kumaso-hayato-1.html)
また、「出雲は「天津日(アマツヒ)系」の「大倭」に九州北部で戦って敗れ、出雲地方に配流された奴国系オオクニヌシの国である。」とあって・・・。
(http://kamodoku.dee.cc/suininki-wo-yomu.html)
頭がウニ・・・。
ま、いったん置いとくとして、「時空捜査局」さんのサイトに、
| スサノオは音霊的に逆転するとオノサスではなく、ローマ字にするとsusanooであるからこれを逆転するとoonasusとなる。すなわち、大成(おおなす)ということになる。それでスサノオはよく茄子と関係づけられるのだ。 (http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki26.htm) |
とあり、茄子で思い出したのが、堺市の行基ゆかりの「開口神社」と神戸市の「網敷天満宮」で。
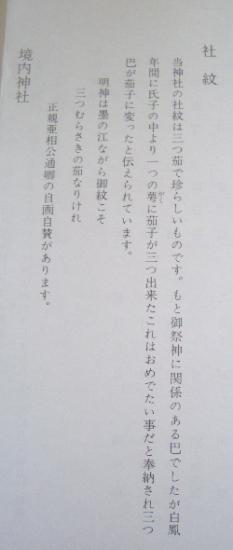
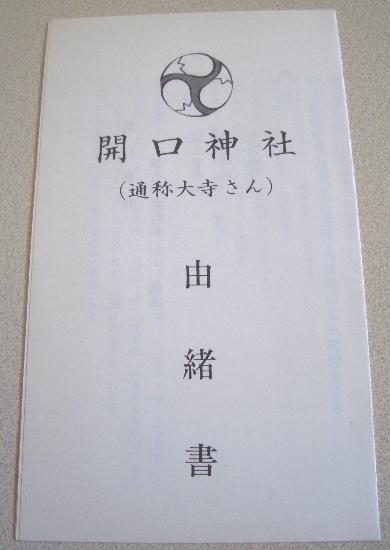

綱敷天満宮 御祭神:菅原道真公
(公式サイト:http://www.tsunashikitenmangu.or.jp/index.html)
大阪の枚方市には「茄子作」という地名があり、由来を検索すると、
| 平安時代、交野ヶ原で鷹狩をしていた惟喬親王(これたかしんのう)がかわいがっている鷹を森の茂みのなかに見失うと言うハプニングがあった。そこで鷹の足につける名鈴(なすず)を作るよう村人に命じ、この地を名鈴作村(なすずつくりむら)と名付けた故事に由来する。 (http://murata35.chicappa.jp/shuhenkaido/higasikoya04/index.htm) |
とのことで、別の意味で関連がありそうな感じもありますね、行基ゆかりのお寺の近くだし、2009.12.25分に書いた神社も近いようだし。
そうそう、昨日のを読み返してて思ったんだけど、「中秋の名月」が「芋」と繋がるなら、「鋳物師」にも繋がりそうで、「日(火)」の繋がりで日置氏とも繋がりそうな。
と思っていると、枚方市招堤南町には「日置天神社」があるようで、上記の「惟喬親王」が「日を止め置かせ給え」と天神に祈願したという伝承があるようで。
(http://www.asahi-net.or.jp/~UZ5A-FRT/god/shrn/hiokiten/hiokiten.html)
枚方市は藤原氏による社域拡大・御祭神隠しが多かったような感じがあり、南中振の「さだ神社」の御祭神が道真というのは興味深いですね。
(http://www.asahi-net.or.jp/~UZ5A-FRT/god/shrn/sada/sada.html)
(http://www12.plala.or.jp/HOUJI/otera-2/newpage1035.htm)
で、富山の小矢部市に「茄子島」という地名があるようで、「神明社」があるようだが、詳細はわからなかった・・・。
「神社」「茄子」で検索すると、埼玉県和光市の「白子諏訪神社」がヒットしたが、なぜ紋が茄子なのかは不明・・・「悪病除けの神様」とのことで、「蘇民将来」が思い出されますが、諏訪だからタケミナカタかと。
(http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5711/_5751/_5758/_5759.html)
タケミナカタは「南方刀美神」とも書きますよね・・・「トミ」がある。
「疱瘡にかかった際に霊験があり・・・」と、徳島県名西郡石井町の「多祁御奈刀弥神社」にあり、「社傳によると、信濃諏訪郡南方刀美神社は、当社から、宝亀10年(779)から移遷されたものという。」というあたり、気になりますね。
(http://www.genbu.net/data/awa2/minatomi_title.htm)
「諏訪大社上社本宮」の「諏訪大明神の秋山祭の事」にある、「我は諏訪の明神である。清水観音の指示によりお供した。」というのは、京都・清水寺と諏訪明神には繋がりがある、ということを示しているようで気になる・・・。
(http://www.genbu.net/data/sinano/hon_title.htm)
しかも、「水内」の「建御名方富命彦神別神社」が「水」であり「蛟」(蛇)で、「諏訪大社上社本宮」とあわせて「風雨」に相当し、「大和の竜田と広瀬にあてはめる見方もある。」とあった。
ならば、「建御名方富命彦神別神社」に祀られている「八坂戸賣命」は「瀬織津姫」?と思ったが、「諏訪神の御子神」とされているので、ん?と。
(http://www.genbu.net/data/sinano/hikokamiwake2_title.htm)
ただ、「水内神とも呼ばれ・・・」とあり、「持統天皇が691年に使者を遣わし、信濃の国の須波、水内などの神を祭らせ、この時犀角牙笏を奉納・・・」とある「水内神」は「戸隠神社」という説もあるそうで、祀られている地主神の「九頭龍大神」が瀬織津姫かと思われるから、両社に繋がりがあることを示しているのでは、と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E9%9A%A0%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
あ・・・「建御名方富命彦神別神社」は2社あるようで、上記のは「上水内郡信州新町」で、もう1社は飯山市大字豊田にあり、かつては「水内郡」だったようで、御祭神は健御名方富命、と。
(http://www.genbu.net/data/sinano/hikokamiwake_title.htm)
後者の「健御名方富命彦神別神社」は、「若宮八幡神社(御祭神:大鷦鷯命)の一段上に建立されている。」とあるのは興味深いですね。
(http://www.omiyasan.com/north/iiyama/post-73.php)
寄り道ついでに書きますと、「健御名方富命彦神別神」が祀られている神社として、上水内郡飯綱町「倉井神社」がヒットし、また、「長野市城山(善光寺)は建御名方の城の跡で、現在の善光寺の西の一段高いところが本丸の跡とされています。」と。
(倉井神社:http://www.tgk.janis.or.jp/~takei/kurai2.html)
(http://www1.kcn.ne.jp/~kikujo/11.html)
(横山城:http://minkara.carview.co.jp/userid/157690/spot/236852/)
あと、「善光寺北側にあった善光寺守護神・年神堂が、神仏分離により城山へ遷った際(現健御名方富命彦神別神社)に当時の年神堂本殿を、当社へ移築したもの。」とされる「守田廼神社」があった。
(http://www.genbu.net/data/sinano/moritano_title.htm)
善光寺守護神「年神堂」ってことは、やはり健御名方富命がニギハヤヒで、彦神別命が瀬織津姫ですよね・・・。
で、かつて「年神堂」のあった場所が、現在は「徳川家大奥関係の廟所」だそうで・・・行ったことがないので、位置関係や土地の高低がよくわからなくて。
(http://w1.avis.ne.jp/~wakaomi/753/index.html)
で、話を戻しますが、「白子諏訪神社」の紋は開口神社のような巴型ではなく、「多祁御奈刀弥神社」の紋「鎌の打ち合い」に似てますね。
(http://blog.goo.ne.jp/zeiss1221/d/20090101)
富山の小矢部市に「茄子島」という地名があるようで、「神明社」という神社があるようだが、詳細はわからなかった。
「茄子は駒込の名産だったそうだ。」と、文京区の「富士神社」にあり、「一富士二鷹三茄子」って、瀬織津姫(富士・コノハナサクヤヒメ)や、スサノオ(茄子)を表してるのかも?と思い、上記の惟喬親王にも絡んでいる「鷹」は「ニギハヤヒ」かな、と。
(http://members.jcom.home.ne.jp/nobish/826fuji.html)
ちなみに、「惟喬親王」についてウィキペディアから引用させていただくと、
| 文徳天皇の第一皇子。母は紀名虎の娘・更衣紀静子。別名小野宮。同母妹に恬子内親王がいる。 父・文徳天皇は皇太子として第四皇子である惟仁親王(後の清和天皇)を立てた後、惟喬親王にも惟仁親王が「長壮(成人)」に達するまで皇位を継承させようとしたが、藤原良房の反対を危惧した源信の諫言により実現できなかったといわれている(『吏部王記』承平元年9月4日条)。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%9F%E5%96%AC%E8%A6%AA%E7%8E%8B) |
とのことで、惟喬親王ゆかりの神社等を書いておきます。
| 惟喬神社:http://blogs.yahoo.co.jp/hiropi1600/48596155.html
玄武神社:http://www5e.biglobe.ne.jp/~hidesan/genbu-jinjya.htm 富士神社・守谷神社:http://www.kamimoude.org/jinjya/kyoto-city/sakyou/sa-fuji/index.html 大皇神社:http://www.kirari1000.com/www.kirari1000.com.base_data.base_data.phpQkirari_cd=00936.html 粟辻神社:http://nekonomiiko.web.fc2.com/kyoto_g057.html 小椋神社:http://ogurajinja.org/Site/yuisyo.html 御殿山神社:http://keihan.ensen.net/retoronatabi/gotenyamajinja/gotenyamajinja.html 巨椋神社:http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/midori/cultureagri/treasure/kyoto/kyoto021.html 惟喬親王の離宮舊跡(水無瀬神宮):http://kamnavi.jp/en/settu/minase.htm 惟喬親王の御陵墓:http://www3.zero.ad.jp/gennbu/koretaka.html 山中漆器と惟喬親王:http://bunkashisan.ne.jp/search/ViewContent.php?from=14&ContentID=162 紀伊神社:http://kamnavi.jp/it/musasi/odakii.htm |
業平との繋がりがあったことや、「漆器」と繋がるあたりに、秦氏・物部氏など行基プロジェクトに関わったであろう氏族と、何らかの繋がりがあったような感じがしますね。
余談:上記のを入力し終えたあと、ご飯食べながらテレビを見てると、長野での野沢菜を収穫する様子が写っていて、野沢菜のルーツは「天王寺蕪」と言われてて。
検索すると、「宝暦6年(1756)、野沢の名刹健命寺の第8代目の住職晃天瑞大和尚は京都に遊学しておりました。そこで手に入れたのが天王寺蕪の種子。」で、蕪は育たなかったけど、葉を漬物にしたようで。
(http://www.localinfo.nagano-idc.com/mikaku/nozawana/index.html)
「健命寺」は永禄11年(1568年)の創立だそうで、そう古くはないようだけど、橘紋で御本尊が薬師如来、四天王寺との繋がりから、長野と天王寺の繋がりは連綿と続いていたのではないだろうか、と。
(http://www.kenmeiji.or.jp/)
野沢菜の畑が写ったあと、野菜を洗っている風景が写り、それが「麻釜(おがま)」というのを見て、そうかぁ!と・・・「麻績」は「おみ」と読み、「麻」といえば物部氏!
(麻釜源泉:http://www.rieko.org/onsen/02shimota/nozawa/ogama.html)
| ●2010.01.12(Tue.) |
10日にまず気になったのが「鷹」で、「時空捜査局」さんのサイトに応神天皇が「八幡神」になった時のこととして、
| 応神の「応」ではわからないが本字の「應」ならばわかる。スサノオの鳥としてのシンボルは烏(からす)であるが、ニギハヤヒの鳥としてのシンボルは「黄金の鷹」なのである。「鷹」を解字すれば隹(ふるとり)の鳥である。それはもちろんニギハヤヒの幼名、布留の鳥に由来する。「應」の文字は隹の心なのだ。すなわち「應神」とはフルトリの心の神という名前であった。ニギハヤヒはその名前に隠れて働いていたのである。名前に「雅」や「雄」のように隹の部首を持つ者はニギハヤヒの魂を継いでいる可能性がある。 (http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki10.htm) |
とあり、なるほど、と思いつつ、その下に行基ゆかりの「長弓寺」の創建譚として、「聖武天皇が鷹狩をしていた時に現れた鳥を射落すと黄金の鷹と化し、佛法守護を誓ったので、行基に十一面観音を祀らせ、長弓寺を創建したという。」とあって。
そのあと、「ここではニギハヤヒは鷹から十一面観音に転生しているのだ。」とされているあたり、かつて読んだ本と同じだが、「十一面観音」は瀬織津姫なのでは、と・・・。
で、「鷹」といえば「四天王寺」に、「聖徳太子が白い鷹になってこの悪鳥を追い払うことになったという」と、悪鳥の「啄木鳥」を太子が「白い鷹」となって追い払ったという伝承があるようで。
(http://www.bell.jp/pancho/k_diary-2/2008_04_29.htm)
「啄木鳥」が気になるところだが、太子が「鷹」になったというあたり、ニギハヤヒとの繋がりを表しているように思えて。
書かれているサイトにあるように、そもそも四天王寺は別の場所にあり、それは兵庫の中山寺とも共通し、場所を移すことによって「守屋」を滅ぼしたという御縁起を加えたように思えたりもするわけで。
あれ?たしか「四天王寺」建立の候補地って、豊里大橋の方だったような・・・。
あ、「聖徳太子が四天王寺建立の候補地に挙げたことから、天王寺庄という地名が付けられていました。」とありますね、かつて行基が「高瀬大橋」を架けたと伝えられている場所の近くで、西に行くと「隼人」がいたと思われる「大隅」があって。
(http://www.osaka-asobo.jp/image-cms/toyosatoeguchi.pdf)
そうか・・・「隼人」って「隼」(はやぶさ)で、「タカ目ハヤブサ科ハヤブサ属」で・・・「啄木鳥」は「キツツキ目はブッポウソウ目と近縁」だとか。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%84%E6%9C%A8%E9%B3%A5)
ということは、「四天王寺の白い鷹」の伝承は、改竄されていることに気づくように、というメッセージだったのかも。
| 『日本書紀』の十七条憲法の第二条「驚く三宝を敬へ、三宝とは仏法僧なり」は、『旧事大成経』では実は一七条目にくるものとして、「十七に曰く、篤く三法を敬へ、三法とは儒仏神なり」と記して、儒仏神の三教一致を教えている。確かに、「三宝とは仏法僧なり」では、あまりに佛教偏重にみえる。『日本書紀』編纂時に佛教庇護者のなんらかの操作があったような気がするほどだ。 (http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki06.htm) |
「仏法僧」とすることによって、太子の仏教色を濃くさせて、廃仏派としての守屋を作り上げ、対立があったと、もっともらしくさせようとしたのかも・・・。
ま、「啄木鳥」が「ブッポウソウ目と近縁」とわかったのがいつなのか、伝承がいつ頃からのものなのか、にもよるが。
だが、身内擁護のために太子の名を利用し、移転させた中山寺や四天王寺に祀らせ、御由緒・御縁起に守屋討伐の記載を強要したのは、やりすぎだったんじゃないだろうか・・・。
(http://kamnavi.jp/mn/kinki/nitiyoubi.htm)
その「守屋」だが、「守屋はツキヨミ(ニギハヤヒ)に供える萩に自らをなぞらえていたのだ。」とあり、長浜市の「波久奴神社」は、
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki43.htm)
| 用明二年七月、物部守屋は河内で蘇我馬子らと対決して敗れたが、そのとき家臣の漆部巨坂という者が守屋に代わって激闘のすえ戦死。その間に守屋は巨坂の弟の小坂を伴って当地へ落ちのび、草庵を結んで定住し、自らを萩生翁と称して土地の人々に読み書きや農業技術を教えるなど恩恵を施した。守屋の死後、人々は彼を萩野大明神として崇敬し、これが当社のはじまりである ― というような創建伝説で知られます。 (http://mononobe.nobody.jp/tabi/hakunu/hakunu.html) |
とのことで、「漆部氏」との繋がりが見える伝承があり、ニギハヤヒ・瀬織津姫ともに藤原氏に隠されてしまったようで。
(http://otd3.jbbs.livedoor.jp/246945/bbs_tree?base=558&range=20)
長浜市といえば先日、「 お客様の会社の近くに『平方(ひらかた)』っていうところがあるらしいわ。『高月』もあるらしいから、大阪と似た地名があるんやな。」と言ってて、詳細は省略しますが、たしかに大阪の枚方・高槻と湖北との繋がりや、行基プロジェクト関連の氏族が、そこここに見えるようで。
お客様の会社の近くに『平方(ひらかた)』っていうところがあるらしいわ。『高月』もあるらしいから、大阪と似た地名があるんやな。」と言ってて、詳細は省略しますが、たしかに大阪の枚方・高槻と湖北との繋がりや、行基プロジェクト関連の氏族が、そこここに見えるようで。
で、「萩」といえば、行基が勅命により開いたとされる豊中市南桜塚の「仏日山 東光院(萩の寺)」や、行基ゆかりの「萩原寺」が「神仏の聖地」として栄えたという堺市の「萩原天神」、2001/05/27分で書いた諸兄の裔「橘為仲」が、「宮城野萩を土産に持ち帰った」という「つま恋」にまつわる故事を思い出し、いずれもニギハヤヒに繋がりそうで。
(http://tsumagoi.net/)
2001/05/27分にもあるように、「萩」については芭蕉も絡んでいて、「ひとつやに遊女も寝たり萩と月」があり、「遊女」絡みでは上記の「大隈」の近くに「江口」があり、西行が絡んでいて、その下地に謡曲「山姥」が見えるようで。
(http://homepage2.nifty.com/melkappa/classic-bashouYUUJYO-1.htm)
(謡曲・山姥:http://www.harusan1925.net/0720.html)
「江口」はかつて住んでた東淀川区で、行基ゆかりとされる大東市の「野崎観音(福聚山慈眼寺)」に、「江口之君堂」があって。

また「宮城野の萩茂りあひて、秋の景色思ひやらるゝ」が詠まれたあたりは、「陸奥国分寺跡」の近くと思われ、行基プロジェクトが垣間見られるような。
(http://www.bashouan.com/Database/Kikou/Okunohosomichi_20.htm#ds20_05)
「宮城野は萩の名所として知られ、中秋の名月の頃に咲き誇る。」というのは、芭蕉の「月に名を包みかねてや痘瘡の神」を思い出し、やはり芭蕉はよく知っていたようだな、と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%A9%E3%81%AE%E6%9C%88#.E5.95.86.E5.93.81.E5.90.8D.E3.81.AE.E7.94.B1.E6.9D.A5)
あ、仙台市宮城野区の「青麻神社」は、「社伝によれば、第五十五代文徳天皇の御世の仁寿二年(西暦八五二年)、現社家の遠祖穂積保昌が山城国(現京都府)よりこの地に来たり、里人に麻の栽培を教え、且、一族の尊崇せる日月星の三光神即ち天照大御神・天之御中主神・月読神の三神を清水湧く山峡の岩窟中に奉祀せしが本杜の創始と伝え・・・」と、2007.04.12分で書いており、穂積氏は物部氏ですね。
で、芭蕉は「白露もこぼさぬ萩のうねりかな」を「採茶庵」で詠んだそうで、現在の江東区だそうで。
(http://moroeya.co.jp/archives/19)
(http://shasinnavi.com/01j41108saichaan.htm)
その句の句碑が巣鴨の「真性寺」にあるそうで、「駒込」と同じ「豊島区」なんですね。「目白不動尊」も豊島区で、「トヨ」との繋がりがありそうで。
(http://www.aitaii.com/shigei/tokyoKosatu/tosimaku/tosima.html)
横道にそれますが、会社の研修で一週間缶詰になったのが、池袋駅近くのビジネスホテルで、そういえばオーナーの祖先は「近江商人」だったなぁ、と・・・その次に勤めた会社のオーナーは、日本名が「長富氏」で下の名前が「○守」で、みょ~なご縁で。
話を戻しますが、「時空捜査局」さんのサイトに「馬(KOMA)はもちろんアナグラムすれば賀茂(KAMO)であり・・・」とされていて、芭蕉の句碑のあるのが「巣鴨」ということで、テリトリーだったことが伺えるような。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki68.htm)
で、「江戸の目白不動尊は武蔵野の天神様と交流がありました。」と、埼玉県所沢市の「北野天神社」がヒットし、「縁起では、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征で武蔵国へ渡られたとき、櫛玉饒速日命(くしたまにぎはやひのみこと=物部氏の氏神)、八千矛命(やちほこのみこと)を祀り、物部天神社と国渭地祇神社(くにいちぎじんじゃ)と称した。」とあった。
(北野天神社 江戸出開帳:http://www.asahi-net.or.jp/~hm9k-ajm/musasinorekisi/gosikifudoutomusasino/mejirofudou/kitanotennjinndekaityou/kitanotennjinnsyadekaityou.htm)
「所沢」と言えば、池袋に研修に行った会社の本拠地とも言える場所で繋がりが見え、湖北でライオンのマークのついたバスが走ってるのを見た時、しみじみとそれを感じました、はい。
で、所沢に「十三塚」があったようですが、大阪の「十三」や青森の「十三湊」など、「十三」は「トミ」と読まれてたのでは、と。
(http://www.asahi-net.or.jp/~ab9t-ymh/kakuchi/tokorozawa01/yamaguchi.html)
で、「トミ」についてですが、「守屋を射落とした」とされるのが「迹見赤檮(トミノイチイ)」で、「物部氏の一族で鳥美物部の伴造氏族とする説もある」ともされており、「波久奴神社」の伝承も含めて考えると、やはりウラがあると思うんですよね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B9%E8%A6%8B%E8%B5%A4%E6%AA%AE)
賀茂氏、大伴氏、蘇我氏、春日氏(和珥氏)、巨勢氏、阿部氏、橘氏ら以上に「物部氏」を歴史から消したかったようで、そのための寺院移設・御縁起の改竄などの大々的手段を取ったように思え、道真の左遷にもそのあたりが絡んでいそうで。
それらの氏族の社域などを奪取し、御祭神を変えて・・・ゆえに、秦氏・紀氏・東漢氏などを含めて、「行基プロジェクト」が活動するようになったように思えて。
「五大夫」の武渟川別(阿倍臣)・彦国葺(和珥臣)・大鹿嶋(中臣連)・武日(大伴連)・物部氏のうち、残っている「中臣氏」の勢力拡大の様子を見てそう思ったのだが、その「中臣氏」も名前が残ってはいるが、不比等に乗っ取られたのでは、と。
(http://kamodoku.dee.cc/suininki-wo-yomu.html)
あと、「長髄彦」が「登美能那賀須泥毘古」とも「登美毘古」ともされていることと、出雲神族の末裔が「富氏」とされていることが繋がりそうで、「天穂日命」も繋がるのかも、と。
「勾玉は祖先の幸魂、和魂、奇魂、荒魂を表し、王家のみがつけることを許された。」ので、「とはずがたり」での「二条」は「勾玉」をつけていたのかも、とも。
(http://www.enjoy.ne.jp/~hisasi/5-10.htm)
それにしても・・・「ツクヨミ」を数字にすると「2943」で、読み方を変えれば「憎しみ」って・・・考えすぎかなぁ。
| ●2010.01.13(Wed.) |
中途半端にしか調べられなかったんで、中途半端にしか書けなくて申し訳ないんですが・・・。
「隹」の字が気になったので検索してみると、
| 同じくトリの姿を描いた象形文字であるが、尾の短いとりを描いたもの。 尾が短くて、小柄でずんぐりと太ったトリのこと。 ずんぐりと太いの意を含み、雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、 鳥とともに、広く、トリを意味することばになった。 (http://1st.geocities.jp/ica7ea/kanji/tori.html) |
とあり、ほぉ~っと見ていたけど、それよりもその上に書かれてた「蔦」が、「長々と垂れる植物だから、草かんむりをつけて「草+鳥」という字形で表したのである」の方が気になってて。
さらにその下にあった「酉」が、「酒をしぼるツボの象形」ということに、やはりニギハヤヒに繋がるのかな、と。
で、「時空捜査局」さんのサイトに、
| 「隹」(ふるとり)音スイ、サイ、セ (一)とり、尾の短い鳥の総称、ふふどり、きじばと。 (二)山の高大なさま。=崔 文字を構成するときは、鳥に関する字の意味で用いる。 「鳥(尾の長いとり)」「酉(ひよみのとり)」と区別して、 「舊(旧ふるい)の字中に隹があるので、ふるとりと称する。 (大修館、新漢和辞典) この隹(ふるとり)の解字を見ると 宝珠の形の頭が乗っかった尻尾の短い、翼をもった鳥である。 この骨組みは竜のものであるのかもしれない。 見る人のイメージ化の力によって大きく見方が異なるだろう。 「舊(旧ふるい)の字中に隹があるというヒントで「舊」の字の項を調べる。 「舊」の文字はクサカンムリに隹(ふるとり)を臼で支えている。 饒速日尊(ニギハヤヒ)のことが記述されている「先代舊事本紀」も 舊の字が使用されていたが今は旧の字で代用されることが多い。 そのために舊の字を眼にする機会が減って、その意味を知ろうとする人もなくなった。 クサカンムリと臼に挟まれた隹(ふるとり)。 どうしてこれでフルいの意になるのか。 それにはどんな意味が込められているのだろう。 (http://homepage1.nifty.com/fumio-y/honoo0054.htm) |
とあり、ここで浮かんだのが、太子ゆかりの「斑鳩」と、善光が「臼」に阿弥陀如来を安置したことで。
「斑鳩」は「まだらばと」と思われ、「きじばと」に繋がりそうだし、クサカンムリは覆い隠すという意味もあるようなので、草に覆い隠されて臼の上に坐す「善光寺如来」が「舊」ということは、「隹」の新しい形として「善光寺如来」が伝わったことを意味するのかも、と。
「斑鳩」について調べてると綾部市がヒットし、「もと何鹿郡(いかるがぐん)」で、太子による草創という「光明寺」があって。
(http://www.ayabun.net/gaiyo/sikinai.html)
(http://club-ayabe.ciao.jp/clubayabe-cont-histo.html)
さらに、上延町の「東光院」が「法隆寺」と呼ばれていたことや、「境内を流れる谷川は富緒川」といわれたことが書かれていて、「かつては奈良の都と深いつながりがあったのではないか」と、そのサイトに書かれているのに頷いてて。
(http://www.satoyama.gr.jp/mt/weekly/2008/04/vol-5.html)
で、「富雄川」で検索すると「いかるがの 富の小川の絶えばこそ わが大君の 御名忘られめ」の歌が書かれていて、「大君」というのはニギハヤヒなのではないかと思われ、物部氏による縁で太子は斑鳩の地に移ったのでは、と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E9%9B%84%E5%B7%9D)
ウィキペディアで「富雄川」の流れる「学園前」を見ると、関連項目に「ニギハヤヒ」があり、上記の歌も書かれてますね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%89%8D_(%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%B8%82))
ちなみに堺市東区にもかつて「登美丘町」があって、現在も学校名に残ってたりしますが、こちらは公募で決まった名だから、「大鳥大社」近辺の「富蔵」の方が古いようで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E7%BE%8E%E4%B8%98%E7%94%BA)
で、「臼」を調べると、
| とくに、長野の善光寺の本尊が初め臼の上に安置されたという『善光寺縁起』の説話は有名だが、神奈川県厚木の厚木神社や江の島の八坂神社(江島(えのしま)神社内)の神輿(みこし)も臼の上に休息するという。また、石川県能登(のと)半島輪島の市神(いちがみ)、市姫様には、大きな石臼が御神体として祀(まつ)られている。さらに、正月行事でも、歳神(としがみ)を迎える祭壇として臼が使用され、これに鏡餅(かがみもち)や若水を供え、正月2日の仕事始めに、臼をおこして餅を搗いたりする習俗は、ほぼ全国各地にみられる。他方、収穫時における十日夜(とおかんや)(10月10日)や11月の初丑(はつうし)の日などにも、臼を祭壇に使用する習俗が行われている。これらはいずれも臼を清浄なものとし、神聖視しているからであろう。 こうした臼に対する考え方は、さらに進んで、なにか特別な呪力(じゅりょく)を秘めた道具と意識されるようになっていった (http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%87%BC/) |
とあり、やはり瀬織津姫やニギハヤヒに繋がりそうな感じで。
(江島神社:http://www.enoshimajinja.or.jp/gosaijin/gosaijin.html)
と、ここまでしか調べられなくて・・・すみません・・・。
| ●2010.01.14(Thu.) |
一昨日、「守屋はツキヨミ(ニギハヤヒ)に供える萩に自らをなぞらえていたのだ。」とあったことから、「仏日山 東光院(萩の寺)」や「萩原寺」、橘為仲の「つま恋」にまつわる故事を「いずれもニギハヤヒに繋がりそうで」と書いたけど、本当にそうなのか?と。
「十一面観音」が「ニギハヤヒ」とされているのと同様に、「瀬織津姫」と混同してしまってるのではないか、と。
「天穂日命」が女性だったのではないかと思ったのが、「萩原天神」で祀られているからだし、「萩の寺」に至っては、元は「豊崎」にあったことや、御本尊が「十一面観音」だから「瀬織津姫」と思ってて。
「つま恋」の故事は「鹿」の鳴き声を聞いて、とのことだから、ひょっとしたらニギハヤヒかもしれないけど、恋しく思う「妻」は瀬織津姫なのでは・・・。
「萩の寺」の御本尊が「萩まつりの祭神である道了大権現」とあったので検索すると、「天正18年豊太閤、小田原の陣中にて両翼脱落の奇瑞を示した霊像を当山に勧請。」とあり、写真もあった。
(http://www.haginotera.or.jp/doryo.html)
うーん、翼のない迦楼羅?不動明王?天狗?
翼のない迦楼羅とは堕天使?悪魔?いや、悪魔にも翼はあるが、「悪魔の頭のアを洗い流してしまうとクマになる。クマは神の元の語、クマから転訛して神となった。」とされる「時空捜査局」さんのサイトに繋がる?「サタン」は人間の敵ではあっても神の僕で。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/honoo0024.htm)
迦楼羅はヴィシュヌの乗り物だが、白狐に乗ってるということは「稲荷神」と思われ、それが「荼枳尼天」であれば女神だが・・・。
(荼枳尼天:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%BC%E6%9E%B3%E5%B0%BC%E5%A4%A9)
それとも「三神一体」を表現したかったのか、「鳥」であるが迦楼羅は蛇・竜など「ナーガ族」と敵対関係にあったが、翼を取ってその関係にないことを表したかったのか・・・。
(三神一体:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%A5%9E%E4%B8%80%E4%BD%93)
だとすると、「道了大権現」が「ヴィシュヌ」ならニギハヤヒと思われ、御本尊の「十一面観音」が「ラクシュミー」で瀬織津姫かと。
(ラクシュミー:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9F%E3%83%BC)
でも、「十一面観音」は「瀬織津姫」と思われるし、「道了大権現」が「荼枳尼天」であれば「瀬織津姫」かと。
かつて「仏日山 東光院(萩の寺)」のホームページはなかったので知らなかったけど、家康も絡んでいたようで、現在の造幣局近くに造営された「川崎東照宮」は明治維新後に廃社になったそうだが、
| 廃社直前に当院に遷座されていたことが判明した。現地蔵堂が東照宮本地堂「瑠璃殿」であり、その際文書類と一緒に発見された薬師如来が御本地仏であることがわかったのである。 (http://www.haginotera.or.jp/index3.html) |
とのことで、関係者は行基が瀬織津姫を祀ったのを知っていて、廃社直前に萩の寺に遷座したのではないかと。
で、「あごなし地蔵尊像」が歯の病気に苦しむ人のために「小野篁」が刻んだ像を壱岐から遷座されたというのも、何やら因縁めいたものを感じますね、小野氏も行基プロジェクトに関わっていたと思われるので。
「明治43年、阪急電車の前身にあたる箕面有馬電気軌道が開業」されたことにより移転されたそうで、当時歌われた「箕面有馬電車唱歌」が書かれてますが、同じく梅田の太融寺の近くから移転した空海ゆかりの「不動寺」、「萩の寺」とわりと近いんですよね。
「不動寺」は小高いところにありますが、その麓あたりに「春日神社」(御祭神:天照皇大神・天児屋根命・建御雷大神)があり、いずれも瀬織津姫やニギハヤヒに繋がりそうで、阪急さんはそれらをご存知で誘致されたのかなと思ったりもするわけで・・・。
「萩の寺」は豊中市南桜塚にありますが、「桜塚の地名の由来」として、
| 原田神社沿いの桜塚碑(石碑)には桜塚古墳がこの場所にあったと書かれている。 この桜塚古墳が地名の由来になったといわれているが、一方で隣接する荒神塚古墳が本来の桜塚であったとする見方もある。 荒神塚古墳は、直径約30mの円墳とみられ、頂上には祠が祭られていた。 大正11年(1922年)頃、墳丘を破壊する最中に頂上から巨大な桜の根が発見された。 現在はスーパーの室内駐輪場となっている。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%A1%9A%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4_(%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C)) |
とあり、「荒神塚古墳」の名称も、「荒神塚古墳」の頂上の「祠」や「桜」も、瀬織津姫に繋がりそうで。
余談になりますが、先日書いてた枚方市の近くの寝屋川市に「太秦」地区があり、「桜ヶ丘」という地名があるので、秦氏のテリトリーと瀬織津姫を表しているようで。
で、かつてあった「讃良郡」は、「持統天皇の名「 野讃良」の「讃良」は讃良郡に由来するものである。」とあり、持統天皇の養育に携わったと思われる「婆羅羅馬飼造」と秦氏との関連が気になるところで。
野讃良」の「讃良」は讃良郡に由来するものである。」とあり、持統天皇の養育に携わったと思われる「婆羅羅馬飼造」と秦氏との関連が気になるところで。
(http://wiki.wowkorea.jp/?word=%E8%AE%83%E8%89%AF%E9%83%A1)
(http://www5.ocn.ne.jp/~asukahis/sararagun.html)
繋がりがあったとすれば、御祭神隠しや改竄・日本書紀の構築は、不比等らが謀って持統天皇を傀儡にしての断行かと。
そうそう、「地名辞典」によると、「豊嶋郡」というのが今の箕面市稲のあたりにあったようで、「豊嶋郡に秦上郡・秦下郡があることから、池田の秦野には伽耶系秦氏の居留が考えられる。」とあり、猪名川沿いから箕面にかけて、多くの秦氏が居住していたようで。
(http://homepage2.nifty.com/mino-sigaku/page193.html)
上記URLに「牧」のことも書かれているので、「讃良郡」と秦氏との関連はやはりあるんじゃないかと思われるわけで。
また、「カヤ」で思い出すのは競争馬の「カノヤ○○」という名前で、鹿児島の「鹿屋」で育ったおんまさんたちで、「鹿屋」は「大隈半島」ということで隼人に繋がるかと。
そうなると、上記URLにも「時空捜査局」さんのサイトにもあった「カヤナルミ」が気になるわけで・・・。
| ●2010.01.15(Fri.) |
昨日、「カヤナルミが気になるわけで・・・」と書きつつも、「鹿屋」から「鹿屋野比売」を連想してて、2009.08.23分で風琳堂さんのブログを拝見して「鹿屋野比売すなわち瀬織津姫なんだな・・・」と書いたのは覚えてた。
(樽前山神社:http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo)
いや、いつ書いたかまでは覚えてなかったけど、書いた内容は覚えてまして・・・だから「津秦天満宮」の「野槌社」にもお参りしたいなと思いつつ、なかなか実現できずにいたりしますが。
で、「カヤナルミ」が「阿陀加夜努志多伎吉比売」で、以前風琳堂さんのサイトで、「阿陀加夜努志多伎吉比売」が「瀬織津姫」で、出雲の「御井神社」の「木俣神」「水神の祖」とも繋がるのを拝見してて。
(http://otd13.jbbs.livedoor.jp/1000045011/bbs_plain)
昨日拝見したサイトに、「かや」と読める字として「賀陽」「高陽」が含まれており、行基ゆかりの伊丹の「昆陽寺」も、ひょっとしたら「かや」だったのかも、と。
「カヤナルミ」の検索で拝見した「飛鳥川上坐宇須多伎比賣命神社」に、宇須多伎比売命、神功皇后、応神天皇が祀られており、「臼瀧姫(=下照姫命) 『五郡神社記』」とあり、「臼瀧姫」も瀬織津姫かと。
(http://www.genbu.net/data/yamato/usutaki_title.htm)
「臼」は「ウズ」で瀬織津姫を表しているようで、だから善光寺如来は「臼」の上に安置され、「舊」はクサカンムリに隠されたニギハヤヒと瀬織津姫で、新しい形として善光寺如来が麻績に運ばれたのかも、と。
だが、「カヤナルミ」と「磯城県主葉江」の関連について書かれていたあたりで、ちと頭が混乱してまして・・・。
(http://www.dai3gen.net/kayanrm2.htm)
カヤナルミ=磯城県主葉江=弟磯城「黒速」(磯城県主)=瀬織津姫、ということになりそうだが、加夜奈留美命=高照姫命、臼瀧姫=下照姫命、高照姫命=下照姫命=瀬織津姫?事代主の妹?と。
ウィキペディア「鴨都波神社」から抜粋すると、
| 「鴨都波神社」 積羽八重事代主命(事代主)と下照姫命を主祭神とし、建御名方命を配祀する。 葛城氏・鴨氏によって祀られた神社 事代主の妹である高照姫命が祀られていたのが下照姫命と混同されたとする説もある。 社伝によれば、崇神天皇の時代、勅命により太田田根子の孫の大賀茂都美命が創建した。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B4%A8%E9%83%BD%E6%B3%A2%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
とあり、同族による祭祀かと思われ、太田田根子の孫「大賀茂都美命」の「都美」が「トミ」とも読めるように思われ、繋がりを示すのかな、と。
(スサノオ-大己貴命-事代主命-天日方奇日方命----阿田賀田須命-大田田根子命)
事代主の子は天日方奇日方命で、鴨主命で三輪君・鴨君の遠祖とされていて、天日方奇日方命の妹が「姫鞴五十鈴姫」で神武の皇后とあるが、
| ・長髄彦は事代主神(飛鳥大神)の子で、磯城の三輪氏一族の族長 ・建御名方命=長髄彦 (http://shushen.hp.infoseek.co.jp/keihu/nagasune/nagasune1.htm) |
ならば、建御名方命=長髄彦=天日方奇日方命かと・・・。
奈良県高市郡明日香村の「飛鳥坐神社」は、
| 延喜式神名帳には「飛鳥坐神社四座」とある。 現在の祭神は事代主神、高皇産靈神、飛鳥神奈備三日女神(賀夜奈流美乃御魂)、大物主神の四座であるが、多くの異説がある。 『大神分身類社鈔』 -- 事代主命・高照光姫命・木俣命・建御名方命 『五郡神社記』 -- 大己貴命・飛鳥三日女神・味鋤高彦神・事代主神 『社家縁起』 -- 事代主命・高照光姫命・建御名方命・下照姫命 『出雲國造神賀詞』 -- 「賀夜奈流美乃御魂乃飛鳥乃神奈備爾坐天(賀夜奈流美の御魂の飛鳥の神奈備に坐て)」との記述がある。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E5%9D%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
とあり、ん?と。
事代主は「都美波八重事代主命」とも表記されるようで、「都美波」には「トミ」「ミワ」の両方を名乗っているようで、すなわち両家を受け継いだ人物ともとれるように思われ、それがウマシマジだとしたら、ナガスネヒコがその子というのはおかしいな、と。
ま、ナガスネヒコもオオクニヌシと同様に個人名じゃないなら、ありうるかもと思うが・・・はい、頭がウニです・・・。
| ●2010.01.16(Sat.) |
昨日、「土産」と「産土」について少し検索してて、「土産」は「宮笥」が語源とする説が有力だそうだが、「土笥」(ハニハコ)が絡んでいそうで、「産土」の語源とされる「産砂」も、「砂」は「主名」だったのかも、と。
「時空捜査局」さんのサイトの「伊雑宮事件」に、「舊事大成経」の序文が書かれていて、「祖神土笥」が「磐余彦天皇(神武天皇)の時、豊天當命・天種子命が、神魂と称して土笥を本祠に安置したものです」とあり、宮の土笥が「宮笥」になり、「土産」となったように思えて。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki06.htm)
ん?「天種子命」は「天押雲命」の子のようだが、「豊天當命」は「天富命」?もしそうなら、「天日鷲命の妹・天比理乃咩命と天太玉命の子が天櫛耳命で、その子が天富命」で、「豊天當命」が「天羽富命」なら「倭文連祖」で天日鷲命の三男と、2008.11.08分に書いてあるが・・・。
また、「伊雑宮」について、「この南伊勢の志摩の砂(主名)は、地主神、伊射波登美命だった。」とあり、宮に坐す地主神を表す際、「宮笥」が「土産」となったことに関連して「産」の字が用いられるようになったのでは、と。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/honoo0081.htm)
「吉備真備が唐から持ち帰った土を埋めてそこに祠を建てたことに始まると伝えられている。」という尼崎の「吉備彦神社」は、そういう意味合いがあるように思われ、「本殿は井戸状の穴の上に据えられており、穴をのぞくと砂になっている。」とのことで、瀬織津姫が浮かんでくるわけで。
ま、いずれも推測の域を出ませんが・・・。
で、なぜ「伊雑宮」を改めてしらべようと思ったかについてですが、ML西行辞典vol・105が届き、伊勢に関する歌が載っており、気になることがいくつかありまして。
「不思議なことに、伊勢在住時代の伊勢の歌が極端に乏しいのです。」とあり、西行は実際に祀られている様子を見て、詠めなかったんじゃないか、と。
「神ろぎの宮」のご説明に女神なら「神ろみ」とあり、「ただしこの歌の場合は女神ではあるけれども主祭神としての天照大神を指していて、天照大神の居る宮ということになります。」とあって。
天照大神は男神のニギハヤヒだと西行は知ったようですね。
神宮の正殿の屋根を「杉」としていることや、その原木を「いけはぎに」としていることについて、「(いけはぎ)は大祓えの儀式における祝詞の文言にあるようです。」とあるのは、隠されている神・ニギハヤヒと瀬織津姫を表そうとしてたのでは、と。
(六月晦大祓祝詞:http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%85%AD%E6%9C%88%E6%99%A6%E5%A4%A7%E7%A5%93%E7%A5%9D%E8%A9%9E)
(岩波文庫山家集261P聞書集261番) 千木を高く構え、大神の神殿の屋根を葺いたよ。杉の原木の皮をはいで。 (和歌文学大系21から抜粋) |
と、MLの最後に書かれていて。
「時空捜査局」さんのサイトでも、「伊勢神宮の真の祭神は天照大神なのか豊受大神なのかどうも判然としない。」とあり、それは2006.01.19分に書いた、酒造りで「櫂入れ」の時に歌われた唄にも「どちら 本社と おがむやら・・・」とありましたね。
(http://homepage1.nifty.com/fumio-y/honoo0081.htm)
「伊雑宮」の相殿神が、玉柱屋姫命(=伊佐波登美神)で「登美」があり、トミヒコの妹「登美夜毘売」(三炊屋姫)で、「玉柱屋姫命(神)は「郷」に在るときの名、瀬織津姫神は「河」に在るときの名」と、「伊雑宮の御師・西岡家」に伝わる文書にあるそうで。
(伊雑宮:http://www.genbu.net/data/sima/izawa_title.htm)
また、狭依毘売命=市杵嶋姫命で、市杵嶋姫命は弁財天と習合することが多く、瀬織津姫のことで、兵庫県佐用郡「佐用都比売神社」の「佐用姫伝説」は関連がありそうで。
(佐用都比売神社:http://www.norichan.jp/jinja/renai2/sayotuhime.htm)
もとは海に浮かぶ岩礁の上に祀られていたという、赤穂市の「伊和都比売神社」は、「元々は豊受比売であるとも、また播磨国一宮である伊和坐大名持御魂神社(現在の伊和神社)の神(大穴牟遅神)の比売神とも言われる。」とあり、関連がありそうな感じはするものの不比等の影が見え隠れしてて、どうなのかな・・・と。
(伊和都比売神社:http://www.genbu.net/data/harima/iwatu_title.htm)
「景行天皇四十年(西暦111)十月、日本武尊、伊勢神宮の荒祭宮である礒宮を此の地へ移祀したと伝えられる」とされる、茨城県桜川市の「桜川磯部稲村神社」は、謡曲「桜川」のふるさととされていて、瀬織津姫に繋がるようで。
(桜川磯部稲村神社:http://www.genbu.net/data/hitati/isobe_title.htm)
(謡曲「桜川」:http://www.harusan1925.net/0204.html)
「桜川磯部稲村神社」の「後水尾天皇」の勅額の「礒部大明神」が、豊岡市出石町の「石部神社」(主祭神:天日方奇日方命)の拝殿の扁額と同じ意味ならば興味深いですね。
(石部神社:http://www.genbu.net/data/tajima/isobe_title.htm)
「石部神社」の御祭神の「瀧津彦命」とは?御所市の「高鴨神社」や、南丹市美山町の「滝神社」にも祀られてますが・・・。
(高鴨神社:http://www5.kcn.ne.jp/~takakamo/keidai.html)
(滝神社:http://tanbarakuichi.sakura.ne.jp/nantan/tree/kodama09.html)
「桜川磯部稲村神社」を奉祭したのが「磯部氏」だとすると「佐々木党」と繋がることや、「石部神社」を崇敬した小出家が信濃に、仙石家が美濃に繋がるあたりは興味深く、石川県小松市の「石部神社」の御祭神が天日方奇日方命だが、「加賀國式内等舊記」などには「大物主神」とあるのも気になりますね。
(磯部氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%AF%E9%83%A8%E6%B0%8F)
(小出家:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%87%BA%E6%B0%8F)
(仙石家:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E7%9F%B3%E5%AE%B6)
(小松市・石部神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%83%A8%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
なお、「伊雑宮事件」や瀬織津姫については、風琳堂さんのサイト「千時千一夜 ──瀬織津姫&円空情報館」に詳しく書かれてますので、ご一読いただければ、と。(http://otd3.jbbs.livedoor.jp/246945/bbs_tree?base=546&range=1)
上記URLに「円空の伊勢神宮の祭祀に対する認識がもっともよく表れている歌を読んでみよう。」と、円空の歌が書かれていた。
円空は西行の歌を目にしたのだろうか・・・。
| ●2010.01.19(Tue.) |
検索しようと思ってたことはあったが、寝る前に頭の中に浮かんでたのが「和珥氏」で、「日本書紀」で真っ先に消された氏族かな、と。
そこで「武埴安彦」を討ったという和邇の祖先「彦国葺命」と、「忍熊皇子」の反乱軍を討伐し、「両面宿儺」を退治したとされる和珥氏の祖「建振熊命」(彦国葺命の孫)が気になって。
(和珥氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%8F%A5%E6%B0%8F)
「ペンは剣より強し。」で、「乱」がどこまで本当にあったことなのか、討ったとされる氏族が本当にその人たちなのか、「日本書紀」の成立前に氏族の消滅があった場合、わかりかねるように思われ、そこに改竄があったように思えて。
ただ、そのカラクリは検索では見出せず、解けずにいますが・・・。
で、一昨日お参りした「布忍神社」で、御祭神:速須佐男之尊、八重事代主之尊、建甕槌雄之尊とあったのが気になり、再度「建甕槌雄之尊」を調べてみようかな、と。
「布忍神社」社記によると、「祭神の素戔鳴命を同社の北18町(2km)に鎮座する天美の氏神である阿麻美許曽神社から、白布を敷いて現在地へ迎えたので、社名を布忍、村名を向井とよぶようになった」とあるが、「阿麻美許曾神社」の御祭神は、スサノオ、事代主命、天児屋根命で、違う神で「春日神」が絡んでるのが気になる。
(http://www.dai3gen.net/nunosi.htm)
事代主命は別として、「白布を敷いて現在地へ迎えた」スサノオが、春日神とともに祀られるのはどういうことなのか?と。
「建甕槌雄之尊」は、「布都御魂」(または佐士布都神、甕布都神)を神格化したものとあるが、「先代旧事本紀では、経津主神の神魂の刀が布都御魂であるとしている」とあること、そして「建御雷之男神と経津主神が同じ神であるように書かれている。」ことなど、「後に中臣氏が擡頭するにつれて、その祭神である建御雷神にその神格が奪われたものと考えられている。」とされている通りなのでは、と。
(経津主神:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%84%E3%83%8C%E3%82%B7)
和珥氏に代わって物部氏が「石上神宮」を奉祭したのを快く思わず、中臣氏は和珥氏に従った氏族だったのだからと「フツヌシ」から「建甕槌雄之尊」を描き出し、調整役として「建葉槌命」を懐柔(?)し、「建甕槌雄之尊」を祀るかたわらで「フツヌシ」を乗っ取っていった、という筋書きにしたのでは・・・。
(http://abekawamoti.at.webry.info/200507/article_2.html)
「布留はスサノオの御子・大歳尊(以下、オオトシ・改名してニギハヤヒ)で、布都斯はスサノオ、布都はスサノオの父で、いずれもこれは蒙古名という。」とあり、「建甕槌雄之尊」が「フツヌシ」でスサノオの父ならば、一緒に祀られることに納得できるが。
(http://www2t.biglobe.ne.jp/~cherimo/history/susano/jinja_susano.html)
奈良・田原本町富本に「富都神社」があり、タケミカヅチ、登美屋彦命、登美屋比売命が祀られていて興味深いですね。
(http://www.d3.dion.ne.jp/~stan/txt0/n1ft01.htm)
登美屋彦命はナガスネヒコ、登美屋比売命はその妹の三炊屋媛で、スサノオの父が一緒に祀られているということは、同族だったことを表しているのかも、と。
また、奈良市石木町の「登彌神社」では、東殿に高皇産霊神、誉田別命、西殿に神皇産霊神、登美饒速日命、天児屋根命が祀られており、同族で祀られているとしたら、中臣氏が「春日神」としてニギハヤヒ系を祀らないことに疑問が生じるわけで、天児屋根命を祖神とした中臣氏はニセモノであった、あるいは乗っ取られたと考えざるをえないような。
(http://www.kamnavi.jp/mn/nara/tomi1.htm)
「皇紀2年、神武天皇がこの地に於いて皇祖天神を祭祀されたのがそもそもの淵源」という由緒をもち、「木島明神と呼ばれていた」のなら、スサノオを祀ってないのはなぜ?という疑問も。
(木島坐天照御魂神社:http://kamnavi.jp/mn/kinki/konosima.htm)
「鹿島神宮」は、「常陸国風土記では、神代の時代に神八井耳命の血を引く肥国造の一族だった多氏が上総国に上陸、開拓を行いながら常陸国に勢力を伸ばし、氏神として建立された」のを起源とされているようで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E5%AE%AE)
「多氏」もまた和珥氏との繋がりが見えるようで、御祭神を取り上げられた和珥氏と、取り上げられなかった物部氏の扱いの違いが、「日本書紀」に顕著に出ているような。
(http://shushen.hp.infoseek.co.jp/keihu/sizokugairan/oho1g.htm)
それは、重要な神を「仏」として置き換えて祀った太子や蘇我氏に対しても見られるようで。
さて、昨日検索を考えてた事柄の残りとして、義弟の実姉が現在鹿児島県いちき串木野市に住んでいて、合併前の住所が「日置郡市来町」ということで気になりまして。
日置氏やイチキシマヒメが出てくるかと思いきや、近隣の神社等もあまり検索で出てこず、代わりにというのも何ですが、「徐福」のことで上記の蘇我氏と繋がって。
「冠岳」には、「蘇我馬子が勅願所として建てた熊野三所権現のひとつ」とされる「岳神社」(御祭神:櫛御気野命(素佐之男命))や、「この地の鎮守として信仰されてきた阿弥陀如来、薬師如来、千手観音を本地仏とする冠岳三山(東岳・中岳・西岳)を守る熊野権現を祀る」という「熊野権現堂」があるようで。
(http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kushikino/kushikino03/kushikino24.htm)
(冠岳マップ:http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kushikino/kushikino03/kushikino29.htm)
「徐福の別名は徐市(じょふつ)で,(市来町は)「徐市が来た町」という意味があるようです。」とあり、「市」が「フツ」というあたりが気になりますね。
(http://www.asukanet.gr.jp/tobira/jofuku/jofuku.htm)
(http://www.syamashita.net/history/johuku/kanmuridake_hozen.html)
丹後の「雄嶋」も「冠嶋」というようで、「籠名神宮祝部丹波国造海部直等氏之本記」に「火明命佐手依姫命を娶りて穂屋姫命を生みます佐手依姫命は亦名市杵嶋姫命亦名息津嶋姫命亦日子郎女神なり」とあり、「男嶋女嶋」に祀られているのが、「彦火明命と日子郎女神」とのことで、ニギハヤヒと市杵嶋姫(瀬織津姫)のようで。
(http://www.geocities.jp/k_saito_site/bunkn13.html)
それがいちき串木野市の「冠島」との繋がりといえるかどうか、というところですが、「市」が同じというのは偶然ではないように思われるわけで、和歌山県新宮市では「丹敷戸畔」、山梨県富士吉田市では「コノハナサクヤヒメ」というように、「男嶋女嶋」も、徐福との関連性を持ちつつ祀られているのでは、と・・・。
(http://homepage2.nifty.com/kodaishinto/page006.html)
ということで、「布都」というスサノオの父と、別名「徐市(じょふつ)」という「徐福」との関連やいかに?神奈備さんの掲示板に、「新羅の原号をソ(徐)と言う」と、金達寿氏は書かれている、とありましたが・・・。
(http://jofuku-net.com/modules/bbs/)
(http://ucgi.kamnavi.net/cgi-bin/kambbs.cgi)
| ●2010.01.20(Wed.) |
「東海の神々をひらく」を一応読み終え、付箋を貼った中でも気になった箇所を検索してみようかと、まず三重県多気郡の「佐那神社」(主祭神:天手力男命、配祀:曙立王命)を再度調べてみた。
「古い文献により、吉野朝以降、室町時代、江戸時代初期に至まで神宮、特に外宮とは深い係わりを次のように保有していた。」とあり、
| ・神宮の宮造使によって、20年に一度の社殿造り替えに預かった12社中の一社であったこと。 ・斎宮の祈年祭に預かれる神社であったこと。 ・外宮禰宜の労社として、祝の制を定め、神田を設け、毎年2月神事が行われていたこと。 (http://www.geocities.jp/engishiki01/ise/bun/is080202-01.html) |
とのことで、「曙立王命」は佐那造の祖、「大俣王」の子、開化天皇の皇子である「彦坐王」の孫であり、伊勢の「品遅部」の祖でもあるようで。
(http://www.yuukitei.com/archives/category/uncategorized)
(http://kamnavi.jp/en/mie/sana.htm)
「曙立王は明立天之御影命」と言われていて、「谷川健一著『青銅の神の足跡』には「明立天之御影命=天目一箇命のゆえに天目一箇命を祖神として奉斎する人々の群れ」があったとしています。佐那神社は天目一箇命を祭神とした神社であることが分かります。」とあった。
(http://www.hpmix.com/home/uraura/C12_1.htm)
「天目一箇命」は「多度大社」の御祭神で、天津彦根神の御子神・伊勢忌部氏の祖神、境内社「美御前社」の御祭神が市杵島姫命で「天津彦根神の御妹神」とあるから、「天津彦根神」はナガスネヒコ?
「天津彦根命」が「天照大御神の御子神」とあって、ん?と・・・天目一箇命は金山彦であり、金屋子神であり、瀬織津姫だったような・・・。
で、「佐那神社は里宮で金剛座寺が神体山ではないかといわれています。」とあり、「金剛座寺」の公式サイトのトップページには、「昔より菩提の樹それながら出し佛の影ぞ残れる」という西行の歌があった。
(http://www.renge.net/kongozaji_frame.htm)
| 『金剛座寺略縁起』によると讃岐の四国八十六番札所 志度寺の別当寺として十一面観音をご本尊としておりましたが、持統七年(693)頃に不比等公が、内妻の菩提寺とすべく行基菩薩刻彫の如意輪観音を志度寺から遷座し、行基菩薩開眼のうえ本尊にしたと伝えられております。 |
と、御縁起を見てビックリしましたよ、行基の名があり、志度寺のことも書かれてて・・・不比等も絡んでるとは、というか、行基の名を使って改竄したな、と。
「房前に伴って志度浦に来て、寺名を「死度寺」から「志度寺」に改めた」のは693年のこととされていて、同じ年に「志度寺」から金剛座寺に遷したことになりますよね?ありえないでしょ、それって。
このあたり一帯は鉱物との関連が強いようで、その地を奪取するための改竄・・・あ、行基が房前と志度寺へ行ったこと自体、作られたものかも。房前の母は魚沼市の「雲洞庵縁起」に出てきますし。
(http://www.untouan.com/category/1253380.html)
「金剛座寺」の御縁起にある「近長谷寺」は、2007.05.09分に書いたように飯高宿禰諸氏が建立したお寺で、「多気郡勢和村丹生から産出する「水銀」で富を築き上げたといわれて」いる豪族で。
(http://f18.aaa.livedoor.jp/~ogino/matusaka/index.htm)
「大和の穴師坐兵主神社」との関連が考えられるとされているようで、当初はそうだったかもしれないが、のちに乗っ取られた・・・が、それがバレないよう、あるいは新たな乗っ取りの礎として、系譜に繋がりがあるように見せかけたのでは。
ただ、行基の背後には秦氏らのプロジェクトがいて、行基を不比等が動かせるのは不可能と思われ、遷座も行基による開眼法要もないと思うし、不比等にはまだそういう力もない頃では?房前12歳だし?と、「歴史」を拝見して思った。
(http://www.renge.net/kongozaji-history.htm)
西行が歌を詠んだとされる953年にはまだ西行は生まれてないし、鎌足の死後に建立は無理でしょ・・・って、行基が絡むとムキになってしまったりして。(苦笑)
そうそう、西行といえば「東海の神々をひらく」に、西行が垂水成就寺に参拝した時、「さるちごとみるより早く木にのぼり」と上の句を詠むと、「犬のやうなる法師来れば」と、境内の桜の木に登った子(お寺の御本尊の大日如来が化けた)が下の句を詠んだ、という「名所図会」の話が載ってました。
(http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Cafe/1154/nature/k65.htm)
「東海の神々をひらく」でもう1つ気になったのが「サエノカミ」で、「兄妹婚したあわれな二人を祭るといった伝承を伴っている」というあたりが気になって。
(http://www.tabiken.com/history/doc/I/I013C200.HTM)
ここでまた「泉鏡花」がヒットし、「高野聖」にはそのあたりが描かれているようで。
(http://blog.goo.ne.jp/masamasa_1961/e/3ee7b6ed21f53d776e48be41609c033b)
「兄妹の結婚」というのは各国の神話でも出てきて、日本でもイザナギとイザナミや「衣通姫伝説」などがあり、衣通姫が「稚日女」(下照姫)という説もあるようで、気になりますね。
(衣通姫:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A3%E9%80%9A%E5%A7%AB)
(稚日女尊:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%9A%E6%97%A5%E5%A5%B3%E5%B0%8A)
また、「古代には、新羅で王族間の通婚が行われていた他、前漢でも恵帝が同母姉・魯元公主の娘である張氏を、武帝が父の同母姉・館陶公主の娘である陳氏を皇后としていた例がある」とのことで、さらに気になったがそれ以上は探せなくて。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A6%AA%E5%A9%9A)
旧立山街道には「星にかかわる道祖神」があるようで。
(http://tulip.web.infoseek.co.jp/sekibutu/sekibutu11.htm)
秋田に「市之助とみの星」という民話があり、道祖神と「みの星」が出てきて、「雄物川」のほとりにある村里、というあたりに何かありそうだけど、これもここまでしかわからなくて・・・。
(http://www.city.akita.akita.jp/city/yuwa/salon/m05.htm)
猿田彦が「賽の神」とされることもありますが、、道祖神=猿田彦+天鈿女という推測をされたブログがあり、京都の「塞ノ神ライン」を探っておられることや、伝承にあるという「それぞれ自分にあう人を探しに行った挙句、結局兄弟で交わることになる」というのも、2009.12.19分の「大若子命」の軍にいたというサルタヒコの後裔の話に近いようで興味深いなと。
(http://blog.goo.ne.jp/penpentaro/e/e0b738fa17afb7c0f88a7f210073eac2)
(http://www.overcube.com/blog/archives/2006/10/post_564.php)
(http://pc-qqbox.com/kodaishi/abiko5.htm)
そういえば、サルタヒコは「佐羅皇子」で、「佐那、佐那武」という別名を持っている。」とのことで、「佐那神社」に繋がりそうな。サルタヒコは「天手力男命」という説もあったし。
(http://hakusan1.jugem.jp/?month=200909)
道祖神の仲間(?)に「柴神」「柴折神」などがあるようで、「柴は炭の原木の意と思われ、産鉄地周辺にシバ地名が多く見られます」とあり、「佐那神社」の「曙立王は明立天之御影命(天目一箇命)」で繋がりますね。
(路傍の神々:http://www.genbu.net/tisiki/robou.htm)
(岡山県内の製鉄たたら地名:http://www.hpmix.com/home/uraura/C8_1.htm)
2009.12.01分で書いた、阿保親王(垂仁天皇の皇子・息速別命)と鉄が繋がるようだけど、その場所って近いのかな?息速別命を祀る「大村神社」も、乗っ取られたような形跡がありますが・・・。
(初期比企氏の系図:http://shushen.hp.infoseek.co.jp/keijiban/hiki1.htm)
(大村神社:http://www.genbu.net/data/iga/oomura_title.htm)
うーん、息速別命の母・薊瓊入媛を検索したところ、垂仁天皇が丹波道主王(彦坐王の子で開化天皇の孫)の娘5人を、「神の嫁」の資格を持つものとしてヨメにしたようだが、そのウラには「鉄」があったのでは、と。いや、瀬織津姫かも。
(http://www.yume-jinja.net/original/contents/venus.php?mode=detail&id=115)
「男浅津間若子宿禰」の「浅津」は「薊瓊」で、「天皇の系譜が「循環している」(月宿に依拠する)」とあり、おもしろいな、と。
(http://www.platz.jp/~hvhy/keifu/k029.html)
薊瓊入媛らの祖母・息長水依比売娘は「天之御影神」の子のようだが、「天之御影神」は天津彦根命の子で「天目一箇命」と同神とされていて・・・。
あ、大俣王と丹波道主王は腹違いの兄弟で、曙立王命は大俣王の子だから丹波道主王の甥になるが、曙立王命=天之御影命で息長水依比売の父だから、丹波道主王の祖父?で、大俣王が天津彦根命?ナガスネヒコ?
(丹波道主王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E9%81%93%E4%B8%BB%E7%8E%8B)
(御上神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%B8%8A%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
大俣王の母が「山代之荏名津比売」で、大俣王の腹違いの兄弟に「山代之大筒木真若王」(母は袁祁都比売命・和邇氏)(神功皇后の曽祖父)がいるが、関連はあるのだろうか・・・頭がウニ。
(山代之大筒木真若王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%BB%A3%E4%B9%8B%E5%A4%A7%E7%AD%92%E6%9C%A8%E7%9C%9F%E8%8B%A5%E7%8E%8B)
(息長氏:http://homepage2.nifty.com/amanokuni/okinaga.htm)
ただ、上記サイト「息長氏」でリンクされていたページに、「剣神社の伝承の通り忍熊王が生きていたとすれば、海人族同士の争いはなかったことになり、ここにも記紀のマジックが隠されているように思う。」とされていて同感だな、と。
(忍熊王http://homepage2.nifty.com/amanokuni/kibi.htm#oshikuma)
ん?先日の「産土」の「土」が「砂」で、「主名」かもって書いたけど、「砂鉄」も関係してたりして・・・砂(鉄)の産まれるところが「産土」の地?それを携えて行くから「土産」になったとか?
「土師氏」はそういう地を見つけるのも職務の1つにあったから、「菅原氏」になったとか?
なーんて寄り道したりして・・・ま、それはしょっちゅうだが。
あと、「東海の神々をひらく」に「本居宣長」「賀茂真淵」「荷田春満」などが出てきたが、「泉鏡花」同様、著書を拝見しないとわからないだろうなと思われ、どうしようかな、と・・・。
「菅の根の長見の浜の春の日にむれたつ鶴(たづ)のゆたに見えけり」という賀茂真淵の歌、意味深な感じがしますね。
(http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mabuti.html)
上記分で鉱物関係を調べてて、「菅」は「砂鉄」の集まりやすいところって読んだばかりで、参考歌として書かれている藤原俊光の歌にもそういう感じがあって。
(岡山県内の製鉄たたら地名:http://www.hpmix.com/home/uraura/C8_1.htm)
「を鹿なく岡辺の萩にうらぶれていにけむ君をいつとか待たん」や「信濃なるすがの荒野を飛ぶ鷲のつばさもたわに吹く嵐かな」、「倭文子をかなしめる歌」なども興味深いですね・・・。
荷田春満の「いひしらぬ神代の春の面かげを見せてかすむや天のかぐ山」や、本居宣長の「咲きにほふ春のさくらの花見ては荒らぶる神もあらじとぞ思ふ」「敷島のやまと心を人とはば朝日ににほふ山ざくら花」なども、ですね。
(http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/azumamaro.html)
(http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/norinaga_m.html)
| ●2010.01.21(Thu.) |
泉北丘陵は窯跡が見つかったことでご存知の方も多いと思われますが、一昨日の「菅の生える所には砂鉄が多いという説があります。」と書かれていたサイトを拝見してから、やはり行ってみるべきだなと、美原区菅生の「菅生神社」に行きまして。
意識して町名を見ていると、金山があり、福田があって、いずれも「製鉄地名」と思われ、福田に「愛宕神社」を見つけた時、地図にはなかったので行きは通りすぎてしまい、帰りに数台前のバスが止まった時に、駐車スペースがないので車内から写真だけ撮りまして。
火の宮とも言われる「野々宮神社」から「菅生神社」まで約6kmで、西から東へとほぼまっすぐ行ったわけだが、阪和道の「平井」の少し北には北垣外(きたがいと)という地名があり、南に陶器川が流れていてその東約2.5kmのところに「陶荒田神社」があって、その1kmちょい北が福田で、さらに福田の1kmちょい北が登美丘(校名でしか残ってない)で。
さすが「陶邑窯跡群」と呼ばれる日本最大の須恵器の生産遺跡のあったことを再認識した、という感じで。
大美野(この南にも登美丘の名のついた学校がある)を通り、南海高野線の北野田駅を越え、一旦大阪狭山市に入り、途中からまた堺市に入って間隔の狭い信号の間に鳥居があり、しばらくして神社が見えて。
「なんでもアルバム」に写真とファイルを追加しましたが、境内社や行くまでの地名を見てて、中臣氏が古くからいたとは思えないんですよね、ナガスネヒコは祀らない一族だし、持って行った地図には「菅生神社」ではなく「余部神社」で載ってて。
で、推測するに、中臣氏が昔からいたとしたら「中臣勝海」か「中臣金」以前の人たちで、いたという形跡を辿って中臣氏を乗っ取った人たちが大勢乗り込んできて、鉱物資源を自分たちのものにしたのでは、と。
その事実を知った神宮寺・高松山天門寺の社僧が道真を勧請し、歪みを正そうとして「天満宮発祥地」を言い出したのでは・・・。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E7%94%9F%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E5%A0%BA%E5%B8%82))
検索によると、岡崎市康生町の「菅生神社」に、
| 合殿 菅生天神社(菅原道真公) 第九十一代伏見天皇正応二年(1289)河内国丹南郡菅生より満性寺の開基了専上人岡崎の菅生天神を祀る (http://www.wa.commufa.jp/~aaioi/page021.html) |
とあり、香川県三豊郡山本町の「菅生神社」は、
| 菅生八幡宮と福生八幡宮の2社からなり、菅生八幡宮、邇々杵命、天種子命、天押雲命、福生八幡宮は品陀和気命、息長帯媛命、依比女命をそれぞれ祭神とする。そのため両八幡宮ともいう。
社伝によれば、嘉禄2年香西資村が河内国菅生神(菅生神社、大阪府南河内郡美原町)の神託により勧進したのが菅生八幡宮で、当地に鎮座する以前に仮殿を造営した場所が雁渡宮(観音寺市古川町)だという。 また福生八幡宮は天福元年に豊前国宇佐から八幡神を勧進したのが創祀だといわれている。いずれも鎌倉期の勧請社伝はいうが、付近には古墳も多く、土地の人々の信奉する神はすでに祀られていたと考えられる。 |
とのことで、な~んかありそうな感じがするんですよね・・・。
で、岡山県倉敷市祐安の「菅生神社」に、
| 「祐安」の地は、元来、須計奈須の里といい、「菅生」の菅(スゲ)生(ナス)の転訛したものという。 (http://www.genbu.net/data/bicchuu/sugo_title.htm) |
とあり、メインは「スサノオ」と、産土神の「姫大神」(瀬織津姫)のように思われ、美原区の「菅生神社」は「余部神社」が元社だったように思われて。
「1334年(建武元年)と1341年(暦応4年)に兵火に罹い、神社の起源についての記録が残っていないが・・・」とのことで、中臣氏がいたことと「新撰姓氏録」によって御由緒を作ったのでは、と。
(http://www12.plala.or.jp/HOUJI/jinja-1/newpage257.htm)
まだ検証はしてないけど、「仲村神社」「酒屋神社(屯倉神社)」「中臣須牟地神社」などが、同様の手口で乗っ取られたように思われて。
(仲村神社:http://kamnavi.jp/en/kawati/nakamura.htm)
(酒屋神社と神への造酒:http://www.city.matsubara.osaka.jp/10,112,51,258.html)
(中臣須牟地神社:http://kamnavi.jp/mn/osaka/sumuchi2.htm)
そういえば、先日枚方市でもそういうのが見られ、いつ頃書いたか忘れましたが、埼玉でもありましたね・・・。
(2007.04.24分・高山不動:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E4%B8%8D%E5%8B%95%E5%B0%8A)
こちらも伝承が曖昧で、行基の名も「志度寺」の時と同じく、利用されたのかも。
| ●2010.01.22(Fri.) |
火曜にML「西行辞典 第106号」が届き、「天王寺」の歌や渡月橋近くの「亀山」の歌など、いろいろ気になる歌があり、「加茂・賀茂」の歌でかつての疑問が復活(?)しまして。
| そのかみこころざしつかうまつりけるならひに、世をのがれて後も、賀茂に参りける、年たかくなりて四國のかた修行しけるに、又帰りまゐらぬこともやとて、仁和二年十月十日の夜まゐりて幤まゐらせけり。 内へもまゐらぬことなれば、たなうの社にとりつぎてまゐらせ給へとて、こころざしけるに、木間の月ほのぼのと常よりも神さび、あはれにおぼえてよみける (岩波文庫山家集198P雑歌・新潮1095番・西行上人集・山家心中集・ 玉葉集・万代集・閑月集・拾遺風体集・夫木抄・西行物語) (05番歌の詞書と歌の解釈) この詞書によって四国旅行に出発した時の西行の年齢が分かります。旅立ちに際して上賀茂社に参詣したのですが、「又帰りまゐらぬこともやとて」とあるように、自分で大変な旅になるかも知れないという覚悟があったことがわかります。 「たなうの社」は現在は楼門の中の本殿の前にあるのですが、詞書から類推すると西行の時代は本殿と棚尾社は離れていたのかもしれません。僧侶の身では本殿の神前までは入られないから、幣を神前に奉納してくれるように、棚尾社に取り次いでもらったということです。 四国行脚へ出かける自分はいつまたお参りできることか、 もしかしたら出来ないのではと思うと。 (新潮日本古典集成山家集から抜粋) |
長く引用させていただきましたが、「棚尾社」の御祭神は豊石窓・櫛石窓の二神で、いくつか別名があり、親子関係などの系図がいまいちよくわからなくて、それが解ければ何かわかるかも、と思ったんだけど・・・。
「とんでもニャ~2-6」の2008.11.01分から数日書いていて、それらを図にしてみると、
| 天太玉命(天櫛玉命?)-天石門別神-天津羽々命-?-天児屋根命 | +天櫛耳命-天富命------------------------- | | +天比理乃咩命 | | | +天日鷲命+大麻彦命-由布津主命(別名「阿八別彦命」)-娘 |(阿波国板野郡の式内・大麻比古神社のご祭神・孫?) +天白羽鳥命(伊勢麻続連(神麻続氏)祖) +天羽富命(倭文連祖) |
・天石戸別命=豊石窓命、櫛石窓命=手力雄命(天太玉命の御子)=伊斯許理度売命=石凝姥命
・大宮売命=天鈿女命(天太玉命の御女)
・天八坂彦命=長白羽神(弟が「健葉槌命」)
・天羽富命=健葉槌命=火結神(火之夜藝速男神・火之炫毘古神・火之迦具土神、軻遇突智、火産霊)
2008.11.18(宝賀寿男氏の説より)
●大物主命(櫛甕玉命)の子が事代主命(玉櫛彦命)で、その子が天日方奇日方命
●天日方奇日方命=櫛御方命=鴨主命(弟磯城、黒速、磯城県主、三輪君・鴨君の遠祖)
●経津主神=天鳥船神=天之夷鳥命(武日照神)=天御影命=天目一箇命=天太玉命=櫛明玉命=天明玉命=高良玉垂神
●天日鷲翔矢命(天日鷲命)=少彦名神=陶津耳命(葛城国造の祖)
●出雲建子命=ニギハヤヒ=伊勢都彦(?)
ということになるようだが、「手力雄命」はサルタヒコと思われ、上の図からだと「天鈿女命」とは兄妹あるいは姉弟ということになりそうで。
天鳥船神はアメノホヒの子で、経津主神と同じならば「国譲り」に矛盾がありそうだし、中臣氏の神となるのはおかしいなと思うし、手力雄命・サルタヒコも天鳥船神となるようだが、天太玉命とは親子なのでは、と。
(土師神社:http://www.norichan.jp/jinja/benkyou/haji.htm)
(香取神宮:http://www.genbu.net/data/simofusa/katori_title.htm)
アメノホヒの兄弟に「天津彦根命」がいて、その子が「天目一箇命」「天之御影神」となっていたから、天鳥船神はアメノホヒの甥になりますよね。
(http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-25.html)
あと、読み方は異なるが、アメノホヒの別名に「阿菩大神(アホノオホカミ)」があり、阿保親王(垂仁天皇の皇子・息速別命)との繋がりが気になるが・・・。
(出雲国造伝統略:http://www.remus.dti.ne.jp/~n-makoto/izushinto/dentouryaku1.html)
埼玉の「氷川神社」では、
| 社殿の脇にまつられてゐる門客人社は、今はてなづち、あしなづちの神をまつるといふが、江戸時代には豊石窓・櫛石窓の二神をまつり、古くは荒脛巾神社といった(新編武蔵国風土記稿)。主祭神を守護する土地の神のことらしい。 (http://nire.main.jp/rouman/fudoki/14sait23.htm) |
とあり、「可美真手命の子の日賢安良彦(ひさかあらひこ)命が東国へ下って物部(もののべ)の姓を名告り、氷川社をまつったといふ」とのことで、豊石窓・櫛石窓は物部氏に関する神なのでは、と。
「アラハバキ神」で思い出すのは瀬織津姫・ニギハヤヒで、だからこそ西行は「仁和二年十月十日の夜まゐりて幤まゐらせけり」だったのでは、と。
うーん、今回もまた頭がウニ・・・。
| ●2010.01.23(Sat.) |
昨日の夕刊の1面に、「銅鏡 主役交代?」という見出しがあり、「桜井茶臼山古墳から大型内行花文鏡の破片が出土したことにより、「最高級の鏡」とされた「三角縁神獣鏡」がBクラス向けで、今まで注目度の低かった「大型内行花文鏡」に脚光をあてる説が浮上した、とのことで。
(http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/100122/acd1001221252002-n2.htm)
「所在地の地名を冠して外山茶臼山古墳(とびちゃうすやまこふん)ともいう。」というあたり、気になりますね・・・あ、「鳥見山」の近くのようで、「土地では饒速日の命、あるいは長髄彦の墓と伝えられている。」のとことで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E8%8C%B6%E8%87%BC%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E5%A2%B3)
(http://www.kashikoken.jp/from-site/2002/chausuyama.html)
(http://www.begin.or.jp/~munakata/tyausuyama.html)
「競馬発祥の地」ということで、「日向の駒」との関連がありそうな。
で、やはりここにも中臣氏が乗っ取りに行ったみたいですね・・・。
そうそう、一昨日の朝刊には、「葛城氏勢力示す 巨大な祭祀施設」という見出しがあり、御所市の「秋津遺跡」の古墳時代前期(4世紀)の集落跡から「板塀跡」が見つかり、「形状から心合寺山古墳(大阪府八尾市)などで出土した祭祀場をかたどった埴輪のモデルになったとみられ・・・」とあった。
(http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2010012000122&genre=M2&area=N10)
「同遺跡の南西約1キロには葛城氏の始祖襲津彦の墓といわれる宮山古墳(5世紀前半)がある。」とのことで、興味深いですね。
御所市は「賀茂建角身命」が天降った地で、そこから山城の岡田の賀茂に至ったわけで、賀茂建角身命(賀茂別雷命?)がニギハヤヒという説もあって。
(http://www.geocities.jp/mb1527/N3-15-2tousen.html)
京都の木津川市の「馬場南遺跡」(奈良時代中期~後期)からは、「水にかかわる祭祀跡」が見つかってて。
(http://osaka.yomiuri.co.jp/inishie/news/ois90812a.htm)
「心合寺山古墳」は、古墳時代中期(5世紀前半)に造られた前方後円墳で、出土した埴輪は「八尾市立歴史民族資料館」で展示されているようで。

物部氏の本拠地でありながら、古墳名の「心合寺」は秦氏の氏寺「秦興寺」からのようだし、「服部川」があったりして、物部氏・秦氏・葛城氏と「桜井茶臼山古墳」との関連も気になるところで。
それらを繋ぐのはニギハヤヒやナガスネヒコと思われ、瀬織津姫がその中心におられるかと・・・瀬織津姫のための「水の祭祀」かと・・・。
2010.01.15分で「カヤナルミ=磯城県主葉江=弟磯城「黒速」(磯城県主)=瀬織津姫、ということになりそうだが・・・」「建御名方命=長髄彦=天日方奇日方命かと・・・」と書いてて、昨日の分と照らし合わせると、さらに頭がウニになった。
「長髄彦」という名の中に「瀬織津姫」も含まれるとしたなら、「少彦名神」と繋がるかもしれないが、あとはどうでしょうね・・・。
「建比奈鳥命の子・建予斯味(たけよしみ)命が、出雲国より入間郡に遷られた。その地を吉見といふ。予斯味命は、牟刺(武蔵)国造の始である。」というのも興味深いですね。
(http://nire.main.jp/rouman/fudoki/14sait13.htm)
で、「武蔵七党のうちの丹党の支流」に「阿保氏」がいて、「可美郡阿保郷」を本拠地としていたそうで、何かありそうな。
(http://nire.main.jp/rouman/fudoki/14sait01.htm)
「宣化天皇」の領地が「河内国丹比郡」にあることから、「宣化天皇」の子「上殖葉皇子」の孫である「多治比彦王」が「多治比氏」を名乗り、その後裔が「丹党」で、そこから派生した一族のようで、松原市に「阿保」の地名があることなどから繋がりそうですね。
(http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-21.html)
で、「多治比彦王」の子「多治比嶋」の娘「阿伎良女」が「大中臣意美麿」の妻となっており、「多治比嶋」の弟「三宅麿」が伊豆に配流されたことにより、「阿伎良女」が「大中臣意美麿」の妻であるのを利用し、埼玉方面の「三宅麿」の領地を乗っ取ったのでは・・・。
(http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-21.html)
で、「建予斯味命」を検索してみたが他では出てこず、「武蔵国造」では、
| 祖先 建比良鳥命。出雲国造・遠淡国造・上菟上国造・下菟上国造・伊自牟国造などと同系。成務朝に二井之宇迦諸忍之神狭命の10世孫の兄多毛比命が无邪志国造に任じられたという。 氏族 丈部氏、のち武蔵氏。姓は直だが、のち宿禰。一族として笠原氏・物部氏・大伴氏・檜隈舎人氏などがある。 本拠 武蔵氏・大伴氏は武蔵国足立郡(東京都足立区と埼玉県東南部)。 笠原氏は武蔵国埼玉郡笠原郷(埼玉県鴻巣市)。 物部氏は武蔵国入間郡(埼玉県入間市・川越市・狭山市・所沢市・富士見市・ふじみ野市など)。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A0%E9%82%AA%E5%BF%97%E5%9B%BD%E9%80%A0) |
とあり、系図では建比良鳥命の子は「櫛瓊命」(伊佐我神)と「出雲建子命」となっているようだが・・・。
(http://www.harimaya.com/o_kamon1/seisi/syake/s_izumo.html)
(http://www.remus.dti.ne.jp/~n-makoto/izushinto/dentouryaku1.html)
(http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/02/021/02119.htm)
「櫛瓊命」「伊佐我神」「出雲建子命」を同一人物とするサイトもあった。
(http://www.geocities.jp/mb1527/N3-15-1tousen5.html)
はて・・・。
| ●2010.01.24(Sun.) |
昨日「阿保」の地名を検索してみまして。
伊賀市と松原市は先日調べたし、秩父市も昨日少し書いたので、初めて知った「徳島県名西郡神山町鬼籠野字阿保坂)」と「兵庫県姫路市四郷町阿保」を検索してみた。
姫路市の方は、駅からだと姫路城とは反対の方向のようで、「阿保神社」や「大歳神社」が地図にあったが、御祭神や御由緒について書かれたサイトがなく、気になった場所としては「6~7世紀の横穴式石室を持つ」という「阿保古墳群」(百穴)かな、と。
(http://minokofungun.net/home/kohunroad/map_zentai.html)
だが、仁寿山の北麓にあって、「元禄時代以前は野阿保村」だったということと、「阿保遺跡は弥生期から室町期までの複合遺跡。奈良期から平安初期の掘っ立て柱建物跡が見つかっている。」というくらいしかわからず・・・あ、「阿保国王神社」などが山中にあるようだが。
(http://himejitimei.seesaa.net/archives/200703-1.html)
(http://www.kobe-np.co.jp/chiiki/hi/0000052385.shtml)
(http://bansyu.com/0506umi/umi.htm)
で、「徳島県名西郡神山町鬼籠野(おろの)字阿保坂」については、神山町のホームページに、
| 神山町神領はすだちや藍が自生し、我が国でも唯一穀類の祖神、大宜都比売命を祭神とする上一宮大粟神社が神領大粟山にあることから、古くから先人たちの生活が営まれていましたことが推測されます。卑弥呼伝説の言い伝えが残る高根・悲願寺は、石段を登りつめた標高700mの付近の山岳地にあり、千手観音や天照大神等が古代より祀られていたと伝えられています。 (http://www.town.kamiyama.lg.jp/intro/chisei.html) |
とあり、まずは「大粟神社」と「悲願寺」をウィキペディアで見たところ、「大粟神社」の主祭神は大宜都比売命のようだが、
| ここでは、大宜都比売命のまたの名を天石門別八倉比売命あるいは大粟比売命としているが、資料によっては天石門別八倉比売命・大粟比売命は配祀神であるとしている。 社伝によれば、大宜都比売神が伊勢国丹生の郷(現 三重県多気郡多気町丹生)から馬に乗って阿波国に来て、この地に粟を広めたという。。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%B8%80%E5%AE%AE%E5%A4%A7%E7%B2%9F%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
とのことで興味深いですね、伊勢国丹生の郷には「丹生神社」があり、主祭神は「埴山姫命」だが、御祭神が馬に乗って来た?「聖武天皇の勅願所」だったことから、瀬織津姫のように思えるが。
「丹生神社」の配祀:美津波女神、合祀:饒速日尊他三十二柱というあたり、やはり物部氏(忌部氏)が関連しているんだな、と。
(http://kamnavi.jp/ny/mienyu.htm)
で、「天石門別八倉比売命」と一昨日の「天石門別神」が似てるなと思って検索していると、阿保坂の東約2kmにある佐那河内村の「天岩戸別神社」(主祭神:天手力男神)について書かれていたブログがあり、20日の多気郡の「佐那神社」に繋がるようで、天手力男神と同神と思われる神名がいくつか書かれていて、またしても頭がウニに。
(天岩戸別神社:http://blogs.yahoo.co.jp/noranekoblues/47581349.html)
天手力男神と同神と思われる神名の、「伊佐布魂神」は「伊佐我神」(建比良鳥命の子)と、「天背男命」は「天香香背男命」(天津甕星)と似ているようで、その関連が気になる・・・。
同名の神々について書かれているという、壱岐市の「天手長男神社」の境内社「物部布都神社には布都主命が祀られている。」そうで。
旧住所には「物部田中触」とあったので、物部氏に関する神々であることを表していると思われ、神社名に「手長」とついているあたりに、一昨日の「てなづち」と関連があるのでは、と。
(壱岐市・天手長男神社:http://members.jcom.home.ne.jp/ochozt-t/ikihtm/IkiIchinomiyaStory.htm)
(壱岐市・天手長男神社:http://www.genbu.net/data/iki/tanagao_title.htm)
(壱岐市・天手長男神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%89%8B%E9%95%B7%E7%94%B7%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
で、徳島県名西郡神山町の「悲願寺」は、
| 雨乞の滝より徒歩約40分のところに位置し、養蚕の守護神として賑った。阿波邪馬壹国説の中心地で卑弥呼の居城した所といわれている。標高700mの山上にあり、千手観音や天照大神等が古代より祀られていたと伝えられている。 寺の開基は源満仲の子息美女丸とされ、卑弥呼の祭壇跡と伝えられる台座と、神々を祀った磐座が残っている。 悲願寺開基以前は山神社で、巫女が神を祀っていたと云われている。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%B2%E9%A1%98%E5%AF%BA) |
とあり、「大宜都比売命」(保食神)も養蚕の神で、「千手観音」が祀られたということで、瀬織津姫に繋がるような。
「源満仲の子・美女丸」のことは2009.03.17分に「美女丸伝説」があることや、源氏一門の祈願所となった川西市の「満願寺」(御本尊:千手観音菩薩)が、「聖武天皇の勅願により勝道上人が創建」というお寺。」であることを書いており、「大粟神社」同様「聖武天皇」が関わっていて興味深いですね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E9%A1%98%E5%AF%BA_(%E5%B7%9D%E8%A5%BF%E5%B8%82))
ウィキペディアの「神山町」の「名所・旧跡・観光スポット」に「神山温泉」の外部リンクがあったので拝見していると、
| 神山温泉 天女が授けた霊水といわれ、郷人はその天女を「塩水大明神」として奉り、その祠は現在も源泉地の近くに建っております。 慶応4年(1866)、小規模ながら地域の人達の共同経営で湯屋として開業したのが神山温泉のルーツになります。 近辺の次郎銅山の労働者を中心に、水質の良さを聞きつけた遠くからの湯客も多数訪れ、賑わいをみせましたが、銅山の衰退に伴い明治8年に廃業となりました。 しかしその後、善覚寺(温泉から徒歩3分)住職がこの名湯を無くしてしまうのを遺憾に思い、鉱泉分析試験を依頼。「温泉として価値高く医治効果も顕著」の確認を得て、大正14年(1925)5月「弁天鉱泉湯」として再開しました。 (http://kamiyama-spa.com/index.php?id=2&dtl=2:11:) |
とのことで、「塩水大明神」の詳細は不明だったが、「次郎銅山」については詳しく書かれていて、埴山姫命は馬に乗ってやってきて、大宜都比売命として粟を蒔くのと並行して、「銅山」の掘削にあたったのでは、と。
「次郎銅山」を検索すると、「藩政時代の阿波の特産は藍と塩だったそうですが、銅鉱石や粗銅も重要な産物でした。」とされていたし。(次郎銅山:http://www7b.biglobe.ne.jp/~tokusima-kouzan/A17_2.htm)
で、神山町には神社・仏閣が25ヶ所あるようで、「法守山 善覚寺」は番外霊場で高野山真言宗であることしかわからなかったが、町内の善長寺、長満寺、神宮寺、善覚寺、神光寺の5ヶ寺で、鮎喰川での「精霊流し」が行われているようですね。
(http://www.geocities.jp/reminopage/shikokuhenro1.html)
(http://www.chizumaru.com/czm/tellist-36342G0109.htm)
(http://www.town.kamiyama.lg.jp/cgi-bin/report/view.cgi?410)
ウィキペディアの「神山町」の「名所・旧跡・観光スポット」にあった「雨乞いの滝」も、やはり瀬織津姫を思い出すわけで・・・。
(http://www.ne.jp/asahi/awa/taki/yoshinogawa/kamiyama/amagoi/amagoi.html)
(http://www.ne.jp/asahi/photo/takeno/waterfall/tokushima/kamiyama/amagoi_kami_me.html)
ということで、「阿保」のほとんどが「鉱物」で繋がるようで、「阿保古墳群」(百穴)は鉱物を掘った跡をお墓にしたのかも、と・・・姫路とは阿波に続く瀬織津姫の路?
行基ゆかりの柏原市の「安福寺横穴群」は、「阿保古墳群」と同じ6~7世紀の横穴式石室なので関連があるかも。
あ、滝で箕面市を思い出し、「粟生間谷」という地名は「あおまたに」と読むんだっけ、とか思ってて、「粟」と「阿保」は似てるなぁ、と・・・。
百穴といえば「吉見百穴」が有名だけど、吉見って昨日の「建予斯味命が、出雲国より入間郡に遷られた。その地を吉見といふ。」と思われ、比企郡であることなど、いろいろと繋がりが見えてきそうな感じがしますね。
ただ、アメノホヒ・タケヒラトリたちと、瀬織津姫・スサノオ・ニギハヤヒ・ナガスネヒコ・サルタヒコたちが、どのようにして繋がるかまでは・・・。
出雲市姫原町の「比那神社」は、御祭神は「比那鳥命」とあるが、「式社考」では「比奈良志毘賣神あるいは武比奈鳥命」、「出雲神社巡拝記」では「このはなさくやひめの命」とあるそうで・・・。
(http://www.genbu.net/data/izumo/hina_title.htm)
「天夷鳥命」の別名「出雲伊波比神」で検索すると、入間郡の「出雲伊波比神社」がヒットし、ヤマトタケルがオオナムチを、成務天皇の御代に武蔵国造兄多毛比命が「アメノホヒノ」を祀り、「大己貴命とともに出雲伊波比神としたとされています。」とのことで、それにより「天夷鳥命」が消されたとしたら、瀬織津姫と同じ運命を辿っているようで。
(http://www.town.moroyama.saitama.jp/kanko/izumo.htm)
「兄多毛比命」はアメノホヒの後裔とされているが、「兄多毛比命とは大伴武日のことらしいことの可能性が一段と高まった。」とあって、アメノホヒと大伴氏の関連が気になるところで。
(http://www.dai3gen.net/osihi.htm)
北埼玉郡騎西町にある「玉敷神社」(主祭神:大己貴命 )の創建が、「多次比真人三宅磨」とも「兄多毛比命」ともされているあたりが興味深いですね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E6%95%B7%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
| (養老5年)羊は謀反の罪で多治比真人県守(三宅麻呂の兄、嶋の子=甥)に攻められ多胡の池村で一族自害する。藤原房前は藤原氏の権力を確かなものにする為に三宅麿を失脚させた。羊太夫が高麗若光の讒言により攻められたのは単なる口実で、中央集権の律令政治に、勢力を持ちすぎた邪魔な地方豪族の国司や郡司を解体したのであろう。西暦703年 高麗若光は従五位下 高麗王姓を賜り西暦716年高麗郡司になっている。不満はなかろうに、讒言したのは秩父鉱山を巡って、三宅麿と羊に対して、確執のあった反動であろうか? (http://members3.jcom.home.ne.jp/yoshi-cp/gfshirsishi.htm) |
というあたり、先に「羊」を消し、多治比氏を失脚させ、土地・鉱物を乗っ取ったという証拠のように思えて。
(http://members3.jcom.home.ne.jp/yoshi-cp/gfshirsishi.htm)
その背後に藤原氏の謀略があるのはわかるが、そのまま納得しかねるような感じもして・・・房前は母方の血を重んじ、瀬織津姫を擁護する立場にあったのではと思っていたんだが、最近はよくわからなくて、本当に房前が?という思いがあって。
その後、「橘奈良麻呂の変」を理由に、藤原仲麻呂は立ちはばかる氏族・皇子を一掃するために処罰を下し、その中に「多治比犢養」「多治比国人」(両者とも多治比嶋の孫)がいたのだが、それを見ているしかなかった家持は、「移り行く時見るごとに心痛く昔の人し思ほゆるかも」(万葉集20巻・4483)を詠んだようで。
(http://www.sysken.or.jp/Ushijima/Mother.html)
(http://blogs.yahoo.co.jp/ichirof57/25558679.html)
家持は多治比国人の妹と旅人の子で、「見ているしかなかった」くらいに藤原氏の謀略はひどかったのだろうな、と・・・。
昨日テレビで見たのですが、「白子川」が23区唯一の湧き水の流れる川で、それにより「大泉」という地名になったとか。
「和泉国」の地名の由来も、「泉井上神社」にある「和泉清水」からで、「泉穴師神社」も近くに湧き水があって。
そういえば、「泉穴師神社」の摂社「春日社」の御祭神の「天富貴命」って?
「天富貴命は貴と命とが重複と見れば天富命と同じ。」で「忌部氏」と神奈備さんの掲示板にあり、なるほど、と。
(http://kamnavi.jp/log/yumv0304.htm)
地名・神社で物部氏が、「毛布の町」ということで秦氏がいただろうなと思われるので、「天富貴命・古佐麻槌命」が本来の春日神なんでしょうね。
ん?・・・練馬、大根、湧き水、ってことでな~んか気になるなぁ・・・へぇ~、練馬は元北豊島郡で、旧武蔵国豊島郡が南北に分割されることによりできた郡なんですか。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E9%83%A1)
大根は「関東ローム層」が栽培に適してたので特産品になったようだが、先日駒込は「茄子」が特産品って書かれてたけど、これも土壌によるものだとしたら、水茄子が産地の貝塚市と土壌が似てるのかも?あ、「賀茂なす」も有名ですね。
ほ~、「奥三河天狗茄子」というのもあるんですね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%84%E5%AD%90)
練馬区に戻りますが、「石神井」の由来が、
| 石神井の名の由来は、この地で井戸を掘った折、石剣が出土したことから、「石神の井」で石神井となったといわれている。現在この石剣は、石神井神社に神体として祭られている。また石剣は、三宝寺池から出土したという記録もある。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%A5%9E%E4%BA%95) |
とのことで、「剣」といえば「草薙剣」でスサノオを、「石神」なら瀬織津姫を思い出すが・・・。
「武蔵野三大湧水地」というのが、「石神井公園」「善福寺池」「井の頭恩賜公園」で、
| 井の頭恩賜公園 平安時代中期に六孫王経基が伝教大師作の弁財天女像を安置するためこの地に建てた堂が、現在井の頭池西端の島にある井の頭弁財天(別当寺は天台宗大盛寺)の起源とされる。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E3%81%AE%E9%A0%AD%E6%81%A9%E8%B3%9C%E5%85%AC%E5%9C%92) |
とあり、こちらも気になりますが、「六孫王経基」は経基流「清和源氏」の初代で、上記の満仲の父だし、「伝教大師作の弁財天女像」なら瀬織津姫だな、と。
「のりぬま(乗潴)という宿駅が「ねりま」に転訛した」そうで、乗潴があったとされる近くに「白山神社」があるようだが、祀られているのが「イザナミ」で、本来の神は隠されてしまっているんだなぁ、と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA))
氷川台の「氷川神社」は、
| 1457年(長禄元年)の創建という。渋川義鏡が古河公方の足利成氏との戦の途上、下練馬で石神井川を渡ろうとした時、淀みに泉を発見し、武運長久を祈ったのに始まるという。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B7%E5%B7%9D%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E6%B0%B7%E5%B7%9D%E5%8F%B0)) |
とあり、「淀みに泉を発見」というのは武神としての瀬織津姫を見出したのかな、と。渋川氏は清和源氏義国流で足利氏の一門、とのことで、興味深いですね。
話が前後しますが、「練馬」の由来の1つに馬術の名人がいて、馬を馴らすことを「ねる」と言ったことから、とあったが、ひょっとしたら近くに「牧」があったのかな、と。
「文武天皇(701-704)の時代、現在の向島から両国周辺にかけて牛島といわれた地域に国営の牧場が設置されたと伝えられ・・・」とあったが、距離感がいまいちよくわからず・・・うーん、遠そうですね。
(http://www.ka2.koalanet.ne.jp/~retsu/sanpo50.htm)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%85%E6%97%A8%E7%89%A7)
(http://sky.geocities.jp/sabutyan66/page050.html)
あ、川島信二騎手と三浦皇成騎手は練馬区の出身なんですね~。
「白子(シラコ)は新羅(シラギ)の、新倉は新座(すなわち新羅)の転化とする説」があるそうで、埼玉県まで検索範囲が広がった・・・。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E5%85%89%E5%B8%82)
ということで、調べていくとのめりこみそうで、そろそろ寝る時間なのでここらでやめときます。(苦笑)
| ●2010.01.25(Mon.) |
21日分の追記になりますが、火の宮とも言われる「野々宮神社」から「菅生神社」まで約6kmで、西から東へとほぼまっすぐ行ったというライン、2008.03.30分に書いた水谷慶一氏著「知られざる古代」にある、伊勢と箸墓古墳を繋ぐラインを淡路島の「伊勢ノ森」まで伸ばしたラインの上なんですね。
「野々宮神社」と「菅生神社」の中間点あたりに「萩原天神」があり、「野々宮神社」から3キロほど西に行くと「大鳥大社」があるわけで。
で、ふと「知られざる古代」の続編「龍王のきた道」について書いた2008.04.05分を読み返し、年代的に合うのかどうかは不明だが、「東海の龍宮から来たという脱解王」と、2009.12.31分の「朱蒙」の父「解慕漱」(北扶餘建国)との関連はあるのかな?と。
「脱解王」(脱解尼師今)は新羅の第4代の王(在位:57年~80年)だそうだが、ウィキペディアの「脚注」に、
| 上垣外憲一は、神話である以上、他系統の伝承が混ざっているだろうと述べた上で、脱解は丹波国で玉作りをしていた王で、交易ルート(紀元一世紀から朝鮮半島南部と日本列島沿岸部の交易は盛んで、朝鮮からは大量の鉄が、日本からは大量のガラス製や碧玉製の玉と奴隷が輸出されていた)を経て新羅にたどり着いたというのが脱解神話の骨子だと推測できるとした。上垣外は脱解の出自を倭と断定することは出来ないが、昔氏は倭と交易していた氏族だと推測できるとした。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E8%A7%A3%E5%B0%BC%E5%B8%AB%E4%BB%8A) |
とあり、また「関連項目」に「稲飯命」(ウガヤフキアエズとタマヨリヒメの子で神武の兄とされている)がリンクされてて。
高句麗初代王「東明聖王(朱蒙?)」の生きていたのは、紀元前58年~紀元前19年とあったが・・・。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%98%8E%E8%81%96%E7%8E%8B)
うーん・・・スサノオは朱蒙の孫?脱解王?
話がそれますが、ふらっと拝見したサイトに、博多区の「立花寺」を「りゅうげじ」と読み、大阪・八尾にも竜華(りゅうげ)があり、「りゅうげ」は朝鮮語で「ゆうげ」で、「弓削は神話時代の立花に由来する地名だとわかります。」とあった。
(http://www7b.biglobe.ne.jp/~iichirou/sub30.html)
ひょっとして「橘」は「立花」とも書けることから、「弓削」に繋がり、諸兄たちは物部氏の末裔か?などと思ったりして、だから諸兄の父・三野王は、物部氏が多くいたであろう信濃の地の地図作りができたのでは・・・。
| ●2010.01.26(Tue.) |
昨日ML「西行辞典 第107号」が届き、前号に四天王寺の歌があって、今号の後記には、発行されている方が四天王寺に行かれたことが書かれていて。
以前にも書いたことがあると思いますが、かつて四天王寺があったとされる「玉造稲荷神社」の「亀池」と、「四天王寺」の「亀井の水」が繋がっているというのを聞いたことがあり、その間には「産湯稲荷神社」(ここも藤原氏が入り込んだ気配あり)に「日高の清水」があったり、温泉の湧き出る場所(現在マンションが建っている)や遺跡があったりして。
それによって「太子の水脈」と勝手に名づけ、太子の足跡を追ってた、というか、行基の足跡を追うと太子の足跡も見え、検索のきっかけの1つになったわけで。
で、「四天王寺」に行かれたあと、「いたすけ古墳」「仁徳天皇陵」をご覧になったそうで、「やはりこういう大切な遺産は、いつまでも守り続けて欲しいものだと改めて思ったものでした。」とあり、ごもっとも!と。
最近どうなったか見てないのですが、一時は不法投棄のゴミが溢れたりしてたので、新市長には環境整備に力を注いでいただきたいなと。ここで書いても、ではありますが。
でも、南海電車が堺東駅の車庫跡地にマンションを建てる際、「仁徳天皇陵」(百舌鳥耳原中陵)を見下ろすのはよくないとして、堺市は計画されてた高さよりも低くさせたらしいんで、大切な「遺産」であることをしっかりと意識していただきたいですね。
で、今号の「唐」に関する歌にも、西行の熱い想いが込められていて、中でも気になったのが、
(岩波文庫山家集58P秋歌・新潮272番・西行上人集・山家心中集) 今日初めて知った。蜀江の水で洗うという唐錦は、萩の咲く野辺にあったのになあ。 (和歌文学大系21から抜粋) |
で、「萩」には何かがあるのをやはり西行も知っていたようで、2010.01.12分にはニギハヤヒとしたが、瀬織津姫に繋がるのではと思い、「諏訪大社」の摂社に、「意岐萩命」「妻岐萩命」や「八杵命」という神も祀られているようで検索してみた。
(http://kamnavi.jp/en/sinano/suwamae.htm)
岡谷市の「出早雄小萩神社」に、「諏訪大神の御次男神・興萩神(意岐萩)は第十三番目の御子神であらせられる。」とあり、「モミジ(紅葉)の名所として知られる」とのことだが、他のサイトでは、「昭和35年3月出早雄神社(旧郷社)と小萩神社(旧村社)とが合祀。」とあり、「出早雄命(諏訪大社の二男)、意岐萩命(諏訪大社の八男)」とあって。
(http://www.lcv.ne.jp/~mnoboru/page/okaya/izuhaya.html)
(http://www.localinfo.nagano-idc.com/suwa/aki/momiji/index1.htm)
また、「タケミナカタは母神に会いに諏訪から日光へ行く途中で 貫前神社の比売大神と契って オキハギノミコトが生まれた と書いてありましたしね。」「意岐萩命(オキハギノミコト)は 佐久開削の神であり 新海三社神社に祭神として祀られていました」と書かれたブログがあった。
(http://blogs.yahoo.co.jp/sweetbasil2007/folder/1032266.html?m=lc&sv=%B0%D5%B4%F4%C7%EB%CC%BF&sk=1)
なんだか6日に引用させていただいた、「下白山の女体后が近江の志賀の都で唐崎明神に見そめられ、妊娠して加賀に帰る途中、愛発山で誕生したのが佐羅王子。」というのに近いような・・・。
「貫前神社」は2009.06.02分に少し書いており、「貫前」が女神で、「神道集」によると「南天竺狗留吠国の長者・玉芳大臣の五女」とのことだが、「ある伝によると、阿育大王の姫宮、倶那羅太子の妹である。」とあり、近江での太子ゆかりのお寺での伝承のように、「アショカ王」との繋がりを示そうとしたのかも、と。
(http://www.genbu.net/data/kouzuke/nukisaki_title.htm)
(http://www.lares.dti.ne.jp/~hisadome/shinto-shu/files/36.html)
「物部姓磯部氏」による祭祀で、水神・財神・機織の神ならば瀬織津姫と思われ、そのあたりについて、風琳堂さんのサイトに詳しく書かれていた。
(http://otd3.jbbs.livedoor.jp/246945/bbs_plain?base=552&range=20)
「貫前神社」の公式サイトのリンクにあった「鷺宮咲前神社」の御由緒に藤原氏の関与が見え、「以後の祭祀を藤原姓和太氏が司る。」には、秦氏も関与してることを匂わせているようで、当時の藤原氏の姑息な手法による乗っ取りに思えて。
(http://www.sakisaki.net/yuisho.html)
話を戻しますが、「意岐萩命」が「新海三社神社に祭神として祀られていました」と書かれたブログを拝見していると、「新海三社神社」の境内図を見ると、先日の「菅生神社」の境内社「菅生えびす神社」を見ているようで。
(http://blogs.yahoo.co.jp/sweetbasil2007/folder/1032266.html?m=lc&sk=1&sv=%A5%AA%A5%AD%A5%CF%A5%AE%A5%CE%A5%DF%A5%B3%A5%C8&p=2)
「意岐萩命」は「興萩命」とも「興波岐命」とも書くようで、「新開神(にいさくのかみ)・大県神・八県宿禰神(やのあがたすくねのかみ)等とも称され」るようですが、「妻岐萩命」「八杵命」についてはわからなかったが、出雲系の神かと。
(http://www.genbu.net/data/sinano/sinkai_title.htm)
検索していると、綾部市の「阿須々伎神社」の「志賀の七不思議と「御用柿」伝説」の御由緒に、
| 今から、およそ、一四〇〇年前の崇峻天皇の頃、大和朝廷は、国の中心勢力をかためるため、金丸親王を遣わし、丹波の国々の地方豪族を征伐することになりました。 なお、この五社のほかに、向田の「しずく松」「ゆるぎ松」にも同時に不思議な霊験があらわれ、これらをあわせ「志賀の七不思議」として、今に語りつがれています。 (http://www.genbu.net/data/tanba/asusuki_title.htm) |
とあり、金丸親王?と思いつつ検索すると、太子の弟・麻呂子親王が、「こちらでは金丸親王・金麿親王、金屋皇子などと呼ばれている」そうで、「金丸親王が丹後国内に建立した7ヶ寺の1つです。」という「円頓寺」の近くには行基の足跡があった。
(http://www5.nkansai.ne.jp/org/syo-kan/syuhen/annai.html)
(http://www2.ttcn.ne.jp/rockwell/BF15.html)
このあたりは太子の母「穴穂部間人皇女」の伝説のある地で、麻呂子皇子(当麻皇子)の母は「葛城広子(葛城(直)磐村の娘)」とあるが、なんらかの関連があったのではないかと思われるわけで。
(穴穂部間人皇女:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%B4%E7%A9%82%E9%83%A8%E9%96%93%E4%BA%BA%E7%9A%87%E5%A5%B3)
(当麻皇子:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E9%BA%BB%E7%9A%87%E5%AD%90)
そうそう、「穴穂部の名は、石上穴穂宮で養育されたことに由来すると考えられる」ということから、穴穂部間人皇女の母・小姉君(蘇我稲目の娘)が物部氏ではないかと思い、ゆえに太子にも物部氏の血が流れていると思ったわけで。
「金丸親王」に関する伝承や「志賀郷の七不思議」など、「鉱物」が関連しているようで、「七不思議」の「茗荷」は「摩多羅神」そして瀬織津姫に繋がるように思われ、ゆかりのあった出雲系の神々を例えて伝承されたものなのかも。
(http://shigasato.com/nanafushigi/)
「茗荷」については2009.05.10分にも書いており、朝来市山東町粟鹿の「粟鹿神社」では、「茗荷神社」に「草野姫命」が祀られていて、瀬織津姫かと思われるわけで。
西行から随分離れてしまいましたが、京都の「修学院」にいた頃に「小野殿」に行って詠まれた歌も載ってまして。
(岩波文庫山家集267P残集20番) かつては滝があり流れていた水も、今では絶えてしまっています。 この邸の昔のことを語るものは何もありません。 ただ、松風のみが往時と同じに吹きすぎて行くばかりです。 (MLを発行されている方による解釈) |
和邇氏の流れを汲む小野氏と惟喬親王(紀氏)、惟喬親王と在原業平(葛井氏)、そして場所柄からの秦氏との繋がりなどにも、背後に「鉄」があるように思われ、その人々によって祀られている神のことも、西行はよく知っていたのでは、と。
そうした人々の想いを汲んで、後水尾天皇は修学院離宮を造営したのでは・・・。
最後の「唐国・唐土」に関する歌の、
(岩波文庫山家集229P聞書集19番・夫木抄) 漢土で、張良は兵法の嬉しい教えを得た、その土橋の上の教えもそのまま受けてそむかなかったのだろう。 (和歌文学大系21から抜粋) |
には解釈に「張良」が出てきており、「張良がいなかったら劉邦は天下を取れなかった。」と言われたほどの優れた「軍師」だったようで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B5%E8%89%AF)
そのことが西行の時代にはもう伝わっていたようだが、いつ頃どのようにして伝わったのかが気になるし、「張良」に重ねて詠んだのは瀬織津姫と思われるが、歌にある「土橋」がまだつかめてなくて・・・。
あ、能「張良」に「大蛇」が出てますね・・・川の中の大蛇は、兵法の奥儀を伝授した「黄石公」の化身だったのかも。
(能・張良:http://www.harusan1925.net/0330.html)
(黄石公:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E7%9F%B3%E5%85%AC)
(始皇帝:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%8B%E7%9A%87%E5%B8%9D)
なーんとなく、業平の歌に対応しているような気がすると同時に、「六韜」を暗唱する程読み込んでいたとされる鎌足を揶揄しているような感じもあるような・・・。
で、もう1つ書れていた「唐国・唐土」に関する歌の、
(岩波文庫山家集160P恋歌・新潮1302番・万代集) 自分ほど恋のもの思いをする人がまたもあろうかと、遠く唐土までも尋ねてみたいものだ。 (新潮日本古典集成山家集から抜粋) |
は、2009.05.06に書いたように、西行と歌談を交わしたという「明恵」は2度インドへの旅を計画しており、西行もまた「明恵」と同じ想いでいることを言わんとしている歌のようで・・・。
| ●2010.01.27(Wed.) |
昨日の分を書き終えて夕食を済ませたあと、再度「萩」で検索し、山口県萩市に何かないだろうかと見ていると、須佐町に「道永の滝」というのがあり、
| 戦国時代、毛利元就に敗れた陶晴賢の残党が山伏となってこの地に逃れたと言われ、その子孫が滝に向かって左側にある大きな洞穴に黄金の茶釜を隠したと言う伝説もあるそうです。 (http://www8.plala.or.jp/takimi/kengai_taki/douei_yamaguchi.htm) |
とのことで、須佐といえば「真カルラ舞う4」で、「黄帝」が祀られているが実はスサノオでは、という神社があったなと調べてみたけど、詳しくはわからなくて・・・。
で、「陶晴賢」という名前が気になって検索したら、「家系は百済聖明王を祖とする渡来系氏族多々良氏の流れを汲む周防国の在庁官人大内氏の傍流にて、平安時代後期に大内盛長が右田氏となり、子孫の弘賢が吉敷郡陶村に居住して陶氏を称した。」とあった。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E6%B0%8F)
「琳聖太子が日本に渡り、周防国多々良浜に着岸したことから「多々良」と名乗」ったそうだが、「琳聖太子の記録は古代にはなく・・・」とのことで。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%B0%8F)
多々良浜に着岸した後、「荒陵(四天王寺)に上って、聖徳太子に謁し、周防国大内県を賜い・・・」とのことだが、太子の弟・来目皇子が、「周防の娑婆(遺称地は山口県防府市桑山)に殯し、土師猪手がこれを管掌した。」というあたり、何か関連がありそうな気がしたりして。
(http://www.city.yamaguchi.lg.jp/oouchi/ouchishi/outline/01.html)
(来目皇子:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A5%E7%9B%AE%E7%9A%87%E5%AD%90)
「吉敷郡陶村に居住して陶氏を称した」ことと「多々良氏」が気になり、「陶村」で検索して「鉱物」に関する遺跡を見ると、「鋳銭坊遺跡」から「鋳滓・鉄火箸」が、「糸根山遺跡」から「鉱滓、須恵器」が出土しているようで。
(http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/kyouiku/bunkazai/isekihyou.html)
あと、「陶陶窯跡」や「大板山たたら製鉄遺跡」、そして現在も「萩焼」の窯があるので、陶村の南に「鋳銭司」が設けられたのも、古くからそうした技術があったからなのではと思われ、大阪の泉北丘陵や千里丘陵よりも規模が大きかったのかもしれないが、工房の移動が早く、跡地に次々と「萩」を植えられたのかも、と。
(http://bunkazai.ysn21.jp/general/summary/genmain.asp?mid=10023&cdrom=)
萩市の地名の由来は、「市花であるツバキの読みの転訛したため、ハギになった、などの説がある。」とされているが、「椿」というと「東大寺」のお水取りで、十一面観音像に供えられる花、としての印象が強く、「椿」もたしか鉄に関係する何かがあったように思うんだが・・・忘れた、すみません。
「聖明王」で「善光寺」を思い出したけど検索に戻り、「鉱山」では「志津木鉱山」がヒットし、見慣れぬ「アタカマ石」「鉱脈鉱床」「ハロゲン化鉱物」「グリーンタフ活動」などの言葉を調べてたけどよくわからず・・・。
(http://www7b.biglobe.ne.jp/~hryk/03-35.html)
| 古代の青銅器の表面にアタカマ石が生じていたとの報告もあり、また古代の岩絵の具(顔料)の素材のひとつにアタカマ石があったともいわれる。 (http://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/gallery8/577atacama.html) |
とあり、色は銅による発色だそうで、ほ~と。
山口県以外では、山形県南陽市の「吉野鉱山」が、「山形県上山市の西方にあり、昔から近辺の萩地区で金を採掘していました。」とあった。
このあとお風呂に入ってて、検索したことを思い返していた時、ウィキペディアの「萩」のところでリンクされてた「肥料木」と、24日の「茄子」のところで「土壌が似てる」などと書いたこと思い出し、そういえば・・・と。
| 肥料木 土壌の形成に貢献する先駆樹木のこと。窒素固定機能(根粒菌との共生による)などが優れる。 概要 主にマメ科植物のうち高木化するもの、非マメ化植物で枝葉を多く付け森林の土壌形成に貢献する高木で、陽・陰、湿・乾を問わない過酷な環境で生育できる樹種が選ばれる。多くの場合は先駆樹種として植栽に用いるものであり、森林が形成される最終局面では自然侵入してくる樹種にバトンタッチし、消えて行く運命にある。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E6%96%99%E6%9C%A8) |
行基ゆかりの堺市東区の「萩原天神」(萩原寺)と、豊中市桜塚の「萩の寺」に共通することといえば、丘陵地にあって「窯跡」が近くにある、ということで。
| 紀元前4~3世紀に大陸から伝わった金属器を伴う農耕文化はこの地方にも及び、急速に発展し人口もふえ、多数の集落ができました。それは、共同体の象徴としてつくられた銅鐸が、桜塚の原田神社旧境内から発見されたことでうかがえます。銅鏡を副葬した前期の待兼山古墳、北摂の古墳文化の隆盛を物語る大規模な中期桜塚古墳群、また、日本最大の規模をもつ堺市旧陶邑につぐ須恵器の窯跡が、旧桜井谷村を中心に、後期古墳群とともに分布しているのは、古代のこの地方がよく開発されていたことを物語っています。 (豊中の歴史と歩み:http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/shoukai/history/history.html) |
とあり、旧桜井谷村は元「豊島郡」で、千里丘陵の「待兼山」では「褐鉄鉱の一種である高師小僧、「待兼山石」を産出した。」と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%85%E5%85%BC%E5%B1%B1)
千里丘陵は’70の万博開催に伴う開発によって、多くの遺跡が潰されたと思われる場所で、しっかりと発掘調査されていれば、もっと多くの発見があったかもしれませんね。
(原田神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(桜塚古墳群:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%A1%9A%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4_(%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C))
ちなみに、「原田神社」のある阪急宝塚線岡町駅の次(梅田寄り)が「曽根駅」で、両駅の中間あたりに「萩の寺」はあり、その次が「服部駅」で道真ゆかりとされる「服部天神宮」があり、その次の「庄内駅」は、「庄内小学校」の敷地内に「庄内遺跡」があり、出土した土器が「庄内式土器」と名づけられていて。
(とよなか百景:http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/kankyou/toshikeikan/hyakei/index.html)
(庄内小学校:http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/shonai/index.cfm/1,0,14,html)
豊中から箕面、池田方面は、秦氏や物部氏のテリトリーだったと思われる地名が、上記の駅名のように見られるわけで。
で、「萩原天神」の近くでも発掘調査が続いており、「余部日置荘遺跡」は西除川の左岸に位置する古墳時代から中世の集落跡で、工房跡も見つかっているようで。
ということで、鋳物生産集団(河内鋳物師)の工房跡が移動しているので、行基が「萩原寺」を建立した頃、あるいはそれ以前に、工房跡地の土壌形成のため、萩を植えたのでは、と。
豊中の「萩の寺」も同様と思われ、仙台の「与兵衛沼窯跡」に工房ができる前は「国分寺」近辺にあったのではないかと思われ、行基プロジェクトは「国分寺」の創建と「萩」の栽培による土壌形成を、「勅命」によって行ったと思われるわけで。
(与兵衛沼窯跡:http://www.city.sendai.jp/kyouiku/bunkazai/yoheenuma/index.html)
守屋創建とされる長浜の「波久奴神社」も、隣町に「木尾窯遺跡」があるので、守屋は工房のあった地に「萩」を植え、それを行基プロジェクトも倣うようにしたのかも・・・。
(木尾窯遺跡:http://www.pref.shiga.jp/edu/content/10_cultural_assets/gakushu2/data/2200/index.html)
で、「萩」で検索していた時に「萩の滝」というのを見つけ、西新宿の「熊野神社」にかつてあったとされる滝のようで。
(http://kkubota.cool.ne.jp/juunisou.htm)
上記URLにあった地図を拝見すると、「青梅街道」や「甲州街道」の文字があり、ひょっとして先日テレビで見た「内藤新宿」のあたりかも?と、検索を始めて。
「内藤新宿は玉川上水の水番所があった四谷大木戸から、新宿追分(現在の新宿三丁目交差点付近)までの東西約1kmに広がり・・・」とあり、追分?と。
(内藤新宿:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E6%96%B0%E5%AE%BF)
もとは「牛馬を追い、分ける場所」を意味した、とあってやはりと思い、「四谷新宿馬の糞の中であやめ咲くとはしほらしい」で、なるほど、と。
(追分:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%BD%E5%88%86)
(新宿:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%BF#.E6.AD.B4.E5.8F.B2)
上記URLの「新宿」で「行政区画」を見たら、「南豊島郡内藤新宿町」とあったが、遡ると「豊島郡」 (武蔵国)で24日で調べてたあたりと同じなのと、ここでも「豊」がでてきたことでさらに興味がわいて。
かつての「牛込区」は、「古くに牛の牧場があり、牛が多くいたことから、「牛」が「込」(多く集まる)に由来するとされる。」とのことで、やはり、と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%9B%E8%BE%BC%E5%8C%BA)
牧場があり、湧き水があり、「熊野神社」や「滝」があれば、やはり瀬織津姫や海人族を思い出し、交通の要衝をより盛んにしたと思われる内藤サンが気になった。
| この地と内藤氏とのつながりは、豊臣秀吉により後北条氏が滅ぼされ、徳川家康が江戸に入府する直前の1590年(天正18年)7月にさかのぼる。三河時代より徳川家康の小姓として仕えていた内藤清成は、家康の入府に先立ち後北条氏残党に対する警備のため、鉄砲隊を率いて甲州街道(国府道)と鎌倉街道が交差していた現在の新宿二丁目付近に陣を敷いた。 この功が認められ、清成は付近一帯を拝領し中屋敷(上屋敷は神田小川町、下屋敷は下渋谷にあったという)を構えた。なお、清成が率いていた鉄砲隊は、1602年に伊賀組鉄砲百人組として大久保に配置され、百人町の名のもととなっている。 この拝領に際しては、家康が「馬が一息で駆け巡るだけの範囲を与える」と伝えたため、清成は馬に乗り榎の大木を中心に東は四谷、西は代々木、南は千駄ヶ谷、北は大久保におよぶ範囲を駆け、その馬はついに倒れて、まもなく死んでしまったというエピソードがある。 (ウィキペディア「新宿」より) |
とあり、「内藤清成」で検索すると、
| 弘治元年(1555年)、三河国岡崎にて竹田宗仲の子として生まれる。内藤忠政の養子となり、19歳で家督を継いだ。浜松にて徳川家康に召し出され、小姓を務めて信任を得る。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E6%B8%85%E6%88%90) |
とのことで、実父「竹田宗仲」が気になったが、「竹田宗仲」を弔うために1603年に建てたという「宗仲寺」しかわからず・・・。
(http://www.snsagami.org/hyakusen/d_jis/sochu/sochu.htm)
「内藤氏」は「藤原氏秀郷流の一族」で、三河系内藤氏は「松平氏に仕えた豪族」で「丹波国の守護代」や「長門国の守護代」と同族とされていて、周防長門系内藤氏が「大内氏」に仕えたというあたり、な~んか気になるし、何かありそうな気もして。
(内藤氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E6%B0%8F)
上記の、子孫が「道永の滝」の洞穴に「黄金の茶釜」を隠したとされることで名前のあった「陶晴賢」の妻は、「長門国の守護代」の「内藤興盛」の孫なんですね。
(内藤興盛:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E8%88%88%E7%9B%9B)
ということで、家康と内藤氏の関連などが気になるところだが、探しきれなくてここまでしか書けず・・・って、けっこう長いですね、すみません。
| ●2010.01.29(Fri.) |
あるチラシを見てたら、伝統工芸品「和泉蜻蛉玉」とあり、貝塚の櫛や堺の包丁は知ってるけど、そんなんあったん?と。
まず、ウィキペディアを見ると、「経済産業大臣指定以外の日本の伝統工芸品」として、「蜻蛉玉」とともに「和泉櫛」「堺五月鯉幟」「なにわべっ甲」があり、ほぉ~と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E5%B7%A5%E8%8A%B8%E5%93%81)
大阪府のホームページの「大阪の伝統工芸品(一覧)」に「和泉蜻蛉玉」があり、「泉州玉・さかとんぼ」とも言われたようで、「その由来をたずねると、奈良時代にさかのぼる。」とあり、「日本ガラス工業史」には、
(大阪の伝統工芸品(一覧):http://www.pref.osaka.jp/mono/seizo/dento-itiran.html)
(和泉蜻蛉玉:http://www.pref.osaka.jp/mono/seizo/dento-26.html)
| 大阪府の和泉國、今の堺市付近では昔からガラス玉が作られ、泉州玉と呼ばれて有名であった。この泉州玉の由来をたずねると、神功皇后が三韓征伐から帰らるる時、高麗から玉を製作する技術者をつれ帰り、浪速朝廷の地に近い堺市で技法を日本人に伝授せしめたのが、その嚆矢であるといい伝えられている。 (とんぼ玉情報局:http://bead2.blog26.fc2.com/blog-entry-20.html) |
とあるようで、神功皇后は成務40年(170年)~神功69年4月17日(269年6月3日)とされており、堺が「浪速朝廷の地に近い」というと、いつのことでどこなの?って感じだが。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%8A%9F%E7%9A%87%E5%90%8E)
ま、古代からの技術の応用部分もあるだろうし、伝承がないだけでずっと作られていたのかも。
で、「大阪の伝統工芸品(一覧)」で深江地区(大阪市東成区)の「菅細工」があり、「大和から移住し、笠などの細工物を作ったのが始まり」とあり、「鉄」があったのかも、と。現在も深江近辺では金属関係の工場が多いし。
(http://www.pref.osaka.jp/mono/seizo/dento-09.html)
| 昔、深江は良質の菅草が豊かに自生する浪速の一島でしたが、第11代垂仁天皇の御代に、大和国笠縫邑より、笠を縫うことを仕事とした一族が移住し、代々菅笠を作ったことから、笠縫島といわれるようになりました。以後、歴代天皇御即位、大嘗祭の時をはじめ、20年に一度の伊勢神宮式年遷宮に使用する菅笠はすべて深江で作り献納してきました。江戸時代には大阪玉造の二軒茶屋を起点として、伊勢音頭をうたいながら、集団で参宮したものですが、人々は道中安全を願って、(菅には浄めるはたらきがあると信じられていました)深江で菅笠を買い求め賑やかに旅をしました。 (http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000046407.html) |
とあり、「玉造稲荷神社」に「伊勢迄歩講起点」の碑があったし、「蜻蛉玉」の技術も笠縫氏(隼人?)によるものかも、と思いつつ、菅を地域の伝統工芸として持つという富山県高岡市福岡町舞谷地区が気になったが、とりあえず深江について検索してみよう、と。
「深江は、皇祖の御神鏡に関係する鋳物師とも関係が深い土地とのことである。」とあり、やはり、と思ったが、それ以上は見つけられなくて・・・ただ、崇神天皇の時代に「天照大御神」がを祀った「元伊勢」の最初が「笠縫邑」で、それに合わせて氏族の移動があったように思われて。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%A0%E7%B8%AB%E9%82%91)
深江の氏神として「深江稲荷神社」があり、御祭神は宇迦之御魂神、猿田彦命、月読命、下照姫命、笠縫祖神(天津麻占命)で、ニギハヤヒが関連しているようで、人間国宝の鋳物氏・角谷一圭氏(明治37年~平成11年)が「鏡」を調進されたことが書かれており、やはり製鉄が行われていたのだろうな、と。
(http://inoues.net/club3/club_mystery4.html)
(深江稲荷神社公式サイト:http://www.fukaeinarijinja.jp/)
「天神本紀に見える「天麻良」「天津真浦」「天津麻占」「天都赤麻良」などは、みな配下・従属の鍛冶者と考えられます。」とあり、「天璽瑞宝」さんのサイトに、ニギハヤヒに随行した神で「船長・梶取ら」の中に「天津麻占」の名があって。
(http://shushen.hp.infoseek.co.jp/keijiban/mononobe2.htm)
(http://mononobe.nobody.jp/kujihonki/tenjinki/tousen.htm)
富山県の「舞谷」には「城ヶ平横穴古墳群」があるようで、「菅笠の生産は、加賀藩によって奨励され、約400年の歴史を持つ高岡市福岡の特産品」とあり、「菅笠の館」があり、氷見三尾では「竹細工」が作られているようで、福岡町について、
(菅笠:http://www.toyama-west.jp/sangyo.html)
(城ヶ平横穴古墳群:http://www.shokoren-toyama.or.jp/~fukuoka/town/kanko/rekishi01.html)
(菅笠の館:http://www.shokoren-toyama.or.jp/~fukuoka/town/kanko/bunka09.html)
| 現在の福岡町赤丸と、これに接する高岡市石堤に延喜式内社浅井神社がある。いずれが本家であるか分からないが、両社に17世紀末ごろまで川人明神という神社があったことを『越中志徴』は伝えている。
(http://www.tkc.pref.toyama.jp/furusato/kawa/t90-7.html) |
とのことで、「福岡町」「赤丸」という地名が「鉄」に関するように思われ、「河神」として瀬織津姫が祀られていたようで、「八尾地区」があることから、深江とは物部氏で繋がりそうな感じですね。
(浅井神社:http://www.genbu.net/data/ecyu/asai2_title.htm)
深江の東隣の東大阪市でも金属関係の工場が多く、さらに東に行けばニギハヤヒが祀られている「石切さん」なんですね。
| ●2010.01.30(Sat.) |
ML「西行辞典 第108号」が届き、やはり興味深いなと検索してみまして。
まず「唐崎」(滋賀県大津市唐崎)の歌が載っていたので検索すると「唐崎神社」があり、御祭神が女別当命で、「琴御館宇志丸宿禰の妻」、とあったが、な~んか気になるなぁ、と。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E5%B4%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(http://www6.ocn.ne.jp/~hiyoshi3/k_index.htm)
(http://www.genbu.net/data/oumi/karasaki_title.htm)
「琴御館宇志丸宿禰」で検索すると比叡の「大崎神社」に、
| 社家祝部氏は、日吉大宮の祭神である大己貴神が、大和国三輪より大津へ影向され唐崎に上陸された時、唐崎に住み、神を迎えた琴御館宇志丸の末裔とされる。 (http://www.biwa.ne.jp/~kasajima/simosakamoto.htm) |
とあり、「大己貴神」を勧請したようだが、本来の御祭神が隠されてしまっているようで、それを暗喩するかのように「風さえてよすればやがて氷りつつかへる波なき志賀の唐崎」と、西行は詠んだのかも・・・。
「祝部氏」は「鴨建角見命の後裔」で、舒明天皇6年(633年)に「琴御館宇志丸宿禰」がこの地に居住し「唐崎」と名づけたそうだが、年代にも改竄があるような・・・。
(http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/02/021/02108.htm)
「唐崎神社」は高島市マキノ町にもあり、御祭神は瀬織津比咩神、速開津比咩神、速佐須良比咩神で、こちらが最初の「唐崎」だったのでは、と思ったりして。
「養老2年、能登置国にある志賀唐崎大神を勧請」したという七尾市小島町の「唐崎神社」は、御祭神が息長足姫命、市杵嶋姫命、深淵水夜禮花命で、「深淵水夜禮花命」はスサノオ系の神のようで。
(唐崎神社:http://www.ishikawa-jinjacho.or.jp/search/detail.php?e7a59ee7a4be4944=1295)
(スサノヲ系図:http://www.dai3gen.net/izumo.htm)
七尾市の「唐崎神社」の勧請元はよくわからないが、「国守多次比真人広成が崇敬」とあり、広成は多治比嶋の子で三宅磨の甥にあたり、24日にあるように、三宅磨(あるいは兄多毛比命)創建とされる北埼玉郡騎西町の「玉敷神社」には「大己貴命」が祀られていて。
(多治比氏:http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-21.html)
あと、詳細はわからなかったが、「鶴間池」の伝説が気になった。
| 藤原秀衡の妹で岩城則道に嫁いだ万徳御前は、藤原氏再興を期して挙兵するが、味方の裏切りにあって敗れ、家臣とともに鶴間池の岸に女別当宮を建て、池の竜王の使いとなった。 (http://www.harubow.com/album/koshonodensetu/KOSHO/14.html) |
「女別当宮」は瀬織津姫の宮なのでは・・・。
で、MLには、
(岩波文庫山家集16P春歌・新潮975番・西行上人集追而加書・夫木抄) 解けかかった雪をぎしぎしと踏み固めながら足柄峠を越えて行くが、風上に向かう道はとてもあるきにくい。 (和歌文学大系21から抜粋) |
という歌もあり、「「から崎」は夫木抄では「かささき」となっています。西行上人集追而加書では「笠さき」です。地名ではなく「風先き」と解釈されています。」とあり、ひょっとしたら「笠沙」に繋がり、鉱物との関連があるのかも、と。
「かささき」で検索すると家持の「かささきの わたせるはしに をくしもの しろきをみれは よそふけにける」があり、「カラスに似るが、腹と翼の一部が白い。」とのことで。
(http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/100i/006.html)
上記URLに「新羅等からの献上品」とありましたが、大阪市中央区に太子と父母を祀る「鵲森宮」があり、
| 上古難波の杜と云っていた推古天皇の御代に、難波の吉士磐金(きしいわかね・聖徳太子の命により新羅へ使者として渡る、鉄鋼業の祖)と云う人がいまして、新羅国より還って来て、鵲(俗に朝鮮烏)二羽を献上しました。この森に飼はせなさったことから「鵲の森」と称え、遂に宮の名となり略して「森之宮」又は「森明神」とも云うようになりました。 (御由緒より抜粋) |
とのことで、鉄鋼業の祖・磐金が献上した「鵲」には、鉱物との関連を示す何かがあったのかと思われ、MLにあった「菅島」に関する歌にも繋がりがありそうに思えて。
「足柄」と「菅島」で共通した鉱物として「カンラン石」があり、鉱物の見え方や、その鉱物をめぐっての乗っ取り、それに伴う御祭神隠しがあったのを、西行は伝えたかったのでは・・・。
苦鉄質岩(http://kotobank.jp/word/%E8%8B%A6%E9%89%84%E8%B3%AA%E5%B2%A9)
カンラン石(http://orebomber.info/834A83938389839390CE/)
蛇紋石(http://jamon.value-net.net/jamon.html)
ポリジム鉱(http://www1.harenet.ne.jp/~s-kishi/yamada_sulf4.html)
三波川変成帯(http://www.osk.janis.or.jp/~mtl-muse/subindex03-03rocksalongmtl.htm)
菅島(http://shima-tabi.net/sugasima.html)
カンラン石の採取場(http://dendenmushimushi.blog.so-net.ne.jp/2008-12-13)
足柄峠をこえて関東に降りてきたところに「寒田神社」があるそうで、「酒匂川に産出する川砂鉄(今では川に砂鉄はほとんど見られません)を使って産鉄にたずさわった人がヤマトタケルを歓迎し、また祀ったのではないかと考えています。」とされていて、「産鉄を思わせる事象」についても書かれてました。
(http://www.geocities.jp/tyuou59/samutajinnjya.html)
で、大分市寒田に「西寒田(ささむた)神社」があり、西寒多大神(天照皇大御神)が祀られていて、足柄の「寒田神社」とは「三波川変成帯」で繋がりそうで、鴨長明もこれらのことをよく知っていて、MLにあった「あきをゆく神嶋山はいろきえてあらしのすゑにあまのもしほ火」を詠んだのかも。
(http://nobyama.com/sasamuta.html)

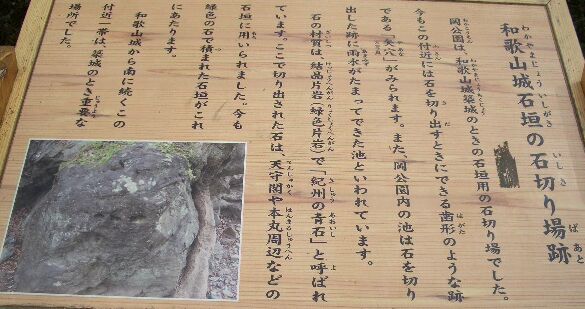
「和歌山城石垣の石切り場跡」の説明板
| ●2010.01.31(Sun.) |
「かささぎ」で少し検索してみたところ、「鵲尾形柄香炉」というのがあり、形が鵲尾に似るところからついた名だそうで、「仏の供養、開経のとき、経典を薫香し、僧侶自らも浄めるために用いる。」のだそうで。
(http://bunka.nii.ac.jp/SearchDetail.do?heritageId=13764)
(http://www.yeohoo.com/sougi/a12.html)
「鵲」とともに「星合町」という地名が、現在の松阪市三雲地域にあるそうで、「奈良時代に中国からやってきた帰化人が住みつき、七夕を祭ることになったことから、いくつかの七夕伝説が残っています。」とのことで、2009.12.25分と繋がるかも。
(http://www.mie-shokokai.or.jp/mikumo/seinenbu/tanabatamachi.htm)
(http://www.city.matsusaka.mie.jp/kankou/mobile/pickup/shrine/01_hoshiai.html)
今回のMLに「香良洲崎」の歌もあったのですが、雲出川を挟んだ向かいが「星合町」で興味深いなと。
まだ詳しく調べてないのですが、神奈備さんのサイトに「棚機神を祭る全国の式内主要神社」が書かれていて、繋がりがあるような気がして・・・。
(http://kamnavi.jp/as/katuragi/tanabata.htm)
●棚機神を祭る全国の式内主要神社
奈良県葛城市当麻町太田「棚機神社」
鳥取県岩美郡福部村「服部神社」
三重県一志郡三雲村星合「波氏神社」
山梨県韮崎市穂坂町宮久保字降宮「倭文神社」
名古屋市帰宅金城「多奈波多神社」
長野県伊那市「天泊(白)神社」
●七夕伝説のある神社(2009.12.25分より)
滋賀県米原市米原町朝妻「朝妻神社」と滋賀県米原市近江町世継「蛭子神社」
(http://www.h3.dion.ne.jp/~kyujitu/biwakosanpo/biwako6/biwako6-3.html)
大阪府交野市倉治「機物神社」
(http://www.eonet.ne.jp/~yumesite/yume/hatanomo-tanabata2.htm)
●天の川の位置に一致する巨石群(2002/04/05分より)
奈良県山辺郡山添村「神野寺」近くの「なべくら渓」
(http://www.yamazoemura.jp/volunteer/volunteer01.htm)
●検索途中分
京都・清水寺の「地主神社」
(http://www.jishujinja.or.jp/enmusubi/tanabata/index.html)
福岡県小郡市大崎「七夕神社」
(http://www.pishari.com/tanabata/index.html)
(http://www.asahi-net.or.jp/~nr8c-ab/tanadenrai.htm)
七夕リンク集
(http://www.asahi-net.or.jp/~nr8c-ab/links13.htm)
で、「星合町」と同様に「鵲橋」があるのが山形の「大沼浮島稲荷神社」で、御祭神が宇迦之御魂命、天熊之大人神だそうだが、天熊之大人神は「天夷鳥命」の別名のようで、2010.01.24分に繋がりそうな・・・。
(http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/ukisima.htm)
(http://mitsurou.com/ecom/oonuma/oonumamiru.html)
(http://www.remus.dti.ne.jp/~n-makoto/izushinto/dentouryaku1.html)
やはり「天夷鳥命」は瀬織津姫なのかな・・・。