 偲傫偱傕僯儍乣俵偺悇應俁亅俇
偲傫偱傕僯儍乣俵偺悇應俁亅俇仸栶偵偨偨側偄悇應偽偐傝偺懯暥偱偡丅(敋)
 偲傫偱傕僯儍乣俵偺悇應俁亅俇
偲傫偱傕僯儍乣俵偺悇應俁亅俇| 仠2011.01.01(Sat.) |
崱擭傕側偐側偐弌曕偗側偄偲巚偆偺偱丄僱僢僩専嶕拞怱偺懠椡杮婅揑丒悇應儊僀儞偺撪梕偵側傞偲巚偄傑偡偑丄傛傠偟偔偍晅偒崌偄壓偝偄傑偣丅
偝偰丄峏怴偝傟偰偄偨晽椩摪偝傫偺僽儘僌傪憗懍堷梡偝偣偰偄偨偩偔偲丄乽媮曥採嶳偵偍偗傞嵟廳梫側楈孉偲偟偰屲孉偺堦偮丒晛尗孉乮戀憼孉乯乿偑偁傝丄偦偙偵偼乽娾戨戝柧恄乿丄偡側傢偪乽悾怐捗昉乿偑釰傜傟偰偄傞偙偲偑婰偝傟偰偄偨偦偆偱丄偦偆偟偰巆偝傟偰偄偨偙偲傪婐偟偔巚偭偨丅
(媮曥採嶳丒將儢妜劅劅惗偒偰偄傞婼恄揱彸亂嘪亃丗http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2011/01/01)
偱丄偦偺偙偲偑彂偐傟偰偄傞慜偵丄乽敀嶳偺墢婲乿偐傜乽杒搇幍惎乿偺乽攋孯惎乿偵偮偄偰傆傟偰偍傜傟丄2003.04.16暘偱乽拞崙偱偼攋孯惎偵岦偐偭偰孯傪恑傔傞偲愴偄偵攋傟傞偲揱偊傜傟偰偄傞丅乿偙偲傪堷梡偝偣偰偄偨偩偄偰偍傝丄傆偲乽恄晲揤峜乿偑孎栰偵塈夞偟偨偺偼乽懢梲怣嬄乿偵傛傞傕偺偩偗偱側偔丄乽攋孯惎乿偵岦偐偭偰孯傪恑傔偰偄偨丄偲偄偆偙偲偩偭偨偺偱偼側偄偐丄偲丅
(柇尒偲嫊嬻憼丄杒扖偲柧惎丄攋孯惎偲懢敀惎丗http://blog.livedoor.jp/susanowo/archives/50045218.html)
偮傑傝丄孯傪恑傔偨応強偑乽柇尒丒杒扖怣嬄乿偑尒偰庢傟傞抧丄偲偄偆傛傝丄怣嬄偑偁傞偙偲傗偦傟傪怣曭偡傞偺偑乽僫僈僗僱僸僐乿偺堦懓偩偭偨偺傪抦偭偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟丄傑偨傕傗乽恄晲搶惇乿偵庱傪傂偹傞傢偗偱丅
偳偪傜偩偭偨偐巚偄弌偣側偄傫偩偗偳丄乽恄晲搶惇乿偼嬨廈撪偱峴傢傟偨偲彂偐傟偰偄偨僒僀僩偑偁傝丄戝暘偵偁傞乽孎栰乿偱偺偙偲側偺偐傪攓尒偟偨偐偭偨傫偩偑丄傑偩巚偄弌偣側偔偰丒丒丒偁丄偁偭偨丄乽恄晲揤峜婭偵搊応偡傞乽孎栰乿偲偼丄塸旻嶳偺偙偲偱偁傞丅乿偲丅
(嶰椫嶳斾妑丗http://www.geocities.jp/oden1947/miwahikaku.html)
偩偲偡傞偲丄惣峴偺塺傫偩乽悂忋乿偑嬨廈偵偁傞偺偐傪専嶕偡傞偲丄僸僢僩偟偨偺偼幁帣搰導擔抲巗悂忋挰偱丄塸旻嶳偲偼侾俉侽僉儘傎偳棧傟偰傞丒丒丒偲巚偭偰偄偨傜丄乽塸旻嶳乿偐傜惣撿惣栺俁侽僉儘偺偲偙傠偺暉壀導彫孲巗偵傕丄乽悂忋乿偲偄偆抧柤偑偁傞傛偆偱丅
(嬨廈偺乽旘捁乿偵峴偭偰棃傑偟偨丗http://lunabura.exblog.jp/tags/%E7%A5%AD%E3%82%8A%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/)
榓壧嶳偺応崌丄悂忋偼孎栰偐傜惣杒惣栺俋侽僉儘偺応強偵偁傞傫偩偑丒丒丒丅
| 仠2011.01.02(Sun.) |
乽妢嵐楬扵朘乿偝傫偺崱寧崋傪攓尒偟偰偄傞偲丄巒傔偵乽塇搰嶈恄幮乿偺乽懢榊懢榊嵳乿偲乽廙帩偪峴帠乿偺娭楢惈偵偮偄偰彂偐傟偰偍傝丄偦偺偁偲偺乽廙壧乿偺壧帉偵乽偒偝傜偓嶳偺擁偺栘傪慏偵憿傝偰崱崀傠偡丒丒丒乿偲偁偭偨丅
(乽傎偔傜乿偺掤巕偑崅偔丄乽涋彈乿傪寚偄偨亀旜挘楢傜偺偨傑偺傑偮傝亁丗http://www4.synapse.ne.jp/yatusiro/newpage44.html)
乽敼恖乿乽擁乿偵娭偡傞偲巚傢傟傞乽塇搰嶈恄幮乿偺屼嵳恄側偳偺徻嵶偼傢偐傜側偐偭偨偑丄乽幁帣搰導撪偵偼偙偺傎偐丆擔抲巗悂忋挰慏栘恄幮偺乽慏偙偓嵳傝乿偱傕丆柾宆慏傪梡偄傞媀楃偑偁傞丅乿偲丄嶐擔彂偄偰偄偨乽擔抲巗悂忋挰乿偑弌偰偒偰丄傗偼傝壗傜偐偺宷偑傝偑偁傞偺偐傕丄偲丅
(塇搰嶈恄幮偺懢榊懢榊嵳傝丗http://www3.synapse.ne.jp/hantoubunka/minzoku/20.01tarotaro.htm)
乽慏偙偓嵳傝乿偼乽戝擆柎抶柦偑媨撪偵壓岦偝傟偨偲偒丄墡揷旻柦偑奀忋傪柍帠偵彫栰柀傑偱憲傝撏偗偨偙偲偵桼棃偡傞丅乿偲偺偙偲偱乽僒儖僞僸僐乿偑釰傜傟偰偄傞偲巚傢傟傞偺偩偑丄偙偪傜傕偦傟埲忋偼傢偐傜側偔偰丒丒丒丅
(慏偙偓嵳傝丗http://www5a.biglobe.ne.jp/~iwanee/kagosima.htm)
擔抲巗悂忋挰偺乽戝擆柎抶恄幮乿偵偼乽愮杮擁乿偲屇偽傟傞戝擁偑偁傞偦偆偱丄乽偁偨偐傕棿偑怮偰偄傞傛偆偵抧偵攚偄丄埥偄偼嬻偵岦偐偄旘隳偡傞偑偛偲偔徑傪怢偽偟偰偄傑偡丅乿偲偺偙偲偩偑丄垻懡敼恖偺偛愭慶偑撧椙偺乽戝恄恄幮乿偐傜姪惪偝傟偨傛偆偱丅
(戝擆柎抶恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/kagosima/hiokisi/oonamuchi/oonamuchi.html)
乽慏栘恄幮乿偱僸僢僩偟偨偆偪偺嶉嬍導孎扟巗彫敧僢椦偺乽慏栘恄幮乿偱偼丄乽枛幮偲偟偰敀嶳恄幮丄恴朘恄幮揤恄媨丄敧敠恄幮側偳偑釰傜傟偰偄傞丅乿偲偁傞偙偲偐傜丄擔抲巗悂忋挰偐傜偺巵懓偺堏摦偵敽偭偨嵳釰偐偲巚傢傟傞偑丅
(捠揳愳丗http://www.geocities.jp/fukadasoft/rivers/tuudono/index.html)
乽擁乿偵偮偄偰偼丄嶰廳偺乽懡搙戝幮乿偱嬻攏偱屼恄栘傪夢傞乽擁夢傝乿偺恄帠偑偁傞偦偆偩偑丄宷偑傞傛偆側偦偆偱側偄傛偆側丄偲偄偭偨姶偠偱偟偰丅
(懡搙戝幮丗http://www.tadogagaku.com/aiba2.html)
恄帠偱偼側偄偑丄乽擁乿傪偔偖傞偲婅偄偑姁偆偲偄偆偙偲偱偼丄惣搒巗偺乽搒漭恄幮乿偵乽愮擭擁偺栘摯乿偑偁傞偦偆偱丄乽婭偺崙偺埳懢孷慮恄幮偵傕偙偺傛偆側栘枔偑抲偐傟偰偄傞丅乿偲偁傞偺傕婥偵側傝傑偡偹丅
(搒漭恄幮丗http://kamnavi.jp/it/tukusi/hyutuma.htm)
乽偔偖傞偲婅偄偑姁偆乿偲偄偆偙偲偱偼奺抧偵懡偔偁傞偲巚傢傟傞偺偱丄乽夢傞乿恄帠偱専嶕偡傞偲丄乽揤暯恄岇俀擭乮俈俇俇乯偵丄埳惃崙搉夛孲屲廫楅愳偺斎傛傝丄屼嵳恖偲偟偰崯偺抧偵姪惪怽偟忋偘偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅乿偲偝傟傞憡妝孲嶳忛挰偺乽榓婈嵖揤擳晇巟攧恄幮乿偺乽偄偛傕傝嵳乿偵乽怷夢傝恄帠乿偲偄偆偺偑偁傞傛偆偱丅
乽屼嵳恄揤擳晇婒攧柦偲偼丄揤徠戝恄偺屼嵃偱偁傞偲婰偝傟偰偄傞丅乿偲偺偙偲偱丄乽悾怐捗昉乿偐偲丅
(榓婈嵗揤擳晇婒攧恄幮丗http://www.geocities.jp/engisiki/yamashiro/html/020802-01.html)
擾峩媀楃偱偁傞乽偄偛傕傝嵳乿偼乽懞恖偨偪偼嫃饽嵳恄帠偺娫偼丄壠偵嫃饽偭偰堦愗壒傪棫偰側偐偭偨偲偄傢傟偰偄傑偡丅乿偲偺偙偲偱丄2010.12.24暘偱偺乽桘擔恄幮乿偺乽戝媨偛傕傝乿側偳偵宷偑傝偦偆偱丄乽擁夢傝乿偺恄帠傗乽怷夢傝恄帠乿偑婥偵側傞偟丄2009.12.22暘偱彂偄偨乽廽墍恄幮乿偺乽偄偛傕傝嵳乿偲乽懳傪惉偡偲偝傟偰偄傑偡乿偲偄偆偺傕婥偵側傞偲偙傠偱丅
(嫃饽嵳丗http://www.city.kizugawa.lg.jp/article.php?id=450&f=276&t=cat)
(嫃饽嵳丗http://www.citydo.com/prf/kyoto/area_minami/kenbun/rekishi/seika001.html)
(廽墍恄幮丗http://aladdin.s57.xrea.com/kanko/seika/housono.htm)
乽妢嵐楬扵朘乿偝傫偺崱寧崋偵彂偐傟偰偄傞乽廃埻傪夲傔怲傑偣傞偨傔乿偺乽杋惡乿偑丄乽偄偛傕傝嵳乿側偳偺恄帠偑峴傢傟偼偠傔偨崰偵偼偁偭偨偺偱偼側偄偐丄偲丒丒丒丅
偦偆偄偊偽丄僐儈僢僋乽堿梲巘俀乿偱惏柧偑丄乽捯傗堎憌偺栧偱幃偨偪偵巐屢傪摜傑偣偨傝晳傪晳傢偣偰偄傞乿偲偄偆応柺偑偁傝丄乽杋惡乿偲摨偠傛偆側堄枴崌偄偑偁傞傛偆側丒丒丒丅
傑丄乽堿梲摴乿偵敼恖偺攐桪偑庢傝崬傑傟偰偟傑偭偨乽揤晲壭乿偲偄偆夝庍傪偝傟偰偄傞傛偆偩偗偳丄巹偵偼乽撽暥岅偄偠傔乿乽斀怴梾乿偑柧傜偐側乽擔杮彂婭乿傪丄乽恊怴梾乿偺揤晲揤峜偑偡傋偰峔抸偟偨偲偼巚偊側偄傫偩偑丅
崱寧崋偺嵟屻偺彂偐傟偰偄傞侾偲俀偵偮偄偰丄懌愓傪扝傟偽嬨廈偺暔晹巵偵峴偒拝偔偲偟偨傜丄晄斾摍偑拞恇巵傪忔偭庢偭偨偺偪偵暔晹巵傪忔偭庢偭偨備偊偺偙偲偲巚傢傟丄乽乽愇忋恄媨乿偵乽悾怐捗昉乿偑嫃側偄丠 仺丂昉偱偼柍棟側乽崅偄掤乿偩偭偨偐傜両両両乿偵偮偄偰偼乽愇忋恄媨乿偵尷傜偢丄忔偭庢偭偨晄斾摍偑乽崅偄掤乿偺忋偱乽悾怐捗昉乿傪尒偊側偔偟偰偟傑偭偰偄側偑傜恄埿偩偗傪棅傒偵偟偰偄傞偐傜偩偲悇應偟偰偄偰丅
乽帒杮丒楯摥椡偺搳壓乿偼丄乽峴婎僾儘僕僃僋僩乿傪傕慡崙揥奐偝偣偨傎偳偺乽恅巵乿偲偄偆乽敼恖乿傪拞怱偲偟偨乽抭幆乿偑摦偒丄嶳妜廋尡幰偺僱僢僩儚乕僋偵傛傞帠慜偺捠払偱丄摨懓偵傛傞乽抭幆乿偐傜偺帒嬥傗恖嵽偺採嫙傗傾僼僞乕働傾傕偁偭偨偐傜偙偦丄崱偺悽偵傑偱慡崙揑偵乽峴婎乿偺柤偵傛傞帥堾寶棫傗憸側偳偺揱彸偑巆偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巚偊傞偺偩偑丅
| 仠2011.01.03(Mon.) |
愭寧峸擖偟偨愄榖偺杮偵丄乽愹寠巘恄幮乿偺乽屜杧乿偑惍旛偝傟偨偙偲偑彂偐傟偰偄偰丄偦偺幨恀偑巗偺峀曬帍偺乽偍偍偮暔岅乿偵嵹偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱丄嶐擔幚壠偵峴偭偨帪偵傕傜偭偰偒傑偟偰丅
(屜杧丗http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/syougaigakusyu/meishokyuseki/kitunebori.html)
峀曬帍偵偼丄乽偒偮偹偑桸悈傪敪尒偡傞偲偄偆揱彸偼丄撧椙導崄幣巗屜堜抧嬫偵傕偁傝傑偡丅乿偲偺偙偲偱専嶕偡傞偲丄乽偒偮偹偺堜屗乿偑嵹偭偰偍傝丄乽屜堜偼傕偲傕偲椙偄悈偑側偐偭偨偺偱丒丒丒乿偲偁傝丄傫丠偲丅
(崄幣偺揱愢丗http://www.city.kashiba.lg.jp/info/shisei/bunkazai/densetsu/)
乽愹寠巘恄幮乿嬤偔偵偼偨傔抮偑偁偭偨偟丄堜屗傕嵟嬤傑偱巆偭偰偄傞壠偑偁偭偨偺偱丄乽姳偽偮乿偱偼側偔乽惢揝乿偵傛偭偰堸梡悈偑晄懌偟偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟丄 偺夛幮偵崄幣嵼廧偺恖偑偄偰丄奺抧偵堜屗偑偁偭偨偲偄偆偁偨傝偼帡偰偄偰丄乽惔悈乿偵娭偡傞揱彸偺偁傞乽巙搒旤恄幮乿傕乽愹寠巘恄幮乿偲摨偠傛偆偵乽惢揝乿偑峴傢傟偰偄偨偺偐傕偟傟側偄側丄偲丅
偺夛幮偵崄幣嵼廧偺恖偑偄偰丄奺抧偵堜屗偑偁偭偨偲偄偆偁偨傝偼帡偰偄偰丄乽惔悈乿偵娭偡傞揱彸偺偁傞乽巙搒旤恄幮乿傕乽愹寠巘恄幮乿偲摨偠傛偆偵乽惢揝乿偑峴傢傟偰偄偨偺偐傕偟傟側偄側丄偲丅
(巙搒旤恄幮丗http://homepage3.nifty.com/katuraki/sub2-2.htm)
偩偑乽巙搒旤恄幮乿偼拞恇巵偵忔偭庢傜傟丄屼嵳恄傕偡傝懼偊傜傟偰偟傑偭偨偺偱偼丒丒丒乽幮揱偱偼乽屆偔偼丄乽幁埊捗昉柦乿傪捔嵳偟偨偑丄壗帪偺掱偵偐尰峴偺嶰恄(昳懮榓焼柦丄揤橺壆柦丄掙摏抝柦)偲惉偮偨丅乿偲偺偙偲偱丄偦傕偦傕偼乽悾怐捗昉乿偑釰傜傟偰偄偨偺偱偼丅
(巙搒旤恄幮丗http://www.geocities.jp/engishiki01/yamato/html/030610-01.html)
崄幣偺偲側傝偺墹巕挰偵乽媣搙恄幮乿偑偁傝丄屼嵳恄偑昳懮榓焼柦偱丄揤橺壆柦丄掙摏抝柦丄媣搙恄偑攝釰偝傟偰偍傝丄乽悈恄乿傪暔晹巵偑釰偭偨傕偺偲巚傢傟丄乽巙搒旤恄幮乿傕摨條偐偲丒丒丒乽巙搒旤恄幮乿偼乽榒暥恄幮乿偱偼側偐偭偨偐偲偺悇應傕偁偭偰丒丒丒丅
(媣搙恄幮丗http://kamnavi.jp/as/ikoma/kudo.htm)
崄幣偵傕乽敀嶳昉恄幮乿偑偁傞傫偱偡偹丄乽抮忋丒慮崻堚愓乿嬤偔偵傕乽敀嶳恄幮乿偑偁偭偰丄巵懓偺堏摦偑尒偊傞傛偆側丅
(撧椙俆俆僠儍儞僱儖丗http://blog.goo.ne.jp/gfi407/m/200812)
(敀嶳昉恄幮丗http://barakan1.exblog.jp/1912538/)
(楺懍傇傜傝扵朘丗http://www2.ocn.ne.jp/~webpeco/burari-08.html)
偱丄乽屜杧乿偺暘偩偗偱側偔丄幚壠偵偁偭偨懠偺暘傕傕傜偭偰偒偰偄偰丄偦偙偵斾妑揑怴偟偄挰柤偺偙偲傕彂偐傟偰偄偰丒丒丒抮傪杽傔棫偰偰偱偒偨彫妛峑偑丄側偤乽擁彫妛峑乿側傫偩傠丠偲偼巚偭偰偨偑丄乽巗偺栘乿偑乽擁乿偩偭偨偺偼抦傜側偐偭偨丅
(擁挰惣丗http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/matizukuri/kawaraban/choumeinohensen/kusunokichounisi.html)
偝傜偵丄偦偺彫妛峑偺偡偖撿偵偁偭偨抮偑乽忦棦惂偺廫嶰偺捸偵偪側傓乽廫嶰抮乿乿偩偭偨偲偄偆偺傕弶傔偰抦傝丄乽廫嶰乿偲偄偊偽2010.01.12暘偵彂偄偨傛偆偵乽僩儈乿偲撉傑傟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟丄乽僫僈僗僱僸僐乿偲偺娭楢偑偁傞偺偐傕偟傟側偄側丄偲丅
(廫嶰偺桼棃丗http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-158.html)
(廫嶰偺桼棃偲楌巎丗http://www10.ocn.ne.jp/~kamitsu/jusonoyurai.html)
偦傟傜偺抮偼丄峴婎備偐傝偲偝傟傞乽嬌妝帥乿偺偁偭偨幮堟偺偡偖搶偱丄峘偐傜棨楬偱晎拞偺乽榓愹媨乿傊岦偐偆捠傝摴偲巚傢傟傞応強偱丅
(榓愹崙丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%9B%BD)
乽巙搒旤恄幮乿偺乽巙搒旤乿偼丄乽榒暥乿偱偁傝乽(巙)僩儈乿偱偁偭偨偺偐傕丒丒丒丅
榖偼曄傢傝傑偡偑丄巗偺峀曬帍偵柧帯侾俆擭偺婰榐偑彂偐傟偨傕偺偑偁傝丄乽彆徏懞偺乽媨乿偲屇偽傟偨応強偵偼丄弔暘丒廐暘偺擔偺弌偛傠丄偦偺徏塭傊嫑偑廤傑傞偨傔丄偦偙偵栐傪擖傟傞偲戝嫏傪摼傞偙偲偑偱偒傞丅乿偲偁偭偨偦偆偱丅
愄榖偵傕偄偔偮偐乽徏椦乿偑弌偰偨偗偳丄乽徏塭傊嫑偑廤傑傞乿傎偳偺乽徏椦乿偑憐憸偱偒偢丄偟偐傕乽弔暘丒廐暘偺擔偺弌偛傠乿偱偁傞偺偼側偤側偺偐偑婥偵側傞偲偙傠偱丒丒丒徏偑奀偵岦偐偭偰巬傪怢偽偟偰偄偨偺側傜丄偍拫偁偨傝傑偱奀柺偵徏塭偼偱偒偨偩傠偆偗偳丅
偁丄偦偺彆徏偺昹偁偨傝偱偡偹丄乽怣懢戝柧恄乿偑忋棨偟丄乽惞恄幮偵岦偐偆嵺偵晍傪堷偄偨偙偲偵桼棃偡傞乿偲偄偆乽晍堷偺摴乿偑偁傝丄愄榖偱偼恄岟峜岪晽偺乽偍斳條乿偑丄昹偐傜俈搙媩傪傂偐偣偰栴偑俈搙栚偵棊偪偨抧偵偍幮傪嶌傝丄偦傟偐傜偺偪偵偦偺嬤偔偵乽惞恄幮乿偑嶌傜傟偨丄偲側偭偰偄偰丄偦偺乽偍斳條乿偼偦偺屻傕乽惣惇乿偟偨傛偆偱丅
惗傑傟堢偭偨応強側偺偵丄抦傜側偄偙偲偑偨偔偝傫偁傝傑偟偰丒丒丒丅
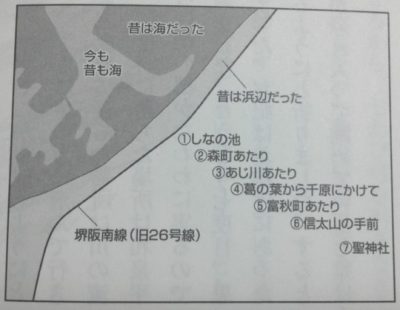 乽愄傓偐偟愹戝捗偱側乿p58偺乽幍偮偺栴乿傛傝 (戝嶃晎榓愹巗墹巕挰廃曈(惞恄幮)偺抧恾) |
| 仠2011.01.04(Tue.) |
嶐栭愻偄暔傪偟偰偄傞帪丄僥儗價傪尒偰偄偨 偑乽媨巌偝傫偑亀挿廆変晹偝傫亁偭偰偄傢偼傞傫傗偰丄徏嶳偺亀捴恄幮亁偭偰尵偭偰偨傢丅乿偲嫵偊偰偔傟偨偺偱丄梡帠偑廔傢偭偰偐傜専嶕偡傞偲乽媣暷巵偺慶恄傪釰傞恄幮乿偲偁傝丄尦偺屼捔嵗抧乽攡杮懞彫栰扟乿偼乽媣暷孲乿偺傛偆偱丄媣暷巵偺杮嫆抧偩偭偨偺偐傕丄偲丅
偑乽媨巌偝傫偑亀挿廆変晹偝傫亁偭偰偄傢偼傞傫傗偰丄徏嶳偺亀捴恄幮亁偭偰尵偭偰偨傢丅乿偲嫵偊偰偔傟偨偺偱丄梡帠偑廔傢偭偰偐傜専嶕偡傞偲乽媣暷巵偺慶恄傪釰傞恄幮乿偲偁傝丄尦偺屼捔嵗抧乽攡杮懞彫栰扟乿偼乽媣暷孲乿偺傛偆偱丄媣暷巵偺杮嫆抧偩偭偨偺偐傕丄偲丅
(FNN僯儏乕僗丗http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00190593.html)
(埳梊摛斾屆柦恄幮 埳槵摛斾屆柦恄幮 捴恄幮丗http://www.genbu.net/data/iyo/iyotuhiko_title.htm)
(埳梊偺嬿乆丗http://www33.ocn.ne.jp/~kotaro_mil/iyosumi/towninfo/matuyama-ono.htm)
(埳槵摛斾屆柦恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B1%AB%E8%B1%86%E6%AF%94%E5%8F%A4%E5%91%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(埳槵摛斾屆柦恄幮丗http://tubaki.or.jp/)
(屆帠婰僀儞捴恄幮丗http://ameblo.jp/yamagatakahori/entry-10665563893.html)
(埳槵摛斾屆恄幮偵偮偄偰丗http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1232358137)
屼嵳恄偺乽埳梌庡柦乿偵偮偄偰専嶕偡傞偲丄乽媣枴崙憿丗墳恄挬偵丄恄嵃懜偺廫嶰悽懛偺埳梌庡柦傪崙憿偵掕傔傜傟偨丅乿偲偁傝丄媣枴崙憿亖媣暷崙憿偺傛偆偩偑丄戝敽巵丠垻撥巵丠暔晹巵丠媣暷巵偺杮嫆抧偺侾偮偲偝傟偰偄傞乽娸榓揷巗媣暷揷抮乿偼峴婎偲宷偑傞偑丒丒丒丅
(崙憿杮婭丗http://mononobe.nobody.jp/kujihonki/yaku/kokuzou.html)
(戝敽巵懓偲媣暷巵懓丗http://enjoy.pial.jp/~kokigi/keihu/sizokugairan/ootomo-k.htm)
(埳梊偺媣暷晹丗http://www.sysken.or.jp/Ushijima/voyage8.htm)
(媣暷巵丒嶳晹巵丗http://homepage2.nifty.com/amanokuni/kume.htm)
(斄數媨偲暔晹巵偲嶳晹巵偺娭傢傝丗http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/8918/yamabe.htm)
乽媣暷崙憿乿傪専嶕偡傞偲乽孠尨敧敠恄幮乿偑僸僢僩偟丄乽墲屆傛傝孠尨懞屆媨偵捔嵗偟丄棜拞揤峜偺捄婅強偱偁偭偨丅媣暷崙憿偑戝媨巌偲側傝巕懛偑戙乆偦偺怑傪庴偗宲偖丅乿偲偁傝丄幮揳偺嵞寶摍偱壨栰巵偲偺宷偑傝偑尒偊偰丄廧強偐傜峴婎備偐傝偲偝傟傞乽斏懡帥乿偲嬤偄傛偆偱丄抧柤偐傜傕恅巵偲偺宷偑傝偑尒偊傞傛偆偱丅
(孠尨敧敠恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%91%E5%8E%9F%E5%85%AB%E5%B9%A1%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
傑偨丄媽媣暷孲偺峴婎備偐傝偲偝傟傞乽惓娤帥乿偱傕丄乽壨栰捠淎岞偺怣嬄傪庴偗丒丒丒乿偲壨栰巵偲偺宷偑傝偑尒偊丄嶳崋偑乽彫栰嶳乿偱乽彫栰彫挰備偐傝偺帥乿偲偝傟偰偄傞偙偲偐傜丄彫栰巵偲媣暷巵偦偟偰恅巵偺宷偑傝偑尒偊傞傛偆偱丅
乽孠尨敧敠恄幮乿偺暿柤偑乽嶰搰恄幮乿偲偁傝丄乽恗摽揤峜偺帪戙偵憂寶乿偲偺偙偲偱偙偪傜偑愭偵釰傜傟偨偲巚傢傟丄乽墇抭嬍弮偑戝嶳媉恄幮傛傝棆恄丄崅偍偐傒恄傪姪惪崌釰偟偰嶰搰媨偲掕傔丄嶰搰怴媨偲徧偊偨丅乿偲偄偆偙偲偱丄乽墇抭嬍弮偑柌偵傛偭偰偙偺抧傪楈抧偲屽傝孎栰廫擇幮尃尰傪釰偭偨丅偙傟偼惞晲揤峜偺捄婅強偲側傝丄揤暯尦擭乮729擭乯偵峴婎偑栻巘擛棃崗傫偱杮懜偲偟偰埨抲偟偰奐婎偟偨乿偲偄偆乽愇庤帥乿傕嬤偔偵偁傝丄墇抭巵偲峴婎偺宷偑傝傕尒偊丄庡偵釰傜傟偰偄傞偺偼乽悾怐捗昉乿偐偲丅
(愇庤帥丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%89%8B%E5%AF%BA)
(愇庤帥丗http://nehan.net/index-06.htm)
乽傕偲偼埨梴帥偲偄偄丄塹栧嶰榊偺場墢偵傛偭偰愇庤帥偲夵傔偨丅乿偲偺偙偲偱乽塹栧嶰榊乿傪専嶕偟偨偲偙傠丄嬻奀棈傒偺揱愢偺傛偆偱丄敨偑俉偮偵妱傟偨偙偲傗俉恖偺巕偳傕偑師乆偵朣偔側傞偙偲側偳丄弌塤傪巚偄弌偝偣傞傛偆側撪梕偱嫽枴怺偄偱偡偹丅
(塹栧嶰榊丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%9B%E9%96%80%E4%B8%89%E9%83%8E)
乽戝曮尦擭乮幍乑堦乯偵暥晲揤峜偺捄婅帥偲偟偰埳梊崙巌墇抭嬍嫽偑幍摪壘棔傪寶棫偡傞偵偁偨傝丄戝摪嶳偵敧僇強偺摴楬傪憿偭偨偲偙傠偐傜乽敧嶁帥乿偺帥崋偑晅偗傜傟偨丅乿偲偄偆乽敧嶁帥乿傗丄乽揤暯廫嶰擭乮幍巐堦乯丄巐崙傪椃偟偰偄偨峴婎偑丄埳梊偺崙巌偱偁傞墇抭嬍弮偲弌夛偄丄堦媨暿摉帥偲偟偰寶棫丅乿偲偄偆乽惣椦帥乿側偳傕偁傝丄宷偑傝偺怺偝偑巉偊傑偡偹丅
(巐崙敧廫敧儠強儈僯帿揟丗http://www.himegin.co.jp/88/temple-dict.php?p_page=oAkkyT)
偱丄乽壨栰捠淎乿偵偮偄偰専嶕偡傞偲乽搾恄幮乿偑僸僢僩偟丄嫬撪幮乽帣庣幮乿偺屼嵳恄偵恄戝巗昉柦乮鐽塽恄丄壨栰幍榊捠淎乯偲偁傝丄
| 墲屆丄徏嶳忛搶榌偵偁偭偨偑丄徏嶳忛抸忛偺嵺丄搾恄幮偺枛幮壨栰楈恄偵崌釰偝傟偨丅壨栰楈恄偼帪廆偺奐慶堦曊 偑晝丒壨栰捠峀傪釰傞偨傔偵寶棫偟偨傕偺偱丄梀峴忋恖偑弰嫵偟偨嵺偵偼昁偢嶲攓傪峴偄丄偦偺搒搙椞庡偼幮揳傪憿塩惍旛偟偨丅捔塽恄偼丄埨惌榋擭丄埆昦棳峴偵偮偒捔塽偺偨傔偵姪惪偝傟偨丅 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
偲偺偙偲偱丄尦偼乽弌塤浖恄幮乿偺曽偩偭偨傛偆偱丄傗偼傝弌塤偲偺宷偑傝偺嫮偝偑尒偊傞傛偆偩偑丄乽巐強戝柧恄乿偲傕徧偝傟偰偄偨偺偵乽戝嶳愊柦乿乽姖栰昉柦乿偼屼嵳恄偲偟偰彂偐傟偰偄側偄傛偆偱丄乽戝嶳媉恄乿偺巕恄乽恄戝巗昉柦乿偑嫬撪幮乽帣庣幮乿偵釰傜傟偰偄傞偁偨傝側偳丄婥偵側傞偺偩偑丒丒丒丅
(搾恄幮丗http://yu.mydns.jp/top.htm)
偁丄乽埳梊摛斾屆柦恄幮乿偺乽帣庣幮乿偱偼乽栘壴奐栯昉柦乿乽揤擵悈暘柦乿偑釰傜傟偰偄傞傛偆偱丒丒丒丅
(捴媨帣庣恄幮丗http://tubaki.or.jp/2300/2300_02.php)
傑偨偟偰傕撲偑憹偊偨偩偗偺傛偆偵側傝偦偆偩偑丄乽埳梊摛斾屆柦恄幮乿偱媽楋惓寧俈擔乣俋擔偵峴傢傟傞乽捴傑偮傝乿偼乽偍敧擔乿乮偍傛偆偐乯偲屇偽傟偰偄偨偦偆偱丄媽楋侾寧俉擔偺栭丄恄幮偺恄梎偑杒搚嫃挰偺乽嬥搧斾梾恄幮乿傑偱搉屼偡傞偲偄偆摿庩恄帠偺乽偍擡傃偺搉屼乿偼丄2009.04.26暘偱偺搶嫗丒晎拞巗乽戝崙嵃恄幮乿偺乽偔傜傗傒嵳乿傗丄俀擔偺乽榓婈嵖揤擳晇巟攧恄幮乿乽廽墍恄幮乿偺乽偄偛傕傝嵳乿側偳偵宷偑傝偦偆側丒丒丒乽偔傜傗傒嵳乿偱乽俉婎偺恄梎乿偑搉屼偝傟傞偦偆偱丄偙偪傜偱傕乽俉乿偑棈傫偱傑偡偹丅
(偍擡傃偺搉屼丗http://tubaki.or.jp/003/003_02_03.php)
(偔傜傗傒嵳丗http://www.ookunitamajinja.or.jp/matsuri/kurayami.php)
乽埳梊摛斾屆柦恄幮乿偺乽屆擁乿偵偼丄乽偍峠偝傫乿偲屇偽傟傞柲扠偑廧傫偱偄傞偲偄偆揱彸偑偁傞偦偆偱丄乽愹寠巘恄幮乿偺乽屜乿偲嬤偄傕偺傪姶偠丄乽挭柭愇乿偑乽帟捝巭傔乿偲偝傟偰偄傞偺偼丄2009.11.26暘偱偺嶄巗乽摡峳揷恄幮乿偺乽榁徏幮乿傗戝嶃丒攡揷偺乽峧晘揤恄幮乿屼椃強偺乽帟恄幮乿丄乽抮忋丒慮崻堚愓乿嬤偔偺乽敀嶳恄幮乿摍偲摨偠偱丄乽廙嶳乿偼嫗搒乽婱慏恄幮乿墱媨偵偁傞乽慏宍愇乿偵帡偰偄傞傛偆側丒丒丒丅
(懘偺懠偺嫬撪晽宨丗http://tubaki.or.jp/006/006_00_00.php)

偦傟偵偟偰傕丄偍嫖慘偵婾嶥偭偰丄側傫偰僶僠摉偨傝側丒丒丒丅
| 仠2011.01.05(Wed.) |
侾擔偵乽悂忋乿偵偮偄偰彂偒傑偟偨偑丄乽傂傕傠偓鐤梱乿偝傫偺僒僀僩傪攓尒偟偰偄傞偲丄乽偙偺撧懡偺昹傪悂忋昹偲屇傫偱偄偨偺偱偡偹乿偲偁傝丄暉壀導搶嬫偺乽巙幃恄幮乿偁偨傝偑偦偺傛偆偱丅
(巙幃恄幮丗http://lunabura.exblog.jp/i7)
傑偨丄乽乽孨偑戙乿偑暉壀巗偺乽巙夑奀恄幮乿偺恄帠偱楢柸偲壧偄宲偑傟偰偄傞偺傪抦傞恖偼傑偩傑偩彮側偄傛偆偱偡丅偦偺堦晹傪徯夘偟傑偡丅乿偲乽偊傃傜媩偨傜偟偺壧乿偑彂偐傟偰偍傝丄乽崄捙楬偺丂偁偺岦偙偆側傞丂悂偒忋偘偺昹偵丂愮戙偵愮戙傑偱乿偲偁偭偨丅
(乽孨偑戙乿備偐傝偺嶰幮嶲傝丗http://lunabura.exblog.jp/tags/%E7%9C%9F%E9%8D%8B%E5%A4%A7%E8%A6%9A/)
乽巙幃恄幮乿偼乽埨撥懓偨偪偑戝愗偵曭嵳乿偝傟偰偒偨恄幮偺傛偆偱丄屼嵳恄偼恄岟峜岪偑乽恑孯偡傞慜偵偍嵳傝偟偨埨撥懓偺嶰拰偺揤恄乿(壩柧恄丄壩恷嬟恄丄朙嬍昉恄)偲乽奙慁偟側偑傜丄抲偒嫀傝偵偝傟偰峴偭偨嶰恖乿(廫堟暿恄丄抰晲墹丄梩嶳昉恄)偲偁傝丄側傞傎偳丄偲巚偄偮偮傕丄梩嶳昉偼乽峀揷偺崙乿偱偍釰傝偟偨傢偗偱偼側偄偺丠偲丅
偲偄偆偙偲偼丄乽悂忋乿偺抧柤摨條丄巵懓偺堏摦偵敽偭偰偁偲偐傜釰傜傟偨丄偲偄偆偙偲側偺偐側丄偲丅
偦傟偲丄偦偺偁偲偵彂偐傟偰偄傞乽戝浽恄幮(俀)乿偱丄乽怴擭傪寛傔傞婎弨偲偟偰弔暘傗廐暘傪慖傇巵懓偲丄壞帄丄搤帄傪慖傇巵懓偑偁傝傑偡丅乿偲偁傞偙偲偐傜丄俁擔偺乽乽彆徏懞偺乽媨乿偲屇偽傟偨応強偵偼丄弔暘丒廐暘偺擔偺弌偛傠丄偦偺徏塭傊嫑偑廤傑傞偨傔丄偦偙偵栐傪擖傟傞偲戝嫏傪摼傞偙偲偑偱偒傞丅乿偼丄弔暘傗廐暘傪怴擭偲偟偨巵懓偵傛傞揱彸側偺偐傕丄偲丅
偁偲丄乽儎儅僩僞働儖傪傕偰側偟偨堦懓偺恄幮乿偲偝傟傞乽敧寱恄幮乿偑暉壀導埰庤孲埰庤挰拞嶳偵偁傞偦偆偱丄2010.02.07暘側偳偱偺惣峴傗攎徳偑塺傫偩乽拞嶳乿偼丄傗偼傝嬨廈傪巚偄婲偙偝偣傞偨傔偺傕偺偩偭偨偺偐傕丄偲丅
(敧寱恄幮丗http://lunabura.exblog.jp/14605149)
偱丄乽擔庒恄幮乿偵偮偄偰彂偐傟偰偄傞偲偙傠偵丄乽榒恖偼乽偟乿亄乽傒偢乿偱丄惔悈偲偄偆尵梩傪憿傝弌偟偨乿偲偁傝丄
| 僔儖僋儘乕僪傪扝偭偰擔杮偵棃偨柉懓偵偲偭偰丄 僆儕僆儞偺嶰僣惎偼摴偟傞傋偱偁傝丄怱偺巟偊偱傕偁偭偨丅 僆傾僔僗偺悈傕傑偨怱偺巟偊偩偭偨丅 偦偙偱斵傜偼丄僆儕僆儞嵗偵傕僆傾僔僗偺柤傪偮偗偨丅 偦傟偑嶰搰偱偁傝丄儈僝僋僀偱偁偭偨偲偄偆帠偱偡丅 (http://lunabura.exblog.jp/i23/) |
偲彂偐傟偰偄偰丄俁擔偺乽惔悈乿偵娭偡傞揱彸偺偁傞乽巙搒旤恄幮乿乽愹寠巘恄幮乿偼摨懓偵傛傞嵳釰偐偲丅
偦傟偵偟偰傕丄侾擭傎偳偱偙傟偩偗偍挷傋偵側偭偰彂偐傟偰偄傞偺偼乽偡偛偄両乿偺傂偲偙偲偱丄巹偼壗傪傗偭偰傞傫偩傠偆偐偲丒丒丒傗偼傝尰抧偵峴偔偺偑偄偄傫偩傠偆偗偳丄柶嫋傪帩偭偰側偄偟丄峴婎備偐傝偺応強偭偰幵偱傕擄媀側強偑懡偔偰丒丒丒偄偮傕尵偄栿偽偐傝傗偹丅(嬯徫)
晽椩摪偝傫偺僽儘僌偑峏怴偝傟偰偄偰丄2010.12.29暘偺乽婼恄幮乿偺屼嵳恄偼傗偼傝乽悾怐捗昉乿偩偭偨傫偩側偀丄偲丅
(戝幹偲偟偰偺嶰搰柧恄劅劅戝嶳媉恄幮尦幮抧傪朘偹偰亂嘥亃丗http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2011/01/05)
乽嶰搰媨屼捔嵗杮墢乿偑堷梡偝傟偰偍傝丄乽彫愮嬍悷乿偑乽捄柦傪曭偠乿偨宍傪偲傝偮偮傕慶恄傪釰傞偨傔偺庤棫偰傪峫偊偰偄偨傛偆偵巚偊丄偦傟偑嶐擔偺屼墢婲側偳偵偁偭偨峴摦側偺偐傕丄偲丅
徚偝傟偰偟傑偆屼嵳恄傪庣傞偐偺傛偆偵丄恄幮偵婑傝揧偆傛偆偵帥堾傪寶棫偟偰暓憸傪埨抲偡傞偙偲偱偟偐崱偼慶恄傪庣傞偙偲偑偱偒側偄丄偲偄偆敾抐備偊偺峴婎偲偺揱彸偺傛偆偵巚偊丄偦傟偑揑拞偟偰乽巐強戝柧恄乿偐傜乽戝嶳愊柦乿乽姖栰昉柦乿偺屼恄柤偑徚偊偨偺偐丄偦傟偲傕怴偟偔暓嫵偱偍釰傝偟偨偺偱婾傝偺屼嵳恄偼婰偡昁梫偑側偄偲徚偟偨偺偐丒丒丒丅
偄偢傟偵偟偰傕丄曭嵵偟偰偄傞巵懓偵偲偭偰丄釰偭偰偄傞恄傪徚偝傟偰偟傑偆偲偄偆偙偲偼乽巰乿偵抣偡傞峴偄傪嫮偄傜傟偨偙偲偲偟偰丄乽曻惗夛乿偑峴傢傟傞傛偆偵側偭偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞傢偗偱丒丒丒偩偐傜擻場偼乽擁乿偵塉岊偄傪偟偨偺偱偼丅
偟偐偟丄巐崙扴摉偺峴婎偑埳梊偺崙巌偱偁傞墇抭嬍弮偲乽弌夛偆乿偲偄偆抜庢傝傪慻傫偩僱僢僩儚乕僋偺憗偝丄偦偟偰偡偖偝傑帥堾寶棫偱偒傞宱嵪椡傗寁夋惈丄墇抭嬍弮偑戝嶳媉恄幮偺忋捗幮丒壓捗幮偐傜棆恄丒崅偍偐傒恄傪姪惪偟偨敾抐椡偼丄偄偐偵慶恄傪戝愗偵巚偭偰偄偨偐偑巉偊傞傛偆偱丅
| 仠2011.01.06(Thu.) |
摢偑僂僯丒丒丒乽傂傕傠偓鐤梱乿偝傫偺僒僀僩偐傜堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨乽(僆儕僆儞偑)嶰搰偱偁傝丄儈僝僋僀偱偁偭偨偲偄偆帠偱偡丅乿偐傜専嶕偟偰偰丄乽奀恖偺晹壆乿偝傫偺僒僀僩偱乽夑栁巵偲嶰椫巵偲墇抭巵偼丄摨懓側偄偟恊愂偺娭學偲尵偭偰娫堘偄側偄偩傠偆丅乿偲偁傝丄乽嶰搰峚嶎帹柦乿偼乽壨撪摡搒帹柦傗夑栁寶妏恎柦恄(垻帯巙婱崅擔巕崻恄)乿偲摨恄偲偡傞宯恾傕偁傞乿偲彂偐傟偰偄偰丅
(墇抭巵(壨栰巵丒懞忋巵)丗http://homepage2.nifty.com/amanokuni/ochi.htm)
2007.03.21暘偱乽栴媨恄幮乿傪専嶕偟偰屼嵳恄偑乽夑栁寶妏恎擵柦乿偱偁傞偙偲傗丄乽恄晲搶惇乿棈傒偺揱彸偑偁傞偺傪堷梡偝偣偰傕傜偭偰偄偰丄嵞搙専嶕偟偰乽偺傝偪傖傫乿偝傫偺僒僀僩傪攓尒偟偰偄傞偲丄乽榓壧悂忋偺戝恄乿偲偁傝丄傑偨丄乽姳挭傪婲偙偝側偄乿偲偄偆屼楈尡偐傜乽柭栧偺塓挭偺娭學乿偵偮偄偰専摙偝傟偰偍傝丄傆偲2010.04.09暘側偳偱偺垻攇偺乽柭栧捔傔偺庺偄壧乿傪巚偄弌偟偨傝丄2010.02.11暘偱偺榓壧偺恄偲偝傟傞乽嬍捗搰恄幮乿偱惞晲揤峜傗攎徳偑棈傫偱偄偨偙偲傪巚偄弌偟丄壗偐傂偭偐偐傞傕偺偑偁傞傫偩偑丅
(栴媨恄幮丗http://www.norichan.jp/jinja/kenkou2/yanomiya.htm)
2009.12.18暘偱偺堷梡偱丄乽尨揷忢帯巵偼丄戝恄恄幮偺庡嵳恄偱偁傞戝暔庡丄忋夑栁恄幮偺庡嵳恄偱偁傞壛栁暿棆戝恄丄孎栰杮媨戝幮偺嵳恄偱偁傞帠夝擵抝懜丄戝榓恄幮偺庡恄偱偁傞擔杮戝崙嵃戝恄丄愇忋恄媨偺嵳恄偱偁傞晍棷屼嵃丄戝嵨恄幮偺庡嵳恄偱偁傞戝嵨恄乮戝嵨懜乯偲摨堦乿偲偝傟偰偄傞偲偁傞偑丄乽夑栁暿棆柦乿偼乽夑栁擵杮抧偱偼垻抶僗僉崅擔巕崻恄偲摨堦帇偝傟偰偄傞丅乿偲偺偙偲偱丄偆乕傫丄偲丅
(僯僊僴儎僸丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%AE%E3%83%8F%E3%83%A4%E3%83%92)
(夑栁暿棆柦丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%80%E8%8C%82%E5%88%A5%E9%9B%B7%E5%91%BD)
偦偙偱乽峴婎乿乽僯僊僴儎僸乿偱専嶕偡傞偲丄乽僯僊僴儎僸乿偑嫬撪抧偵崀椪偟偨偲偄偆揤棟巗偺乽戝恊帥乿偑僸僢僩偟丄峴婎偑壘棔傪惍旛偟偨偲偝傟偰偄傞偙偲傗丄峴婎嶌偺愇暓丒晄摦柧墹偑偁傞偙偲傪彂偒朰傟偰偄偨偙偲偵婥偯偒丄岞幃僒僀僩偵乽搷旜偺戧乿偺偙偲偑彂偐傟偰偄偰丄2009.02.12暘側偳偱彂偄偰偨乽愇忋恄媨乿偺尦媨偺傛偆偩偗偳丄忋婰偵偼宷偑傝偦偆偵側偄側偀丄偲丅
(戝恊帥丗http://daishinji.msc2001.com/taki.html)
(愇忋恄媨丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E4%B8%8A%E7%A5%9E%E5%AE%AE#.E6.A1.83.E5.B0.BE.EF.BC.88.E3.82.82.E3.82.82.E3.81.AE.E3.81.8A.EF.BC.89.E3.81.AE.E6.BB.9D.E3.81.AE.E7.9F.B3.E4.B8.8A.E7.A5.9E.E7.A4.BE)
(搷旜偺戧丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E5%B0%BE%E3%81%AE%E6%BB%9D)
懠偵傕僯僊僴儎僸偲偺宷偑傝偼乽嬀懍擔暛曟偺巎彂乿偵傛偭偰傢偐傞傛偆偩偑丄乽悾怐捗昉乿偲峴婎傪僟僀儗僋僩偵宷偖傕偺偼僱僢僩偱偼側偐側偐尒偮偐傜側偔偰丅
(閌懍擔柦暛曟傪朘偹傞丗http://www.geocities.co.jp/marebit/nigi.html)
峴婎偺晝丒崅巙嵥抭偼乽嵨抭乿偱乽戝嵨恄乿偐傜丄峴婎偺曣丒朓揷屆帰斾攧偺乽屆乿偼乽僯僊僴儎僸偺梒柤晍棷乿偱丄峴婎備偐傝偲偝傟傞乽挿媩帥乿偼乽幹恄怣嬄偺挿悜旻偺僫乕僈乕(棾)偲僯僊僴儎僸偺媩(僉儏僂)傪崌傢偣偨柦柤乿偲偝傟偰偄傞僒僀僩傕偁偭偨偑丒丒丒丅
(憂寶幰丄峴婎丗http://blog.goo.ne.jp/fumioyamashita/m/200603)
偙傟偼偄偮傕偺僷僞乕儞偱墶摴偵偦傟偰偟傑偄偦偆偩側偲巚偭偰偄偨偲偙傠丄
| 崱偐傜1,200擭慜丄榓婥惔杻楥乮733乣799乯偑戝愗偵偟偰偄偨戦偑巰偵傑偟偨丅偦偺堚崪傪嶰偮偵暘偗丄婭廈偺崅旜嶳偲丄搒偺崅梇嶳偲嫿棦偺旛慜偺崅旜嶳偵暘偗偰憭偭偨偦偆偱偡丅偦偺帪婭廈偺崅旜嶳偵偼愮岝帥傪寶偰丄搒偺崅梇偵偼恄岇帥傪寶偰丄庤岤偔挗偭偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅 (愮岝帥丗http://akizuno.kii-area.jp/cnts2/siru/) |
偲偁傝丄乽杮懜偼娤悽壒曥嶧偱丄峴婎偺嶌偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅乿偲傕丅
(廐捗栰僈僀僪儅僢僾丗http://www.kiteraga.com/satoyama/satoyama.html)
偐偲巚偊偽丄乽憂寶帪婜偼晄柧丅幮揱偵傛傞偲丄朙嬍昉柦偑婽偵忔偭偰嶿婒崙嶳揷孲妰尦乮壆搰晅嬤乯偵忋棨偟丄塋晿憪晿晄崌懜傪偙偺抧偱嶻傓丅偦偺屻榢偵忔偭偰愳傪慿傝丄偙偺抧偵忋棨偟偨偲偄偆丅峴婎偑偙偺抧偵憂寶偟偨偲偄偆丅乿偲偝傟傞乽榢壨恄幮乿傪弶傔偰傒偮偗偨丅
(榢壨恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B0%90%E6%B2%B3%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
恅巵偲榓鐜巵偑棈傫偱偄傞丄偲偄偆偙偲偩傠偆偐丒丒丒丅
梉曽偺僯儏乕僗偱塮夋乽嶃媫揹幵乿偺嶣塭偵偮偄偰偺摿廤偑偁傝丄偐偮偰増慄偵廧傫偱偄偨偙偲傕偁偭偰偄傠偄傠偲楢憐偟偰偄偰丄偐偮偰偺夛幮偺嵟婑墂偑乽撿曽乿偩偭偨偗偳丄偦偺桼棃偭偰壗偩偭偗丠偲丒丒丒挷傋偨偙偲偑偁傞傛偆側丄側偄傛偆側丒丒丒丅
媽搶梽愳嬫偵偐偮偰撿曽挰偑偁偭偰丄抧柤帿揟偵傛傞偲撿妰偲傕彂偐傟偰偄偨偲偁偭偨偩偗偱丄徻嵶偼傢偐傜側偐偭偨偲偙傠偵丄媨嶈偺抧恾偵乽撿曽乿偑偁傞偺傪尒偮偗丄専嶕偡傞偲丄俀擔偺乽塇搰嶈恄幮乿偲摨偠偔乽懢榊懢榊嵳乿偑峴傢傟傞偲偄偆乽撿曽恄幮乿偑僸僢僩偟偨丅
(撿曽恄幮 (嶧杸愳撪巗)丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%96%B9%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%B8%82))
媨嶈偺撿曽偼惣搒巗偵偁傞傛偆偱丄乽撿曽恄幮 (忋曚杒偺僋僗)乿偑僸僢僩偟偨傕偺偺丄乽屼嵳恄丒姪惪擭寧丒墢婲丒増妚摍偼慡偰晄柧乿偱偟偰丅
(撿曽恄幮 (忋曚杒偺僋僗)丗http://ameblo.jp/m-meguri/entry-10325339980.html)
(撿曽恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/miyazaki/saitosi/minamikata/minamikata.html)
偁偲丄媨忛導搊暷巗偵撿曽挰偑偁傞傛偆偩偑丄偙偪傜傕偄傑偄偪傛偔傢偐傜偢丒丒丒捗嶳挰偵偼峴婎備偐傝偲偝傟傞偍帥偑偄偔偮偐偁傞傫偩偑丒丒丒偁丄撿曽挰杮嫿戝妜偺乽娾愗娰乮楅幁忛乯乿偼乽嶁忋揷懞枦偺屼戜強楅幁屼慜偑嫃娰偝傟偨偲偝傟偰偄傞丄偲偺偙偲偱丅
(搊暷巗 撿曽挰丗http://www.nandemomiyagi.com/district/021tome/021_7minamikata/index.htm)
(撿曽挰丗http://homepage1.nifty.com/akabeko/minakata.htm)
撿曽挰壓暯奓偵乽塛惔悈乿偲傕屇偽傟偨偲偄偆乽暯奓偺惔悈乿偑偁傝丄乽撿曽挰偵偼愄偐傜幍偮偺惔悈偲敧偮偺戲偑偁傝幍惔悈敧戲偲岅傝揱偊傜傟偰偒傑偟偨丅偦偺惔悈傕奐敪摍偵傛偭偰偄偮偟偐徚柵偟尰懚偡傞偺偼暯奓偺惔悈偩偗偲側傝丄暯惉擇擭偵撿曽挰乮尰搊暷巗乯暥壔嵿偲偟偰巜掕偝傟偨丅乿偲偺偙偲偱丅
(媨忛導偺戙昞揑側桸悈丗http://www.env.go.jp/water/yusui/result/sub4-2/PRE4-4-2.html)
(暯奓偺惔悈丗http://www.mediaship.ne.jp/~pino/simizu/hirakai.htm)
乽傕偭偙傝偵傜乿偲偄偆偵傜偑偁傞偦偆偱丄挰偺僉儍僢僠僼儗乕僘偼丄乽傕偭偙傝傒側傒偐偨乿偩偦偆側丅
(媨忛/愬杒丗http://wiki.chakuriki.net/index.php/%E5%AE%AE%E5%9F%8E/%E4%BB%99%E5%8C%97)
偁偲丄娾庤導堦娭巗攱憫峕愳撿曽偑偁傞傛偆偩偑丄偙偪傜傕傛偔傢偐傜側偐偭偨丅
| 仠2011.01.07(Fri.) |
嶐擔偺乽傕偭偙傝偵傜乿偑摢偐傜棧傟偢丄専嶕偟偰傒偨丅(敋)
尒偨栚偼偪傚偭偲抁傔偩偗偳晛捠偺偵傜偲曄傢傝側偄傛偆偱丄鄠羵眰鑲蓚鐞鳀荩乽傕偭偙傝偵傜儔乕儊儞"偵傜偭偙長巕乿乽傕偭偙傝偵傜栞乿乽傕偭偙傝偵傜擏僷儞乿側偳偑偁傝丄乽傕偭偙傝偺棦偼乭偵傜乭偯偔偟両乿偩偦偆側丅
(7偮偺抧堟偐傜擑儊乕儖乮搊暷抧堟乯丗http://www.pref.miyagi.jp/et-tmsgsin/tisin/kensei/kensei1503.html)
(壚惗偺偄偮偐偒偨摴丗http://www.mmt-tv.co.jp/bandesu/teiban/burabura/050510.htm)
(摴偺墂僣乕儕儞僌儗億乕僩乽傒側傒偐偨乿曇丗http://anytown.jp/michinoeki/report04.html)
専嶕傪懕偗偰偄傞偲丄乽墱廈嶰廫嶰娤壒戝浽嶳嫽暉帥乿偼嶁忋揷懞杻楥偺憂寶丄墑捔朄巘偺奐婎偩偦偆偱丄乽嬤悽偺墢婲偵傛傟偽埼懐偺彨傪戝晲娵偲偄偄丄揷懞杻楥偼偙偺埼懐傪摉嶳偵偍偄偰嶦奞丄堚奫傪俈暘偟丄俈偐張偵暘憭偟偰偦傟偧傟娤壒偺忩妕傪寶偰偨偑丄戝浽娤壒偼偦偺堦偮偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅乿偲偁偭偨丅
(傒側傒偐偨(撿曽) 摴偺墂:傕偭偙傝偺棦丗http://michieki.web.fc2.com/miyagi/mi11.html)
傗偼傝揷懞杻楥備偐傝偲偝傟傞偍帥偑懡偄傒偨偄偩偗偳丄乽戝浽娵偺彣杺婼傪惇鎛偟嫙梴偟偨乿偲偝傟傞偙偲傗丄乽柤憪屗斎乿偺偙偲側偳傕丄峏怴偝傟偰偄偨晽椩摪偝傫偺僽儘僌偵彂偐傟偰偄偨乽戝幹亖幹恄傪棿麀偵徃奿偝偣偰傑偮傞偙偲偱丄棿麀偺峳嵃亖埆恄乮戝幹乯傪捔傔偨乿偺偲摨偠傛偆側姶偠側偺偱偼側偄偐偲巚偊丄乽獐曱帥乿偵乽偙偙偱偼乽偊傒偟乿傕娷傔偰揋枴曽堦弿偵嶁忋揷懞杻楥偼挗偭偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅乿偲偁傞偙偲偐傜丄乽惇鎛乿偲偼巚偊側偔偰丅
(墱廈俁俁娤壒丗http://www.geocities.jp/koji_jyunrei/ohshu8.htm)
(搶榓挰偺揷懞揱愢丗http://www.bakebake.com/kaido/miyagi/kuritoyo/kt08tamu.htm)
(擔崅尒崙偺婼亀戝抾娵亁丗http://members3.jcom.home.ne.jp/sadabe/oni-megami/oni-megami-4-1.htm)
(戝幹偲偟偰偺嶰搰柧恄劅劅戝嶳媉恄幮尦幮抧傪朘偹偰亂嘦亃丗http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2011/01/06)
偦傟偼戝嶃偺乽巐揤墹帥乿偵釰傜傟偰偄傞乽暔晹庣壆乿傗乽拞恇彑奀乿偲摨條偐偲丒丒丒丅
偱丄晽椩摪偝傫偺僽儘僌偱婥偵側偭偰偨戝嶳愊恄偲嶰搰柧恄偑乽帡偰旕側傞恄乿偱偁傞偲偄偆偺偵帡偨姶偠偺偙偲傪丄偐偮偰攓尒偟偨偙偲偑偁偭偨傛偆側偲専嶕偟丄乽嶰戭婰偼埳摛偺嶰搰柧恄偲戝嶰搰偺嶰搰柧恄偼暿偱偁傞偲偄偆棫応偵棫偭偰偄傑偡丅乿偲偁傞偺傪尒偮偗丄偗偭偙偆慜偵攓尒偟偨偗偳僒僀僩傪宲懕偝傟偰偄偨偙偲偵姶幱丅
(夑栁扵媮(28)埳摛偺嶰搰恄幮偵偮偄偰丗http://219.94.190.145/fortune/onmyo/kamo/kamo28.htm)
偦偺棟桼偲偟偰丄嶰戭搰偺恜惗壠偵揱傢傞捠徧乽嶰戭婰乿暿柤乽嶰搰戝柧恄墢婲乿偵丄乽偙偙偵戝嶰搰偺嶰搰柧恄偑朘栤偟偰乽偁偺曯偼柺敀偄偐傜巹偵偔傟傑偣傫偐乿偲尵偭偰嶳傪傂偲偮傕傜偆婰弎偑偁傞乿偲偺偙偲偵傛傝丄乽帡偰旕側傞恄乿偲偝傟偰偄傞傛偆偱丄乽墊杮柧恄乿偲乽弔擔柧恄乿偺乽搚抧岎姺愢榖乿偺傛偆側恾乆偟偝傪姶偠丄乽帠戙庡恄乿傪怣曭偡傞夑栁堦懓偺椞抧傪乽嶰搰柧恄乿偺柤傪傕偭偰摗尨巵偑忔偭庢偭偨偺偱偼丄偲丅
(弔擔戝幮丗http://kamnavi.jp/as/yamanobe/kasugata.htm)
偝傜偵丄
| 尰嵼嶰搱戝幮偑偁傞応強偵偼庒媨敧敠偑偁偭偨偲偝傟傑偡丅偙偺帪丄嶰搰柧恄偑庒媨敧敠條偵乽榤堦攃暘搚抧傪忳偭偰偔傟側偄偱偡偐乿偲尵偭偨偺偱丄庒媨敧敠條偑乽偦偺偔傜偄偄偄偱偡傛乿偲尵偭偨傜嶰搰柧恄偼偦偺榤攃傪夝偄偰椫偵偡傞偲峀戝側晘抧傪愯桳偟偰偟傑偭偨丅偦偙偱庒媨敧敠條偼傛偦乮摨巗杮挰乯偵堏傜側偗傟偽側傜側偔側偭偨偲偄偄傑偡丅
(夑栁扵媮(32)埳摛乛嶰搱戝幮丗http://219.94.190.145/fortune/onmyo/kamo/kamo32.htm) (揤擔榟柦丗http://tokyo.atso-net.jp/pukiwikip/index.php?%C5%B7%C6%FC%CF%C9%CC%BF) |
偲偺偙偲偱丄乽搚抧岎姺愢榖乿偲帡偰偍傝丄乽庒媨敧敠乿偼傑傞偱嶄丒旤尨嬫偺乽悰惗恄幮乿偵偁傞乽梋晹恄幮乿偺傛偆偱丄拞恇巵(摗尨巵)偺庤岥偼偳偙偱傕摨偠偩偭偨傫偩側丄偲丅
偲偄偆偙偲偼丄乽嶰搰峚嶎帹柦乿傗乽嶰搰峚峐昉乿傕乽晄斾摍偺曽曋偺恄乿側傫偩傠偆偐丄乽帠戙庡恄乿偺僥儕僩儕乕傪忔偭庢傞偨傔偺丒丒丒夑栁巵丒暔晹巵摍偺僥儕僩儕乕傪戝乆揑偵忔偭庢偭偨傢偗偐丒丒丒丅
(夑栁扵媮(31)戝嶃乛峚嶎恄幮丗http://219.94.190.145/fortune/onmyo/kamo/kamo31.htm)
偦偆偄偊偽丄2010.01.15暘偵乽挿悜旻偼帠戙庡恄乮旘捁戝恄乯偺巕乿偲偝傟偰偄傞僒僀僩偑偁傝傑偟偨偹丒丒丒丅
(挿悜旻偺屻遽偲偦偺曭嵵恄幮丗http://enjoy.pial.jp/~kokigi/keihu/nagasune/nagasune1.htm)
恅巵偑庣傜側偔偰扤偑庣傞偲偄偆姶偠偩偑丄摗尨丒拞恇巵偺忔偭庢傝偺帥堾斉偑丄2007.04.24暘偱偺乽崅嶳晄摦懜乿傗丄乽巙搙帥乿傗2010.04.22暘偱偺乽巙搙帥乿偐傜屼杮懜偑堏偝傟偨偲偄偆嵅夑巗敀嶳偺乽悙愇嶳棿憿帥(崅帥)乿傗嶰廳偺乽嬥崉嵗帥乿側偳偱丄峴婎偺柤慜傑偱棙梡偟偰偄傞偲偄偆丒丒丒丅
(崅嶳晄摦丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E4%B8%8D%E5%8B%95)
(巙搙帥丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%BA%A6%E5%AF%BA)
(悙愇嶳棿憿帥(崅帥)丗http://www.sysken.or.jp/Ushijima/Mother.html#anchor743273)
(嬥崉嵗帥丗http://www.renge.net/kongozaji_frame.htm)
乽崅嶳晄摦乿偵彂偐傟偰偄傞傛偆偵丄乽摗尨姍懌偺巕偺挿妎朧偲偄偆恖暔偺懚嵼偼巎椏偱妋擣偱偒側偄丅傑偨丄擔杮偱孯涠棙柧墹傪娷傓屲戝柧墹偺怣嬄丒憿憸偑峴傢傟傞偺偼俋悽婭偺嬻奀埲屻乿偲偄偆偙偲偐傜丄帥堾偱偺忔偭庢傝偺曽偑傢偐傝傗偡偄偗偳丄側傫偩偐側偀丄偲丅
愭擔乽廧媑戝幮乿偵弶寃偵峴偭偨偗偳丄偙偙悢擭偼婅偄帠傪偡傞婥偵側傜偢丄偛垾嶢偵側傞偐丄乽偳偆偧偙偺抧偵偄偮傑偱傕偍傜傟傑偡傛偆偵乿偲欔偔偔傜偄偱丒丒丒丅
| 仠2011.01.09(Sun.) |
晽椩摪偝傫偺僽儘僌偑峏怴偝傟偰偄偰丄乽恄暓廗崌偵傛偭偰丄怴庤偺恄塀偟偑側偝傟傞傕丄挿偒偵傢偨傞恄暓廗崌帪戙偼丄暓偑慜柺偵弌偰偄偨暘丄徚偝傟巆偭偨恄偼偦偺攚屻偵壏懚丄偁傞偄偼椻搥曐懚偝傟偰丄柧帯婜傪寎偊傑偡丅乿偲偁傝丄乽怴庤偺恄塀偟乿偵偪偲歑傝偮偮傕偍偭偟傖傞捠傝偲尵偊偦偆偱丄2009.05.14暘偺乽惛楈偺墹乿偵偁偭偨乽屻屗偺恄乿偐偲丅
(嶰搱棿麀偲偄偆戧恄劅劅嶿婒擇媨丒戝悈忋恄幮傪朘偹偰丗http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2011/01/09)
偱丄乽戝悈忋恄幮乿偺嫬撪幮乽戧偺媨恄幮乿偺戧媨恄偑乽悾怐捗昉乿偲偺偙偲偱丄傗偼傝偙偪傜傕娭楢偑偁偭偨傫偩側偀丄偲丒丒丒堦嶐擔偩偭偨偐側丄乽戝悈忋恄幮乿偵偮偄偰彂偗側偐偭偨偗偳丄偪傜偭偲尒偰偄偨偲偙傠偩偭偨傢偗偱丅
乽戝悈忋恄幮乿偼擇媨偱丄堦媨偺乽揷懞恄幮乿偼墱揳偺壓偵偁傞乽掕悈堜乿偵偄偐偩傪晜偐傋偰偦偺忋偱釰偭偰偄偨偺傪峴婎偑幮揳傪憂寶偟偨傛偆偱丄嶰媨偺乽懡榓恄幮乿偼丄峴婎偑晄斾摍偺巕丒朳慜偲摪塅傪寶棫偟偨偲偝傟傞乽巙搙帥乿偺椬側偺偱丄傂傚偭偲偟偨傜壗偐偟傜偺宷偑傝偑尒偊偦偆偩偭偨偗偳丄乽戧偺媨恄幮乿偵扝傝拝偗偰偄側偐偭偨偺偱丒丒丒丅
(揷懞恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%B8%82))
(懡榓恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%92%8C%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
偱丄乽戧偺媨恄幮乿偑乽屆戙偐傜偺婩塉恄嵳堚愓偱敀塚丒崟塚偺揱偊偑偁傞丅乿偲偺偙偲偱丄2008.11.01暘偱偺嶰搰巗偺乽塃撪恄幮乿暿柤乽偆側偓偺媨乿偵宷偑傝偦偆偱丄乽嶰搰廻偱偼峕屗帪戙枛婜傑偱偆側偓傪怘傋傞偺偼偛朄搙乿偩偭偨偺偑丄乽枊枛偵姱孯偵壛傢偭偰偄偨嶧杸乮幁帣搰導乯挿廈乮嶳岥導乯偺暫戉偑怤擖偡傞偲丄庤摉偨傝偟偩偄偵曔傜偊偰姉從偵偟偰怘傋偰偟傑偭偨偦偆偱偡丅乿偲偁傝丄嶧挿偺恖乆偼乽嶰搰柧恄乿偺堘偄傪尒攋偭偨偐偺傛偆側偍榖偑偁偭偰丅
(柧恄偺偆側偓偺榖丗http://www.city.mishima.shizuoka.jp/kakukaHP_system_kanrika/amenity/bunka/meisuino/shoku.htm)
(嵍撪恄幮丗http://www.city.mishima.shizuoka.jp/kakukaHP_system_kanrika/amenity/rekishi/jinja/jinnja.htm)
埳梊偲摨條偵丄乽嶰搱戝幮乿偺愛幮偲偟偰乽釶強恄幮乿偵釶屗巐拰恄偑釰傜傟偰偍傝丄乽杮幮偵晅懏偟丄杮幮偵墢屘偺怺偄恄傪釰偭偨恄幮乿偲偝傟偰偄偰丅
(釶強恄幮丗http://www.city.mishima.shizuoka.jp/kakukaHP_system_kanrika/amenity/rekishi/jinja/jinnja.htm)
2008.11.01暘偱偼丄2003.04.11暘偱偺庒幠偺乽嫊嬻憼怣嬄乿偲乽偆側偓乿偺偙偲偵偮偄偰傕怗傟偰偄偨偑丄乽僂僫僊偵悈恄偦偺傕偺丄偁傞偄偼悈恄偺巜椷幰偲峫偊傜傟偰偄偨偺偱偁傠偆丅乿偲偁傝丄乽惎媨恄幮偺恄條偺巊偄乿偑乽偆側偓乿偲偝傟偰偄偰偙偪傜偼杮暔偺恄偑釰傜傟偰偄偨偺偱丄懞恖偼偆側偓傪怘傋側偐偭偨偺偱偼側偄偐丄偲丒丒丒屼嵳恄偑乽揤屼拞庡戝恄乿偵側偭偰偼偄傞偑丅
(庒幠偺揱愢(媿媣徖丒惎媨恄幮)丗http://www.ushikunuma.com/minwa/wakashiba.htm)
(棿働嶈巗庒幠挰丒惎媨恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/jinjya/hosimiya_a.html)
摨條偵丄孲忋巗旤暲挰崅嵒偱傕乽嫊嬻憼怣嬄乿乽偆側偓乿乽惎媨恄幮乿偑宷偑傝丄乽墌嬻乿傕偙偙偱乽悾怐捗昉乿傪尒偨傛偆偵巚偆偺偩偑丄2010.02.10暘偱偺乽墡娵懢晇乿偺晝偲偝傟偰偄傞乽摗尨崅岝乿偑偳偆傕傂偭偐偐偭偰丒丒丒撊栘偺乽惎媨恄幮乿偱偼乽揤崄崄攚抝柦乿偑懡偔釰傜傟偰偄傞傛偆偩偑丒丒丒
(惎媨恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/jinjya/hosimiya_a.html)
(孲忋巗旤暲挰崅嵒丒惎媨恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/gifu/gujyosi/hosimiya_minami/hosimiya.html)
(撨斾怴媨恄幮丗http://www.windsnet.ne.jp/inaka/080418/inaka.html)
尵偄揱偊偵偁傞偲偄偆乽楈婽擭娫丄崅夑偺抧偵偼岝傪曻偮杺暔廧傒拝偄偨乿偲偟偰乽挬掛乿偺柤偱晄斾摍傜偑愭廧柉傪捛偄弌偟丄僥儕僩儕乕傪忔偭庢偭偨偺傪丄乽揤楋擭娫丄偙偺抧偵梔夦偝傞偲傜傊傃偑廧傒晅偒丄懞恖偵婋奞傪壛偊偰偄傞乿偲偟偰偙偺抧偵巊傢偝傟偨乽摗尨崅岝乿偑丄乽挬掛乿偺柤偱愭廧柉偺嵳釰偵栠偟偨丄偲偄偆偙偲偵側傞傛偆側丒丒丒偦傟偱乽屆崱揱庼乿偵乽闗乿偑偁傞偺偐傕丠
(撨斾怴媨恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E6%AF%94%E6%96%B0%E5%AE%AE%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(擔杮偺尮棳傪夝偔丗http://www.syakusyorin.com/rokusyameguri.html)
偩偲偡傞偲丄戝嶰搰偱偺乽堏揮愭乮尰嵼偺幮抧乯偵偼恖乆偵埆偝傪偡傞乽戝幹乿偑偄偨偲彂偐傟丄偦傟傪捔傔傞偨傔偵乽撿嶳乿乮尰嵼偺埨恄嶳乯捀忋偵乽屲棿墹乿傪傑偮偭偨乿偲偝傟偰偄傞偺偲摨偠傛偆側姶偠偐偲丒丒丒丅
| 仠2011.01.10(Mon.) |
巚偆偵丄晽椩摪偝傫偺僽儘僌偵偁偭偨乽戝幹亖幹恄傪棿麀偵徃奿偝偣偰傑偮傞偙偲偱丄棿麀偺峳嵃亖埆恄乮戝幹乯傪捔傔偨乿偺偑婎杮側偺偐傕丄偲丅
壗搙偐彂偄偰偒偨傛偆偵丄揷懞杻楥偵傛傞搶崙偺暯掕偲偐丄恄晲搶惇偵敽偆棎偲偐丄杮摉偵偁偭偨偙偲側偺偐偳偆偐偵媈栤傪帩偭偰偄偰丄乽骐缁偡傞墔楈乿偲偄偆屆杮傪敿暘傎偳撉傫偱丄傗偼傝偦偆偠傖側偄偐偲巚偭偨傢偗偱丅
暯埨帪戙偵偼乽墔楈乿偲偟偰嫲傟傜傟傞傎偳偺僷儚乕傪帩偨偣丄偺偪偵庤岤偔釰傞偙偲偵傛偭偰乽峳嵃乿偲偝傟偰偄偨帪偲摨偠僷儚乕傪傕偭偰乽榓嵃乿偲側傞偲柉廜偵偼懆偊傜傟偰偄偨偺偐傕偟傟側偄偑丄摴恀側偳丄墔楈偲偝傟偨恖乆偑偦傟傎偳傑偱偵憺偟傒傪帩偭偰偄偨偐偵媈栤偑偁傝丄杮恖傛傝傕傑傢傝偵偄偨恖乆偑丄娮傟傜傟偨忬嫷傪庴偗擖傟偞傞傪摼偢懴偊偰偄傞偺傪尒偐偹丄乽恎偑楐偐傟傞巚偄乿偑岅傝宲偑傟偨偺偱偼丅
偨偩丄偦偙偵偼庴偗擖傟偞傞傪摼側偐偭偨忬嫷傗丄杮恖偺堄巚偼偁傑傝斀塮偝傟偰偄側偐偭偨偺偐傕偟傟側偄傛偆偵巚傢傟傞偑丒丒丒丅
乽婰婭乿偑乽惓巎乿偲偝傟傞側傜丄偦偙偵偼昤偐傟偰偄側偄柍幚偺嵾偱攕幰偲偝傟偰偟傑偭偨懁偺乽帠幚乿傪丄乽婰婭乿偺庤朄傪梡偄偰棳晍偝偣丄僷儚乕傾僢僾偝偣偨偺偑乽墔楈乿側偺偱偼丄偲丅
揷懞杻楥偑庡偵乽惇敯乿偟偨揋偲偝傟偰偒偨傛偆偩偑丄偦偺傛偆偵側傜側偄傛偆偵僶儔儞僗傪偲偭偨偺偑丄乽墔楈乿傪弉抦偟偰偄偨(墔楈偲偟偰惉挿偝偣偨丠)埨攞巵傗夑栁巵側偳偺乽堿梲巘乿偱偼側偄偐偲丅
偩偑丄偦偺僇儔僋儕偑僶儗偨偐媡偵棙梡偝傟偨偐偵傛偭偰乽堿梲巘乿偺椡偑嶍偑傟偨偺偪丄帺傜惗偒傞乽墔楈乿偲側偭偨偺偑乽尮棅挬乿偱偼側偄偐偲峫偊傜傟丄姍憅側偳偱峴婎偺懌愓偲廳側傞偺偼乽峴婎僾儘僕僃僋僩乿偺懚嵼傪抦偭偰偄偰丄偦偺攚屻偵偄偨巵懓偺僶僢僋傾僢僾傪摼傞偙偲偵傛偭偰姍憅枊晎傪抸偔偙偲偑偱偒偨偺偱偼側偄偐丄偲丅
棅挬偺晝丒媊挬偼乽搶崙傊偺摝旔峴乿偺搑拞偱乽壠恖(摗尨廏嫿棳庱摗巵偺堦懓偺姍揷惌惔偺鋘丒挿揷拤抳)偵棤愗傜傟杁嶦偝傟偨乿傛偆偩偑丄棅挬偼乽搶崙傊偺摝旔峴乿偟偨棟桼傕傢偐偭偰偄偨偩傠偆偟丄乽壠恖偵棤愗傜傟杁嶦偝傟偨乿偲偄偆偺傕丄乽(挿揷拤抳偺)巕懛偼晲揷巵傪棅偭偰峛斻崙傊摝偘偨偲偄偆愢乿偑偁傞偲偄偆偙偲偐傜帠幚娭學偑晄柧偱丄攚屻偱摦偔塭偑尒偊傞傛偆偱丅
(尮媊挬丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E6%9C%9D)
(挿揷拤抳丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%94%B0%E5%BF%A0%E8%87%B4)
榓揷枽側偳偱偺惔惙偺懌愓傪尒偰偄傞偲丄媊挬偑乽搶崙傊偺摝旔峴乿偱峴偒拝偔梊掕偩偭偨巵懓偺釰傞乽悾怐捗昉乿偵偮偄偰抦偭偰偄偨偲巚傢傟丄愴崙帪戙偱偺壨栰巵偲挿廆変晹巵傗晲揷巵偲忋悪巵側偳偺傛偆偵丄怣嬄傪挻偊偨揋懳娭學偑惗偠偨攚宨偑婥偵側傞偑丒丒丒偁丄彨栧偲廏嫿傕摨條偐偲丅
墶摴偵偦傟偰偟傑偭偨偑丄乽骐缁偡傞墔楈乿偲偄偆杮偵乽棅挬偑巰幰偺楈嵃偵晀姶偱丄偦偺嫙梴偵怱傪攝偭偰偄偨偙偲偑偆偐偑偊傛偆丅乿(p113)偲偁偭偨偑丄偦偺慜偺儁乕僕偵乽掃壀敧敠媨偑墔楈捔嵃偲偄偆柺傕堷偒懕偒帩偭偰偄偨偙偲傪堄枴偟偰偄傛偆丅乿偲偁傞傛偆偵乽敧敠媨乿偑娭梌偟偰偄傞偲巚傢傟傞偙偲傗丄乽暯壠暔岅乿偱乽埨摽揤峜埲壓偑棿恄偺崤懏偵側偭偨乿偙偲傪寶楃栧堾偑柌偵尒偨偲偄偆偙偲偵偮偄偰丄乽棿媨偲偼丄揤峜偵傛偭偰巟攝偝傟偰偄傞尰悽傪丄尒偊側偄椡偵傛偭偰憖傞傕偆堦偮偺悽奅偱偁傞偲擣幆偝傟偰偄偨偙偲偑傢偐傞丅乿(p106)偲偺偙偲側偳偐傜丄乽棿媨乿偵宷偑傞乽搶崙乿偺巵懓偑尒偊偰偔傞傛偆偱丄偦偺恖乆偑棅挬偺攚屻偵偄偨丄偲偄偆偙偲偱偼丄偲丅
偡側傢偪乽墔楈乿偲偼丄乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿傪帩偮奀恖懓偱偁傝丄乽峴婎僾儘僕僃僋僩乿傪巟偊偨巵懓偱偁傝丄嬨廈偱偼乽孎廝乿乽敼恖乿偲屇偽傟丄搶崙偱偼乽壼埼乿偲屇偽傟偨乽挬揋乿偲偝傟偨巵懓側偺偱偼丅
偦偆偟偨夁嫀傪尒偰偒偰丄帺傜乽墔楈乿偵傕側傝乽慞恄乿偲偝偣偨偺偑乽壠峃乿偐偲丅
| 仠2011.01.11(Tue.) |
乽嬭庫乿乽擁乿乽嬨摢乿乽妺乿側偳丄宷偑傝偑偁傞偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偄偨偺偱丄恄撧旛偝傫偺乽惵憪択榖幒乿偱偺丄乽戝搧榚恄幮乿偺屼恄懱偺嵍榚偑乽嬨摢戝柧恄乿偱乽悈恄乿偺乽彈恄乿偲偁傞偺偼嫽枴怺偄偱偡偹丅
(5830丒嬨摢戝柧恄偼彈恄丗http://ucgi.kamnavi.net/cgi-bin/aokbbs.cgi)
(彈恄偺嬨摢恄丗http://6314.teacup.com/kamnavi/bbs/)
偁丄2009.11.28暘偱偺乽慮崻崙捗恄幮乿偺乽崙捗乿傗丄乽崙惒乿乽崙憙乿乽崙炰乿側偳傕宷偑傞偐偲丅
(乽崙惒乿乽崙憙乿乽崙炰乿丗http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/61449/m0u/)
(擇揷崙捗恄幮丗http://mononobe.nobody.jp/tabi/sone/sone.htm)
(嶗堜巗丒崙捗恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/nara/sakuraisi/kunitu/kunitu.html)
(堧婒巗丒崙捗恄幮丗http://www.genbu.net/data/iki/kunitu_title.htm)
(崅徏巗丒崙捗恄幮丗http://kagawa.bine.jp/jinnjya/kounan/17kuni/17kuni.html)
(柤挘巗丒崙捗恄幮丗http://hitozato-kyoboku.com/kunitsujinja-sugi.html)
(壀嶳巗丒崙捗恄幮丗http://www.okayama-jinjacho.or.jp/cgi-bin/jsearch.cgi?mode=detail&jcode=01028)
(桳揷孲丒崙捗恄幮丗http://kamnavi.jp/ki/nanki/kunitu.htm)
(徏嶳巗丒崙捗斾屆柦恄幮丗http://mononobe.nobody.jp/tabi/kazahaya/kunitu-kusitama.htm)
(徏嶳巗丒崙捗斾屆柦恄幮丗http://www.genbu.net/data/iyo/kunitu_title.htm)
(婭偺愳巗丒奀恄幮(崙捗昉柦)丗http://www.genbu.net/data/kii/umi2_title.htm)
(杊晎巗丒崙捗昉恄幮丗http://www.geocities.jp/mb1527/N3-15-1tousen4.html)
(梬愔傔偖傝丂崙惒丗http://www.harusan1925.net/0107.html)
偐偮偰偺妎偊彂偒傪娷傔丄峴婎棈傒偺棅挬偺懌愓傪傑偲傔偰彂偄偰偍偔偙偲偵偟傑偡丅偐偮偰挷傋偨拞偱偼丄偄偔偮偐倀俼俴偑側偔側偭偰偄傞僒僀僩偑偁偭偨偺偱丄暿偺僒僀僩傪扵偟偰儕儞僋傪偼偭偰偍傝丄堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨売強偺娫堘偄摍傕廋惓偟偰偍傝傑偡丅
- 2004/03/29暘偺乽媊宱乿乽棅挬乿偲峴婎偵娭偡傞妎偊彂偒偲乽恄撧愳乿偱偺乽棅挬乿偲峴婎偵娭偡傞帠暱 -
仭棾岇嶳 枮暉帥(崢墇枮暉帥)丂姍憅巗崢墇
744乮揤暯16乯擭偵峴婎偑奐偄偨偲偄傢傟傞屆檵偱丄尮媊宱偑乭崢墇忬乭傪彂偄偨帥偲偟偰柤崅偄偍帥偱偡丅
仭悪杮帥丂姍憅巗擇奒摪
俈俁係擭乮揤暯俇擭乯峴婎偑廫堦柺娤壒傪埨抲偟偰憂寶偟偨偺偵巒傑傞偲揱偊傜傟傞丅1189擭乮暥帯5擭乯摪塅偑從幐偟偰偄傞偑丄偙偺偲偒娤壒憸偼帺傜杮摪偐傜弌偰丄嫬撪偵旔擄偟偨偲揱偊傜傟傞丅偦偺屻丄1191擭乮寶媣2擭乯偵偼尮棅挬偑偙偺帥傪嵞嫽偟偨偲偄偆丅
仭悙墳嶳 峅柧帥丂墶昹巗撿嬫峅柧帥
乮奐婎丗峴婎曥嶧乯亀屷嵢嬀亁偵傛傟偽姍憅帪戙偼尮壠椵戙偺婩婅強偲偟偰丄尰悽埨塀偺棙塿傪懚暘偵晲彨偨偪偵梌偊偰偒偨傛偆偩丅尮棅挬偼憁峴婎傪懜悞偟偰偄偨偺偱丄偙偺帥傪嶁搶嶥強偺拞偵擖傟偨偲傕峫偊傜傟傞丅
仭擔岦栻巘丂埳惃尨巗擔岦
帥揱偱偼楈婽2擭乮716擭乯丄峴婎偺奐嶳偲偄偆丅(拞棯)姍憅帪戙偺巎彂亀屷嵢嬀亁偵傕擔岦栻巘偵偐偐傢傞婰帠偑尒傜傟傞丅寶媣3擭乮1192擭乯8寧9擔忦偵偼丄尮棅挬偺嵢丒杒忦惌巕偺埨嶻婩婅偺偨傔偵撉宱傪偝偣偨帥堾偺1偮偲偟偰楈嶳帥偺柤偑尒偊傞乮偙偺帪惗傑傟偨巕偑屻偺尮幚挬乯丅傑偨丄寶媣5擭乮1194擭乯8寧8擔忦偵偼丄尮棅挬偑柡偺戝昉偺昦暯桙婩婅偺偨傔帺傜乽擔岦嶳乿傊嶲寃偟偨偲偺婰嵹偑偁傞丅
仭挿扟帥乮斞嶳娤壒乯丂岤栘巗斞嶳
俈俀俆擭乮恄婽俀擭乯偵峴婎偵傛偭偰奐偐傟偨偲傕丄俉侾侽乣俉俀係擭偺峅恗擭娫偵峅朄戝巘乮嬻奀乯傛偭偰奐偐傟偨偲傕揱偊傜傟偰偄傞丅傑偨丄尮棅挬偑廐揷忛夘媊宨乮埨払惙挿偺巕乯偵柦偠偰摪塅傪憿塩偝偣偨偺偑丄偙偺帥偺偼偠傑傝偲傕揱偊傜傟偰偄傞乮榌偺嬥崉帥偵惙挿偺曟偲揱偊傜傟偰偄傞屲椫搩偑偁傞丅乯丅杮懜偼廫堦柺娤壒偱丄峴婎偑僋僗僲僉偱憿偭偨偲偄偆懜憸偑戀撪偵擺傔傜傟偰偄傞偲偄偆丅
仭棿憼恄幮丂岤栘巗斞嶳
俈俀俆擭乮恄婽俀擭乯丄峴婎偵傛傝姪惪偝傟偨偲揱偊傜傟傞丅侾侾俉侽擭乮帯彸係擭乯丄尮棅挬偺婅偵傛傝丄恄釲姱(敀壨揳)曭暭偺憡柾崙榋廫堦幮偵擖傞丅侾俆俋侾擭乮揤惓侾俋擭乯偵偼丄摽愳壠峃偐傜幮椞俀愇偺庨報忬傪帓偭偰偄傞丅嵟嬤傑偱丄敀棿揱愢乮斞嶳偺幍晄巚媍乯偺敀嶳恄幮偑崌釰偝傟偰偄偨丅屼嵳恄丗媺挿捗旻柦丄媺挿屗曈柦
仭敀嶳恄幮丂岤栘巗斞嶳
幮揳偺慜偵偼丄抮乮敀嶳抮乯偑偁偭偰丄屆偔偐傜塉岊偄偺楈抧偲偝傟偰偒偨丅斞嶳娤壒乮挿扟帥乯傪奐偄偨偲偝傟傞峴婎偼丄偙偺嶳傪搊傝丄楈悈偑桸偒弌偟偰偄傞抮傪敪尒偟丄壛夑崙敀嶳柇棟戝尃尰傪姪惪偟偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅偦偟偰丄僋僗僲僉偱挙傜傟偨廫堦柺娤壒偑釰傜傟偨偲偄偆丅偙偺廫堦柺娤壒偑尰嵼偺斞嶳娤壒乮挿扟帥乯偺杮懜偲偄傢傟偰偄傞丅柧帯弶擭崰偵壩嵭偵憳偄丄棿憼恄幮偵崌釰偝傟偰偄偨偑丄徍榓俆俆擭偵尰嵼偺幮偑嵞寶偝傟偰偄傞丅
仭惎扟帥丂嵗娫巗擖扟
惞晲揤峜偺屼塅峴婎曥嶧偑彅崙嫵壔偺嵺埡啵偨傞嬥岝惎偺擛偔嶳扟偵婸偔偺傪尒丄帺傜惞娤壒偺憸傪挙崗偟丄摪塅傪塩傒傑偟偨丅壴嶳朄峜偑娭搶弰岾偺嵺偙偺楈応偵棫偪婑傜傟埲屻悽傪嫇偘柤強媽愓偲塖摫偟丄嶁搶嶰廫嶰儢強偺戞敧斣偲偟偰弰攓幰偑擔枅偵懡偔側傝傑偟偨丅尮棅挬岞偺怣嬄撃偔摽愳壠峃岞偐傜傕婣埶傪庴偗傑偟偨丅
仭撧椙暯埨婜偺姍憅丂屆戙姍憅偺孮棊偲摴丗http://www.ktmchi.com/rekisi/cys_11.html
- 偦偺懠乽棅挬乿偲峴婎偵娭偡傞帠暱 -
仭搶戝帥丒楌巎擭昞丂撧椙導撧椙巗嶨巌挰
1185擭丄尮棅挬丄廳尮偵暷1枩愇丒嵒嬥愮椉丒忋對愮旸傪憲傝嵞嫽傪彆惉丄1190擭丄尮棅挬丄枾偐偵巐揤墹帥丒搶戝帥偵嶲寃丄1195擭丄尮棅挬丄攏愮摢丒暷1枩愇丒墿嬥愮椉丒對愮旸摍傪廳偹偰婑恑丄戝暓揳棊宑嫙梴偄偰椪傓丅
仭榋灩嶳丂廆暉堾丂嶳宍巗嶳宍巗揝朇挰侾亅俀亅俀侽
憂寶偼峴婎偲偝傟偰偄傞丅掑娤擇擭乮俉俇侽擭乯偵帨妎戝巘偑摉抧傪朘傟丄榋杮偺僋僰僊偺栘傪怉嵧偟偰乮尮棅挬偑僋僰僊傪怉偊偨偲偺愢傕偁傞乯尰嵼偲枹棃偺擇悽埨妝傪婩傝擖嵃偟偨偙偲偐傜Z灩茤綎紓祩絺苽爞鑲軅穪B屼杮懜偼峴婎嶌偲偄傢傟傞惞娤悽壒曥嶧偲惃帄曥嶧偺擇懱丅乮旈暓乯
仭嶌暲壏愹丂愬戜巗惵梩嬫
栺侾俀俉侽擭慜偵峴婎偑敪尒偟偨愢丄栺俉侾侽擭慜偵尮棅挬偑敪尒偟偨偲偄偆愢偑偁傞丅
仭憪捗壏愹丂孮攏導屷嵢孲憪捗挰
俆悽婭偛傠丄擔杮晲懜偑搶惇偺愜偵敪尒偟偨偲偄偆愢丄梴榁俆(721)擭偵峴婎偑栻巘摪乮尰嵼偺岝愹帥撪乯傪奐婎偟偨嵺偵奐搾偟偨偲偄偆愢丄寶媣係擭(1193)俉寧丄尮棅挬偑愺娫嶳偱偺姫庪傝傪峴側偭偨嵺偵棫偪婑偭偰敪尒偟偨偲偡傞愢偑偁傞丅
仭怴嵗柉榖乮愮懱抧憼偝傑乯丂嶉嬍導怴嵗巗
嶁忋揷懞杻楥丄峴婎丄棅挬偲乽抧憼曥嶧乿偲偺宷偑傝偑暔岅偲側偭偰偄傞丅
仭峛廈傇偳偆敪惗偺揱愢 嶳棞導峛廈巗彑徖
暥帯俀擭乮侾侾俉俇擭乯忋娾嶈偺廧恖丄塉媨姩夝桼偑愇懜嵳傊偺嶲楍偺搑拞偱敪尒丒嵧攟偟丄棅挬偑挿栰偺慞岝帥偵嶲寃偺嵺丄偦偺傇偳偆傪嶰売偛專忋丄偦偺屻丄塉媨姩夝桼偺巕懛偺塉媨怐晹惓偼椞庡晲揷怣尯傊傇偳偆傪專忋偟偨偲偄偆乽塉媨姩夝桼揱愢乿偲丄梴榁俀擭乮俈侾俉擭乯偵峴婎偑峛廈巗彑徖偺抧偱楈柌傪尒偰丄働儎僉偺戝庽傪愗偭偰栻巘擛棃偺屼巔傪崗傫偱戝慞帥偵埨抲偟偨偲偄偆乽戝慞帥愢乿偑偁傞丅
仭壛巕曣戝悪抧憼懜丂婒晫導拞捗愳巗壛巕曣(媽宐撨孲壛巕曣懞)
尮棅挬偑丄寶媣屲擭(1194)偵惣曽嶰昐儊乕僩儖偵偁偭偨抧憼摪偵棫偪丄偙偺戝悪傪巜偟偰偙偺戝栘偺壓偵抧憼懜傪埨抲偡傞傛偆崘偘偨偲偄傢傟傞傕偺偱丄墑柦挿庻丄埨嶻偺庣偲偟偰怣嬄傪廤傔傞杮懜偼峴婎偺嶌偲偄傢傟傞栘挙傝憸偱偁傞丅
仭崅憅嶳恀栰帥乮恀栰戝崟揤乯丂愮梩導撿朳憤巗(媽埨朳孲)娵嶳挰
恄婽擇擭 (725擭)偵丄崅憁丒峴婎曥嶧偵傛偭偰杮帥偼奐嶳偟傑 偟偨丅(拞棯)帯彸嶰擭偵偼丆尮棅挬岞偑尮巵嵞嫽偺婩婅偺偨傔偵棫偪 婑傝丄傑偨丄屻偵偼棦尒媊嬆岞偵傛傝椞揷傪帓傝丄摽愳彨 孯壠偐傜偼丄屼庨報巐廫嶰愇傪帓偭偰棽惙傪嬌傔傑偟偨丅屼杮懜丗愮庤娤壒丅
(峴婎曥嶧愮擇昐屲廫擭屼墦婖婰擮帍乽峴婎曥嶧乿婰嵹偺峴婎備偐傝偺帥堾)
仭擔杮帥丂愮梩導埨朳孲嫎撿挰
惞晲揤峜偺捄徺偲丄岝柧峜岪偺偍尵梩傪庴偗偨峴婎曥嶧偵傛偭偰恄婽2擭乮725擭乯6寧8擔偵奐嶳偝傟傑偟偨丅奐嶳摉弶朄憡廆偵懏偟丄揤戜廆丄恀尵廆傪宱偰摽愳嶰戙彨孯壠岝岞偺帯悽偺帪偵憘摯慣廆偲側傝丄崱擔偵帄偭偰偍傝傑偡丅(拞棯)尮棅挬偼愇嫶嶳偺愴偄偵攕傟偨屻丄朳廈偵摝傟嵞婲傪恾偭偨愜偵擔杮帥偱晲塣傪婩婅偟丄帺傜慼揝傪庤怉偊偟丄尰嵼傕戝慼揝偲偟偰嫬撪偵巆偭偰偍傝傑偡丅棅挬偼姍憅枊晎傪奐偔偲偡偖偵峳攑偟偰偄偨擔杮帥偺慡嶳廋岺偵椡傪恠偔偟丄梴榓尦擭乮1181擭乯 栻巘杮揳傪嵞寶偟傑偟偨丅棅挬偵傛傝慡嶳廋岺偝傟偨擔杮帥偼丄偦偺屻丄姍憅枊晎屻婜偐傜撿杒挬帪戙偵偐偗偰偺懕偔愴壩偵傛傝嵞傃峳攑偟傑偡偑丄懌棙懜巵偵傛傝嵞傃暅嫽偝傟傑偡丅屼杮懜偼栻巘椱棡岝擛棃丅
仭愮梩帥丂愮梩導愮梩巗拞墰嬫愮梩帥挰
愮梩孲抮揷嫿傪朘傟偨峴婎偑丄榓摵俀乮俈侽俋乯擭丄娤壒憸擇懳傪挙偭偰摨抧偵埨抲丅寶媣俁乮侾侾俋俀乯擭丄棅挬偼忢堺偵柦偠偰愮梩帥嵞寶偺搚栘岺帠傪偼偠傔丄棊惉偺揟傪峴偄丄暓巘塣宑嶌偺垽愼柧墹憸傪婑恑丅揤惓侾俋乮侾俆俋侾乯擭丄摽愳壠峃偑壘棔傪嵞寶丄帥椞偲偟偰昐愇傪塱戙婑恑偟偨丅
(峴婎曥嶧愮擇昐屲廫擭屼墦婖婰擮帍乽峴婎曥嶧乿婰嵹偺峴婎備偐傝偺帥堾)
仭恀働扟懢巕摪丂愮梩導巗尨巗恀働扟
尦敔崻尃尰偺暿摉丒尮奀垻妕棞偵傛傞乽恀儢扟懢巕摪墢婲乿偵傛傞偲丄峴婎丄惞摽懢巕丄棅挬偺宷偑傝偑彂偐傟偰偄傞傛偆偱丄棅挬偺塺傫偩偲偝傟傞壧乽尮偼偍側偠棳傟偧愇惔悈丂偣偒偁偗偙偨傊 偐傒偺偆傊傑偱乿偵偼丄乽暎偺柧恄偝傑乿偺悈偺棳傟偼棅挬偺怣曭偡傞敧敠戝曥嶧偲尮偼摨偠偱偁傞偐傜丄娭傪偁偗偰帺暘偺朷傒偵偙偨偊偰愇忋偺恄乆偵嶲寃偱偒傞傛偆偵偟偰偔偩偝偄(愇惔悈敧敠媨偼丆搒偺棤婼栧傪庣岇偡傞恄偱偁傞丅偮傑傝丆忋嫗偟偰揤壓傪庢傜偣偰偔偩偝偄丆偲偄偆偙偲)偲偄偆堄枴傪娷傫偱偄傞丄偲偝傟偰偄傞丅
仭撨屆帥丂愮梩導娰嶳巗撨屆
奐婎偼峴婎丅拞嫽偺慶偼帨妎戝巘丅尮棅挬丄懌棙丒棦尒丒摽愳巵傛傝斴岇(傂偛)傪庴偗丄掃扟敧敠媨偺暿摉帥偱傕偁偭偨偑丄柧帯堐怴偱帥椞偼杤廂偝傟偨丅(拞棯)愮庤娤壒曥嶧偺桼弿偼丄梴榁尦(俈侾俈)擭尦惓揤峜偺昦婥暯桙偺偨傔丄峴婎偑奀拞傛傝忋偘偨堎栘偱愮庤娤壒憸傪挙傝丄婩摌偵傛傝夣桙偝傟偨偙偲偵傛傞丅屼杮懜偼愮庤娤悽壒曥嶧丄嶁搶嶰廫嶰斣娤壒嶥強偺寢婅帥丅
仭嵟彑帥丂撊栘導懌棙巗
杮懜偼堦悺敧暘屲l僙儞僠偺弮嬥惢偱丄惞摽懢巕偺嶌偲揱偊傜傟偰偄傑偡乮旕岞奐乯丅峴婎忋恖 嶌偲尵傢傟傞丄幍広擇悺乮擇儊乕僩儖廫敧僙儞僠乯偺旟嵐栧揤偑戀撪暓偲偟偰擺傔傜傟偰偄傑偡乮旕岞奐乯丅(拞棯)尮棅挬偺墱廈惇敯偺嵺偵傕愴彑婩婅傪峴偭偰偄傑偡偑丄偙傟偼棅媊丄媊壠偺屘帠偵廗偭偨偺偩偲巚傢傟傑偡丅
仭婅惉廇堾丂惷壀導埳摛偺崙巗(媽揷曽孲擝嶳挰)
峴婎偺奐憂偲揱偊傞丅嵞嫽偼暥帯5擭乮1189乯丄奐婎偼杒忦帪惌丅尮棅挬偑丄帪惌偵柦偠偰杒忦巵斏塰偲墱廈摗尨巵惇敯傪婩傝嵞嫽偝偣偨傕偺丅
仭晛栧帥丂垽抦導朙嫶巗塤扟挰僫儀嶳壓7
憂寶擭戙偵偮偄偰偼晄徻偱偁傞偑丄亀嶰廈慏宍嶳晛栧帥棯墢婲亁偵傛傟偽丄撧椙帪戙偺憁峴婎乮俇俇俉-俈係俋乯偵傛偭偰恄婽係擭乮727擭乯偵憂寶偝傟偨偲偝傟傞丅壝墳擭娫乮侾侾俇俋擭 -侾侾俈侾擭乯偵揤戜廆偺憁偑恀尵廆帥堾偵側偭偰偄偨摉嶳偱庡摫尃傪偲傠偆偲偟偰晲椡徴撍偟暫壩偵偁偭偰從幐偟偨偲揱偊傜傟丄偦偺屻尮棅挬偵傛偭偰暅嫽偝傟偨偲偝傟傞乮妬尨宨婫傪捠偠偰帥椞傪婑恑偡傞偲嫟偵棅挬帺恎傕嶲寃乯丅棅挬偺柦椷偱丄暥妎傕摉嶳偵偍偄偰婩摌傪偟偰偄傞丅
仭愒娾帥丂垽抦導朙嫶巗懡暷挰愒娾嶳
峴婎偑恄婽3擭(726)偵奐婎偟偨偲揱偊傜傟丄偦偺屻丄嬻奀 偺崅掜壥椬偑揤埨尦擭(857)偵嵞嫽偟偨偲偄傢傟偰偄傞丅尮棅挬偑丄嶰壨偺柤檵7帥傪慖傫偱摪塅傪憿塩偟偨丄嶰壨幍奀摪偺堦偮偱傕偁傞丅
(峴婎曥嶧愮擇昐屲廫擭屼墦婖婰擮帍乽峴婎曥嶧乿婰嵹偺峴婎備偐傝偺帥堾)
仭嵿夑帥丂垽抦導朙愳巗嵿夑挰娤壒嶳
惞晲揤峜偺捄婅偵傛傝恄婽2擭乮725乯憁峴婎偵傛傝寶棫偝傟偨摴応偱丄偦偺摉帪偼幍摪壘棔偑偁傝丄嶳撪奜偵悢昐偺堾朧傪旛偊偨帥堾偩偭偨丅偦偺屻丄戞俆俀戙嵉夈揤峜偺峅恗4擭 (俉侾俁)恀尵廆慶峅朄戝巘偺拞嫽偵偐偐傝堦憌偺憫尩傪憹偟丄戞俉俀戙屻捁塇揤峜偺寶媣俁擭 (侾侾俋俀擭)尮棅挬偑丄杮摪側傜傃偵恗墹栧傪嵞寶偟偰丄嶰壨幍屼摪 偺堦偮偵悢偊傜傟傞傛偆偵側偭偨偑丄墳恗擭拞 (1468擭崰)暫壩偵偐偐傝丄傢偢偐20梋堾傪巆偡偺傒偲側偭偨丅
仭慡暉帥愓丂垽抦導姉孲巗憡妝挰
慡暉帥偼惞晲掗偺恄婽擭拞丄峴婎偑廫堦柺娤壒傪崗傒丄偙傟傪釰偭偨偺偑婲尮偲偄偆丅偦偺屻丄尮棅挬 偑嶰壨偺庣岇埨払摗嬨榊惙挿偵柦偠偰摪搩傪寶棫偝偣偰嶰壨幍屼摪偺堦偮偲偟偰塰偊丄侾俀憁堾傪旛偊偨戝婯柾側帥堾偱丄揤戜廆偵懏偡傞戜枾偺廋峴摴応偱傕偁偭偨丅
仭戝岝嶳 埨妝帥丂垽抦導忢妸巗姟壆帤怺揷
摉帥偑埵抲偡傞姟壆抧嬫偼丄尮棅挬庡廬偑堦栭傪夁偛偟偨壖偺廻偑抧柤偺傕偲偲尵傢傟傞丅杮懜偼峴婎曥嶧偺嶌偲揱偊傜傟丄侾俆俁俈擭怐揷丄崱愳偺愴壩偐傜庣傞偨傔戞俇侾斣崅嶿帥偐傜堏偝傟偨丅侾俉係俆擭偵杮懜(垻栱懮擛棃)偑嵞寶丅
仭惣椦嶳丂忩搚帥丂垽昋導徏嶳巗戦巕挰1198
帥揱偵傛傟偽揤暯擭娫(俈俀俋乣俈係俉)偵宐柧忋恖偑奐憂偝傟丄杮懜丄庍夀擛棃偼峴婎曥嶧偺嶌偲揱彸偝傟偰偄傞丅偦偺屻丄峅朄戝巘偑偙偺抧傪弰庎偝傟壘棔傪嵞嫽偝傟巐崙楈応偵掕傔傜傟偨丅捗媣俁擭(侾侾俋俀)偵偼尮棅挬偑壠栧偺斏塰傪婩傝摪搩偺廋棟偵椡傪拲偓丄榋廫榋朧丄枛抧俈摍傪桳偡戝帥偲偟偰塰偊偰偄偨偑墳塱擭娫偺暫壩偱從幐丅暥柧侾係擭(侾俈俉侾)偵偼椞庡丄壨栰摴媂偵傛偭偰嵞寶偝傟偨丅巐崙敧廫敧偐強楈応戞巐廫嬨斣丄埳梊廫嶰暓楈応戞擇斣丅
(峴婎曥嶧愮擇昐屲廫擭屼墦婖婰擮帍乽峴婎曥嶧乿婰嵹偺峴婎備偐傝偺帥堾)
- 乽棅挬乿偲乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偵娭楢偡傞偲巚傢傟傞帠暱 -
仭擻乽幍婻棊乿丂
仭昳愳恄幮丂搶嫗搒昳愳嬫杒昳愳嶰挌栚
暥帯3擭乮1187擭乯尮棅挬偑埨朳崙偺廎嶈恄幮偐傜揤斾棟擳鷵柦傪姪惪偟偰釰偭偨偺偵巒傑傞偲揱偊傜傟傞丅
仭廎嶈恄幮(杮抧悅鐟帒椏曋棗)丂愮梩導娰嶳巗廎嶈
孨捤暥梇乽埨朳偺嶳妜怣嬄乿偵丄乽廎僲嶈柧恄偵偼曮楋嶰擭乮1753乯偺乽廎僲嶈戝柧恄桼弿媽婰乿偲丄枩帯擇擭乮1659乯暿摉媑徦堾桳尦偵傛偭偰婰偝傟偨乽朳廈埨朳孲廎嶈戝柧恄墢婲乿媦傃惉棫擭戙晄徻偺乽廎僲嶈戝柧恄墢婲乿偲偑偁傞丅偙偺拞偺枩帯墢婲偵傛傞偲丄尦惓揤峜梴榁尦擭乮俈侾俈乯嬨寧揤斾棟擳鷵柦傪姪惪偟曭偭偨偙偲丄揤暯廫擇擭榋寧乮740乯峴婎曥嶧偑偙偺柧恄偵嶲寃偟偰堦広屲悺偺廫堦柺娤壒憸傪挙崗偟杮抧暓偲偟偨悅鐟柧恄捔嵗偺擭崋偵婎偯偔梴榁帥偺柤徧偺桼棃傗栶僲峴幰偺戝幹戅帯偺揱愢傪婰偟丄傑偨姍憅帪戙偵偼媑徦堾丒梴榁帥丒娾杮朧丒拞擵朧丒擖擵朧摍幍暿摉帥傪傕偮惃偄偱偁偭偨偙偲丄偦偺屻偵廎嶈柧恄偺岟摽丒棙惗偑婰偝傟偰偄傞丅乿偲偁傞傜偟偄丅
仭廎嶈恄幮(尯徏巕偝傫偺僒僀僩)(墑婌幃恄幮偺挷嵏偝傫偺僒僀僩)(傇傜傝帥幮傔偖傝偝傫偺僒僀僩)丂愮梩導娰嶳巗廎嶈1697
| (僂傿僉儁僨傿傾傛傝) 庡嵳恄乽揤斾棟搧鷵柦乿偼埨朳恄幮嵳恄揤懢嬍柦偺岪恄偱尦偺柤傪廎僲恄乮偡偝偒偺偐傒乯偲徧偟偨丅 宑挿2擭乮1597擭乯偺挊偲偝傟傞亀嬥娵壠椵戙娪亁偵乽埨朳孲廎媨懞嫑旜嶳偵捔嵗偡傞廎媨岪恄幮偼丄屻偵廎媨柧恄偲徧偟丄偦傟傪墱揳偲偟擇僲媨偲濰偆丅傑偨丄廎嶈懞庤愻嶳偵廎嶈柧恄偁傝丄偙傟傪攓揳偲偟丄堦媨偲濰偆乿偲偁傞偙偲偐傜丄亀拞悽彅崙堦媨惂偺婎慴揑尋媶亁偱偼摉幮偲廎媨恄幮偼乽廎偺恄乿傪釰傞2幮堦懱偺恄幮偱丄摉幮偑乽廎偺恄乿傪釰傞堦媨丄廎媨恄幮偑乽廎偺恄乿傪釰傞擇媨偲偝傟偨偺偱偼側偄偐偲峫嶡偟偰偄傞丅 戝摨2擭乮807擭乯偺亀屆岅廍堚亁偵傛傟偽丄恄晲揤峜尦擭乮婭尦慜660擭乯偵恄晲揤峜偺柦傪庴偗偨揤晉柦偑旍梹側搚抧傪媮傔偰垻攇崙傊忋棨偟丄偦偙傪奐戱偟偨屻丄偝傜偵旍梹側搚抧傪媮傔偰垻攇婖晹巵偺堦晹傪棪偄朳憤敿搰偵忋棨偟偨偲偝傟偰偄傞丅曮楋3擭乮1753擭乯偵惉棫偟偨摉幮偺幮揱亀廎嶈戝柧恄桼弿媽婰亁偵傛傟偽丄恄晲揤峜偺帯悽丄揤晉柦偑慶曣恄偺揤斾棟擳鷵柦偑帩偭偰偄偨嬀傪恄懱偲偟偰丄旤懡椙廎嶳乮屼庤愻嶳乯偵釰偭偨偺偑摉幮偺巒傑傝偱偁傞偲偄偆丅 傑偨丄亀埨朳婖晹壠宯擵恾亁傗亀嵵晹廻擧杮宯挔亁偵偼丄揤晉柦15戙栚偺巕懛偱偁傞嵅夑巣偺戞2巕丒怓暏偑弶傔偰慶恄揤懢嬍柦偺岪恄傪釰偭偨偲偺婰弎偑偁傞丅亀埨朳婖晹壠宯擵恾亁傗亀嵵晹廻擧杮宯挔亁偱偼怓暏偺孼偺戞4巕丒壛撧枩楥偑埨朳恄幮戞22戙釱姱偲偟偰彑媊偲夵柤偟丄彑塝嶈乮廎嶈乯偵壖媨傪嶌偭偰揤斾棟搧鷵柦傪釰偭偨偲偟偰偍傝丄亀擔杮偺恄乆 -恄幮偲惞抧-丂11丂娭搶亁偱偼怓暏偑弶傔偰釰偭偨嵵応偼戝榓崙偱丄壛撧枩楥偑彑塝嶈乮廎嶈乯偵壖媨傪嶌偭偨梴榁4擭乮720擭乯7寧偑摉幮偺憂巒偲偝傟偰偄傞丄偲偺愢傪徯夘偟偰偄傞丅 摉幮偺幮揱偵傛傟偽丄梴榁尦擭乮717擭乯戝抧曄偺偨傔嫬撪偺忇儢抮偑杽傑傝丄抧掙偺忇傪庣偭偰偄偨戝幹偑嵭偄偟偨偺偱栶彫妏偑7擔7栭偺婩摌傪峴偄丄柧恄偺偛恄戸偵傛傝戝幹傪戅帯偟偰嵭栵傪彍偄偨偺偩偲尵偆丅傑偨丄栶彫妏偑奀忋埨慡偺偨傔昹捁嫃慜偺奀娸偲墶恵夑偵屼恄愇傪1偮偢偮抲偄偨側偳丄摉幮偵偼廋尡摴偺奐慶偱偁傞栶彫妏偵傑偮傢傞揱彸偑懡偔偁傝丄亀擔杮偺恄乆 -恄幮偲惞抧-丂11丂娭搶亁偱偼摉幮偑屆偔偐傜恄暓廗崌巚憐傗廋尡摴偺塭嬁傪嫮偔庴偗偰偄偨偙偲傪暔岅偭偰偄傞偲弎傋偰偄傞丅 帯彸4擭乮1180擭乯8寧丄尮棅挬偼愇嫶嶳偺崌愴偵攕傟奀楬偱埨朳崙傊摝傟偨丅亀屷嵢嬀亁帯彸4擭乮1180擭乯9寧5擔偺忦偵傛傟偽丄埨朳偵摝傟偨尮棅挬偼忋憤夘媦傃愮梩夘傊嶲忋傪梫惪偡傞巊幰傪憲傝丄摉幮傊嶲攓偟偰巊幰偑岎徛傪惉岟偝偣偰柍帠婣娨偟偨応崌偵偼恄揷傪婑恑偡傞偲偺屼婅彂傪曭偠偰偄傞丅偙偺巊幰偼柍帠偵栶栚傪壥偨偟丄摨擭9寧12擔偺忦偱偼摉幮偵恄揷偑婑恑偝傟偨丅傑偨丄庻塱尦擭乮1182擭乯8寧11擔偺忦偱偼丄棅挬偺嵢惌巕偺埨嶻婩婅偺偨傔丄埨朳崙偺崑懓偱偁傞埨惣嶰榊宨塿偑曭暭巊偲偟偰摉幮傊攈尛偝傟偨偙偲偑婰偝傟偰偄傞丅埲崀傕娭搶晲壠偺悞宧傪庴偗偨丅 |
乽揤斾棟擳鷵柦乿偵偮偄偰偼2008.11.08暘側偳偱彮偟挷傋偰偄偰丄乽垻攇婖晹巵嶲峫宯恾乿偵傛傞偲乽揤攚抝柦乿偺巕偱乽揤擔榟柦乿偺枀偺傛偆偱丄2008.11.10暘偱偼乽揤斾棟擳鷵柦偼搊旤栭恵旟攧丠乿偲彂偄偰偄偰丒丒丒丅
(婖晹巵丗http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/south/s_inbe.html)
徻嵶偼傢偐傜側偐偭偨偑丄婖晹巵偵傛偭偰乽旤懡椙廎嶳乮屼庤愻嶳乯乿偵釰傜傟偨偙偲丄乽摉幮偲廎媨恄幮偼乽廎偺恄乿傪釰傞俀幮堦懱偺恄幮乿偲偝傟偰偄傞偙偲偐傜丄乽悾怐捗昉乿偱偼側偄偐偲巚傢傟傞偑丒丒丒丅
乽廎媨恄幮乿傕庡嵳恄偑乽揤斾棟搧鷵柦乿偱丄憡揳恄偲偟偰乽揤珥彈柦 乿乽揤晊柦乿偑釰傜傟偰偄傞傛偆偱丄乽廎嶈恄幮乿偼崌釰偝傟偰偄傞乽揤懢嬍柦乿偑庡嵳恄偩偭偨壜擻惈傕峫偊傜傟傞偑丄乽廎媨恄幮揱婰乿偵傛傞偲乽巒傔柧恄嶳偺廎偺曈偵捔嵗偟偰偄偨偑丄屻偵嫑旜嶳傊慗嵗丅乿偟丄暥塱侾侽擭乮1273擭乯偺幮揳偺從幐偱壖媨偵捔嵗丄塱嫕侾侾擭乮1439擭乯尰嵼抧傊慗嵗丄偲偺偙偲偱丄偦偺娫偵屼嵳恄偑擖傟懼傢偭偨壜擻惈傕偁傞傛偆側丅
(廎媨恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%B2%E5%AE%AE%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(廎媨恄幮丗http://www.genbu.net/data/awa/sunomiya_title.htm)
(廎媨恄幮丗http://www.geocities.jp/engisiki02/awa1/bun/awa180102-02.html)
偱丄婒晫偺乽壛巕曣戝悪抧憼懜乿偲垽抦偺乽晛栧帥乿偱丄2009.05.03暘偱乽惣峴乿棈傒偱弌偰偒偨乽暥妎乿偺柤偑偁傝丄棅挬偲偺宷偑傝偺怺偄恖暔偺傛偆偱丅
| 暥妎 暯埨帪戙枛婜偐傜姍憅帪戙弶婜偵偐偗偰偺晲巑丒恀尵廆偺憁丅晝偼嵍嬤彨娔栁墦乮傕偪偲偍乯丅懎柤偼墦摗惙墦乮偊傫偳偆傕傝偲偍乯丅暥妛丄偁傞偄偼暥妎忋恖丄暥妎惞恖丄崅旜偺惞偲傕屇偽傟傞丅掜巕偵忋妎丄懛掜巕偵柧宐傜偑偄傞丅 愛捗尮巵嶱壓偺晲巑抍偱偁傞搉曈搣丒墦摗巵偺弌恎偱偁傝丄杒柺晲巑偲偟偰捁塇揤峜偺峜彈摑巕撪恊墹乮忋惣栧堾乯偵巇偊偰偄偨偑丄侾俋嵥偱弌壠偟偨丅 嫗搒崅旜嶳恄岇帥偺嵞嫽傪屻敀壨揤峜偵嫮慽偟偨偨傔丄搉曈搣偺搹椑丒尮棅惌偺抦峴崙偱偁偭偨埳摛崙偵攝棳偝傟傞乮摉帪偼棅惌偺巕尮拠峧偑埳摛庣偱偁偭偨乯丅暥妎偼嬤摗巐榊崙崅偵梐偗傜傟偰撧屆壆帥偵廧傒丄偦偙偱摨偠偔埳摛崙昰儢搰偵攝棳偺恎偩偭偨尮棅挬偲抦嬾傪摼傞丅 |
乽尮暯惙悐婰乿偼丄乽暥妎乿偺弌壠偺尨場偼丄乽廬孼掜偱摨椈偺搉曈搉偺嵢丄孶嵕屼慜偵墶楒曠偟丄岆偭偰嶦偟偰偟傑偭偨偙偲偵偁傞偲偡傞乿偲偁傞傛偆偩偑丄2009.05.06暘側偳偱乽柧宐乿偵傕乽墶楒曠乿愢偑偁偭偨偙偲側偳偐傜悇應偟偨傛偆偵丄乽暥妎乿偺乽墶楒曠乿愢傕丄乽柧宐乿偲宷偑傝偑偁偭偨乽惣峴乿偑塺傫偩彈惈(彈恄)偲嫟捠偡傞偺偱偼側偄偐丄偲丅
乽撢垻乿偑挊偟偨壧榑彂乽堜奮彺乿偵傛傟偽丄乽暥妎乿偼乽惣峴乿傪憺傫偱偄偨偲偺塡偑偁偭偨丄偲偺偙偲偩偑丄2009.05.03暘偱彮偟彂偄偨傛偆偵丄乽愭擖娤偵傛偭偰壗偐傪塀偦偆偲偟偰偄傞乿偙偲偵傛傞傕偺丄偁傞偄偼乽撢垻乿偑偦偺俀恖偵拲栚偡傞傛偆偵巇岦偗偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟偰丅
乽撢垻乿偼乽暥妎乿傕乽惣峴乿傕傛偔抦偭偰偄傞恖暔偲偟偰乽堜奮彺乿偱彂偄偨偲巚傢傟丄2010.02.10暘偵彂偄偨傛偆偵乽撢垻乿偼乽擇忦堊悽乿偐傜乽屆崱揱庼乿傪庴偗偰偍傝丄乽暥妎乿乽惣峴乿偲乽屆崱揱庼乿偺娭楢傪憐憸偝偣傛偆偲丄報徾揑偵彂偄偨偺偱偼側偄偐丄偲丅
乽暥妎乿(搉曈搣)偺懛掜巕偵乽柧宐乿(搾愺搣)偑偄傞偙偲側偳丄乽晲巑抍乿偺宷偑傝偺僂儔偵嫟捠偡傞怣嬄偑偁傞偺偐傕丄偲巚偊傞偙偲偐傜傕丄乽惣峴乿偑塺傫偩彈惈(彈恄)偲宷偑傞偺偱偼側偄偐偲丒丒丒丅
(搣揑晲巑抍丗http://www.ktmchi.com/rekisi/cys_38_55.html)
(乽晲巑抍乿偺寢崌丗http://www.ktmchi.com/rekisi/cys_38_50.html)
埲忋偺傛偆偵丄乽尮棅挬乿偑峴婎傪乽懜悞偟偰偄偨乿崻掙偵偼乽悾怐捗昉乿傊偺怣嬄偑偁傝丄婖晹巵傪偼偠傔丄乽悾怐捗昉乿傪懜悞偟偰偄偨巵懓偐傜偺僶僢僋傾僢僾傪摼偰偄偨偺偱丄乽嫙梴偵怱傪攝偭偰偄偨乿偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞傢偗偱丅
| 仠2011.01.12(Wed.) |
乽棅挬乿偲乽墔楈乿偵偮偄偰彂偔偵偁偨傝丄宷偑傝偺尒偊傞乽暥妎乿乽惣峴乿偵壛偊丄乽墔楈乿偵偮偄偰偑彂偐傟偰偄傞偲偄偆乽嬸娗彺乿偺挊幰乽帨墌乿偵偮偄偰傕挷傋側偒傖偄偗側偄側偀丄偲丅
(嬸娗彺丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9A%E7%AE%A1%E6%8A%84)
(帨墌丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E5%86%86)
(帨墌 愮恖枩庱http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/jien.html)
(尮棅挬 愮恖枩庱丗http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yoritomo.html)
(CiNii 榑暥-惣峴偲帨墌(PDF)丗http://ci.nii.ac.jp/naid/110006607648)
(惣峴偺嫗巘vol.18丗http://sanka05.web.infoseek.co.jp/sankasyu4/218.html)
(惣峴偺嫗巘vol.39丗http://sanka05.web.infoseek.co.jp/sankasyu4/239.html)
(柌枍嘌偺昤偔惣峴丗http://59155480.at.webry.info/200801/article_4.html)
(斾塨嶳柍摦帥丗http://hattoris2.sakura.ne.jp/himudouji991107.htm)
惣峴偺恖娫娭學偼嫽枴怺偄偱偡偹丅
忋婰偺暘傪専嶕偟偰偄傞娫偵丄偝傜偵挷傋傞偙偲偑弌偰偒偨偺偱丄崱擔偼倀俼俴傪彂偔偩偗偵側偭偰偟傑偭偰偡傒傑偣傫丅
| 仠2011.01.13(Yhu.) |
偆乕傫丄傑偨傕傗摨偠撲偵傇偪摉偨偭偨傛偆偱丅
2010.02.09暘偱乽掕壠丄弐惉丄壠棽丄廆釲丄擻場朄巘側偳偺壧旇傕偁傝丄側偺偵攎徳偺偼側偄偺偐側偲巚偭偰偄偨傜丄捠傝夁偓偨偩偗偩偭偨傛偆側丒丒丒揱彸偡傞恖乆偑偄偨偐傜丄帺傜壧偵巆偡昁梫偼側偄偲巚傢傟偨偺偐側偀丄偲丅乿偲丄側偤攎徳偑埳扥偱塺傑側偐偭偨偺偐偑婥偵側偭偰偄偨偑丄乽弐惉丒惣峴丒帨墌偑偦傟偧傟乽杧寭乿傪庡戣偵偟偨榓壧傪巆偟偰偄傞丅乿偲偄偆乽杧寭偺堜乿偵傕婑偭偰偄側偄傛偆偩偟丄摨偠偔惣峴丒庘楡丒棅挬丒帨墌傜偑壧傪塺傫偱偄傞懡夑忛偺乽氣偺旇乿偱傕丄乽媈側偒愮嵨偺婰擮丄崱娽慜偵屆恖偺怱傪墈偡丅峴媟偺堦摽丄懚柦偺墄傃丄悴椃偺楯傪傢偡傟偰煟傕棊傞偽偐傝栫乿偲丄塺傫偱偄側偄傛偆側偺偑婥偵側傞丅
(杧寭偺堜丗http://hattoris2.sakura.ne.jp/noheirinji06120801.htm)
(嶰晉嵞朘婰丗http://www.olff.net/ina13/news/siseki/santome2.htm)
(擔杮晲懜梬愔俀丗http://www.harusan1925.net/0105.html)
(壧岅傝晽搚婰丒杧寭偺堜丗http://nire.main.jp/rouman/fudoki/14sait29.htm)
(杧寭恄幮丗http://www.asahi-net.or.jp/~ab9t-ymh/kakuchi/sayama01/horikane2.html)
(媨忛導撪偺攎徳偺懌愓丗http://yanagi879.donburako.com/drive.utamakura.html)
乽懡夑忛旇乿(氣偺旇)傕丄埫崋乽嶳忋壇椙乿偝傫偺僒僀僩偺乽懡層旇乿偺傛偆偵丄乽屆戙偺抧恾偲應検偵娭傢傞埫崋乿偑塀傟偝傟偰偄偰丄惣峴偨偪偺壧偵傛偭偰偦傟偑傢偐傞偐傜攎徳偼塺傑側偐偭偨偺偐丄偦傟偲傕懠偺棟桼偐傜側偺偐丒丒丒丅
(懡層旇偲偺弌夛偄丗http://www.geocities.jp/yasuko8787/6-nakasone.htm)
乽氣偺旇乿丄乽枛偺徏嶳乿偺偁偲偵朘傟偨丄乽尮媊宱偵巇偊愴巰偟偨拤峵偑丄暥帯3擭乮1187乯偵婑恑偟偨乿偲偄偆乽暥帯摃饽乿偺偁傞媨忛偺乽阣鈣恄幮乿傗乽徏搰乿偱傕丄攎徳偼塺傫偱偄側偄傛偆偱丒丒丒丅
(攎徳摴丗http://bashomichi.com/meisyouchi100/miyagi/)
媨忛導偺乽懡夑忛旇乿丄孮攏導偺乽懡層旇乿偲偲傕偵乽擔杮嶰屆旇乿偲偝傟傞乽撨恵栰崙憿旇乿偺嬤偔偵偼丄乽孼棅挬偺椡偵側傠偆偲丄姍憅偵抷偣嶲偠偨傕偺偺丄寢嬊偼偦偺孼偵捛傢傟傞恎偲側偭偨帪傕偙偺奨摴傪扝偭偨丅乿偲偄偆乽媊宱奨摴乿偑偁傞傛偆偱丄偦偙偱偼惣峴傕攎徳傕壧傪塺傫偱偄傞傛偆偩偑丒丒丒丅
(埌栰壏愹傆傜傝椃丗http://www.basho.jp/cafe/zuihitsu/zuihitsu_06.html)
(梬愔傔偖傝乽惣峴嶗侾乿丗http://www.harusan1925.net/0130.html)
乽懡層旇乿偲乽攎徳乿傪宷偖帠暱偼専嶕偱偼弌側偐偭偨丒丒丒媊拠偑乽媊尗偑嫃廧偟偰偄偨忋栰崙懡層孲乮尰孮攏導懡栰孲乯乿傪弌惗抧偲偡傞愢傗丄孮攏偵偼媊宱偵傑偮傢傞榖偑懡偄傛偆偩偑丒丒丒丅
(尮媊拠丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E4%BB%B2)
偪偲婥偵側偭偨偺偑丄忋栰崙偺斅旲乮尰嵼偺孮攏導埨拞巗乯偱媊宱偑弌夛偭偨偲偄偆乽埳惃嶰榊媊惙乿偑乽搉夛巵乿偲偝傟偰偄傞傛偆偩偑丄懠偺僒僀僩傪攓尒偟偰偄傞偲丄擡幰丠暫朄摴壧乽媊惙昐庱乿偺挊幰丠奀懐丠偲庱傪偐偟偘偨丅
(埳惃嶰榊媊惙偼嶳懐偱偼側偄両両丗http://blog.goo.ne.jp/yositune1189/e/1abcb8b6670857bd27d0f08ee433a990)
(埳惃媊惙丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E7%BE%A9%E7%9B%9B)
(桳柤側擡幰偺柤慜偺姫丗http://sites.google.com/site/mgoshinobiclan/yuumei-na-ninja-no-namae-no)
(擡壧偺棃楌丗http://ci.nii.ac.jp/naid/110000376090)
(戝壨曋忔僔儕乕僘丗http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Sakura/4823/U-dia/sanpo4.html)
暫朄偲壧偲偄偊偽丄2010.05.19暘偺乽昐恖堦庱乿偼乽榋廫巐孴乿偲乽暫朄嶰廫榋寁乿偵嫟捠惈傪帩偮壧偵傛偭偰峔惉偝傟偰偄傞偲偄偆丄彫椦峩巵偺乽怴昐恖堦嬪偲恀幚偺昐恖堦庱乿偺傛偆側姶偠側偺偐側丠徻嵶偼傢偐傜側偐偭偨偗偳丒丒丒丅
偱丄媊拠偑乽恴朘戝幮偵揱傢傞揱彸偱偼堦帪婜丄壓幮偺媨巌偱偁傞嬥巋惙悷偵梐偗傜傟偰廋峴偟偨偲偄傢傟偰偄傞丅乿偙偲傗丄媊宱偑乽埰攏帥乿偵偄偨偲偝傟傞偙偲側偳丄乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偵怺偔娭梌偟偰偄偨偲巚傢傟傞偺偩偑丄偦偺偁偨傝傪挷傋傛丄偲偄偆攎徳偐傜偺儊僢僙乕僕側偺偐丄偲丅
(暥錣嶶曕丒尮媊宱丗http://www51.tok2.com/home/sendatakayuki/bungei/bungei17.html)
乽CiNii 榑暥-惣峴偲帨墌(PDF)乿傪攓尒偟丄偦偙偵彂偐傟偰偄傞壧偵傕壗偐偁傝偦偆側姶偠偑偟偨偑丄巹偵偼傛偔傢偐傜側偔偰丒丒丒偨偲偊偽惣峴偑乽柍摦帥乿偱塺傫偩偲偝傟傞乽偵傎徠傞傗撯偓偨傞挬偵尒傢偨偣偽憜偓備偔愓偺攇偩偵傕側偟乿偑丄乽嵐栱枮惥乿偺乽悽偺拞傪壗偵鏍傊傓挬奐偒憜偓嫀偵偟慏偺愓側偒偛偲偟乿傪杮壧偵偟偰偄傞偲偁傞偑丄乽埫崋 嶳忋壇椙乿偝傫偺乽嵐栱枮惥偺壧偺嶌堊乿偲偺娭楢傕姶偠傜傟傞傛偆偱偁傝側偑傜丄傗偼傝偦傟埲忋偼傢偐傜側偔偰丒丒丒丅
(嵐栱枮惥偺壧偺嶌堊丗http://www.geocities.jp/yasuko8787/0x-t6.htm)
(嵐栱枮惥 愮恖枩庱丗http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/manzei.html)
乽栘慭恖偼奀偺偄偐傝傪偟偢傔偐偹偰巰弌偺嶳偵傕擖傝偵偗傞偐側乿偲偄偆壧傕嵹偭偰偄偨偑丄惣峴偑攎徳偺傛偆偵媊拠傪岲偒偩偭偨偺偐斲偐傕傛偔傢偐傜側偄偟丒丒丒丅
(攎徳偺偆偪側傞惣峴丗http://www.d4.dion.ne.jp/~happyjr/saigyo3/n032_1.html)
(惣峴偑巰偵峴偔媊拠偵曺偘偨壧巐庱丗http://www.st.rim.or.jp/~success/kisoY_ye.html)
愜岥巵偼壗偐婥偯偄偰偍傜傟偨偺偩傠偆偐丒丒丒丅
(愜岥怣晇 抁壧杮幙惉棫偺帪戙 枩梩廤埲屻偺壧晽偺尒傢偨偟丗http://www.aozora.gr.jp/cards/000933/files/46955_26851.html)
偲偄偆偙偲偱丄攎徳傪娷傔偰壧偵娭偡傞帠暱偵偮偄偰偼堦扷抲偄偰偍偔偲偟偰丄傕偆彮偟乽帨墌乿偵娭偡傞専嶕傪偟偨偲偙傠丄乽帨墌乿偲恊偟偐偭偨偲偄偆乽梩幒拞擺尵尠棽偺懛丄尠擻偺巕乿偱乽揤戜嵗庡傪偮偲傔偨尃憁惓尠恀偺掜乿偲偄偆乽娤惈忋恖乿(娤惈朄嫶)偵彽偐傟丄乽廫堦悽婭偺慜敿偵尮嶼忋恖偑偙偺抧偵彫摪傪寶偰丄帺嶌偺廫堦柺愮庤娤壒傪傑偮傜傟偨偺偵巒傑傝傑偡丅乿偲偄偆乽慞曱帥乿偺拞旜楡壺庻堾偵廧傫偱峴朄傪偍偙側傢傟乿偨偦偆偱丄乽屷嵢嬀乿偵傛傞偲乽娤惈忋恖乿偼尮棅挬偑寶棫偟偨乽掃壀敧敠媨乿偺戝搩偱嫙梴偺摫巘傪柋傔偨丄偲偺偙偲偱丅
(慞曱帥偺楌巎丗http://www.yoshiminedera.com/rekishi.htm)
(慞曱帥丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E5%B3%AF%E5%AF%BA)
(惣崙俁俁働強丂戞俀侽斣慞曯帥丗http://www.geocities.jp/koji_jyunrei/saigoku16.htm)
(娤惈忋恖丗http://kotobank.jp/word/%E8%A6%B3%E6%80%A7)
乽娤惈忋恖乿偺慶晝乽摗尨尠棽乿偼乽摗尨杒壠崅摗棳乮姪廋帥棳乯乿偱丄孼偺乽尠恀乿偼乽廳尮乿傜偲宷偑傞傛偆偱丄惣嫗嬫戝尨栰偺乽嶰屫帥乿偼乽墲惗堾偲崋偡傞憪埩偵巒傑傞乿偲偝傟丄1161擭乮墳曐尦擭乯娤惈偐傜帨墌偵忳傜傟偨屻丄徹嬻偑擖帥偟偰尰嵼偺帥崋偵夵傔傜傟偨乿偲偺偙偲偱丄乽徹嬻乿偲偄偆偲2009.04.01暘偱乽偲偼偢偑偨傝乿偺乽晄摦柧墹乿偵娭楢偟偰弌偰偒偰偰丄偦傟偵偼乽惏柧乿傕棈傫偱偄傞傛偆偱丅
(摗尨尠棽丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E9%A1%95%E9%9A%86)
(尠恀丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E7%9C%9F)
(嶰屫帥丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%88%B7%E5%AF%BA)
(嶰屫帥丗http://blogs.yahoo.co.jp/hiropi1700/4341199.html)
(徹嬻丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E7%A9%BA)
(惔忩壺堾丒媰晄摦奊姫丗http://jozan.jp/index.php?nakifudou)
乽嶰屫帥乿偵娭偡傞僽儘僌偵傛傞偲丄嬤偔偵乽垻抭嶁柧恄幮乿偑偁傞傛偆偩偑徻嵶偼傢偐傜偢丄乽垻抭乿偲偄偆偲恅巵偺僥儕僩儕乕偲巚傢傟傞抮揷巗偺乽埳嫃懢恄幮乿偺嫬撪幮乽挅柤捗旻恄幮乿偺屼嵳恄乽垻抦巊庡乿(壓嶁恄)傪巚偄弌偟丄乽尮嶼忋恖乿偑乽宐怱憁搒乿偺崅掜偲偄偆偙偲偱丄2009.08.05暘側偳偱偺乽宐怱憁搒乿偲峴婎偺宷偑傝傜偟偒傕偺傪巚偄弌偟丄傗偼傝乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偺宷偑傝偑尒偊偦偆偱丅
(寠怐媨埳嫃恄幮丗http://www.norichan.jp/jinja/hitokoto/ayahaikeda.htm)
(嶿婒偺孲巌丗http://tokyo.atso-net.jp/pukiwikip/index.php?%BB%BE%B4%F4%A4%CE%B7%B4%BB%CA)
(尮嶼忋恖丗http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/reikenki/saigoku/gendai20.html)
(愱擮帥丗http://www.kadode.com/sennenjiseizan.htm)
(悪杮帥丗http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page042sugimoto.htm)
(嬌妝帥丗http://www.h3.dion.ne.jp/~m.oku/garan02.html)
(杮婅帥丗http://blogs.yahoo.co.jp/gonngennsann629/50135218.html)
(攱偺帥丗http://www.haginotera.jp/tre003.html)
(暓朄帥丗http://www33.ocn.ne.jp/~kotaro_mil/iyosumi/towninfo/kawanoe.htm)
(慞婅帥丗http://tempsera.at.webry.info/201003/article_17.html)
(偍傫偽偝傑丗http://blog.livedoor.jp/mono130/archives/50322801.html)
侾侽擔偵乽骐缁偡傞墔楈乿偐傜丄乽暯壠暔岅乿偱乽埨摽揤峜埲壓偑棿恄偺崤懏偵側偭偨乿偙偲傪寶楃栧堾偑柌偵尒偨偲偄偆偙偲偵偮偄偰堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨偑丄乽帨墌乿偵傛傞乽嬸娗彺乿偱傕乽惔惙乿偑棿偲側偭偰抧恔傪婲偙偟偰偄傞偲彂偐傟偰偄傞偙偲側偳偐傜丄乽抧恔偼棿恄偺巇嬈偱偁傞偲棟夝偝傟偰偄偨偺偱偁傞乿(p106)偲偝傟偰偍傝丄乽揤峜偑巟攝偡傞尰悽傪嵍塃偡傞懚嵼偲偟偰丄棿恄偼墔楈偲寢傃偮偔偺偱偁傞丅乿(p107)偲傕偝傟偰偄偰丅
帨墌偑乽晄壜巚媍乿側偙偲偵偮偄偰丄乽敧敠戝曥嶧偺屼偼偐傜偄偵傛傞傕偺乿偐丄乽揤嬬丒抧嬬偺巇嬈乿偐丄乽墔楈偵傛傞傕偺乿偐傪丄偼偭偒傝偝偣傞昁梫偑偁傞丄偲彂偄偰偄偨傛偆偩偑(p7)丄偦傟傜偺慄堷偒偵偼乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偺乽潀乿偺傛偆側傕偺偑懚嵼偟偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞傢偗偱丅
| 仠2011.01.14(Fri.) |
傗偭傁傝攎徳偑婥偵側傞丒丒丒乽撊栘乿偱塺傑傟偨壧偱丄傑偢乽栰傪墶偵攏尅傓偗傛傎偲乀偓偡乿偑婥偵側偭偨偑丄偦偺壧偵娭偡傞愢柧偵偁偭偨乽嶦惗愇乿乽嬍憯偺慜乿偑婥偵側偭偰丄儕儞僋偑偁偭偨偺偱偦偙傪攓尒偡傞偲丄幚挬偺壧乽傕偺偺傆偺栴暲偮偔傠傆彫庤偺忋偵枧偨偽偟傞撨恵偺幝尨乿偑丅
(墱偺嵶摴丒嶦惗愇丗http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/okunohosomichi/okuno064.htm)
(墱偺嵶摴丒撨恵敧敠丗http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/okunohosomichi/okuno061.htm)
(梬愔傔偖傝丒嶦惗愇丗http://www.harusan1925.net/0307.html)
(屆崱柌憐丒尮幚挬丗http://www.geocities.jp/kokonmusou1182/siryou/03sanetomo.html)
(尮幚挬 愮恖枩庱丗http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sanetomo.html)
(尮幚挬丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E5%AE%9F%E6%9C%9D)
(嬍憯慜丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E8%97%BB%E5%89%8D)
幚挬偑乽撨恵傪朘傟偨婰榐偼側偄乿偲偺偙偲偱丄攎徳偼乽饽庤乿傪乽彫庤(昉)乿偲偟偰巚偄弌偟丄壗偐尵傢傫偲偟偰偄偨偺偐傕丄偲丄乽墱偺嵶摴丒撨恵敧敠乿偺儁乕僕偵偁偭偨乽嬍憯堫壸恄幮乿偺廧強偵偁傞乽朓憙乿傪尒偰巚偭偨偺偩偑丄偦傟埲忋偼撉傒庢傟側偔偰丒丒丒恄幮偵乽嬀偑抮乿偑偁傞偲偄偆偺傕婥偵側傞傫偩偑丒丒丒攎徳偑乽屘堄偐搈愶偐丄屌桳柤帉傪偢傜偟偰偄傞椺乿偑偁傞偲偝傟偰偍傝丄偦傟側傜偽乽恀娫偺庤帣撧乿偐偲巚偊偨傝丒丒丒丅
(墱偺嵶摴in撊栘丗http://maywind.sakura.ne.jp/okhos/krbnekistu.htm)
(嬍憯堫壸恄幮丗http://beccan.blog56.fc2.com/blog-entry-1633.html)
(庤帣撧楈摪偐傜壓憤崙暘帥傊丗http://members.jcom.home.ne.jp/okamoto.n/machi/chiba/simousakokubunji/simousakokubunji.html)
偁偲乽嬍憯乿偱巚偄弌偡偺偼2010.02.06暘偱偺乽晀攏塝乿傪塺傫偩壧偵偁偭偨偟丄2010.03.12暘偱偼奀憪偺乽儂儞僟儚儔乿偵偮偄偰丄乽媊宱偑擻搊偵摝傟偰偒偨偲偒偵丄媊宱偺攏偵恄攏憪傪怘傋偝偣偨偲偙傠戝曄尦婥偵側偭偨偲偄偆揱愢乿偑偁偭偨偙偲傪彂偄偰偄偰丄嬍憯堫壸恄幮嫬撪偺嬪旇乽鈇晧偆恖傪巬愜偺壞栰嵠乿傕堄枴偁傝偘偵巚偊偨傝丅
(杒棨偵偍偗傞媊宱揱愢丗http://www.geocities.jp/une_genzaburo/YoshitsuneRunningAwaysRouteInHokurikuArea.htm)
(鈇晧偆恖傪巬愜偺壞栰嵠丗http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/magusa.htm)
摨條偵丄乽嶦惗愇乿偺揱愢偑嬪偵崬傔傜傟偰偄傞偲偄偆乽棊偪棃傞傗崅媣偺廻偺妔岞乿傗丄乽栰傪墶偵攏尅傓偗傛傎偲乀偓偡乿偵傕丄壗偐傎偐偺堄枴偑偁傝偦偆側丒丒丒乽尦婥偑傛偄偑堄枴晄柧側嬪偱偼偁傞丅乿偲偝傟偰偄傞偟丄乽妔岞乿偑擖偭偰偄傞偁偨傝偼摿偵丅
(棊偪棃傞傗崅媣偺廻偺妔岞丗http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/takaku.htm)
偄傗偼傗丄偍傕偟傠偄僒僀僩傪尒偮偗偨丒丒丒偑丄偳偆栿偣偽偄偄傫偩傠丠慜偺壧偼乽崅媣偺廻乿偱僀偭偪傖偭偨丠栰偺墶偺憪傓傜偱傗偭偪傖偭偨丠
(儂僩僩僊僗夝懱怴彂丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/hoto.htm)
乽悾尒偺彫愳偱扥揾栴傪廍偭偰恎饽傕偭偨偲側傞偲嬍埶昉偼妔岞偵柍墢偱偼偁傞傑偄丅乿偲暿偺儁乕僕偵偁傝丄嬍埶昉偲妔岞偑宷偑傞側傜丄乽嶦惗愇乿偱偺俀庱偼暿偺堄枴傕帩偭偰偄傞偺偐傕丒丒丒丅
(惔彮擺尵偺埫崋1丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/seisyo1.htm)
(擻丒夑栁丗http://www.the-noh.com/jp/plays/data/program_033.html)
(梬愔傔偖傝丒壛栁丗http://www.harusan1925.net/1226.html)
崅媣偺廻偵乽嬍埶昉乿偑釰傜傟偰偄偨偺偐傕偟傟側偄偟丄2009.08.21暘偱怷巵偺挊彂偵乽栰乿偺偮偔抧偼乽惞抧乿偩偭偨偺偱偼偲偝傟偰偄偨偺偱丄惞抧偵攏偵忔偭偰棃傞恄(嬍埶昉)傪懸偭偰偄偨偺偐傕丒丒丒乽墶乿偼晽椩摪偝傫偺俇擔偺僽儘僌偵彂偐傟偰偄偨乽悾怐捗昉乿傪昞偟偰偄傞偺偐傕丒丒丒丅
偱丄暿偺儁乕僕偵乽搻嶌壧恖幚挬乿偲偁偭偰丄幚挬嶌偼杮摉偼屻捁塇忋峜嶌偱偼側偄偐偲偝傟偰偄偰丄偨偲偊偽壧傪塺傫偩偲偝傟傞乽彑挿庻堾乿偼帬夑偺乽挿庻帥乿偩偭偨偺偱偼側偄偐偲偝傟偰偄偰丄椙曎偺奐嶳偩偑丄屼杮懜偺巕埨抧憼娤壒偼峴婎嶌偲偝傟偰偄傞偍帥偱傕偁傞偺偱嫽枴怺偄側偲丅
(屻捁塇忋峜偺曄恎丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/gotoba2.htm)
(挿庻帥丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AF%BF%E5%AF%BA_(%E6%B9%96%E5%8D%97%E5%B8%82))
(挿庻帥丗http://achikochitazusaete.web.fc2.com/ouminotera/choujuji/higasitera.html)
攎徳偼偦傟傜傪傕偪傠傫夝偭偰偄偰丄偦傟偱墦夞偟偵偟偮偮傕宷偑傞傛偆偵塺傫偩偐傜丄嶐擔偺傛偆偵庱傪偐偟偘傞応強偑弌偰偔傞偺偐傕丅
偱丄乽屻捁塇忋峜偺曄恎乿偺嵟屻偺曽偵乽掕壠偺懅巕偺堊壠偑掕壠愶偺昐恖廏壧傪丄屻捁塇丒弴摽忋峜偺壧傪擖傟偨昐恖堦庱偵庤捈偟偟偰偟傑偭偨丒丒丒乿偲偁傝丄側傞傎偳偲巚偄偮偮丄偟偽傜偔乽屆揟丂傃偭偔傝嬄揤丂崌揰乿偝傫偺僒僀僩偵僴儅傝偦偆側丅
(屆揟丂傃偭偔傝嬄揤丂崌揰丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/)
偁丄晽椩摪偝傫偺僽儘僌偑峏怴偝傟偰偰丄乽戝擁偵偼戝嶰搰偺悈楈恄偑廻傞偲偄偆揱彸偑偁偭偨傕偺偐傕偟傟傑偣傫丅乿偲偺偙偲偱丄傗偼傝擻場傕悾怐捗昉偵偮偄偰弉抦偟偰偄偨丄偲偄偆偙偲偐偲丒丒丒攎徳偺乽傎偲偲偓偡棤尒偺戧偺棤昞乿傕婥偵側傞丒丒丒丅
(戝嶰搰丒擖擔偺戧劅劅嶰搱棿麀偺恄摽亂嘥亃丗http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/MYBLOG/yblog.html)
(傎偲偲偓偡棤尒偺戧偺棤昞丗http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/urami.htm)
幚挬嶌偼杮摉偼屻捁塇忋峜嶌丄偺師偼丄弴摽忋峜偺戙栶偑乽幃巕撪恊墹乿偺傛偆偱丄偨偲偊偽乽傛偣偐傊傞丂側傒偺壴偢傝丂傒偩傟偮偮丂偟偳傠偵偆偮偡丂傑偺偺偆傜攱乿偼弴摽忋峜偑攝棳抧偺嵅搉偱塺傫偩傕偺偱偁傞丄偲丅
(幃巕撪恊墹亖弴摽忋峜丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/sikiko-zyunntoku1.htm)
乽弴摽忋峜乿偵偮偄偰偼2010.02.06暘偺乽晀攏塝乿傪垽偱偨壧恖偺傂偲傝偲偟偰専嶕偟偰偍傝丄惣峴偲傕宷偑傝偑偁傞偙偲偑傢偐傝丄2010.10.14暘偱偼惣峴傕攎徳傕壧枍偺乽恀栰偺姙尨乿傪塺傫偱偄側偄偙偲偵偮偄偰丄乽愇姫巗偺恀栰丒姙尨抧嬫偱傕暉搰導撿憡攏巗幁搰嬫偺恀栰愳棳堟偱傕側偄丄偲偄偆偙偲傪尵傢傫偲偟偰偄傞偲偐丠乿偲嶐擔偲摨偠忬嫷偵側偭偰偄偰丄忋婰偺偙偲偐傜乽弴摽忋峜乿偺偍傜傟偨乽恀栰乿傪帵嵈偟偰偄偨傫偩側偀丄偲丅
偨偩丄乽傒偨傜偟傗丂塭愨偊偼偮傞丂怱偪偟偰丂巙夑偺攇楬偵丂懗偧偸傟偙偟乿偵偮偄偰丄乽偁偁屼庤愻愳傛丅塭乮屻捁塇乯偑巰傫偱偟傑傢傟傞怱抧偑偟偰丄偟偐乮幁亖忋峜乯偺忔傞廙偺攇楬乮椳乯偑丄娸偱尒憲傞巹偺懗偵傑偱忔傝墇偊偰丄傗偭偰偒傑偟偨丅乿偲偄偆夝庍埲奜偵傕丄乽偦傕偦傕釹偓偼丄惞側傞屼庤愻愳偱偺戝愗側峴帠側偺偩傠偆丅乿偲偝傟偰偄傞偙偲傗丄乽愮嵹廤乿偺弴摽掗偺傕偺偲巚傢傟傞壧偑夑栁巵偺壧偵嫴傑傟偨乽偝傝偲傕偲丂棅傓怱偼丂恄偝傃偰丂媣偟偔側傝偸丂夑栁偺悙奯乿(1272)偲偄偆偙偲偐傜傕丄偝傜側傞僂儔偑偁傝偦偆側姶偠偑偟偰丒丒丒屻捁塇堾偺曣曽偼摗尨杒壠摴棽棳偵宷偑傞偙偲偵傕娭楢偑偁傞偺偐傕丒丒丒丅
(摗尨怋巕丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%AE%96%E5%AD%90)
乽恄嶳偺丂榌偵側傟偟丂偁傆偄憪丂堷偒傢偐傟偰傕丂擭偧傊偵偗傞乿偵偮偄偰丄乽恄嶳偺榌偱撻傟恊偟傫偩埁憪傛丅暿傟暿傟偵側偭偰偐傜傕偆悘暘擭寧偑宱偭偨偙偲偱偟偨乿偲偄偆堦斒揑(?)夝庍偺壓偵丄僒僀僩偺曽偑乽恄嶳偺榌偱丄撻傟恊偟傫偱偒偨傢偑壠懓乮埁憪乯傛丅柍棟栴棟乮塀婒偲嵅搉偵乯棧暿偝偣傜傟偰偐傜丄傕偆悘暘偲擭寧偑宱偭偰偟傑偭偰偄傞丅乮傢傟傜偺庣岇恄偼丄堦懱壗傪偟偰偍傜傟傞偺偩傠偆丅乯乿偲彂偐傟偰偄偰丄僫僢僩僋丅
梬嬋偺乽掕壠乿偱乽妺乿偲側偭偰撪恊墹偺曟偵傑偲偆偲偄偆応柺偱丄乽撪恊墹乿偺戙傢傝偵乽弴摽掗乿偲偡傟偽丄掕壠偺幏怱偑傢偐傞傛偆側丒丒丒丅
(梬愔傔偖傝丂掕壠丗http://www.harusan1925.net/0403.html)
偱丄乽偆偖偄偡乿偼乽曕偒涋彈乿偩偦偆偱丄堦斒弾柉偼乽傆偝偓偺拵埥偄偼暊偺拵傪怘傋偰偔傟傞曕偒涋彈乿傪乽拵怘偄乿偲屇傫偱偄偨偦偆偱丄傂傚偭偲偟偨傜枼柺偺乽惣峕帥乿偺峴婎備偐傝偲偝傟傞乽拵捤乿偼丄乽曕偒涋彈乿偺慜恎偲側傞恖乆傪釰偭偨傕偺側偺偐傕丒丒丒乽惣峴乿偺壧偱乽偆偖偄偡乿傪乽曕偒涋彈乿偵抲偒姺偊丄乽曕偒涋彈偺妶摦偺尷奅傪惓妋偵巜揈偟丄惣峴帺傜偺暓嫵娤丄曕偒涋彈娤傪揻業偟偨壧偱偁傞偲庴偗庢傟乿傞偲偝傟偰偄偰丄偦傟偼擺摼偱偒傞傫偩偗偳丄偦偺偁偲偺栿偼暿偺堄枴傪帩偭偰偄傞傛偆偵巚偆傫偩偑丒丒丒丅
(轵偺沍惡丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/uguisu.htm)
乽壗偩偐乽傕偆堦偮偺枩梩廤乿偺棝擩辘乮僀儓儞僸乯偝傫傪恀帡偨傛偆側栿偵側偭偰偟傑偆丅乿偲彂偐傟偰偄偨偑丄巹傕偦偆巚偭偨丅(嬯徫)
師偵乽偐傜偡乿偑乽墱曽條乿偩偦偆偱丄乽幍偮偺巕乿偵偮偄偰偺栿偑彂偐傟偰偄偨偗偳丄偐偮偰攓尒偟偨僒僀僩偱乽偐傜偡乿偼乽僗僒僲僆乿偱丄乽幍偮偺巕乿偼僗僒僲僆偺幍恖偺巕嫙偑乽擑偺愴巑乿偨偪偱偁傞丄偲偺夝庍傪偝傟偰偍傝丄偳偪傜偑僂儔偐僆儌僥偐偼傢偐傜側偄偑丄侾偮偺壧偺拞偵條乆側堄枴偑塀偝傟偰偄傞偲偄偆偙偲偩傠偆偲偄偆偙偲偱丄師偺乽愮憗傇傞乿偱傕巹偲偼夝庍偑堎側傝丄巹偺夝庍傕傑偨懠偺曽乆偲堎側偭偰偄傞傢偗偱丅
(偐傜偡側偤媰偔偺丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/karasu.htm)
(幍偮偺巕偺撲丗http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki34.htm)
(愮憗傇傞丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/tihayaburu.htm)
嬼慠偵傕師偵攎徳偺乽嶦惗愇乿偺偙偲偑弌偰偒偨丒丒丒乽栰傪墶偵偟偰偺岎棳偱恖嵢偝傫偺婂偑壒偑暦偙偊傞丄傎偲偲偓偡乮梀彈乯偝傫傛丄拠娫偺攏乮偵偼梀彈偲偄偆堄枴傕偁傞乯偝傫傪尅偒岦偐偣偰殀乮偄側側乯偐偣傛乮晧偗傞側丄晧偗傞側丄婂偝傫偵晧偗傞側乯乿偲栿偝傟偰偄偨丅(嬯徫)
(婂偦傔偺楒丗http://www006.upp.so-net.ne.jp/k-tomohiko/kari.htm)
| 仠2011.01.15(Sat.) |
嶐擔乽嬍憯偺慜乿偱専嶕偟偰偄偨帪丄乽壀杮鉟摪乿偺彂偑偁傞偺傪抦傝丄嶌昳偺堦晹傪惵嬻暥屔偱撉傔傞傛偆偩偭偨偺偱偦偺拞偐傜乽擻場朄巘乿傪撉傫偱偄偨傫偩偗偳丄偙傟偑傑偨柺敀偔偰丅
(擻場朄巘丒壀杮鉟摪丗http://www.aozora.gr.jp/cards/000082/files/49536_39460.html)
(壀杮鉟摪丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E7%B6%BA%E5%A0%82)
摨偄擭偱摨偠偔乽掗崙寍弍堾夛堳乿偩偭偨乽愹嬀壴乿偲偺柺幆偲偐偼偳偆側偺偐偑婥偵側偭偨傝偡傞丒丒丒摨偠傛偆偵乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偵婥偯偄偰偄偨恖偺傛偆偵巚偊偰丒丒丒乽奍枮帥墢婲乿偵弌偰偔傞乽幗娫偺墺乿偑壗偐傪揱偊傛偆偲偟偰偄傞傛偆偱丒丒丒丅
(擔杮寍弍堾丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8A%B8%E8%A1%93%E9%99%A2)
(奍枮帥墢婲丗http://www.aozora.gr.jp/cards/000082/files/48032_33677.html)
乽奍枮帥乿偼恅巵偲峴婎偺愙揰偑尒傜傟傞偍帥偱丄乽幗娫巵乿偱巚偄弌偡偺偑晝丒幗娫帪崙丄曣丒恅巵孨偲偝傟傞乽朄慠乿偱丄2009.12.08暘偱偼2009.08.23暘偱偺乽幗晹乿偲乽幗娫巵乿偺娭楢偑婥偵側偭偰専嶕偟偰偄偰丒丒丒乽堫斞柦乿偲壩柧柦偐傜俆戙栚偲偝傟偰偄傞乽嶰尒廻擧乿偵宷偑傝偑尒偮偐傟偽丄暔晹巵偺傛偆側傫偩偑丒丒丒乽朄慠乿偺惗抋抧偑旤嶌偺媣暷孲偩偑丄係擔偺埳梊偺乽媣枴崙憿乿偲偺娭楢偑偁傞偺偩傠偆偐丒丒丒丅
(朄慠丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%84%B6)
(奍枮帥丗http://www.anraku.or.jp/jiin7.htm)
丒屼嵳恄丗嶰尒廻擧柦
(暔晹恄幮(嫬撪幮丒壋尒恄幮)丗http://kamnavi.jp/mn/nisi/iwami.htm)
丒屼嵳恄丗堫斞柦
(幒屆恄幮丗http://kodai.sakura.ne.jp/nihonnkennkokusi/1-4arasaka.htm)
(挿惗孲杛戲挰杒嶳揷丒嶰擵媨恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/chiba/tyouseigun/sanmiya/sanmiya.html)
(摽搰導柤惣孲恄嶳挰壓暘嶰僣栘丒堫斞恄幮丗http://goutara.blogspot.com/2010/11/blog-post.html)
(摽搰導撨夑孲撨夑挰丒塅撧啜恄幮丗http://www.genbu.net/data/awa2/unai_title.htm)
(戝暘巗戝帤嵅夑娭恄嶳丒捙崻捗旻恄幮(憗媧擔彈恄幮)丗http://www.hayasuihime.biz-web.jp/page444.html)
(媨嶈導搶彅導孲崙晉挰丒杮彲堫壸恄幮丗http://shogo33333.ninja-web.net/miyazaki-kourakuti/honjyouinarijinjya/honjyouinarijinjya.html)
(崅愮曚挰娾屗丒棊棫恄幮丗http://takachiho-kanko.info/modules/info/index.php?cat_id=11&start=10)
乽幗娫偺墺乿偱専嶕偟偰偄傞偲丄乽忋揷廐惉乿偺乽塉寧暔岅乿偵偁傞乽愺姖偑廻乿偑僸僢僩偟丄庡恖岞丒彑巐榊傪懸偮嵢丒媨栘偑塺傫偩偲偝傟傞壧偑乽偝傝偲傕偲巚傆怱偵偼偐傜傟偰悽偵傕偗傆傑偱偄偗傞柦偐乿偱丄彑巐榊偑壠傪嬻偗偰偐傜偺媨栘傪抦傞恖偲偄偆偺偑乽幗娫偺墺乿偱丄彑巐榊偲偲傕偵媨栘偺嫙梴傪偟偨偁偲丄搚抧偵揱傢傞乽恀娫偺庤帣彈乿偺揱愢傪榖偟丄偦傟傪暦偄偰彑巐榊偼乽偄偵偟傊偺恀娫偺庤帣撧傪偐偔偽偐傝楒偰偟偁傜傫恀娫偺偰偛側傪乿傪塺傫偩丄偲偄偆僗僩乕儕乕偺傛偆偱丄偼偀丠偲丅
(塉寧暔岅丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8%E6%9C%88%E7%89%A9%E8%AA%9E)
(愺姖偑廻丗http://mouryou.ifdef.jp/ugetsu/asadi-ga-yado.htm)
乽塉寧暔岅乿傪撉傫偩偺偑悘暘慜偩偐傜丄偡偭偐傝撪梕傪朰傟偰偨傫偩偗偳丄媨栘偑塺傫偩偲偝傟傞壧偼丄嶐擔偺乽弴摽忋峜乿偺戙栶乽幃巕撪恊墹乿偑塺傫偩偲偝傟傞壧傪杮壧庢傝偟偨傛偆偵巚偊偨偟丄搨撍偵岅傜傟傞乽恀娫偺庤帣撧乿偵偮偄偰傕嶐擔偪傜偭偲彂偄偰偨偟丒丒丒傒傚乣側嬼慠偱丅
偦傟偲傕壗偐宷偑傝偑偁傞丄偲偄偆偙偲側傫偩傠偆偐丒丒丒乽塉寧暔岅乿偺乽敀曱乿偵偼惣峴偑弌偰偔傞傛偆偩偟丄乽幗娫偺墺乿偑乽杻傪懡偔怉偊偨敤偺庡乿偲偄偆偺傕婥偵側傞偟丄媨栘偑塺傫偩偲偝傟傞壧偼乽撝拤廤乿偵偁傞偲偺偙偲偱専嶕偡傞偲丄堎摨壧乽偝傝偲傕偲巚傆怱偵偼偐傜傟偰悽偵傕偗傆傑偱偄偗傞変偑恎偐乿偑偁傞傛偆偱丄乽恀娫偺庤帣撧乿偲偄偆偲峴婎傗乽嶳晹愒恖乿傪巚偄弌偡偺偩偑丅
(撝拤廤丗http://tois.nichibun.ac.jp/database/html2/waka/waka_i092.html)
(摗尨撝拤 愮恖枩庱丗http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/atutada.html)
(摗尨撝拤丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%95%A6%E5%BF%A0)
壀杮鉟摪傕丄愹嬀壴傕丄忋揷廐惉傕丄愜岥怣晇傕丄尨嫆偵暣傟崬傑偣偰壗傪揱偊偨偐偭偨傫偩傠偆偐丒丒丒丅
乽奍枮帥墢婲乿傪撉傫偱偰丄乽奮乿偼侾.俆僉儘傎偳杒偵偁傞彅孼偺僥儕僩儕乕偵偁傞乽堜庤帥乿傪巚偄弌偟丄棨偵偼晐偄傕偺偑偄傞偺傪抦偭偰偄傞偲偄偆乽奮乿偺廸晝偺乽奍乿偼丄奀傕棨傕弉抦偟偰晲憰偟偨恅巵偲偄偆偙偲側偺偐側偀丄偲丅
(奮捤丗http://www.town.ide.kyoto.jp/50.html)
(堜庤偺嬍愳丗http://minami-lo.jp/member/sugiyama_6.html)
乽幗娫偺墺乿偑乽塉寧暔岅乿偲摨懓偩偲偟偨傜丄乽杻傪懡偔怉偊偨敤偺庡乿偱巚偄弌偡偺偼暔晹巵宯偵側傞偑丄側傜偽乽奮乿傪彆偗偨偐傢傝偵柡傪傕傜偄偵峴偭偰戅帯偝傟傞乽幹乿偲偼丠偲丄摢偐傜偟偽傜偔棧傟側偄傛偆側婥偑偡傞丒丒丒丅
| 仠2011.01.16(Sun.) |
嶐栭偐傜愥偺梊曬偺偲偙傠偑懡偔丄嫗搒嫞攏応偼崱擔偺廳徿偺慜攧傝偑敪攧拞巭偵側偭偰偄偨偑丄挬偵側偭偰傒偨傜嫗搒嫞攏応偼偝傎偳偺愊愥偱偼側偐偭偨偺偵丄拞嶳嫞攏応偺曽偑愊愥偺塭嬁偑弌偰敪憱帪崗偑侾帪娫抶傟偵側傝丄忈奞嫞憱偑拞巭偵側偭偰偄偨丅
傑丄偦傟偱傕奐嵜偝傟偨偺偱椙偐偭偨側偲巚偄偮偮丄帪婜揑偵嫗搒偲嶃恄偺奐嵜傪擖傟懼偊傟偽偄偄傫偠傖側偄偐側偲巚偭偨傝偡傞傫偩偑丒丒丒丅
傑丄偦傟偼抲偄偲偄偰丄俹俠傪棫偪忋偘偨傜俵俴乽惣峴帿揟vol丒157乿偑撏偄偰偍傝丄乽擭偨偗偰枖墇備傋偟偲偍傕傂偒傗丂偄偺偪側傝偗傝偝傗偺拞嶳乿(1963擭丂惣峴摪廋抸婰擮丂愳揷弴巵婗焲)偲偄偆偺傪尒偰丄拞嶳嫞攏応偺乽拞嶳乿偑傆偲婥偵側偭偨丅
僂傿僉儁僨傿傾偵傛傞偲丄乽拞嶳偺柤徧偼挰撪偵偁傞拞嶳朄壺宱帥偺嶳崋偵偪側傓丅乿偲偁傝丄乽拞嶳朄壺宱帥乿偼
(拞嶳挰丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E7%94%BA_(%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C))
| 擔楡偼偦偺晍嫵妶摦偺拞偱婔搙偲柍偔敆奞傪庴偗偨偑丄偦偺嵺愮梩巵偵巇偊偰偄偨晉栘忢擡傗懢揷忔柧偼娗妽偟偰偄偨敧敠憫偵擔楡傪寎偊擖傟曐岇偟偨丅摿偵愮梩巵偺旐姱偱偁偭偨晉栘忢擡偼丄擔楡偺偨傔偵庒媨偺帺揁偵朄壺摪傪憿塩偟埨懅偺応傪採嫙偡傞偲偲傕偵丄暥棛偱偁偭偨偨偨傔巻昅傪採嫙偟偰偦偺幏昅傪彆偗偨丅摉帥偵懡偔偺擔楡偺堚暥偑堚偝傟偰偄傞偺偼偦偺墢偱偁傞偲尵傢傟偰偄傞丅擔楡杤屻偵忢擡偼弌壠偟帺揁偺朄壺摪傪朄壴帥偲夵傔弶戙廧帩丒忢廋堾擔忢偲側傝丄擔楡偺桳椡側抙墇偱偁偭偨懢揷忔柧偺巕擔崅偼丄晝偺壆晘傪杮柇帥偲偟2戙栚廧帩偲側偭偨丅偦偟偰敧敠憫偺椞庡偱偁傝媽庡偱偁傞愮梩堺掑偺婣埶傪庴偗懎暿摉偵寎偊丄堺掑桺巕偺擔桽傪3戙栚廧帩偲偟偨丅偩偑丄旍慜崙彫忛孲偵偍偄偰偼堺掑偺掜堺峃偑嬨廈愮梩巵偲偟偰懚懕偟偨傕偺偺丄壓憤崙偱偼揋懳娭學偵偁偭偨掑堺棳愮梩巵偑戜摢偟丄堺掑棳偺愮揷巵偼悐戅偟偰摉帥傕婋婡傪寎偊偨丅偦偺傛偆側側偐丄擔桽偼幒挰枊晎偲偺娭學傪嫮傔偙傟傪忔傝愗傝丄偙偙傪嫆揰偲偡傞拞嶳栧棳偑惉棫偡傞偙偲偵側偭偨丅
擔崅埲棃戙乆偺廧帩偼杮柇帥偲朄壴帥偺椉帥偺寭柋偑姷傢偟偲側偭偰偄偨偑丄揤暥14擭乮1545擭乯屆壨岞曽懌棙惏巵傛傝乽彅朄壺廆擵捀忋乿偲偄偆徧崋偑憽傜傟乽朄壺宱帥乿偲偄偆帥柤偑抋惗偟丄朄壴帥偲杮柇帥偺椉帥傪崌傢偣偨堦偮偺帥堾偵側偭偨丅 (拞嶳朄壺宱帥丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%8F%AF%E7%B5%8C%E5%AF%BA) |
偲偺偙偲偱丄愮梩巵偺婩婅強乽愮梩帥乿偑峴婎偵傛傞奐婎偲揱傢傝丄峴婎備偐傝偲偝傟傞偍帥偑愮梩偵懡偄偙偲偐傜丄晉栘忢擡傗懢揷忔柧傕乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偵娭偡傞恖暔偐偲巚傢傟傞偑丄徻嵶偼傢偐傜偢丒丒丒丅
乽愮梩帥乿偱丄乽偩傟偲傕暘偐傜偸傛偆偵婄傪偍偍偆側偳偟偰廤傑偭偨恖乆偑丄戙姱傗懞栶恖偨偪偺埆峴丒晄惓傪旕擄偟偰徫偭偨丅乿偲偄偆乽愮梩徫偄乿偑峕屗帪戙偺戝夾擔偺斢偵偁偭偨偦偆偱丄壀杮鉟摪偺媃嬋乽愮梩徫偄乿傕偁傞偲偐丅
(愮梩徫偄丗http://www.weblio.jp/content/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%AC%91%E3%81%84)
(愮梩徫偄丗http://tibakyogen.exblog.jp/i4/)
拞嶳挰偺抧棟偵偮偄偰丄乽尰嵼偺抧柤偱偼丄偍偍傓偹婼墇丄婼崅丄杒曽丄崅愇恄丄杮杒曽丄拞嶳丄杒曽挰丄庒媨偵憡摉偡傞丅乿偲偁傝丄乽婼墇乿偑婥偵側偭偰専嶕偡傞偲乽杮敧敠偺乽恀娫偺擖傝峕乿偐傜戝挰偺乽扟捗乿傪扝傞乿偲偄偆尒弌偟偑偁傝丄嶐擔偐傜摨偠偁偨傝傪偆傠偮偄偰傞傫偩側偀丄偲丅(嬯徫)
(巗愳丒尦敧敠偐傜戝挰偺扟捗偵梀傇丗http://yoyochichi.sakura.ne.jp/yochiyochi/2009/08/post-12.html)
偱丄乽崅愇恄乿偑偪偲婥偵側偭偨偺偱尒偰傒傞偲丄抧柤偺桼棃偼乽摉抧偵偁傞崅愇恄幮偐傜丅乿偲偺偙偲偱丄屼嵳恄偼恄岟峜岪偩偦偆偱丅
(崅愇恄丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%B3%E7%A5%9E)
(崅愇恄幮丗http://8.pro.tok2.com/~tetsuyosie/chiba/itikawasi/takaisigami/takaisigami.html)
峴婎偺晝曽偺棦偵傕乽崅愇恄幮乿(屼嵳恄丗彮柤旻柤柦丄揤徠戝恄丄孎栰嵖恄)偑偁傝丄愳嶈巗杻惗嬫偵傕乽崅愇恄幮乿(屼嵳恄丗揤徠戝恄)偑偁傞傛偆偱丄偙偺俀幮偼乽揤徠戝恄乿乽孎栰嵖恄乿偱宷偑傞傛偆偱丄巗愳巗偲崅愇巗偼偐偮偰偼奀偺嬤偔偱徏偑惗偊偰偄偨偙偲偑嫟捠偡傞傛偆偩偑丄巵懓偺堏摦偵敽偆抧柤側傫偩傠偆偐丒丒丒丅
(崅愇巗丒崅愇恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%B3%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(杻惗嬫丒崅愇恄幮丗http://www.jp-spiritual.com/takaishi_jinjya1.htm)
(巗愳帺慠攷暔娰偩傛傝丗http://www.city.ichikawa.chiba.jp/shisetsu/haku/sizen/dayor/dayor_46.htm)
偪傚偭偲婥偵側偭偨偺偼丄杻惗嬫偺杒俆僉儘傎偳偺晎拞偵偼乽搶嫗嫞攏応乿偑偁傝丄偐偮偰墦夑愳幃搚婍偑弌搚偟偰傞偐傜丄傗偼傝乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偵娭楢偟偨堏摦抧柤偐偲丒丒丒乽杻傪懡偔怉偊偨敤偺庡乿偐傕丠
偦偆偄偊偽丄巗愳巗偵乽悰栰乿偲偄偆抧柤偑偁偭偨傛偆偵巚偄丄杻惗嬫偺杒搶侾僉儘偁偨傝偵傕乽悰乿偲偄偆抧柤偑偁傝丄崅愇巗偺乽崅愇恄幮乿偼乽崅巘昹乿偵偁偭偰乽崅巘彫憁乿偑憐憸偝傟丄乽揝乿偱宷偑傞壜擻惈偑偁傞傛偆側丒丒丒丅
乽擔杮彂婭乿偵乽悅恗35擭9寧丄壨撪崙偵攈尛偝傟丄崅愇抮傗姖熧乮偪偸乯抮傪巒傔懡偔偺抮峚傪奐偔丅摨條偵峀偔彅崙傪傑傢傝擾嬈傪惙傫偵偟偰恖乆偺惗妶偵埨掕傪傕偨傜偟丄柉偐傜岤偔悞宧偝傟偨偲揱偊傞丅乿偲偁傞傛偆偱丄乽屲廫帙晘擖旻柦乿偵娭偡傞巵懓偲偄偆偙偲偵側傞傫偩傠偆偐丒丒丒杻惗嬫傗巗愳巗偱偺乽屲廫帙晘擖旻柦乿偺懌愓偼傛偔傢偐傜側偄偑丅
(屲廫帙晘擖旻柦丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%8D%81%E7%93%8A%E6%95%B7%E5%85%A5%E5%BD%A6%E5%91%BD)
| 仠2011.01.17(Mon.) |
乽骐缁偡傞墔楈乿偐傜丄悞摽堾偑釰傜傟偰偄傞崄愳導嶁弌巗偺乽敀曯媨乿傪専嶕偡傞偲丄乽峕屗帪戙偵偼悞摽揤峜幮栰戲堜媨丒悞摽揤峜柧偺媨側偳偲屇偽傟丄嬥壺嶳柇惉廇帥杸擈庫堾偲堦懱偺懚嵼偲偟偰巐崙敧廫敧売強偺幍廫嬨斣嶥強偱偁偭偨丅乿偲偁傝丄乽嬥壺嶳柇惉廇帥杸擈庫堾乿偑婥偵側偭偰丅
(敀曯媨丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B3%B0%E5%AE%AE)
忋婰倀俼俴偵偁傞傛偆偵丄乽柧帯偺恄暓暘棧偱悞摽揤峜幮偼敀曯媨偲側傝丄杸擈庫堾偼攑帥偲偝傟偨偨傔丄昅摢枛帥偺崅徠堾偑偦偺愓偵堏揮偟丄揤峜帥傪嵞嫽偟偰嶥強傪堷偒宲偄偩丅乿偲偺偙偲偱乽揤峜帥乿傪尒傞偲丄
| 揱彸偵傛傟偽丄屆戙偵撿奀偺戝嫑傪戅帯偟偵岦偐偭偨嶿棷楈墹傜俉俉恖偺暫巑偑戝嫑偵慏傪撣傑傟偰搢傟偨偲偒丄墶挭柧恄偑愹偺悈傪帩偭偰偁傜傢傟丄偦偺悈傪暫巑偵堸傑偣偨丅偡傞偲丄慡堳偑柦傪悂偒曉偟偰彆偐偭偨偲偄偆丅偦傟偐傜偙偺愹偼乽敧廫応乮傗偦偽乯偺楈悈乿偲屇偽傟傞傛偆偵側偭偨偲偄偆丅偦偺屻嬻奀乮峅朄戝巘乯偑敧廫応偺愹傪朘傟偨偲偒丄廫堦柺娤壒丄垻栱懮擛棃丄垽愼柧墹偺嶰懜憸傪偮偔偭偰摪傪寶偰埨抲偟偨偲偄偄丄傑偨丄栻巘擛棃傪崗傫偱埨抲偟偰丄愹傪鑴壘堜偲偟偨偺偑婲尮偱偁傞偲偄偆丅摉弶偼杸擈庫堾柇惉廇帥偲徧偟偨偲偄偆丅 (揤峜帥丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%AF%BA_(%E5%9D%82%E5%87%BA%E5%B8%82)) (揤峜帥丗http://www.ko-pri.com/88/kagawa/79/79_tennoji.htm) |
偲偁傝丄2010.12.02暘偱偺嶿棷楈墹乮晲棏墹丒恄孂墹丒寶奓帣墹丒晲妅墹丒晲陦墹丒晲梴嶾柦丒懡孷斾屆墹柦丒晲柧墹丒抾嵽巕柦)偑弌偰偒偰丄乽晲梴嶾柦乿偼乽愭戙媽帠杮婭乿偱偼乽攇懡恇傜偺慶乿偲偝傟偰偄傞傛偆偱丄暫巑傜傪彆偗偨偲偄偆乽墶挭柧恄乿偑婥偵側偭偨丅
(嶿棷楈墹恄幮丗http://www.geocities.jp/seiji_maturi/hanzan1.html)
(嶿棷楈墹揱愢丗http://www.geocities.jp/hanzan_cho/hanzan/sarureo1.html)
(愭戙媽帠杮婭偺悽奅丒姫戞幍 揤峜杮婭丗http://mononobe.nobody.jp/kujihonki/yaku/tennou.html)
乽墶挭柧恄乿傪釰傞偲偄偆乽墶挭恄幮乿偑偁傞傛偆偩偑丄屼嵳恄丗揤徠戝屼恄丄崌釰丗擔杮晲懜丄庒媨恄偲偝傟偰偄傞傛偆偱丄乽墶挭柧恄乿偺旘傃婣偭偨嶳偑乽敀曯偺帣働浽乿偩偦偆偱丄乽悾怐捗昉乿偺傛偆偵巚傢傟傞偺偩偑丅
(嶿婒偺晽搚婰丗http://dekiya.blog57.fc2.com/blog-entry-56.html)
(墶挭恄幮丗http://kagawa.bine.jp/jinnjya/sakaide/63yokosi/63yokosi.html)
(抰帣僲戧丗http://www.geocities.jp/seiji_maturi/taki1.html)
僂傿僉儁僨傿傾偵乽揤峜帥乿偺墱偺堾偲偟偰乽椱棡岝帥乿乮嬥嶳栻巘乯偲乽杸擈庫堾乿乮忛嶳晄摦戧)偑彂偐傟偰偄偰丄偦傟傜偺埵抲娭學偼傛偔傢偐傜側偄偑丄乽弰庎拞偵敧廫慼応偺愹晅嬤偱楈婥傪姶偠偨峅朄戝巘偼丄揤峜帥偺慜恎偱偁傞柇惉廇帥傪寶棫偟偨嵺丄栻巘擛棃偺愇憸傪崗傫偱嬥嶳拞暊偺悈尮偵埨抲偟偨偲偄偆丅乿偲偺偙偲偩偟丄尰嵼乽杸擈庫堾乿偲偄偆偍帥偼側偄偦偆偩偑丄晄摦柧墹偑埨抲偝傟偰偄傞乽晄摦戧乿偑偁傞傛偆偱丄乽抰帣僲戧乿摨條乽悈恄乿偱偁傞乽悾怐捗昉乿偐偲巚傢傟傞偑丒丒丒丅
(椱棡岝帥丗http://blogs.yahoo.co.jp/kazuno_mitu/31450511.html)
(杸擈庫堾丗http://wilderness.web.infoseek.co.jp/temple/manijuin/manijuin.htm)
偱丄忋婰倀俼俴偺乽嶿婒偺晽搚婰乿偝傫偺偲偙傠偵丄乽戅帯偝傟偨埆嫑偺楈傪捔傔傞偨傔丄峴婎偑嫑屼摪偑寶偰丄峅朄戝巘偑慗偟偰朄孧帥乿偲徧偟丄偺偪偵乽惗嬵堦惓乿偵傛偭偰崅徏偵堏偝傟丄晝丒恊惓偺朄柤偵偪側傫偱乽峅寷帥乿偲側偭偨偙偲偑彂偐傟偰偍傝丄惗嬵巵偵偮偄偰偼2010.12.22暘偱偺専嶕偱乽杒壠乿偺傛偆偱丄乽嶿棷楈墹恄幮乿墶偺尰懚偡傞乽朄孧帥乿偲偺娭楢偼晄徻偩偑丄峴婎偺柤偑弌偰偒偨偲偄偆偙偲偼丄偦偺堦懷偼乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偲偺宷偑傝偑嫮偐偭偨偺偱偼側偄偐丄偲丅
(忛嶳丗http://homepage3.nifty.com/ishildsp/kikou/kagawa2.htm)
摨偠偔乽嶿婒偺晽搚婰乿偝傫偺偲偙傠偵彂偐傟偰偄偨丄尦偼辍攓強偺乽嬨摢棿恄幮乿(屼嵳恄丗揤屼拞庡柦)偵乽塅晇巙撧戝恄乿偲偟偰釰傜傟丄偺偪偵慗嵗偝傟偨乽塅晇奒恄幮乿(屼嵳恄丗戝屓婱柦)傕婥偵側傝傑偡偹丄偛恄懱偱偁傞乽嫄愇乿傗乽嬨摢棿恄幮乿偺屼嵳恄偲偺娭楢側偳傕丅
(塅晇奒恄幮丗http://kagawa.bine.jp/jinnjya/utazu/ubusina/ubusina.html)
(嬨摢棿恄幮丗http://kagawa.bine.jp/jinnjya/utazu/34kuzu/34kuzu.html)
悇應偩偑丄晽椩摪偝傫偺僽儘僌偵偁偭偨乽戝嶳媉恄幮乿偵偍偗傞乽慗媨乿偱偺弌棃帠偲摨偠傛偆偵巚傢傟丄尰懚偟側偄偲偄偆乽杸擈庫堾乿偲乽晄摦戧乿偵偮偄偰傕丄峏怴偝傟偰偄偨暘偵彂偐傟偰偄傞乽戝嶳媉恄幮偑乽擖擔偺戧乿偲偼柍娭學偲偟偨偑偭偰偄傞傛偆乿偱偁傞偺偲帡偰偄傞傛偆偱丅
(戝嶰搰丒擖擔偺戧劅劅嶰搱棿麀偺恄摽亂嘦亃丗http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2011/01/15)
乽悞摽堾乿偺乽敀曯媨乿偲乽嬥壺嶳柇惉廇帥杸擈庫堾乿偑乽堦懱偺懚嵼乿偱偁傞偲偄偆偙偲偼丄乽悞摽堾乿偑乽墔楈乿偲偝傟偨攚屻偵偼丄乽恖乆偺怱偺崻掙偵偁傞乽偁傞傋偒巔乿傪媮傔傛偆偲偡傞堄幆乿(p4)傪帩偮巵懓偑乽悞摽堾乿偲乽悾怐捗昉乿傪廳偹偰尒偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟丄乽曐尦偺棎乿屻偵搚嵅偵堏傝廧傫偩乽恅擻弐乿傜偑偦偺戙昞揑側巵懓偐偲丅
傑偩徻偟偔偼挷傋偰側偄偺偩偑丄乽悞摽堾乿傜傪釰傞嫗搒偺乽敀曱恄媨乿偵乽愽棿幮乿偑偁傝丄徍榓俁侽擭偵悈恄乽愽棿戝恄乿傪釰偭偨傛偆偱丄乽愽棿戝柧恄乿偺屼恄懱偲偝傟傞乽愽棿堜乿傗乽旘捁堜乿偑偁傝丄乽廟媐偺廆壠偱偁偭偨岞壠丒旘捁堜壠(摗尨杒壠巘幚棳乮壴嶳堾壠乯)偺壆晘偺愓抧乿偱偁傞偙偲偐傜丄乽朄孧帥乿傪崅徏偵堏偟偨乽惗嬵巵乿偲偼楢摦偟偰偄偨偺偐傕丄偲丅
(敀曱恄媨丗http://www10.ocn.ne.jp/~siramine/page019.html)
(愽棿堜丗http://www10.ocn.ne.jp/~siramine/page008.html)
(旘捁堜壠丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E4%BA%95%E5%AE%B6)
旘捁堜壠偺慶乽旘捁堜夒宱乿偑乽幚挬偲摗尨掕壠丒姏挿柧偲偺娫傪庢傝帩偭偰偄傞丅乿偲偄偆偁偨傝偑婥偵側傞偟丄乽惣峴乿偲偼2009.04.07暘偱偺乽擄攇棅曘乿(旘捁堜夒宱偺慶晝)偐傜偺宷偑傝偑尒傜傟偦偆偱偡偹丅
(旘捁堜夒宱丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E4%BA%95%E9%9B%85%E7%B5%8C)
(擄攇棅曘丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E9%A0%BC%E8%BC%94)
侾係擔偵婥偵側傞偲彂偄偰偨攎徳偺乽傎偲偲偓偡棤尒偺戧偺棤昞乿偩偑丄乽巄帪偼戨偵饽傞傗壞偺弶乿乽傎偲偲偓偡妘偮偐戨偺棤昞乿傕摨偠応強偱塺傑傟偨傛偆偱丄乽棤尒偺戨乿偺墶偵偼乽姲塱尦擭乮侾俇俀係乯弌塇嶰嶳傛傝塇崟嶳峳郪晄摦柧墹偑姩惪偝傟乿偰偄傞偲偺偙偲偱乽峳郪晄摦柧墹乿傪専嶕偟偨傜丄偪偲婥偵側偭偨偙偲偑丅
(棤尒偺戧丗http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/okunohosomichi/okuno053.htm)
(棤尒偺戨偲庘岝偺戧丗http://outdoor.geocities.jp/gmrbg004/urami1.html)
乽峳郪帥偼塇崟嶳偺墱偺堾偱偁傝丄塇崟廋尡偺崻杮偱偁傞忢壩傪庣偭偰偄偨丅偙偙偼搾揳嶳丄戝擔擛棃偺峳嵃乮偁傜傒偨傑乯傪晄摦柧墹丄榓嵃乮偵偓傒偨傑乯傪抧憼曥嶧偲偟偰釰傝丄搾揳峴偺崻杮摴応偱偁偭偨丅乿偲偁傝丄乽棤尒偺戨乿摨條偵杒嬫拞廫忦俁挌栚偵傕姪惪偝傟偰偄傞傛偆偱丅
(廋尡摴侾丗http://ameblo.jp/kumanowakou/entry-10557665569.html)
(偄偵偟偊偺塇崟嶳傪扝傞嘦丗http://hagurokankoblog.sblo.jp/article/33529990.html)
(塇崟嶳丂峳戲帥丗http://www12.plala.or.jp/inookadera/rekisimini/33kannon.htm)
(杒嬫偺抮丗http://peepooblue.cocolog-nifty.com/blog/cat36372556/index.html)
媨忛導杮媑孲撿嶰棨挰壧捗旙偺岥偲偄偆廧強傪尒偮偗丄乽峳郪晄摦摪乿偑偁偭偨偦偆偩偑徻嵶偼傢偐傜偢丄恄暓暘棧屻偵乽寁愬杻戝搱恄幮偼墑婌幃撪柧恄戝幮偱丄婥愬徖偺戝搰偵媈掕偝傟傞偑丄柧帯婜偵撍慠揷懇嶳偵嵳傜傟傞偙偲偵側偭偨宱堒偼椙偔暘偐偭偰偄側偄丅乿偲偺偙偲偱丄僨僕儍償丠偲丒丒丒壧捗偲偄偆抧柤傕丄崄愳偲偺宷偑傝偑偁傝偦偆偱婥偵側偭偰丅
(寁愬杻戝搱恄幮丗http://mutsusousya.web.fc2.com/tazukanesan/tazukanesan.html)
偁偲丄徻嵶偼晄柧偩偑丄乽峳郪晄摦柧墹乿偑忔埰丄怴忛巗挿幝丄嬎惗巗揤恄挰偺乽媣徆帥乿偵埨抲偝傟偰偄傞傛偆偱丄乽媣徆帥乿偱偼乽擔杮嶰懱晄摦偺堦懱偲偟偰丄偐偮偰墱廈丒搾揳嶳偺墱抧丄峳戲偺抧偵曭埨偝傟偰偄傑偟偨丅偙偺晄摦柧墹偑丄帺峴朄報偵壓帓偝傟丄墢偁偭偰摉抧傊慗嵗偝傟傑偟偨丅乿偲偺偙偲偱丅
(僲儕僋儔 愥宬僇儗儞僟乕丗http://www.norikura.org/norikura-calender/2010/vol2010-06/calender2010-06_03.htm)
(怴忛巗挿幝丒峳郪晄摦柧墹丗http://plaza.rakuten.co.jp/shomire100/diary/200911080000/)
(媣徆帥丗http://www.hosenji.or.jp/shichifuku/5.html)
偦偟偰乽媽晉巑愳挰杒徏栰丄桳柍悾愳傪尒壓傠偡導摴76崋慄増偄偺嶳拞偵偁傝傑偡丅乿偲偝傟傞乽峳郪晄摦懜乿偼丄乽惞摽懢巕偺掜巕偩偭偨峳郪抏惓偑懢巕偵庼偗傜傟偨晄摦柧墹傪偙偺抧偵釰傝丄埲棃亀峳郪晄摦懜亁偲屇偽傟傞傛偆偵側偭偨偦偆偱偡丅乿偲偺偙偲偱丄塇崟嶳偱釱傪憂寶偟偨乽朓巕峜巕乿偼懢巕偵傛偭偰搶崙擖傝偟偨偲偝傟傞偺偱丄懢巕偲晄摦柧墹偑宷偑傝偦偆偱丅
(晄摦偺戧乮峳郪晄摦懜乯丗http://outer-network.com/townguide/diary.cgi?no=43)
(弌塇嶰嶳丗http://www.tsuruokakanko.com/haguro/midokoro/haguro.html)
戝嶃偺乽巐揤墹帥乿偺乽婽堜晄摦懜乿偼丄乽惞摽懢巕偑婽堜偺悈傪擿偐傟傞偲偦偙偵晄摦柧墹乮懜乯偺屼巔偑塮偭偰偄偨偨傔丄偙偙偵晄摦懜傪釰傜傟偨偺偑婲尮偲偝傟傑偡丅乿偲偺偙偲偩偟丄懢巕備偐傝偺乽怣婱嶳 挬岇懛巕帥乿偺乽曎嵿揤偺戧乿偵傕乽晄摦柧墹乿偑釰傜傟偰傑偡偹丅
(婽堜晄摦懜丗http://www.shitennoji.or.jp/keidai/kameifudo.htm)
(怣婱嶳 挬岇懛巕帥丗http://www.sigisan.or.jp/keidai.html)
偲偄偆偙偲偱丄攎徳偼乽棤尒偺戨乿偺棤偐傜乽悾怐捗昉乿傪尒偰偄偨偺偐傕丒丒丒乽峳戲晄摦柧墹乿傪巚偭偰乽岅傜傟偸搾揳偵偸傜偡逶偐側乿傪塺傫偩偺偐傕丒丒丒丅
(墱偺嵶摴弌塇嶰嶳丗http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/okunohosomichi/okuno25.htm#ku4)
(攐惞 徏旜攎徳丒傒偪偺偔偺懌愓丗http://www.bashouan.com/pzPhoto09.htm)
| 仠2011.01.18(Tue.) |
乽骐缁偡傞墔楈乿傪撉傒廔偊偨偗偳丄偄偔偮偐棟桼偑偮偐傔側偄帠暱偑偁偭偰丄偦偺偆偪偺侾偮偑乽摗尨峀巏乿偑墔楈偲偝傟偰偄偨偙偲偱丅
乽挬掛撪偱斀摗尨巵惃椡偑戜摢偟偨攚宨偺傕偲丄恊懓傊偺旑鎺傪棟桼偵摨擭12寧4擔偵戝嵣彮擉偵嵍慗偝傟傞丅乿偲偁傞偑丄乽揤抧偵傛傞嵭栵偺尦嫢偼斀摗尨惃椡偺梫偱偁傞塃塹巑撀丒媑旛恀旛偲憁惓丒尯偵婲場偡傞偲偺忋憈暥傪挬掛偵憲傞乿偙偲偲偳偆娭楢偡傞偺偐偑晄柧偱丄巹偵偼乽峀巏偺棎乿偺撪梕偐傜墔楈偲側傞強埲偑撉傒庢傟側偐偭偨傫偩偑丅
(摗尨挬恇峀巏丗http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/hirotugu.html)
搨捗巗偺乽嬀恄幮乿偱偼堦偺媨偺乽恄岟峜岪乿偑撿岦偒偵丄擇偺媨(斅烠恄幮)偺乽摗尨峀巏乿偼搶岦偒偵釰傜傟偰偄傞偦偆偩偑丄側偤偙偙偵釰傜傟偨偺偐偑傛偔傢偐傜偢丄偦偙偐傜姪惪偝傟偨乽撿搒嬀恄幮乿偑側偤乽怴栻巘帥乿偺捔庣側傫偩傠偆偐丒丒丒丅
(搨捗巗丒嬀恄幮丗http://kakitutei.web.fc2.com/yukari/karatu/matura.html)
(搨捗巗丒嬀恄幮丗http://www5f.biglobe.ne.jp/~dayfornight/akatsuchi/01kagami/01kagami.html)
(撿搒嬀恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%BD%E9%8F%A1%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
乽嬀乿偑偮偔恄幮偲偟偰偼丄搶戝嶃巗偺乽庒峕嬀恄幮乿(屼嵳恄丗戝埳夀捚壩柧戝恄丄懌拠旻揤峜柦丄攝釰丗懅挿懌昋峜岪)傗丄姉惗孲棾墹挰偺乽嬀恄幮乿(屼嵳恄丗揤擔憚)偑偁傞傛偆偱丄搨捗巗偺乽嬀恄幮乿偲偼乽恄岟峜岪乿偱宷偑傝偦偆偩偑丄搨捗巗偺乽嬀恄幮乿偱偼乽恄岟峜岪乿傛傝傕側偤乽摗尨峀巏乿偺曽偑廳傫偠偰釰傜傟偰偄傞偺偩傠偆偐丒丒丒丅
(庒峕嬀恄幮丗http://kamnavi.jp/mn/osaka/wakae.htm)
(姉惗孲棾墹挰丒嬀恄幮丗http://www.town.ryuoh.shiga.jp/yoshitune/genpuku/kagami-jinja.html)
偱丄搨捗偺乽戝懞恄幮乿偺屼嵳恄偱傕偁傞傛偆偩偑丄2010.01.20暘傗2010.10.08暘偱偺乽戝懞恄幮乿偲偼堎側傞傛偆側姶偠傕偁傝丄搨捗偲摨偠偔屲斀揷偲偄偆抧偵偁傞垽抦偺乽戝懞恄幮乿偲偺宷偑傝傕傛偆傢偐傜傫丒丒丒丅
挿嶈導戝懞巗丒戝懞恄幮(庡嵳恄丗戝懞捈悷岞 奜俇拰)
嵅夑導搨捗巗昹嬍挰屲斀揷丒戝懞恄幮(屼嵳恄丗摗尨峀巏挬恇)
嶳岥巗拻慘巌丒戝懞恄幮(屼嵳恄丗戝懞塿師榊)
埳夑巗垻曐丒戝懞恄幮(庡嵳恄丗戝懞恄(懅懍暿柦丠))
怴忛巗壓媑揷屲斀揷丒戝懞恄幮(晄柧)
峀巏偵廬傢偞傞傪摼偢偵柦傪棊偲偟偨敼恖偨偪偺恎戙傢傝偲偟偰丄峀巏傪墔楈偵偟偨偺側傜傢偐傞傛偆偵巚偆偑丒丒丒偦傟偲傕曣曽(愇忋杻楥堦愢偵偼慼変憅嶳揷愇愳杻楥偺彈乯偺巵懓偑棈傫偱偄傞偺偐傕丠
暉壀偺敧敠搶嬫崅尒媦傃捨揷抧嬫偵丄乽揤暯12擭(740擭)丄斅烠愳偺愴偄偱攕傟偨摗尨峀巏偺楈傪嵳傞偨傔尰嵼偺敧墹帥嫶晅嬤偵偁偭偨柧恄幮偲娾暎墎庢悈岥(尰嵼偺幍忦嫶壓)偺庣岇恄偲偟偰嵳偭偨悈恄幮傪柧帯35擭崌暪偟偰峳惗揷恄幮偵夵徧偝傟傑偟偨丅乿偲偝傟傞乽峳惗揷恄幮乿傗丄乽峀巏傪峳晲搣柧恄偲偟偰釰偭偨偺偑巒傑傝乿偲偝傟傞乽愇釱乿偑尰懚偟偰偄傞傛偆偱丄乽撿搒嬀恄幮乿偺愛幮乽斾攧恄幮乿傗暿幮乽愒曚恄幮乿傕娷傔偰攚屻偵乽悾怐捗昉乿偑尒偊傞傛偆側丒丒丒丅
(敧敠搶嬫崅尒丄捨揷抧嬫偺巎愓摍丗http://members.jcom.home.ne.jp/eirakuan2/yahi-takami-new.htm)
(峳惗揷恄幮丗http://www.kcta.or.jp/kaidou/jinzya/yahatahigashi/arouda/arouda.html)
(峳惗揷恄幮丗http://members2.jcom.home.ne.jp/jinja/page061.html)
(斾攧恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E5%A3%B2%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%B8%82))
(愒曚恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%A9%82%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
乽嬸娗彺乿偱帨墌偼側偤乽堜忋撪恊墹乿偑乽棿恄乿偵側偭偨偺偐偼彂偄偰偄側偄傛偆偩偑丄乽堜忋撪恊墹乿偵偮偄偰偺揱彸偼丄桯暵偝傟偰偄偨偲偄偆乽堜忋堾愓乿偺偁傞屲瀶巗偵懡偔偁傞傛偆偱丄偦偪傜偱偼乽惞恄偝傫乿偲屇偽傟偰偄傞偲偐丅
(屲瀶巗丗http://www.city.gojo.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1149221753029&SiteID=1139107257399&ParentGenre=1000000100003)
(堜忋撪恊墹丒屼楈恄幮偺揱愢丗http://www.7kamado.net/den_yamato/gojyou_den.html)
(堜忋撪恊墹丗http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/inohe.html)
乽堜忋峜岪偑桯暵偝傟偰偄偨偲偒偛夰擠偝傟偰偍傝乿偲偄偆偺傪弶傔偰攓尒偟丄乽偦偺偲偒偵惗傟偨巕偑棆恄偲側傝丄 曣偑棳偝傟偨偙偲傪墔傫偱丄庬乆偺釳傝傪側偟偨偺偱恄偵釰偭偨偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅乿偲偺偙偲偱丄棿恄丒惞恄丒棆恄偲偄偆偲僯僊僴儎僸傗悾怐捗昉傪巚偄弌偡傫偩偑丒丒丒丅
(屼楈怣嬄丒屼楈恄幮丗http://www.7kamado.net/goryo-index.html)
乽堜忋撪恊墹丒屼楈恄幮偺揱愢乿偺拞偵乽壓攏乿偵娭偡傞傕偺偑彂偐傟偰偄偰丄偦傟傕婥偵側偭偰偄偨偲偙傠丄嫗搒偺乽摗怷恄幮乿偵傕釰傜傟偰偄傞傛偆偱丄乽堜忋撪恊墹乿偺攚屻偵乽悾怐捗昉乿偑尒偊傞傛偆偵巚偭偨偺偩偑丄乽堜忋撪恊墹乿偑釰傜傟偰偄傞乽惣揳乿偼丄乽墑楋侾俋擭乮俉侽侽乯捤杮偺抧偵捔嵗丄墑墳尦擭乮侾俀俁俋乯怺憪彫揤峜傊慗嵗丄暥柧俀擭乮侾係俈侽乯摗怷傊崌釰丅乿偲偁傝丄偳偆偄偆偙偲側傫偩傠偆偐丄偲丅
(摗怷恄幮丗http://www.genbu.net/data/yamasiro/fujinomori_title.htm?print=on)
嵟弶偺屼捔嵗抧偺乽捤杮偺抧乿偵偮偄偰丄乽摗怷恄幮偺杮揳撪偵崌釰偝傟偰偄傞捤杮幮偺媽捔嵗抧偼丄搶嶳嬫杮挰捠傝16挌栚偱柉壠偺棤懁偵偁傝傑偡丅捤杮偲偼丄屆暛偺壓曽傪偄偄丄峀偔偦偺晅嬤傪偄偆丅屆暛傪怣嬄宍懺壔偟恄偲偟偰釰偭偨偺偑丄捤杮幮偱偡丅乿偲偁傝丄師偺乽怺憪彫揤峜乿偮偄偰偼丄乽捤杮幮偑摗怷偵堏偝傟偨強偱屆棃偼彫揤峜恀敠悺(傑偼偨偓)恄幮偲徧偝傟傑偟偨偑墳恗偺棎偱從柵偟傑偟偨丅暥柧2擭(1470擭:堦愢偵塱嫕10擭)偵尰嵼偺摗怷恄幮偵崌釰偝傟傑偟偨丅乿偲偁偭偨丅
(怺憪丄堫壸奅孏偺偛徯夘丗http://miyakoweb-lj-hp.web.infoseek.co.jp/inari/inari.htm)
乽屆暛傪怣嬄宍懺壔偟恄偲偟偰釰偭偨偺偑丄捤杮幮偱偡丅乿偲偺偙偲偱専嶕偡傞偲丄屆暛屻婜偺墌暛乽捤杮屆暛乿偑偁傞傛偆偱丄乽撪晹庡懱偼墶寠幃愇幒乿偲偁傝丄恅巵娭學偺敼恖偺捤偩偭偨偺偐傕偟傟側偄側偀丄偲丅
(550 捤杮屆暛丗http://www.city.kyoto.jp/bunshi/maibun/tizudaityou/higasiyamaku.html)
乽傒偝偝偓宖帵斅乿偝傫偺乽嫗搒怺憪偺揱彸抧乿偵徻偟偔彂偐傟偰偄偰丄屲瀶巗偺乽惞恄乿偺偙偲傗丄忋婰偺乽嬀恄幮乿暿幮偺乽愒曚恄幮乿偵娭偟偰傕彂偐傟偰傑偡偑丄乽捤杮屆暛乿偵偮偄偰偺徻嵶偼傢偐傜側偄傛偆偱偡偹丅
(嫗搒怺憪偺揱彸抧丗http://8918.teacup.com/ryobo/bbs/1135)
(撧椙巗崅敤挰偺廫巗峜彈偺揱彸抧丗http://8918.teacup.com/ryobo/bbs/1149)
(屲瀶巗偺傂偠傝恄偝傫丗http://8918.teacup.com/ryobo/bbs/1029)
埳夑巗垻曐偺乽戝懞恄幮乿偺庡嵳恄乽戝懞恄乿偱丄僇僢僐撪偵彂偄偨乽懅懍暿柦乿傕乽垻曐恊墹乿偲尵傢傟偰偄偨傛偆側偺偱丄乽搶暉帥嬤曈偺垻曐恊墹曟強乿偺曗堚曇偲偟偰乽垻曐恊墹乿偑弌偰偒偨偺偵偼嬃偒傑偟偨偑丄乽垻曐恊墹乿乽幧恖恊墹乿乽憗椙恊墹乿乽堜忋撪恊墹乿乽埳梊恊墹乿偑宷偑傞偲偄偆偙偲側傫偩傠偆偐丠偲丅
傫丠乽埳梊恊墹乿偺巕丒摗尨堊悽乮晜寠巐榊乯偑埳梊崙偺媖巵傗墇抭巵偺慶偲偝傟傞愢偑偁傞傛偆偱丄乽堜忋撪恊墹乿偺曣偼乽導將梴峀搧帺乿偱乽媖巵乿偵宷偑傞丒丒丒偄傗丄乽媖巵乿偲乽埳梊媖巵乿偲偼暿側偺偐丒丒丒丅
(埳梊恊墹丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E8%A6%AA%E7%8E%8B)
(導將梴峀搧帺丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C%E7%8A%AC%E9%A4%8A%E5%BA%83%E5%88%80%E8%87%AA)
(媖巵丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%98%E6%B0%8F)
(埳梊媖巵丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E6%A9%98%E6%B0%8F)
乽埳梊恊墹乿偺巕丒摗尨堊悽乮晜寠巐榊乯偵偮偄偰専嶕偡傞偲丄
| 丒堊悽 俆侽姾晲揤峜戞係峜巕埳梊恊墹乮丠亅俉侽俈乯偺挿抝偱曣恊偼壠帪彈愢偁傝丅埳梊恊墹偺曄偵嵺偟壠帪偑恊墹傪愞偐偵梴堢偟丄埳梊偵壓岦偟偨媖惔桭偵梐偗偦偺巕偲徧偡傞丅俈嵥偺帪忋棇偟俆俀嵉夈揤峜岪媖壝抭巕偵挒垽偝傟丄摗尨惄傪帓傞丅壓岦偟偰晜寠孲崅堜棦偵廧傒晜寠巐榊傪徧偡丅偲尵偄揱偊桳傝丅 怴嫃巵慶丅 偙偺曈傝偱屻悽偺壨栰巵偑宯恾傪漵憿偟偨偲偺愢嫮偄丅偙偙傑偱墇抭巵丒壨栰巵偑懚嵼偟偰偒偨偑偙偺曈傝偱屻悽偺壨栰巵偑墇抭巵偺抧埵傪櫽扗偟丄宯恾偵怤擖偟偰偒偨壜擻惈偑崅偄偲偝傟偰偄傞丅 (墇抭巵峫丗http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-15.html) (屗揷壠偺壠宯恾丗http://www.biwa.ne.jp/~toda-m/history/todaroot.html) |
偲偁傝丄偼偭偒傝偟側偄傛偆偩偑丄乽埳梊恊墹乿偲偄偆偙偲偼梴堢偟偨偺偑埳梊偲娭楢偑偁傞恖偲偄偆偙偲偱偡傛偹丒丒丒丅
偱丄乽埳梊恊墹乿偺偲偙傠偵乽堎曣孼暯忛揤峜偺懁嬤偱偁偭偨摗尨幃壠丒摗尨拠惉偵憖傜傟偨摗尨廆惉偵幐媟偝偣傜傟偨丒丒丒乿偲偁傞偗偳丄乽摗尨拠惉乿傕墔楈偲偟偰彂偐傟偰偄偨傛偆側丒丒丒乽摗尨峀巏乿偑彂偄偨偲偄偆忋憈暥偵柤偺偁偭偨乽媑旛恀旛乿傕乽屼楈恄幮乿偵釰傜傟偰傑偡傛偹丒丒丒丅
偆乕傫丄壗偵偮偄偰専嶕偡傟偽偄偄偺傗傜丒丒丒丅
偁丄崱崰婥偯偄偨傫偩偗偳丄乽摗尨峀巏偺棎乿偱乽搶奀摴丄搶嶳摴丄嶳堿摴丄嶳梲摴丄撿奀摴偺屲摴偺孯1枩7,000恖傪摦堳乿偱偒偨偙偲丄乽嵅攲忢恖乿傜偑晹壓偺敼恖偵揋懁偺敼恖偵搳崀傪屇傃偐偗偝偣傞偲峀巏孯偺敼恖偼栴傪幩傞偺傪傗傔偨偙偲丄峀巏偑捄巊偼扤偐傪栤偆偨帪偵乽嵅攲忢恖乿偲乽垻攞拵杻楥乿偱偁傞偙偲傪崘偘傞偲壓攏偟偰攓楃偟偨偲偁傞偙偲側偳丄戝彨孯丒戝栰搶恖傗暃彨孯丒婭斞杻楥傗捄巊偑搶崙偺恖乆偲偺宷偑傝偑偁傝丄偦偺孯帠椡傪峀巏偼傛偔抦偭偰偄偨偱偁傠偆偙偲傗丄廬孯偟偰偄偨挬掛偵弌巇偟偰偄偨敼恖偲峀巏孯偺敼恖偲偺宷偑傝偑嫮偐偭偨偙偲傪昞偟偰偄傞傛偆偱丅
(摗尨峀巏偺棎丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%BA%83%E5%97%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1)
乽骐缁偡傞墔楈乿偵丄乽悞摴揤峜乿埲奜偼乽杒壠斏塰偺慴偵偝傟偨恖乆偺楈傪偡傋偰堅晱偟傛偆偲偟偨偺偑掑娤偺屼楈夛偱偁偭偨丅乿(p53)偲偁偭偨偑丄峀巏偑傛偔抦偭偰偄偨偲巚傢傟傞孯帠椡偺摑棪幰偑丄乽杒壠乿偲偺宷偑傝傪帩偭偰偄偨偺偩傠偆偐丒丒丒丅
(屼楈夛丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%9C%8A%E4%BC%9A)
| 仠2011.01.19(Wed.) |
嶐擔偺乽骐缁偡傞墔楈乿偱偺乽掑娤偺屼楈夛乿偵偮偄偰彂偐傟偰偄傞懕偒偵丄乽塽昦棳峴偺尨場傪惌帯揑幐媟幰偺墔楈偱偁傞偲偡傞柉廜偵傛傞惌帯斸敾偑崅傑傞偙偲傪杊偖偙偲偑屼楈夛偵婜懸偝傟偨丅乿偲偁傞丅
偦偟偰師偺儁乕僕偵偼丄乽屼楈夛偑峴傢傟偨応強偑恄愹墤偱偁偭偨偙偲傕廳梫偱偁傞丅乿偲偝傟偰偄偰丄乽恄愹墤乿偼棿恄偑廧傓堎奅傊偺愙揰偱丄乽棿墹偼偙偙偐傜尰悽偵弌擖傝偡傞偲巚傢傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅乿偲偟丄乽墔楈偲棿媨偁傞偄偼棿偲偼怺偄偐偐傢傝傪帩偭偰偍傝丄堎奅偵廧傓墔楈偲岎怣偡傞偵偼偙偆偟偨応強偑傆偝傢偟偐偭偨偺偱偁傞丅乿偲丅
偝傜偵偦偺懕偒偵偼丄乽崱愄暔岅廤乿偵愒偄忋堖傪拝偨乽敽慞梇乿偑乽峴塽棳峴恄乿偲偟偰尰傟偨榖偑彂偐傟偰偄偰丄塽昦偺尨場偑墔楈偵偁傞偲棟夝偝傟偰偄偨丄偲偄偆偙偲傪帵偝傟偰偍傝丄乽(敽慞梇偑)愒偄堖傪拝偰偄傞偙偲傕丄偺偪偺醰釋恄偑愒怓偱昞尰偝傟傞偺偲娭楢偟偰丄嫽枴怺偄丅乿(p57)偲丅
(崱愄暔岅廤丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%98%94%E7%89%A9%E8%AA%9E%E9%9B%86)
(敽慞抝丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%B4%E5%96%84%E7%94%B7)
(墳揤栧偺曄丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E5%A4%A9%E9%96%80%E3%81%AE%E5%A4%89)
乽墳揤栧偺曄乿偵偮偄偰偼僐儈僢僋乽堿梲巘乿偺係姫偵偁傝丄乽墔楈乿偲偝傟偨恖乆偑墔楈偵帄傞傑偱偺宱堒偼偍偍傛偦帡偰偄傞偲巚傢傟傞偺偱丄嫽枴偺偁傞曽偼僐儈僢僋乽堿梲巘乿傪偍姪傔偟傑偡丒丒丒偭偰丄夞偟幰傗側偄偗偳丅(徫)
偱丄偙傟傜偺偙偲偐傜傑偢摢偵晜偐傫偩偺偑丄2010.01.09暘偱偺乽愹嬀壴乿偺乽栭嵆儢抮乿偵乽曯偺拑揦偵拑媯彈偑愒慜悅偲偄偆偺偑帠幚側傜丄醰釋偺恄偺寶応偱傕嵎巟偊傫丅搾偺旜摶傪墇偦偆偲傕巚偄傑偡丅乿偲偁傞偙偲偱丄乽愹嬀壴乿偼乽搾旜摶乿偵乽醰釋恄乿偑偄傞偺傪抦偭偰偄偰乽愒慜悅乿偱偁傞偙偲偵宷偘丄攎徳傕摨條偵抦偭偰偄偨偐傜乽寧偵柤傪曪傒偐偹偰傗摋釋偺恄乿傪塺傫偩丄偲偄偆偙偲側傫偩側偀丄偲丅
(撊僲栘摶乣崱廻(2)丗http://www.fuku-e.com/theme/03/03/01/3-3-1-1b.html)
乽醰釋乿乽愒乿偱専嶕偡傞偲丄乽愒偄怓偑杺椡傪旈傔偰偄傞偲夝庍偝傟丄愒偄椡偱晄岾偺栵暐偄傪偟偰偒偨偺偱偡丅乿偲丄峕屗帪戙偵乽醰釋恄傪婌偽偣昦婥傪帯偦偆乿偲偟偰乽偍愒斞乿傪怘傋丄昦婥偑帯偭偰栵暐偄偵傕乽偍愒斞乿傪怘傋偰偄偨丄偲偁偭偨丅
(愒斞偺側偧丗http://www.narumi-mochi.jp/nazo.html)
乽偍愒斞乿偱巚偄弌偡偺偼2009.12.08暘側偳偱偺乽敔崻恄幮乿偺乽屛悈嵳乿偱丄2010.02.02暘偱偼乽嶰曱恄幮乿偺乽戝嶳釲恄幮偺釱傪偐傝偰丄戝嶮偵崅惙傝偺愒斞偲偍恄庰傪嫙偊偰曭傝丄偙偺愒斞傪偄偨偩偒傑偡丅乿偲偄偆乽戝擔嵳乿偵丄乽敔崻恄幮乿偺乽屛悈嵳乿偲偺娭楢傪憐憸偟偰偄偰丅
(嬨摢棾揱彸丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E9%A0%AD%E7%AB%9C%E4%BC%9D%E6%89%BF)
(戝擔嵳丗http://www.mitsuminejinja.or.jp/saiten/index.htm)
乽嶰曱恄幮乿偺乽戝嶳釲恄幮偺釱傪偐傝偰乿偲偄偆偺偼丄乽戝嶳釲恄乿偺柤偵塀偝傟偨杮棃釰傜傟傞傋偒恄偵曭偘傞偙偲傪尵傢傫偲偟偰偄傞傛偆偱丄乽敔崻恄幮乿偺乽屛悈嵳乿傕乽醰釋恄乿偲廗崌偟偨乽嬨摢棾恄乿傊偍愒斞傪曭偘偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟丄偡側傢偪乽墔楈乿偲傕尒傜傟偰偄偨乽悾怐捗昉乿傊偺乽偍嵳傝乿乽屼楈夛乿偱丄偦傟偼乽悾怐捗昉乿傪曭嵵偡傞巵懓傊偺媀幃偱傕偁偭偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞傢偗偱丅
乽醰釋彍偗偺恄乿偲偝傟傞乽嶗栘恄幮乿偺幮柤傗丄乽偟偐偟側偤丄揤晲偼偙偺嶗栘幮偱戝屓婱丄彮旻柤丄偦偟偰枛幮偵嵖偡戝嶳釲乮嶳恄乯偲偲傕偵釰傜傟傞偺偐丅揤晲偼媑栰偱嶳偺恄偲側偭偰偄傞丅乿偲偝傟傞偁偨傝偼乽嶰曱恄幮乿偺乽戝擔嵳乿偵宷偑傝偦偆偱丄乽揤晲乿偲乽愒乿偺娭學傗丄乽懽悷乿偲乽醰釋乿偺偙偲側偳嫽枴怺偄偱偡偹丅
(撧椙丒嶗栘恄幮丗http://urano.org/kankou/yoshino/yoshino16.html)
(*243乮6乯媑栰丗http://www.sysken.or.jp/Ushijima/Mother.html#敮挿昉)
(戝奀恖峜巕偲媑栰丗http://www.geocities.jp/tyuou59/tennmuyosino.html)
(懽悷丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%B0%E6%BE%84)
乽嶋戝柧恄偲偦偙(惣攲孲丒拞嶳恄幮)偱釰傜傟偰偄傞堫攚泺柦偲敀揺恄偼丄偡傋偰醰釋恄偲偄偆嫟捠揰傪帩偭偰偄傑偡丅乿偲偁傞偙偲側偳丄乽醰釋彍偗乿偺恄幮偵釰傜傟偰偄傞恄偑條乆側偁偨傝傕嫽枴怺偄側丄偲丅
(攲闼偺傕偆堦偮偺敀揺恄榖丗http://www.rs.tottori-u.ac.jp/bunka/student/report/2008/2008pdf/4_sirousagi-2008.pdf)
(朙搰嬫丒戝捁恄幮丗http://www.tobusdeiko.jp/spot/temples/otori.html)
(醰釋偺庣岇恄丗http://taisha.jp/index.php?ID=1463)
(淺榓恄幮丗http://www.genbu.net/data/wakasa/miwa_title.htm)
(姍憅巗丒孎栰恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E9%87%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B8%82))
(峀搰巗丒醰釋恄幮丗http://www.hicat.ne.jp/home/yakuoudo/kimagure%20tusin/order3/326.htm)
(峀搰巗丒醰釋恄幮丗http://www.harusan1925.net/0813.html)
(媑旛捗恄幮丗http://blogs.yahoo.co.jp/kanezane2/18333399.html)
(崅屼慜恄幮丗http://kamnavi.jp/it/kii/takatumi.htm)
婥偵側偭偨偙偲偲偟偰丄乽醰釋傪昦傫偩彫挰偼偙偙偵擔嶲丄愹偺惔悈偱婄傪愻偄帯桙傪婩偭偨乿偲偄偆乽堥慜恄幮乿偑廐揷導梇彑挰偵偁傝丄嫍棧偼傛偔傢偐傜側偄偑丄梇彑挰廐偺媨偵偁傞偲偄偆乽戦偺搾壏愹乿偼峴婎備偐傝偲偝傟偰偄偰丄峴婎偼岤栘巗偺乽彫栰恄幮乿側偳偱彫栰巵偲偺宷偑傝偑巉傢傟傞偺偱丄乽悾怐捗昉乿偱宷偑傝偦偆側姶偠偑偟偰丅
(梬愔傔偖傝丒捠彫挰丗http://www.harusan1925.net/1228.html)
(彫栰彫挰丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E5%B0%8F%E7%94%BA)
(彫栰恄幮丗http://www.geocities.jp/engisiki/sagami/bun/sag160401-01.html)
廐揷偲偄偊偽峴婎備偐傝偲偝傟傞乽彫摛戲戝擔摪乿偑偪偲婥偵側偭偨偑丄醰釋恄偲偺宷偑傝偼傢偐傜偢丒丒丒丅
偁偲丄乽寧撉柦乿傪釰傞徏屗巗偺乽嶰擔寧恄幮乿偵偼丄乽醰釋屼曕幩乿偲偄偆乽巵巕偺埨慡婩婅傗醰釋栵彍偗傪偡傞峴帠乿偑偁傞偦偆偱丄乽嶰擔寧恄幮乿偱専嶕偡傞偲乽嶰擔寧乿抧柤偑彂偐傟偨僽儘僌偑偁傝丄偦偙偵儕儞僋偺偁偭偨乽嶰擔寧嶁偺桼棃乿傪攓尒偡傞偲愒塇偵丒丒丒丅
(抧尦傪抦傞丒嶰儢寧曇丗http://www.hellomatsudo.com/paper/show_tokushu.php3?id=237)
(乽嶰擔寧乿抧柤丗http://blogs.yahoo.co.jp/kmr_tds/44190822.html)
(嶰擔寧嶁丗http://homepage2.nifty.com/tokyo-walk/a050449.htm)
乽嶁傪搊傝偒偭偨杒懁偁偨傝偵嶰擔寧拑壆偑偱偒傑偟偨丅 嶁柤偼偙傟偵桼棃偟偰偄傑偡丅 傑偨丄摴燇搾偑奐嬈偟偨偙偲偐傜摴燇嶁偲傕屇偽傟偰偄傑偡丅乿偲偺偙偲偱丄乽栭嵆儢抮乿偺乽曯偺拑揦乿傪巚偄弌偟偨偺偲丄偦偺慜偵専嶕偱尒偰偄偨乽愒塇敧敠恄幮乿偵栠偭偨丅
(愒塇敧敠恄幮丗http://www3.kitanet.ne.jp/~ak8mans/hatiman.htm)
乽愒塇敧敠恄幮乿偺嫬撪幮偵乽醰釋恄幮乿偑偁傞偺偲丄乽摴燇搾乿偺桼棃偼傢偐傜側偄偗偳丄2010.01.09暘側偳偱偺嫗搒丒嶳忛偺乽堦岥乮偄傕偁傜偄乯堫壸恄幮乿傪姪惪偟偨乽懢揷昉堫壸恄幮乿偼乽懢揷摴燇乿棈傒側偺偱丄乽愒塇乿偺偁偨傝偼乽懢揷摴燇乿傗乽醰釋恄乿偺娭楢偺偁傞応強側偺偐傕丅
(懢揷昉堫壸恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%A7%AB%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
乽愒塇乿偼乽愒搚乮愒忹丒偁偐偼偵乯偑懡偄搚忞偐傜丄偙偺柤偑偮偄偨丅乿偲偺偙偲偱乽揝乿偵宷偑傝偦偆偱丄偙偪傜偵傕乽彫摛戲乿偲偄偆抧柤偑偁傞傫偱偡偹丒丒丒乽屼庤愻晄摦媽愓乿乽屼庤愻偺愹乿偑婥偵側偭偨偗偳徻嵶偼傢偐傜側偐偭偨丅
(愒塇丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%BE%BD)
(彫摛戲丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E6%B2%A2)
(愒塇奅孏柤強埬撪丗http://www.ukima.info/meisho/akabanej.htm)
(屼庤愻晄摦摪丗http://www.ukima.info/meisho/kaiwai/ryuhukuj/mitarai1.htm)
| 仠2011.01.20(Thu.) |
乽骐缁偡傞墔楈乿偐傜偺専嶕偱丄僨僗僋僩僢僾偵僔儑乕僩僇僢僩傾僀僐儞偑係侽屄傎偳暲傫偱傞傫偩偗偳丄偳偆傑偲傔傟偽偄偄偺傗傜丒丒丒嶐擔偺乽屼庤愻乿偲摨條偵乽悾怐捗昉乿偲偺娭楢偼晄柧偩偑丄嶰廳偵乽旤懡梾巙恄幮乿偑偁傞傛偆偱丄乽棿乿偺傛偆側庽偑偁偭偨丅
(旤懡梾巙恄幮丗http://blog.livedoor.jp/ogita5/tag/%E7%BE%8E%E5%A4%9A%E7%BE%85%E5%BF%97%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
乽棧搰暥壔懱尡丒摎巙搰僐乕僗乿偺徯夘偺僒僀僩偵偼丄乽憂棫擭戙偼晄徦偱偡偑丄嫕曐4擭偺搹嶥傗墑嫕3擭專昳偺巶巕堦懳丄屆暥彂側偳偑曐懚偝傟偰偄傑偡丅庡嵳恄偼旤懡梾巙恄偱丄柧帯41擭偵揤墹幮丄嶳恄幮丄揤恄幮傎偐10幮傎偳傪崌釰偟偰丄旤懡梾巙恄幮偲側傝傑偟偨丅乿偲偁傝丄乽傞傞傇乿偵偼乽旤懡梾巙恄偼屲抝嶰彈偺巕傪傕偮恄條偱丄巕庼偗偺偛棙塿偑偁傞偲偝傟偰偄傞丅晇晈偱嶲攓偟偰偮偑偄偺傾儚價傪曭擺偡傞偲丄旤偟偄摰偺巕嫙偑庼偐傞偲偐丅乿偲丅
(旤懡梾巙恄幮丗http://www.iseshima-kanko.jp/contents/museum/ritou/ritou_tousijima.html)
(旤懡梾巙恄幮丗http://www.rurubu.com/sight/detail.aspx?BookID=A3401220)
2007.04.26暘偱攓尒偟偨恄撧旛偝傫偺乽揤崄崄攚抝柦傪釰傞恄幮堦棗乿偵偼丄屼嵳恄偼乽揤擡鈔帹柦丂崌丂杒搇惎恄丄嶰廫嶰栭惎恄傎偐乿偲偁偭偰丄乽屲抝嶰彈偺巕傪傕偮恄條乿偲偄偊偽傾儅僥儔僗亄僗僒僲僆偺巕傪巚偄弌偟丄堦懳恄偐偲憐憸偟丄乽旤懡梾巙恄乿偑乽揤崄崄攚抝柦乿側傜偽乽悾怐捗昉乿偲宷偑傞傛偆偵巚偊偰丒丒丒丅
(旤懡梾巙恄幮丗http://kamnavi.jp/jm/kakaseo.htm)
寢嬊傛偔傢偐傜側偄傑傑側偺偩偑丄乽旤懡梾巙恄幮乿傪抦傞偒偭偐偗偲側偭偨偺偑乽偟偩傜恄乿偱偺専嶕偱丄乽杮挬悽婭乿偵傛傞偲俋係俆擭偵乽巙懡椙恄擖嫗帠審乿偑婲偙偭偨偦偆偱丅(p79)
偦偙偱傑偢攓尒偟偨偺偑偐偮偰乽偲偼偢偑偨傝乿偱攓尒偟偰偄偨僒僀僩偱丄乽揤宑敧擭巙懡椙恄偲傕敧柺恄丒彫錫妢恄偲傕偄偆怴偨側恄乆偑搶惣彅崙偐傜擖嫗偟偰偒偨丅乿偲偄偆偙偲偼杮偺婰嵹偲傎傏摨偠偱丄乽屼楈怣嬄偑揥奐乿偟丄乽怴偟偄嫗奜偺嫮僇側恄乿傪寎偊偨傛偆偱丄乽偙偺巙懡椙恄偑幚偼敧敠恄偺崤懓偱偁傞偲偝傟丄愇惔悈敧敠偵慗嵗偟曪娷偝傟偨丅乿偲偄偆偺偑婥偵側偭偨丒丒丒侾侽擔偺乽掃壀敧敠媨乿偱偺乽墔楈捔嵃乿摨條丄乽敧敠媨乿偑娭梌偟偰偄傞傛偆偱丅
(愇惔悈敧敠媨丗http://www015.upp.so-net.ne.jp/gofukakusa/kyotofuno-chimei-iwashimizu.htm)
偟偐傕乽偟偩傜恄乿傪釰偭偨恄梎偑丄埳扥偺乽崺梲帥乿偵傕婑偭偰偄偰丄弶傔偼悢昐恖偩偭偨偺偑乽愇惔悈敧敠媨乿摓拝偺嵺偵偼乽悢愮丒枩恖偵払偟偰偄偨偲偄偆丅乿偲偺偙偲偱丄乽崺梲帥乿嬤椬偺恖乆傕懡偔嶲壛偟偨偱偁傠偆丄偲丅
(巙懡椙恄丗http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%BB%D6%C2%BF%CE%C9%BF%C0)
乽堦庬偺塽恄丒屼楈恄偱偼側偄偐偲偡傞尒夝偑偁傞丅乿偲偝傟偮偮傕乽擾懞偵偍偗傞奐敪偲惗嶻傪庣傞恄乿偲偺尒夝傕偁傞傛偆偱丄乽崺梲帥乿偑棈傫偱偄傞偙偲傗乽壧晳乿偑偁傞偙偲側偳偐傜丄乽恅巵乿偺懚嵼偑尒偊傞傛偆偱丒丒丒乽椑恛旈彺乿偵傛傞偲丄乽帺傜捔惣乮嬨廈乯偐傜忋棇偟丄偙偺擔巼栰慏壀嶳偵摓拝偟偨偲偄偆丅乿偲偺偙偲偱丄乽慏壀嶳乿偼恅巵偺僥儕僩儕乕偱丅
(椑恛旈彺岥揱廤姫戞廫巐丗http://homepage3.nifty.com/false/garden/kuden/kuden14-6.html)
(桍揷崙抝乽梮偺崱偲愄乿丗http://www.touhoku.com/00x-10-02yk-odori-01.htm)
(寶孧恄幮丗http://www5e.biglobe.ne.jp/~hidesan/takeisao-jinjya.htm)
乽慏壀嶳乿偵愭偵釰傜傟偰偄偨偲偄偆乽塽恄乿偵偮偄偰丄尦偼乽僗僒僲僆乿傪釰傞幮偱尰嵼偼乽崱媨恄幮乿偺愛幮乽塽恄幮乿偺傛偆偩偑丄懠偺嫬撪幮偺乽寧撉幮乿傗丄乽廆憸幮乿偺幮抎偺懁柺偺戜愇偵挙傜傟偨乽槲乿偲丄乽偙偺幮(廆憸幮)偼懎偵乽曎揤偝傫乿偲屇偽傟丄槲偼偦偺恄偺巊幰偲偟偰挙傜傟偨傕偺偲塢傢傟偰偄傞丅乿偲偄偆偺偑婥偵側偭偨丅
(崱媨恄幮丗http://imamiyajinja.org/)
(槲偺戜愇丗http://imamiyajinja.org/jpn/imamiya_JPN/jing_nei_she.html)
乽悾怐捗昉乿偺偙偲偱偡傛偲尵傢傫偽偐傝偺傛偆偱丄乽嫗偺嶰婏嵳乿偼恅巵偵傛傞悾怐捗昉偺偨傔偺偍嵳傝側偺偱偼側偄偐丄偲丒丒丒乽偟偩傜恄乿偲偐偮偰2003.03.21側偳偱挷傋偨乽杸懡梾恄乿偲偺娭楢偑婥偵側傞偑丄崱偺偲偙傠捈愙寢傃偮偗傞傕偺偼側偄傛偆偱丒丒丒丅
乽岅傝晹壆僽儘僌乿偝傫偺乽偟偩傜偺恄乿傪攓尒偟偰偄傞偲丄乽偟偩傜恄乿偵偮偄偰娙寜偵彂偐傟偰偍傝丄乽巙懯娸敧敠媨乿偲偺娭楢偑偁傝偦偆側偺偱儕儞僋愭偺僒僀僩傪攓尒偟偨偲偙傠丄乽恄條偑崙搶偐傜偱偨傝婣偭偨傝丅乿偵桴偒偮偮丄乽巙懯娸敧敠偵偼彫徏偺壂偑栭婸偄偰偄偰偦傟傪挷傋傞偲丄僔僟偵姫偐傟偰昚偭偨恄條傪傒偮偗丄偦傟傪媢偵埨抲偟偨乿偲偄偆揱愢偑婥偵側偭偨丅
(岅傝晹壆僽儘僌丗http://www.chinjuh.mydns.jp/blog02/archives/2004/12/post_1.html)
(僒僀僋儖僺僋僯僢僋丗http://www.cyclesforum.net/cyclepicnic/course_syoukai/oshima/01/01.htm)
忋婰僒僀僩偱偼乽愇惔悈敧敠乿偐傜偺姪惪偲偝傟偰偄偨偑丄乽曮婽3擭(772)塅嵅偐傜壆戙偵姪惪偟偨傕偺傪峅埨4擭(1281)戜晽偱棳弌丄梻擭尰嵼抧偵壖壆傪寶偰丄墑暥3擭(1358)戝撪惌峅偺柦椷偱嵞寶偟丄巙懯娸偲姤柤偟傑偟偨丅乿偲彂偐傟偨僒僀僩傕偁偭偰丄僔僟偵娭偡傞揱愢傕傛偔傢偐傜偢丒丒丒丅
(巙懯娸敧敠媨丗http://park22.wakwak.com/~suo-oshima-shoko/oshima/sightseeings/sidagisihatimangu/index.htm)
偱丄乽岅傝晹壆僽儘僌乿偝傫偺偲偙傠偵乽愝妝恄乿偼乽偣偮傜偔偟傫乿偲傕撉傒丄乽埢錫妢傪偐傇偭偰梮傞恄乿偲彂偐傟偰偄偨偺偱乽埢錫妢乿偱専嶕偡傞偲丄乽椑恛旈彺乿偺壧偑僸僢僩偟丄乽夑栁愳乿偑塺傑傟偰偄傞偁偨傝偵壗偐偁傝偘偱丒丒丒丅
(愹嘹偺恄乆偺帿揟丗http://www.geocities.jp/izumikawauso/kami/k_bse.html#se)
(椑恛旈彺姫戞擇丂巐嬪恄壧丒嶨丗http://www.nextftp.com/y_misa/ryoujin/hisyo_05.html)
偁偲丄愜岥巵偺乽暭懇偐傜婙偝偟暔傊乿偵偼丄乽彮擉巵偺婙偺墶忋偵丄埢錫妢傪偮偗偨偺偼丄崤懏偺屼楈偺塭岦偁偮偰丄愪岥偵屼嵗偁傞偐傜偲偺壠孭偑偁傞乮攡徏榑乯丒丒丒乿偲偁偭偨偑傛偔傢偐傜偢丄乽攡徏榑乿傪専嶕偟偨傜丄
(暭懇偐傜婙偝偟暔傊丗http://www.aozora.gr.jp/cards/000933/files/18394_19352.html)
| 彮擉棅彯偼丄婙偺墶忋乮棳傟婙偺忋偵丄婙偺暆偱晅偗偨墶栘乯偵埢昈妢乮昈偺敄斅傪栐戙偵曇傫偱嶌偭偨妢乯傪晅偗偰偄偨丅偙傟偼丄屼崤懏屼楈乮堦栧偺楈乯偑塭岦乮恄暓偑尰傟傞偙偲乯偝傟偰愪岥乮婙偺娖愭偺丄婙晍傪忋壓偡傞偨傔偺妸幵偺偁傞晹暘乯偵偍傢偡偺偱丄愄偐傜偙傟傪晅偗傞偺偑偙偺壠偺掚孭偲偝傟偰偄偨偨傔偱偁傞丅
(攡徏榑丗http://homepage1.nifty.com/sira/baisyouron/baisyou39.html) |
偲偺偙偲偱丄側傞傎偳丄偲丒丒丒乽敧敠恄偺崤懓乿偑乽埢錫妢乿偱丄偦傟傪偐傇偭偰梮傞恄偑乽愝妝恄乿偲偄偆偙偲偺傛偆偱丄乽埢錫妢乿偺戙昞偑乽恅巵乿偐偲丅
彮偟墶摴偵偦傟傞偑丄愜岥巵偺暥復偱椺偵嫇偘傜傟偰偄傞帠暱傪捛偊偽丄暿偺妏搙偐傜宷偑傞傛偆偵巚偊偨偺偩偑丄偄偐傫偣傫丄暥復偑擄偟偔偰側偐側偐偦偆傕偄偐側偔偰丒丒丒乽暭懇偐傜婙偝偟暔傊乿偺巒傑傝偑乽垻楃乿偱乽夑栁乿偺偙偲傗惣峴偺壧偑弌偰偒偨傝丄忋婰偺乽攡徏榑乿偲偼乽摨偠塭岦姪惪偺巚憐乿偲偝傟傞乽孎栰暿摉扻憹乿偺偙偲傕丄壗傗傜堄枴偁傝偘側姶偠偑偟偰丅
愜岥巵偺乽孎栰偺扻憹偑丄慏偵庒墹巕偺屼惓懱傪嵹偣丄婙偺墶忋偵嬥崉摱巕傪彂偄偰丄抎偺塝傊偍偟婑偣偨乮暯壠暔岅乯乿偺堷梡傪捛偆偲丄乽抎偺塝傊嬤偯偄偰棃傞偺傪尒偰丄尮巵傕暯壠傕偲傕偵攓傓丅偟偐偟側偑傜尮巵偺曽傊偮偄偨偺偱丄暯壠偼堄婥徚捑偟偨丅乿偲乽暯壠暔岅乿偵偁傞傛偆偱丄怣嬄偑摨偠偩偭偨偙偲偑巉偊傞傛偆偱丅
(婭埳懕晽搚婰丗http://www.keyspot.info/fudoki/minatotoukei.html)
傑丄乽暯壠暔岅乿傪抦偭偰偄偨側傜丄僱僢僩偱捛傢側偔偰傕傢偐傞偙偲偩傠偆偐傜丄傂偲偊偵巹偺晄曌嫮偝偑業掓偟偰偄傞傢偗偩偑丅(嬯徫)
偱丄乽彫錫妢恄乿乽敧柺恄乿偵偮偄偰傕専嶕偟偰傒偨偲偙傠丄乽塱挿戝揷妝偵偍偗傞婱懓偲柉廜乿偲偄偆PDF僼傽僀儖偵丄抮忋攷擵巵偵傛傞偲乽敧柺恄乿偼乽峳恄偺斖醗偵擖傞偲婣擺偣傜傟傞乿偲偝傟丄乽彫錫妢恄乿偼乽崱屻揷妝偺婲尮傪偝偖傞拞偱幚嵺偺揷怉媀楃偲娭傢傜偣偰専摙偟偰傒偨偄丅乿偲偝傟偰偄偰丄乽巙懡椙恄擖嫗帠審乿偱偺俁婎偺恄梎偵偼丄帺嵼揤恄(摴恀)丒塅嵅弔墹嶰巕丒廧媑恄偑釰傜傟偰偄偨偙偲偑乽棛晹墹婰乿偵偁傞傛偆偱丄忋婰偺傛偆偵乽堦庬偺塽恄丒屼楈恄偱偼側偄偐偲偡傞尒夝乿傕彂偐傟偰偄偨丅
(塱挿戝揷妝偵偍偗傞婱懓偲柉廜丗http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp:8080/dspace/bitstream/10191/985/1/18_0115.pdf)
(棛晹墹婰丗http://kotobank.jp/word/%E5%90%8F%E9%83%A8%E7%8E%8B%E8%A8%98)
乽揷怉媀楃乿傊偺攈惗偲巚傢傟傞傕偺偲偟偰丄墶昹偺乽掃尒恄幮乿偺乽揷嵳傝曐懚夛乿偝傫偺僒僀僩偑僸僢僩偟丄乽強嶌偺尋媶乿偲偟偰乽偙傟傑偱尒妛偟偰偒偨奺抧偺揷梀傃偼丄搶奀摴嬝摿桳偺墡妝丄嫸尵偲愝妝恄壧(偟偩傜偐傒偆偨)丄愮廐枩嵨偺梈崌宍幃偑偲傜傟偰偄傞丅乿偲偁傝丄傗偼傝恅巵偑尒偊偰偔傞傛偆偵巚傢傟偰丅
(掃尒恄幮丗http://www18.ocn.ne.jp/~tsurujin/contents/group/tamaturi.html)
乽敧柺恄乿偵偮偄偰偼乽峳恄乿偲偟偰乽墌嬻暓乿偑僸僢僩偟丄2007.05.02暘偱偺乽敧柺戝墹乿偲偺宷偑傝偑婥偵側偭偨傕偺偺傛偔傢偐傜側偔偰丅
(旤暲傆傞偝偲娰 敧柺峳恄丗http://shigeru.kommy.com/enkuu7.htm)
(敧柺戝墹嵞峫丗http://jyashin.net/evilshrine/gods/momiji_shrine/momiji_08.html#4)
敧柺恄幮丗廐揷導搾戲巗嬵宍挰帤敧柺媨偺慜
屼嵳恄丗悰尨戝恄丄慺滬歫柦丄戝嶳媉柦丄嶰媑戝恄丄朙庴昉柦丄揤徠戝恄
| 搾戲巗敧柺抧嬫偵偁傞敧敠懢榊棨墱庣尮媊壠挬恇偑愬杒嬥戲偺忛捛摙偺帪丄擄愴偟偰偙偺懜恄偵婩婅偟偨偲偙傠丄偦偺栭恄慜傛傝敀幁偑尰傟偰丄婼愗曈偺嶳拞偵擖偭偰偄偭偨幁偺愓傪捛偭偰丄悢枩偺孯惃偼柍帠偦偙傪愗傝偸偗傞偙偲偑弌棃偨丅枖丄偦偺屻傕搙乆偺愴偄偱擄愴偺偨傃偵敀幁偑尰傟偰戝彑棙傪偟偨偺偱丄媊壠偼帺暘偱恄憸傪挙崗偟丄敧柺戝峳恄偲偟偰恄幮偺揷抧偲偲傕偵婑恑偝傟偨偲婰偝傟偰偄傞丅 (http://www.yuzawamarugoto.com/yatsuomotejinja/index.html) |
堫壸敧柺恄幮丗惷壀導晉巑巗澍尨帤忋杮揷
屼嵳恄丗塅夀擵屼嵃恄丄敧柺恄乮峳恄乯
| 堫壸恄幮偲敧柺恄幮傪崌釰偟偰偄傞丅堫壸丄敧柺偲傕偵憂釰擭寧偼晄徻丅偨偩敧柺恄幮偼丄晉巑愳偑偙偺曈傝傪棳傟偰偄偨偙傠丄昚拝偟偨恄懱傪棦恖偑尒偮偗偰姪惪偟偨丄偲岥揱偝傟偰偄傞乮亀弜壨婰亁乯丅敧柺恄幮偼巗撪偵俀幮偁傝丄傕偆侾幮偼娾杮嶳偺悶偵偁傞丅偄傑晉巑愳偼娾杮嶳偺惣傪撿壓偟偰弜壨榩偵拲偖偑丄傓偐偟偼嶳悶偱搶撿傊岦偒傪曄偊丄娾杮敧柺恄幮偺撿傪偐偡傔偰偙偙壛搰暯栰偵棳擖偟偨丅岥揱偝傟傞乽昚拝偟偨恄懱乿偼丄娾杮敧柺恄幮偲娭傢傝偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅婰榐偵栚傪揮偠傞偲丄峕屗拞婜乣屻婜偺搹嶥偑懡偔巆傞丅敧柺恄幮偼埨塱俉擭乮侾俈俈俋乯偑嵟傕屆偔丄恄柤偼乽敧柺戝尃尰乿丅堫壸恄幮偼暥壔侾俀擭乮侾俉侾俆乯偑嵟屆偱丄恄柤偼乽堫壸戝柧恄乿丅 (http://iiduna.blog49.fc2.com/blog-entry-372.html) |
敧柺恄幮丗惷壀導晉巑巗娾杮
庡嵳恄丗敧柺戝峳恄乮壩嶻楈恄丒墱捗斾屆恄丒墱捗斾攧恄乯
| 戝塱俇擭乮侾俆俀俇乯娾杮塱尮帥偑尰抧偵摪塅傪寶棫偟偨偝偄丄抧庡恄偩偭偨摉幮傪捔庣偲偟偰嵞寶偟偨丅峕屗婜偺屇徧偼乽敧柺峳恄幮乿丄恄暓敾慠椷偱塱尮帥偲暘棧丅 (http://iiduna.blog49.fc2.com/blog-entry-313.html) |
埰壀媉墍恄幮丗媨嶈導屲儢悾挰埰壀帥懞
屼嵳恄丗慺岬柭戝恄丄戝屓婱戝恄丄埳淨檉戝恄丄婏堫揷昉恄丄屲僢悾僲恄丄慼柉彨棃丄嫄扷彨棃丄揤枮揤恄丄懌柤捙恄丄庤柤捙恄丄堫壸戝柧恄
| 戞擇廫嬨戙嬙柧揤峜偺廫榋擭崰丄抦曐嫿偵栵昦棳峴偟塽昦媦傃栵擄徚彍偺婩婅庣岇恄偲偟偰憂巒媉墍幮偲徧偟丄戞屲廫屲戙暥摽揤峜偺揤埨尦擭慮抝恄(慺岬柭戝恄)暲傃偵姤敧柺戝柧恄(埮偍偐傒恄)偵惓屲埵壓偺恄奒曭庼偺屆偄恄幮偱偁傝傑偡丅(暥摽幚榐戞嬨傛傝) 戞屲廫榋戙惔榓揤峜偺掑娤廫堦擭嶳忛崙(嫗搒)敧嶁恄幮傛傝慺岬柭戝恄傪姪惪丄偦偺懠偺彅恄傪崌釰偟敧嶁恄幮偲夵徧丅徍榓廫擭媉墍恄幮偲夵徧尰嵼偵帄偭偰偍傝傑偡丅(媉墍恄幮埬撪傛傝) (http://www.kiroku-miyazaki.jp/contents/index.php?itemid=192) |
鈣恄幮丗堬忛導壓嵢巗旙嫶
屼嵳恄丗墱捗斾屆柦丄墱捗斾攧柦
| 俈俈俇乮曮婽俈乯擭偺憂棫偲偝傟傞屆幮丅旙嫶嫿偵堦杮偺徏偑偁傝丄偦偺徏偐傜岝柧偑幩偟偰偄傞偺偱懞恖偑尒偰傒傞偲丄徏偺壓偵乽敧柺峳恄乿偺憸偑偁偭偨丅懞恖偼偦偺憸傪丄偍媨傪寶偰偰釰偭偨偺偑恄幮偺偼偠傑傝偲偝傟傞丅捠徧乽峳恄偝傑乿丅 峳恄偼丄暓朄憁偺嶰曮傪庣岇偡傞嶰柺榋鋆偺嶰曮峳恄偲偝傟傞偑丄鈣恄幮偺恄偼敧柺榋鋆偱敧柺峳恄偲徧偝傟傞丅晄忩傪寵偄丄鈣乮偐傑偳乯丄戜強偱釰傜傟偰偄傞丅傑偨丄墢寢傃偺峳恄偝傑偱抦傜傟傞丅 (http://www.tsukubapress.com/shimotsuma.html) |
敧柺恄幮(奀恄恄幮愛幮)丗懳攏巗曯挰栘嶁
屼嵳恄丗戝殸嵃恄
(http://kamnavi.jp/en/kyuushu/tusimaumi.htm)
| 奀恄恄幮 屼嵳恄丗娌嬍昉柦丄攝釰丗旻壩壩弌尒柦丄廆憸恄丄摴庡婱恄 塋姖憪晿晄崌柦 憂釰擭戙偼晄徻丅懳攏偺堦擵媨偲偟偰悞宧偝傟偰偄傞戝幮丅 亀洈廈恄幮帍亁偵偼乽敧敠媨乿偲婰偝傟丄柧帯傑偱偼乽敧敠媨乿偲徧偟偰偄偨丅堦愢偵偼丄宲懱揤峜偺屼戙丄嵳揳傪寶偰丄敧敠媨偲徧偟偨偲偄偄丄変偑崙敧敠媨偺敪徦偺抧偲傕丅 傑偨丄摉幮傪幃撪幮丒榓懡搒旤屼巕恄幮偲偡傞愢傕偁傞丅懳攏偺嵳釰偱偼丄恊巕恄偑釰傜傟傞偲偒丄恊恄傪棦嬤偔偵丄巕恄傪恖棦棧傟偨惞抧偵釰傞偙偲偑懡偄偑丄榓懡搒旤屼巕偺応崌傕丄惞抧乮埳摛嶳乯偵釰偭偨偲偄偆峫偊丅 (奀恄恄幮丗http://www.genbu.net/data/tusima/kaijin_title.htm) |
偝偰丄愭傎偳乽巙懡椙恄乿偺恄梎偵乽帺嵼揤恄(摴恀)乿偑娷傑傟偰偄傞偲偁偭偨偑丄乽悰壠屼揱婰乿偵摴恀偺偙偲傪乽揤枮帺嵼揤恄乿偲偁傞傛偆偱丄乽帺嵼揤恄乿偲偼乽僔償傽恄偑暓嫵壔偟偨傕偺乿偩偦偆偱(p74)丅
(挿壀揤枮媨丗http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-9-2.html)
(僔償傽丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B4%E3%82%A1)
乽骐缁偡傞墔楈乿偵偼摴恀偺乽墔楈偲偟偰偺妶摦乿偵偮偄偰偺婰嵹偑偁傝丄乽偙偙偱傕敧敠恄偑摴恀偺楈嵃偺忋埵幰偲偟偰巟攝傪峴偭偰偄傞偲棟夝偝傟偰偄傞偙偲偑拲栚偝傟傞丅乿(p77)偲偁傞偺偼嫽枴怺偔丄敧敠恄偲摴恀偺宷偑傝傪帵偟偰偄傞傛偆偱丅
乽摴尗忋恖柣搑婰乿偵傛傞偲丄摴恀偼乽懢惌埿摽揤恄乿偲側偭偰偄偰丄嵭偄傪婲偙偟偰偄傞偺偼摴恀偺乽崤懏乿偱丄摗尨惔娧傜傊偺棊棆偼摴恀偺戞嶰偺巊幰乽壩棆揤婥撆墹乿偩偲偟偰丄偦偆偟偨崤懏偵懳偟乽嬥曱嶳偺憼墹尃尰傗敧敠恄偦傟偵塅懡朄峜偺楈嵃偑彑庤側怳傞晳偄傪偡傞偺傪棷傔偰偄傞偲偄偆丅乿(p76)偲偺偙偲偱丄乽憼墹尃尰乿偲傕宷偑傞偙偲傪帵偟偰偄傞傛偆偱丅(塅懡朄峜偼摴恀偺柡柟丅)
(摴尗(擔憼)丗http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E8%94%B5?dic=nihonjinmei)
乽僔償傽恄乿乽戝埿摽柧墹乿乽摴恀乿偑乽媿乿偱宷偑傞偺偵傕壗偐偁傝偦偆偱丄乽暥庩曥嶧偼偦偺埆婼偲摨偠傛偆側媿柺偱丄偟偐傕埆婼埲忋偺晲婍傪傕偭偨巔偵曄壔偟偰愴偄丄偮偄偵埆婼傪搢偟偨丅偙偺巔偑戝埿摽柧墹側偺偩偲偄偆丅乿偱晜偐傫偩偺偼丄埳梊偺乽戝嶳媉恄幮乿偺偙偲偱丄乽憼墹尃尰乿偲乽懢惌埿摽揤恄乿偺宷偑傝偑棟夝偱偒傞傛偆側丅
(戝埿摽柧墹丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A8%81%E5%BE%B3%E6%98%8E%E7%8E%8B)
偱丄乽揤枮戝帺嵼揤恄乿偵偮偄偰丄乽揤岓傪巌傞棆恄偲偟偰偺揤恄偲丄悰岞偺屼楈丄嶦媿嵳恄偵偍偗傞娍恄丄枾嫵偺岇朄恄丄恄榖忋偺揤捗恄乮揤恄乯偑廗崌偟偰惉棫偟偨恄奿偲塢傢傟偰偄傑偡丅乿偲偁傝丄偦偺偆偪偺乽嶦媿嵳恄偵偍偗傞娍恄乿偺嵳傝偵傕恅巵偑娭學偟偰偄偦偆偱丅
(揤恄怣嬄丗http://d.hatena.ne.jp/nisinojinnjya/20060225)
(戝庰恄幮丗http://kamnavi.jp/yamasiro/oosake.htm)
乽懕擔杮婭乿偵丄埳惃丒旜挘丒嬤峕丒旤擹丒庒嫹丒墇慜丒婭埳側偳偵乽媿傪嶦偟偰娍恄傪釰傞偙偲傪嬛巭乿偟偰偄傞婰帠偑偁傞傛偆偱(p37)丄偦傟偵偮偄偰乽庒嫹抧曽偵偍偗傞崑懓偺拞偱栚棫偮偺偼恅巵偺宯摑偱偁傞丅庒嫹偺栘娙偵偼恅恖偺柤偑懡偔傒傜傟傞丅乿偲偺偙偲偐傜恅巵偺娭梌偑峫偊傜傟丄嬛巭偝傟偨崙偺宷偑傝偐傜丄乽奀恖懓乿乽敼恖乿偺娭梌傕偁偭偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞傢偗偱丅
(暉堜導偺怴梾恄幮乮3乯丗http://www.shiga-miidera.or.jp/serialization/shinra/119.htm)
(亀暉堜導巎亁捠巎曇丗http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T1/4-01-02-03-12.htm)
(扥屻偺揱愢係丗http://www.geocities.jp/k_saito_site/bunken4.html)
(暉堜導丒崄嶳恄幮丗http://www.genbu.net/data/wakasa/kayama_title.htm)
(攐桪偺恄乆偲傑偮傝丗http://www4.synapse.ne.jp/yatusiro/newpage4.html)
| 仠2011.01.21(Fri.) |
側乣傫偲側偔丄侾俉擔偺乽晜寠巐榊乿偑婥偵側偭偰偄偨偲偙傠偵丄侾俋擔偺乽愒塇乿偺嬤偔偱乽晜娫乿偲偄偆抧柤傪尒偰丄傕偆彮偟挷傋偰傒傛丄偲偄偆偙偲偐側丄偲丅
僂傿僉儁僨傿傾偵傛傞偲乽晜娫乿偺桼棃偼丄乽峳愳偵撍偒弌偨宍偑晜搰偵尒偊偨偙偲偐傜婲偒偨抧柤丅乿偲偺偙偲偱丄偳偙偩偭偨偐朰傟偨傫偩偗偳嵟嬤乽揝乿娭學偱専嶕偟偰偰丄屆戙偼棨懕偒偵側偭偰偍傜偢偵棧搰偩偭偨丄偲偄偆応強偑偁偭偨偺傪巚偄弌偟丄偨偟偐弌塤偐偳偙偐偱乽晜搰尰徾乿偲偄偆偺偑偁偭偨側偀丄偲丅
(晜娫丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E9%96%93)
(晜搰尰徾丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E5%B3%B6%E7%8F%BE%E8%B1%A1)
(晜搰丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E5%B3%B6_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF))
偱丄壗婥側偔僂傿僉儁僨傿傾偺乽晜搰乿 (孮攏導)傪尒偨傜乽悂妱偺戧乿偵儕儞僋偑偁傝丄幨恀傪尒偰偙偺戧傕晜搰偵尒偊偨偺偐傕丄偲丒丒丒丅
(悂妱偺戧丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%B9%E5%89%B2%E3%81%AE%E6%BB%9D)
偝傜偵媨忛偺乽晜搰恄幮乿傪尒偰丄屼嵳恄偑乽墱墫榁墺恄偲墱墫榁彈恄乿偺俀恄偲側偭偰偄偰丄偦傟側傜乽晇晈娾乿傕晜搰偺側偐偵擖傞偐傕偟傟側偄偟丄嵟婑墂偐傜揹幵偵忔偭偰偟偽傜偔偟偰尒偊傞屆暛傕晜搰偭傐偄姶偠偑偟偰丄暛媢偵恄幮偑偁傟偽乽晜搰恄幮乿偵側傞偐傕偟傟側偄側偲巚偄丄奺抧偺晜搰抧柤傗晜搰恄幮傪攓尒偟偨丅
(晜搰恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(愳墇巗丒晜搰堫壸恄幮丗http://www.koedo.biz/040shrine/ukishimajinjya.html)
(孎杮丒晜搰孎栰嵗恄幮丗http://www.kumashoko.or.jp/kashima/kankou01.htm)
(垽昋丒晜搰恄幮丗http://www.dokidoki.ne.jp/home2/ghh00713/ukisima.html)
(廐揷丒晜搰恄幮丗http://www.kensoudan.com/firu-naka-y/kariwano/ukisima.html)
(嶳宍丒戝徖晜搰堫壸恄幮丗http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/ukisima.htm)
(撨攅巗丒攇忋媨丗http://www.genbu.net/data/ryukyu/naminoue_title.htm)
(杗揷嬫丒嬿揷愳恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%85%E7%94%B0%E5%B7%9D%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(惣埳摛挰晜搰丒恄柧恄幮丗http://www.genbu.net/data/izu/sinmei2_title.htm)
(挿栰丒晜搰恄幮丗http://wiki.fdiary.net/psylab/?%C9%E2%C5%E7%BC%D2)
(敧旜巗丒廰愳恄幮(嫬撪幮丒晜搰恄幮)丗http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka-sibukawa.html)
(堬忛丒晜搰丗http://www.geocities.jp/hitoshtt/kantou/ibaraki/kasumigaura2.htm)
(愮梩丒晜搰丗http://www.town.kyonan.chiba.jp/kyonan/pages/gp/idx.jsp?page_id=200)
(嶳岥丒晜搰乮偆偐偟傑乯丗http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a123003/island/ukashima.html)
乽晜娫乿傗乽晜寠孲崅堜棦乿偼摨條偺抧宍偱丄乽晜寠巐榊乿傪徧偟偨偲偄偆偙偲偼丄偦偺抧偵偄偨巵懓偲宷偑傝偑偁偭偨偙偲傪帵偡傛偆偵巚傢傟丄専嶕偱乽晜寠巵偼媣暷偲摨懓偱偁傞偙偲偼娫堘偄側偔丒丒丒乿偲偁傝丄係擔偵宷偑傝偦偆偱丅
(抧柤偲桼棃丗http://kutani.web.fc2.com/ebara-rekishi/hajimari1.html)
偱丄忋婰偺惣埳摛挰偺乽恄柧恄幮乿偵丄乽晍搧庡庒嬍柦偺乽晍搧乿偼丄捔嵗抧偺乽晜搰乿偐傜庢傜傟偨偲巚傢傟丒丒丒乿偲偁傝丄乽傑偨丄堦愢偵偼丄乽晍搧庡乿傪乽僼僣僰僔乿偲夝庍偟宱捗庡恄傪嵳恄偲偡傞帒椏傕偁傞丅乿偲偝傟偰偍傝丄乽僼僣僰僔乿偵宷偑傞偺偱偁傟偽乽悾怐捗昉乿偵宷偑傞壜擻惈傕偁傝丄乽晜寠孲崅堜棦乿偼暔晹巵偺僥儕僩儕乕偱偁傞壜擻惈傕偁傝偦偆偱丅
偄偔偮偐偵嫟捠偟偰傒傜傟傞乽徖抧乿偺傛偆側応強偼丄侾俇擔偺乽崅巘彫憁乿傪巚偄弌偟丄偁傜偨傔偰乽彫摛戲乿傪専嶕偡傞偲丄偐偮偰乽埮偺擔杮巎乿偝傫偺宖帵斅偱偄傠偄傠嫵偊偰偔偩偝偭偨乽偐傢偐偮乿偝傫偺僒僀僩偵丄乽彫摛乮偁偢偒乯偲偼嵒嬥傪壛岺偟偰嶌傞乽摛嬥乿偺偙偲丒丒丒乿偲偁傝丄乽晜娫乿乽愒塇乿嬤曈偱偼乽揝乿偑嵦傟偨偺偐傕偟傟傑偣傫偹丅
(幚嵺偺峼嶳偵擖傞 俀 朙塰峼嶳丗http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/houeikouzan.html)
偦偆偄偊偽俀侽擭傎偳慜偵戝暘偵峴偭偨帪偺幵憢偐傜丄嶳偺拞暊偑孈嶍偝傟偰傐偭偐傝偲嬻偄偨寠偑晜偐傫偱偄傞傛偆偵尒偊偨偙偲偑偁偭偰丄偨傇傫崙搶敿搰偁偨傝偩偭偨偲巚偆傫偩偑丒丒丒丅
侾俋擔偵堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨乽嶋戝柧恄偲偦偙偱釰傜傟偰偄傞堫攚泺柦偲敀揺恄偼丄偡傋偰醰釋恄偲偄偆嫟捠揰傪帩偭偰偄傑偡丅乿偲彂偐傟偨PDF偵丄乽嶋戝柧恄丄堫攚泺柦丄敀揺恄傪嵳傞恄幮乿偺暘晍恾偑偁傝丄彂偐傟偰偄傞恄幮傪挷傋偰偄偙偆偲偟偨偗偳丄側偤偐墶摴偵偦傟偰偽偐傝偱丅(嬯徫)
恄撧旛偝傫偺宖帵斅偵丄尯徏巕偝傫偺僽儘僌偵乽僂僒僊乿偵場傫偩恄幮偵偮偄偰彂偐傟偰偄傞偲偁偭偨偺偱攓尒偟偨偲偙傠丄僐儊儞僩偺偍曉帠偵乽悰尨摴恀岞偲揺恄偵娭楢偑偁傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅乿偲偁傞偺傪尒偰丄摴恀偲慶恄傪廳偹偰釰偭偰傞偐傕丄偲巚偭偨偺偑丄忋婰偺PDF偺乽揤曚擔柦恄幮乿偵偮偄偰彂偐傟偰偄傞晹暘偱丄
(尯徏巕偝傫偺僽儘僌丗http://www.genbu.jp/201101/01-0047.php)
| 揤曚擔柦恄幮偵偼丄惣懁偺惃椡偺徾挜偱偁傞嶋偲丄搶偺惃椡偺徾挜偱偁傞攇僂僒僊偺挙崗偑尒傜傟傑偡丅揤擔捁柦恄幮偼揤曚擔柦恄幮偲恊巕偱偁傞偙偲偐傜丄摨條偺惈幙傪帩偮偲峫偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅壛偊偰丄揤擔捁柦偼堫攚泺柦偲摨偠惈奿傪傕偭偨恄偲偄偆偙偲丄偙偺恄幮偼偐偮偰揤嶋偺媨偲屇偽傟偰偄偨偲偄偆偙偲偐傜丄偙偺抧堟偱梈崌偑峴傢傟偨偲憐憸偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅 |
偲偝傟偰偄傞偙偲偱丄摴恀偼僇儌僼儔乕僕儏偱釰傜傟偨姶偠偑偟側偔傕側偄偑丅乽彮旻柤柦乿傕僇儌僼儔乕僕儏偟偨傝偝傟偨傝丄偲偄偆姶偠偑偁傝傑偡偹丄釰傜傟傞応強偵傛偭偰偼丅恅巵偺僥儕僩儕乕偺朙拞偺乽暈晹揤恄媨乿偱偼丄摴恀偲乽彮旻柤柦乿偑釰傜傟偰傑偡偹丅
(暈晹揤恄媨丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%8D%E9%83%A8%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%AE%AE)
乽揺乿偐傜専嶕偟偨傜傛偐偭偨傫偩側丒丒丒側偤墶摴偵偦傟傞偐丄偩偗偳丄嶨巌儢扟偺乽戝捁恄幮乿偺屼嵳恄乽嶋戝柧恄乿偵偮偄偰丄乽弌塤偺崙嶋懞嶋偵捔嵗偡傞丄僗僒僲僆僲儈僐僩偺墱偝傫偱偁傞丅乿偲彂偐傟偰偄偰丄偳偆偄偆偙偲偐傪専嶕偟偨傝丄乽崅椙壓媨幮乮媉墍偝傫乯偵偼丄嶋戝柧恄傪嵳傞幮偑偁傞丅乿偲彂偐傟偰偄偨偑丄懠偵偦偆彂偐傟偰偄傞偲偙傠偑尒偮偐傜偢丒丒丒丅
(戝捁恄幮丗http://www.5012.jp/onstage/disp.asp?kno=2&cno=1&dno=283)
(戝捁恄幮丗http://www.asahi-net.or.jp/~br3n-szk/newpage42.htm)
(嶩掹丗http://tobifudo.jp/butuzo/10rasetu/09.html)
(帥偲弾柉怣嬄丗http://snkcda.cool.ne.jp/miimachisi/2-5shominnsinko.html)
傑偨丄憡惗巗偺乽恵夑恄幮(戝旔恄幮丒崌釰)乿偵丄乽忋徏懞峳恄幮丄嶋枽戝旔柧恄偲婰偝傟傞丅乿偲偁傞偑丄偙偪傜傕専嶕偱懠偵偼弌偰偙偢丄嶉嬍偺乽嶋惒恄幮乿偺乽嶋憙戝柧恄乿傕摨條偩偟丄屼恄栦偵偮偄偰乽媏偵堦偼堦尵庡偲摨偠偩丅乿偲偁偭偰偪偲僷僯僢僋丒丒丒妧尨巗偵傕乽嶋惒恄幮乿偑偁傞傛偆偩偑丄2010.01.26暘偺乽嶋媨嶇慜恄幮乿摨條丄摗尨巵偵忔偭庢傜傟偨傛偆偱丅
(恵夑恄幮丗http://lec10.suppa.jp/oozake/11-20/11suga.html)
(嶋惒恄幮丗http://www.tesshow.jp/saitama/gyoda/shrine_tanada_sagi.html)
(嶋惒恄幮丗http://www.genbu.net/data/yamato/sagisu_title.htm)
(妧尨巗丒嶋惒恄幮丗http://kamnavi.jp/as/sagisu.htm)
(嶋媨嶇慜恄幮丗http://www.sakisaki.net/yuisho.html)
(嶇慜恄幮丗http://mononobe.nobody.jp/tabi/nukisaki/kkitinomiya.htm)
偲偄偆偙偲偱丄彮乆傔偘偰傑偡偑懕偒偼屻擔丒丒丒丅
偦偆偦偆丄乽嶋戝柧恄乿偱偺専嶕偱丄暉壀偺乽攇愜恄幮乿偺嫬撪幮偵乽嶋戝柧恄乿偑偁傞傛偆偩偑丄屼嵳恄偺侾拰偺乽悾怐捗昉乿偺昞婰偑乽悾愜捗昉乿乽悾怐捗戝恄乿偵側偭偰偄傞偲偙傠偑偁傝丄偁偪偙偪専嶕偟偰丒丒丒丅
(攇愜恄幮丗http://www.geocities.jp/turiten2010/jinja_db_tsuyazaki/109_namiori/index.html)
(攇愜恄幮丗http://nobyama.com/namiori.html)
(攇愜恄幮丗http://nonbiri.boo.jp/jinguukougou26.html)
(攇愜恄幮丗http://blog.goo.ne.jp/noyamany/e/b062ebcaefa43752b7f3533a16129a3a)
(攇愜恄幮丗http://blog.livedoor.jp/keitokuchin/archives/65445582.html)
(攇愜恄幮丗http://wadaphoto.jp/maturi/tuyazaki1.htm)
偪側傒偵丄乽捗壆嶈乿乽峴婎乿偱専嶕偟偨傜丄乽幧棙嶳彑曮帥乿偲偄偆峴婎奐婎偲偡傞偍帥偑偁偭偨傛偆偩偑丄攑帥偲側偭偰娤壒摪偺傒巆偭偰偄傞傛偆偱丄偦偺偍帥偲娭楢偑偁傞偲偝傟傞乽揤崀揤恄幮乿偑嫽枴怺偄丅
(捗壆嶈僙儞僎儞丗http://blog.goo.ne.jp/magpie03/c/344d36130c9731bbeee0c70856cdc90c)
(幧棙憼丗http://www.yado.co.jp/tiiki/munakan/syarikr/syarikr.htm)
(揤崀揤恄幮丗http://blog.livedoor.jp/keitokuchin/archives/65425198.html)
(揤崀恄幮丗http://kazenoyadori.seesaa.net/article/180495430.html)
(揤崀恄幮丗http://blogs.yahoo.co.jp/ruriironohahasama/17453639.html)
捛婰(2011.01.24)丗
乽敀揺恄乿偼傑偩専嶕偱偒偰側偄傫偩偗偳丄乽偆偝偓乿偼乽塅嵅乿偮傑傝恅巵棈傒偐偲悇應偟偰偍傝傑偟偰丄悾怐捗昉偵宷偑傞偺偱偼側偄偐丄偲丒丒丒丅
| 仠2011.01.22(Sat.) |
乽杮嫃愰挿乿偲偺榑憟丄抦傜側偐偭偨丒丒丒巹偺婰壇偺拞偵偼乽塉寧暔岅乿偺嶌幰偱偟偐側偔丄侾俆擔偺専嶕偱偼廐惉偺傾僫儕僗僩偼偟偰側偔偰丒丒丒傑偨偟偰傕柍抦偝丒媗傔偺娒偝傪業掓丅(嬯徫)
愰挿傕廐惉傕傛偔抦偭偰偄偨傫偱偡偹丄偦偟偰拞悽偺恖乆傕丒丒丒偼偄丄埮偺擔杮巎偝傫偑嶣塭偝傟偨偍幨恀傕偁傞偲偄偆嵵摗巵偺乽傾儅僥儔僗乿傪嶐擔攓尒偟傑偟偰丒丒丒傾儅僥儔僗偑乽嫊尵傪嬄傜傞傞恄乿偵偟偨偺偼晄斾摍偩偲夵傔偰巚偭偨丅
偄傗乣丄晽椩摪偝傫偺僽儘僌偵懕偄偰帺暘偺媗傔偺娒偝傪嵞妋擣偟偨傢偗偱丄暥專傪傕偭偲偟偭偐傝偲撉傫偱偄偐側偒傖偄偗側偄側丄偲丒丒丒丒偱傕丄尵偆偼堈偔丄峴側偆偼擄偟丄偱丒丒丒丅
嫽枴怺偄側偲巚偭偨偺偑丄乽媨庡旈帠岥揱乿偺婽杕偱梡偄傜傟傞偲偄偆乽娵挍抾乿乽彫挍抾乿偱丄敼恖偲偺宷偑傝傪昞偟偰偄傞傛偆側丅(p64)
偁偲丄2010.12.15暘偱偺乽恀彴暍逦乿偺娭楢偑婥偵側傞乽戝彟嵳乿偺乽旈媀乿(p74)丄俀侽擔偵弶傔偰抦偭偨乽杮挬悽婭乿偵彂偐傟偰偄傞偲偄偆乽嵵恏烠乿偵娭偡傞帠暱(p84)傕婥偵側傝丄偦偟偰乽塉寧暔岅乿摨條偵偡偭偐傝撪梕傪朰傟偰偄傞偺偱撉傒捈偝側偒傖偲巚偭偨偺偑丄乽棩椷崙壠偐傜墹挬崙壠傊偺悇堏偲偄偆楌巎乿(p97)偑奯娫尒傜傟傞偱偁傠偆乽峏媺擔婰乿偱丅(偁丄椉曽偲傕幚壠偵帩偭偰偭偨傫偩傢丅娋)
偝傜偵弶傔偰抦偭偨暥專偼悢懡偔丄乽拞奜彺乿偐傜偺婰帠偺偁偲偵乽偦傟偼撪帢強偺傾儅僥儔僗偑丄嬥怓偵婸偔暓幧棙偺傛偆側巔偵曄杄偟偨偙偲傪埫帵偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丅乿(p108)偲偝傟偰偄傞偙偲偵丄偍偋乣両偲丅
乽峳嵳媨乿偵娭偡傞偙偲偑彂偐傟偰偄傞乽懢恄媨彅嶨帠婰乿傗丄乽嵵恏烠乿偵娭偡傞乽恄妝乿偵偮偄偰偺婰嵹偑偁傞乽弔婰乿丄俀侽擔偺乽摴尗乿偺偙偲傕彂偐傟偰偄傞偲偄偆乽戝峕嫥朳乿偺乽杮挬恄愬揱乿丄偦偺懠乽愭戙媽帠杮婭戝惉宱乿丄乽屼捔嵗杮婭乿丄乽曮婎杮婰乿丄乽尦挿廋釶婰乿丄偦偟偰乽愰挿乿偲乽廐惉乿偺榑憟偑彂偐傟偰偄傞偲偄偆乽欒姞溲乿傗乽庰愜媨乿側偳傕婥偵側傞丒丒丒偲摨帪偵丄懡偡偓偰婥偑墦偔側傝偦偆丅(嬯徫)
(庰愜媨丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E6%8A%98%E5%AE%AE)
偱丄p156偵偁傞乽婾愶偝傟偨彂暔乿偺壖戸偝傟偨恖暔偵峴婎傕嫇偘偰偍傜傟丄2008.09.29暘偱偺乽戝榓妺忛曮嶳婰乿偑偦偺侾偮偩側偀丄偲丅
(戝榓妺忛曮嶳婰丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E8%91%9B%E5%9F%8E%E5%AE%9D%E5%B1%B1%E8%A8%98)
(戝榓妺忛曮嶳婰丗http://www.lares.dti.ne.jp/~hisadome/honji/files/KATSURAGI.html)
偦傟偲乽峴婎偺夛乿偱弶傔偰攓尒偟偨丄乽朄婲曥嶧乿乽惞晲揤峜乿乽惞摽懢巕乿乽栶彫妏乿乽寱偵棈傓棿乿乽峴婎乿偑昤偐傟偰偄傞乽朄婲曥嶧欀涠梾恾乿傕丄偱偡偹丅
(朄婲曥嶧欀涠梾恾丗http://www.city.sakai.lg.jp/kyoiku/_syougai/_kyouiku/bunyabetu.html)
偱傕丄棅挬傪捛偭偰偐傜乽棩椷崙壠偐傜墹挬崙壠傊偺悇堏乿偑傒傜傟傞拞悽偺曽偑丄峴婎偨偪偑揱偊偨偐偭偨偙偲傪彂偐傟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巚傢傟丄偦傟偼乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿偑旈偐偵揱偊偰偒偨恀幚偑傛偆傗偔柧傜偐偵偱偒傞傛偆偵側偭偨偐傜偱偼側偄偐偲丄乽釶偊偺恄偐傜幹懱偺恄傊乿(p180)偵彂偐傟偰偄偨乽悾怐捗昉乿偵偮偄偰彂偐傟偰偄傞乽榒昉柦悽婰乿傕丄2009.11.06暘埲棃撉傫偱偄側偄偺偱丄嵞搙偠偭偔傝偲撉傒捈偝偹偽偲巚偭偨師戞偱偡丅
恄撧旛偝傫偺僽儘僌偵丄戝嶃偺搚嵅杧俀挌栚偺弌塤偺徏峕岓偺壆晘偱丄乽醰釋恄偲偟偰柤崅偄妢堫壸偲嶋戝柧恄偑釰傜傟偰偄偨丅乿偙偲偑彂偐傟偰偄偰丄偦偺乽嶋戝柧恄乿偲乽嬥旟梾尃尰乿乽屲媿戝柧恄乿乽榓楈恄乿偼丄斔傪偁偘偰釰傜傟偰偄傞傛偆偱丄乽攡揷媿嬱偗忸乿偺乽婅妡偗偺懳徾乿偲偝傟偰偄偨偙偲偑丄堦嶐擔専嶕偟偰攓尒偟偨僒僀僩偵彂偐傟偰偄偨偺偑婥偵側偭偰偰丅
(乽攡揷媿嬱偗忸乿峫丗http://homepage3.nifty.com/osaka-web-museum/tano7-1.htm)
(嬤悽偺婅寽廳曮婰偺悽奅丗http://homepage3.nifty.com/osaka-web-museum/tano7-4.htm)
昹徏壧崙偺乽恄幮暓妕婅寽廳曮婰乿偵婰嵹偝傟偰偄傞媽楋偺屲寧屲擔偵峴傢傟傞乽醰釋彍偗乿偺峴帠傛偆偱丄拞悽偺乽嶦媿嵳恄偵偍偗傞娍恄乿偺怣嬄偑曄壔偟偮偮傕宲懕偝傟偰偄傞傛偆偵巚傢傟丄乽屲媿戝柧恄乿乽榓楈恄乿偵偮偄偰婥偵側偭偰傞偑専嶕偟懝偹偰偄偰丒丒丒悇應偩偗偳乽嬥旟梾尃尰乿偼傕偪傠傫宷偑傞偱偟傚偆丅
(昹徏壧崙丗http://kotobank.jp/word/%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E6%AD%8C%E5%9B%BD)
(柉娫堛椕怣嬄偺彫偝側椃丗http://mayanagi.hum.ibaraki.ac.jp/kjsmh/tayori3.htm)
偆乕傫丄乽屲媿戝柧恄乿偼側偄側偀丄塅榓搰偺乽榓楈恄乿偼2008.10.22暘偱偺乽榓楈恄幮偼乽埳払惌廆乿偺挿抝偺壠恇乽嶳壠惔暫塹乿偲娭學偑偁傞傛偆偱丄庡偵巐崙丒拞崙抧曽偵暘楈偝傟釰傜傟偰偄傞乿偲偄偆丄乽榓楈恄幮乿偺乽偆傢偠傑媿婼傑偮傝乿偺乽媿婼乿偺偙偲側偺偐丄乽嶳壠惔暫塹乿側偺偐丄偦傟傜偺塭偵塀偝傟偨暿偺恄側偺偐丒丒丒丅
(榓楈恄幮傪扵偣丗http://tack7.fc2web.com/Warei/wareiwanted.html)
| 仠2011.01.23(Sun.) |
堦嶐擔偺乽攇愜恄幮乿偺屼嵳恄偑廧媑戝恄丄悾怐捗昉恄丄巙夑戝恄丄悰尨摴恀丄曐怘恄偲偁傝丄乽拀慜殸銛晽搚婰晅榐乿偵偼乽嵳傞強廧媑戝恄丄巙夑柧恄丄婱慏恄側傝丅乿偲彂偐傟偰偄傞僒僀僩偑偁偭偰丄乽巙夑戝恄乿偼乽垻塤巵乿偩偭偨傛偆側偲専嶕偟偨傜丄廆憸巗忇嶈偺乽怐敠恄幮乿偑僸僢僩偟偰丅
(怐敠恄幮丗http://www.genbu.net/data/tikuzen/orihata_title.htm)
| 恄岟峜岪偺嶰娯惇敯偺嵺丄廆戝恇乮廆憸偺恄乯偑曺偘帩偭偨乽屼庤挿乿偵丄晲撪戝恇偑怐偭偨乽愒敀擇棳偺婙乿傪晅偗丄孯偺慜恮偱丄怳傝忋偘丄怳傝壓偘偟偰丄揋傪東楳偟偨丅嵟屻偵丄偦偺乽屼庤挿乿傪乽懅屼搱乿偵棫偰抲偄偨丅偙偺乽屼庤挿乿偑乽堎殸惇敯屼婙濿栫乿丅 堧婒偺揤庤挿恄幮偼丄偙偺乽屼庤挿乿偵桼棃偟丄摉幮偼丄乽愒敀擇棳偺婙乿傪釰傞幮偱偁傞丅幮揱偵傛傟偽丄氥婒恀崻巕恇偺巕懛偑偙傟傪釰傝揱偊偰偄傞丅 |
偲偺偙偲偱丄乽屼庤挿乿偼2002.02.05暘偱偺堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨暥傗丄愭擔偺愜岥巵偺乽暭懇偐傜婙偝偟暔傊乿偵偁傞傛偆偵丄乽埶戙乿偺傛偆偱乽悾怐捗昉乿偺傛偆偵巚傢傟丄拞嵗偵釰傜傟偰偄傞乽晲撪廻擧乿傕傑偨摨條偐偲丅
(怐敠恄幮丗http://blog.goo.ne.jp/yufunogi/e/ca31b48c09cea05ed82b9d323f0dc0bf)
偱丄偦偺乽怐敠恄幮乿偵偮偄偰偼2010.02.12暘偱傕乽捑忇揱愢乿偐傜専嶕偟偰偄偰丄偦偺帪偼攎徳偺乽寧偄偯偙忇偼捑傞偆傒偺偦偙乿偲惣峴偺壧偐傜丄愇愳導晉棃挰偱塺傫偩偲巚傢傟傞壧偵丄乽嬨廈偵栚傪岦偗傠乿偲偄偆攎徳偐傜偺儊僢僙乕僕偺傛偆偵巚偭偰偰丄嶐擔撏偄偨惣峴俵俴偵乽巙夑乿偺壧偑偁偭偰丄嵞搙挷傋偰傒傛偆偐側偲丅
俵俴偵傛傞偲丄乽偪傝偦傓傞壴偺弶愥傆傝偸傟偽傆傒暘偗傑偆偒巙夑偺嶳墇乿偼丄乽嫗搒偺杒敀壨偐傜嬤峕偺嶁杮偵敳偗傞墲娨摴乿偺偁偨傝傪塺傫偩壧偺傛偆偩偑丄乽傎偲偲偓偡側偒傢偨傞側傞攇偺忋偵偙傦偨偨傒偍偔巙夑偺塝晽乿偼夝愢偵偁傞乽斾塨嶳偐傜悂偒壓傠偡晽乿埲奜偵傕壗偐偁傝偦偆偱丅
偁偲丄乽怐敠恄幮乿偱乽愒敀擇棳偺婙乿傪乽氥婒恀崻巕恇乿偺巕懛偑釰傝揱偊傞偲偺偙偲偩偑丄乽擔杮彂婭乿偱乽晲撪廻擧乿偲偦偭偔傝偩偭偨偲偝傟傞乽氥婒恀崻巕恇乿偲偺榖偵傕丄壗偐僂儔偑偁傝偦偆偱丒丒丒偲丄傑偨偟偰傕杮戣偐傜墦偺偄偰偄偔偲偄偆丒丒丒丅
(怐敠恄幮丗http://lunabura.exblog.jp/i32/)
(堧婒丒恀崻巕偺懌愓丗http://homepage1.zashiki.com/HAKUSEN/ikimaneko/ikimaneko.htm)
偟偐傕丄崱擔偼帪娫偑側偄偺偱丄偄偮傕埲忋偵拞搑敿抂偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丄偡傒傑偣傫丒丒丒丅
忋婰暘傪彂偄偨偁偲丄梡帠傪嵪傑偣偰偐傜幚壠偵峴偒丄懱挷晄椙偱僟僂儞偟偰偨枀偵戙傢偭偰媊掜偑偍偡偦暘偗偲偟偰僉儍儀僣傪帩偭偰偒偰偔傟偨偺偱丄偪傚偙偭偲乽偛椉恊偼偢偭偲崣搰偵丠乿偲暦偄偰傒偨丅
偡傞偲乽偦偆傒偨偄丒丒丒壠宯恾偑偁傞偭偰彮偟尒偣偰傕傜偭偨偙偲偑偁傞傢丅乿偲偺偙偲偱丄戙乆偍傜傟偨傛偆側偺偱丄乽崣敼恖乿偺枛遽偺傛偆偱丄乽恊懓偱嶳偵抜乆敤傪嶌偭偰偨偙偲傕偁偭偰側丄崱偼傕偆嶨栘椦偵側偭偰傞偗偳丅乿偲偄偆偺偱丄乽傆偮偆偺愇傪愊傒廳偹偰嶌偭偰偼偭偨傫丠乿偰暦偔偲丄乽偦傗丅偆偭偲偙傜偼崅戜偵偁偭偰愇奯偑偁偭偰側丄偄偮傗偭偨偐棤偺愇奯偑曵傟偨偙偲偑偁偭偨傫傗偗偳丄奀傑偱峴偭偰愇傪廍偭偰偒偰側丄偦傟傪愊傒忋偘偰曗廋偟偨偙偲傕偁偭偨偱丅乿偲丄愹廈曎偱岅偭偰偔傟偨丅
乽偦傫側偵愊傒忋偘傞偙偲偑偱偒傞戝偒側愇偑昹偵偁傞傫丠乿偲暦偔偲丄乽攇偑峳偄偝偐偄丄嶍傟偰娵偅側偭偰偰側丄偦傟傪塣傇傫偑戝曄傗偟丅崱偼寉僩儔偔傜偄偼捠傟傞偹傫偗偳丄摉帪偼庤墴偟偺嶰椫偺偱塣傫偩傫傗偗丅乿偲偺偙偲偱丄愄側偑傜偺抦宐傪庴偗宲偄偱偍傜傟傞傛偆偩偭偨丅
偪側傒偵愇偵偮偄偰偺幙栤傪偟偰偨帪偵摢偵晜偐傋偰偨偺偼丄2010.12.11暘偱偺幨恀偺帬夑偺乽斞暉帥乿嬤曈偺抜乆敤傗丄係擔偺幨恀偺婱慏恄幮乽墱媨乿偺嫬撪偵偁傞乽慏宍愇乿偱丄娭楢偡傞巵懓偺帩偮媄弍偐偲丅
(崣搰偭偰偳傫側搰丠丗http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1186033725484/index.html)
(崣搰侾丗http://www.minc.ne.jp/~hotei/kamikosiki.html)

捛婰(2011.01.24)丗
乽崣乿偱専嶕偟偰傞偲丄惣媨偺乽墇栘娾恄幮乿偑僸僢僩偟丄偛恄懱偺乽崣娾乿偼彈惈恄偩偦偆偱丄乽崣娾悞宧夛乿偺偍嶥偵乽塽恄嵵乿偲彂偐傟偰偄偰丄乽娾幮乿偵乽崣娾恄釱丒尩搰恄幮偺屼暘楈傪偍釰傝偟偰偄傑偡丅乿偲偁傝丄乽榋峛嶳幮乿偵乽媏棟昉戝恄乿偑丄乽塉岊幮乿偵乽婱慏戝恄丒棿恄乿偑釰傜傟偰偍傝丄乽崣晄摦柧墹乿傕埨抲偝傟偰偄傞傛偆偱丄摉抧偱攎徳偑乽偝偞傟奍丂懌攪偄忋偑傞丂惔悈偐側乿傪塺傫偩偲偄偆偙偲偱丄乽屼恄悈強乿(屼嵳恄丗悝徾柶戝恄)偵壧旇偑偁傞偦偆偱丄乽戝嶈堫壸乮暁尒堫壸戝幮偺屼暘楈乯乿偼乽僞僰僉偑偍庣傝偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅乿偲偄偆偺傕婥偵側傞丅
(墇栘娾恄幮丗http://www.koshikiiwa-jinja.jp/index2.htm)
(崣娾悞宧夛丗http://www.koshikiiwa-jinja.jp/suukeikai.htm)
乽悾怐捗昉乿偑釰傜傟偰偄傞恄幮偺傛偆偵巚傢傟丄乽崣搰乿偺抧柤偺桼棃偼忋婰倀俼俴偵偁傞傛偆偵乽崣宍偺嫄娾(崣搰戝柧恄)乿側偺偱丄乽墇栘娾恄幮乿偺偛恄懱偲摨偠側偺偱偼側偄偐丄偲丅
攎徳偺乽偝偞傟奍丂懌攪偄忋偑傞丂惔悈偐側乿偺嬪旇偑丄挿栰丒杻愌懞偵偁傞偲偄偆偺傕嫽枴怺偄偟丄杻愌懞偺乽晲悈暘恄幮乿偵乽傪偽偡偰偼丂偙傟偐傜備偔偐丂偐傓偙偳傝乿偺攎徳偺嬪旇偑棫偰傜傟偰偄偨偲偄偆偺傕婥偵側傝傑偡偹丄惣峴偑塺傫偩乽汬幪乿偺壧偑惣峴俵俴俉侽崋偵彂偐傟偰偄偨偟丒丒丒丅
(偙偙偑偍傒偛偲両丗http://omigoto.vill.omi.nagano.jp/zenkojimiti/route02_00.html)
(偙偙偑偍傒偛偲両丗http://omigoto.vill.omi.nagano.jp/zenkojimiti/route02_01.html)
| 仠2011.01.25(Tue.) |
杮擔傕傑偨墶摴偵偦傟偰偽偐傝偱丒丒丒丅
愭擔攓尒偟偰偄偨乽嵦峼怑恖偵傛傞揱彸乮敀捁揱愢乯乿偺儁乕僕偵丄乽娾崙嬭壪楌巎暔岅乿偵乽敀嶋偼醰釋偺恄丅敀嶋偼楈椡偁傝丄怣怱偡傟偽傛偔醰釋傪帯偟偨乿偲彂偐傟偰偄偨偦偆偱丄偦傟傪堷梡偝偣偰偄偨偩偔慜偵乽嬥壆巕恄嵳暥乿偱墶摴偵偦傟偰丄偝傜偵乽嬥壆巕恄仌拞嶳恄偑媑旛偺恄廻偵尰傟傞乿偲彂偐傟偰偄偨偙偲偐傜丄乽拞嶳恄偵偙偺抧傪忳搉偟偨偲偝傟傞暔晹揱彸乿偑偁傞偙偲偑彂偐傟偰偄偨僒僀僩偵旘傃丄偦偙偐傜乽拞嶳懢恄媨乿偺偍嶥傪宖偘傞偲偄偆摗撪壠偑丄恄偵曭偭偨乽僠儅僉乿偼乽嵦屧乿偵傛傝摼傜傟偨乽崅巘彫憁乿偺傛偆側傕偺偐傜嶌傜傟偨偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲偱丄乽摗撪巵乿偺専嶕偵側傝丄僸僢僩偟偨僒僀僩偐傜乽媿婼乿偵宷偑偭偰丒丒丒丅
(嵦峼怑恖偵傛傞揱彸乮敀捁揱愢乯丗http://www.geocities.jp/astpa693/yamasi.html)
(嬥壆巕恄峫嶡峴媟丗http://kibi33.ddo.jp/kibi/index.php)
(摦梙偡傞拞嶳偺庡嵳恄丗http://www.tvt.ne.jp/~zhilaohu/nakayama/nakayama2saishin.htm)
(搰揱愢丗http://www.geocities.jp/ushimajp/simaden.htm)
壗偐偟傜偺堘榓姶偑偁偭偨傕偺偺丄偦傟偑壗偱偁傞偐偑偼偭偒傝偟側偄偺偱丄婑傝摴僐乕僗偩偗彂偄偰偍偔偙偲偵偟傑偟偨偑丄俀俀擔偺乽恄幮暓妕婅寽廳曮婰乿偵婰嵹偝傟偰偄傞媽楋偺屲寧屲擔偵峴傢傟傞乽醰釋彍偗乿偺峴帠偼丄乽摗撪偺慶偵恄偑帵尰偟偨偺偑宑塤嶰擭(706)丆暩屵偺擭偺屲寧忋弡乮擇偺屵偺擔乯偲偁傞丅乿偲偄偆偺偵宷偑傞傛偆偵巚傢傟丄慡偔偺柍娭學偵偼巚傢傟側偄偑丄偳偆傕攚屻偵摗尨巵偺忔偭庢傝偑尒偊傞傛偆偵姶偠傜傟傞傕偺偺丄偦傟傪徹柧偱偒傞傕偺傕側偔偰丒丒丒丅
攎徳偺壧偐傜乽拞嶳乿偑婥偵側偭偰偄傞偑丄乽曽曋偺恄乿偲偝傟偰偄傞僇儔僋儕偑傢偐傝偯傜偄傛偆側丒丒丒丅
(拞嶳恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
偱丄傛偆傗偔PDF偺乽攲闼偺傕偆堦偮偺敀揺恄榖乿偵偁傞乽僆僆傾僫儉僠偲堫攚泺柦偲嶋偲敀揺乿傪釰傞恄幮傪専嶕偟偨偑丄尰抧偺曽偵偟偐傢偐傜側偄忣曬偑偁傝丄崿棎偟偰偄傞偺偱丄偳偺傛偆偵彂偗偽偄偄偺偐側偀丄偲丒丒丒傑丄挷傋偨傑傑偵彂偙偆偲巚偆偗偳丄挿偔側傝偦偆側丒丒丒丅
専嶕偱傢偐傜側偐偭偨屼嵳恄偼丄乽攲闼偺傕偆堦偮偺敀揺恄榖乿偐傜堷梡偝偣偰偄偨偩偄偰惵帤偱彂偄偰偍傝傑偡丅傑偨丄乽攲闼偺傕偆堦偮偺敀揺恄榖乿偲摨偠屼嵳恄傕惵帤偵偟偰偍傝傑偡丅
乽壛栁恄幮乿丗捁庢導敧摢孲敧摢挰(媽孲壠挰)媨扟
屼嵳恄丗敀揺恄
(捁庢導娤岝楢柨丗http://www.tottori-guide.jp/188/513/7064.html)
乽敀揺恄幮乿丗捁庢導敧摢孲敧摢挰(媽孲壠挰)暉杮
屼嵳恄丗敀揺恄
(捁庢導娤岝楢柨丗http://www.tottori-guide.jp/188/513/7064.html)
乽搚巘昐堜恄幮乿乮傕偲敀揺恄幮丒尰嵼偼帨廧帥嫬撪幮乯丗捁庢導敧摢孲敧摢挰(媽孲壠挰)搚巘昐堜
屼嵳恄丗敀揺恄
(捁庢導娤岝楢柨丗http://www.tottori-guide.jp/188/513/7064.html)
乽戝峕恄幮乿(搚巘巵偺枛棳戝峕巵偵桼棃偡傞恄幮)丗捁庢導敧摢孲慏壀挰嫶杮734
屼嵳恄丗戝屓婱柦丄揤鈔擔柦丄嶰鈔捗昉柦丄(堫攚泺柦)
(http://kamnavi.jp/en/inaba.htm)
(http://www.genbu.net/data/inaba/ooe_title.htm)
乽敀揺恄幮乿丗捁庢導捁庢巗敀揺俇侽俁
屼嵳恄丗敀揺恄丄崌釰丗曐怘恄
(http://www.genbu.net/data/inaba/hakuto_title.htm)
乽拞嶳恄幮乿(僒僊偺媨丄攲闼偺敀揺敪徦偺抧丄戝怷戝柧恄丠)丗捁庢導惣攲孲戝嶳挰(媽拞嶳挰)懇愊
屼嵳恄丗敀揺恄丄堫攚泺柦丄嶋戝柧恄丄戝屓婱柦
(拞嶳挰丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E7%94%BA_(%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C))
(僒僊偺媨恄幮丗http://www.daisen.jp/p/2/area/umigawa/14/)
乽慜揷恄幮乿丗捁庢導惣攲孲柤榓挰戝帤屆屼摪378
屼嵳恄丗抰擔彈柦丄堫攚泺柦丄戝屓婱柦
(抰擔彈懜傪釰傞恄幮堦棗丗http://kamnavi.jp/ny/wakahirume.htm)
乽崙怣恄幮乿丗捁庢導惣攲孲戝嶳挰殸怣920-1
屼嵳恄丗梍揷暿柦丄懷挿懌昉柦丄揷怱昉柦丄熦捗醽昉柦丄巗媙搱昉柦丄晲撪廻擧柦丄抰嶻楈柦丄憅堫嵃柦丄曐怘柦丄堫攚泺柦丄慺岬柭柦
(http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/tottori/saihakugun/kuninobu/kuninobu.html)
乽壛栁恄幮乿丗捁庢導惣攲孲戝嶳挰強巕107斣
屼嵳恄丗帙乆媙柦丄暿棆柦丄恄擔杮斨梋旻柦丄嬍埶昉柦丄塋憪晿晄崌柦丄埳淨戻柦丄埳淨檉柦丄堫攚泺柦丄梍揷暿柦丄憅堫嵃柦丄戝擔傔婱柦丄戝嶳媉柦丄堫揷昉柦丄悈徾彈柦丄墡揷旻柦丄珥彈柦丄戝屓婱柦丄彮旻柤柦丄戝??柦丄悰尨摴恀丄屲廫栆柦
(崌釰傪彍偄偨屼嵳恄丗帙乆媙柦丄暿棆柦丄梍揷暿柦丄戝屓婱柦丄彮旻柤柦)
(http://1st.geocities.jp/huhito80/F-Jinja-houkiW-C-daisentyou.html)
乽擔媑恄幮乿乮揤擳嵅撧斎恄偺恄幮丠乯丗捁庢導暷巕巗梽峕挰惣尨俈俇俈
庡嵳恄丗戝屓婱柦丄彮柤旻柤柦丄墡揷旻柦丄揤擵嵅撧鷵恄乮偁傔偺偝側傔乯
崌釰丗慺岬柭懜丄寶屼柤曽柦丄晲酨捚柦丄抰嶻楈柦丄曐怘恄丄揤擔曽婏擔曽恄丄昰巕柦丄堫愐泺晹柦丄憅堫嵃柦丄堫揷昉柦丄抰擔彈柦丄揤徠戝屼恄
嫬撪恄幮乽揤恄恄幮乿乮嵳恄丗帙乆媙柦乯丄乽崙捗恄幮乿乮嵳恄丗慺岬柭懜乯
(http://1st.geocities.jp/huhito80/F-Jinja-yodoe-hiezu1.html)
乽彫栰恄幮乿丗捁庢導惣攲孲娸杮挰
(枛幮)屼嵳恄丗堫攚泺柦丄戝屓婱柦
(http://www.houki-town.jp/gappei/page-0-machi-1-1.htm)
徍榓30擭俁寧俁侾擔偵擔栰孲偺敧嫿懞丄惣攲孲偺戝敠懞丒敠嫿懞偺3偐懞偑崌暪偟偰尰嵼偺娸杮挰偑抋惗偟傑偟偨丅
(http://www.green21.com/kanko/tottori/saihaku.htm)
塀婒搰偵棳偝傟偨慶晝丒夤傪曠偭偰丄偙偺抧偵朘傟偨暯埨彈棳壧恖丒彫栰彫挰偺曟偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅
乽壛栁恄幮乿丗捁庢導惣攲孲惣攲挰乮戝崙懞乯
(嫬撪恄幮)屼嵳恄丗堫攚泺柦丄嶋戝柧恄丄戝屓婱柦
乽埦搰恄幮乿丗捁庢導暷巕巗旻柤挰1404
屼嵳恄丗彮旻柤柦丄戝屓婱柦丄恄岟峜岪
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%9F%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E7%B1%B3%E5%AD%90%E5%B8%82))
(http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/jinjya/awasima_a.html)
乽將揷恄幮乿丗捁庢導暷巕巗堿揷挰1440
屼嵳恄丗堫攚泺柦丄戝屓婱柦
(http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/tottori/yonagosi/inuta/inuta.html)
乽榓揷屼嶈恄幮乿丗捁庢導暷巕巗戝嶈1320斣
屼嵳恄丗慺岬柭懜丄戝屓婱柦丄堫揷昉柦丄堫攚泺柦
(http://houki.yonago-kodaisi.com/F-Jinja-yonagoG-kyuhinhantou.html)
屆榁偺揱傆傞強偵嫆傟偽擈巕巵偺巆搣埨揷媊掕偺堦懓棳楺偟偰崯抧偵棃傝擾偲側傞丅
幚偵崯奐戱偺慶偨傝偟偲嫟偵摉幮傕枖埨揷巵偺弌塤崙擔屼嶈恄幮偺屼暘楈傪姪惪憂棫偣偟傕偺側傝偲塢傊傝丅
乽恴朘恄幮乿乮屲愮愇懞乯丗捁庢導暷巕巗恴朘
屼嵳恄丗寬屼柤曽柦丄憅堫嵃柦丄堫攚泺柦丄揤徠戝擔傔柦丄慺岬柭懜
(http://houki.yonago-kodaisi.com/F-Jinja-yonagoD-hinogawa.html)
墲屆傛傝敧敠恄幮偺愛幮偵偟偰恴朘戝柧恄偲崋偣偟傪丄柧帯尦擭尰崱偺幮崋偵夵徧偣傜傞丅
憅堫嵃柦埲壓偺恄偼杮幮偺枛幮側傝偟傪柧帯尦擭崌嵳偡丅
乽恴朘恄幮乿丗捁庢導嫬峘巗
屼嵳恄丗堫攚泺柦丄戝屓婱柦
(嵅斻恄挰丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E6%96%90%E7%A5%9E%E7%94%BA)
乽彲恄幮乿丗捁庢導擔栰孲峚岥挰
屼嵳恄丗堫攚泺柦
乽嶳岥恄幮乿丗捁庢導擔栰孲峚岥挰戝帤嬥扟扟帤弌岥(尰嵼抧丗捁庢導惣攲孲攲闼挰嬥壆扟726斣)
屼嵳恄丗戝嶳媉柦丄堫攚泺柦
(http://homepage2.nifty.com/mino-sigaku/page772.html)
憂棫擭戙晄徻丄墲屆傛傝嶳恄偲崋偣偟傪柧帯尦擭恄幮夵惓偺嵺嶳岥幮偲夵傔傜傟丄摨屲擭懞幮偵楍偡丄摨幍擭嶳岥恄幮偲徧偡丅堫攚泺柦偼愛幮偲偟偰懞撪偵捔嵗偁傝偟傪柧帯尦擭崌嵳偣傜傞丅
乽孎栰恄幮乿丗捁庢導擔栰孲峕晎挰枔栰471斣
屼嵳恄丗堫攚泺柦
(http://1st.geocities.jp/huhito80/F-Jinja-kouhutyou.html)
乽峕旤恄幮乿(峕旜恄幮)丗捁庢導擔栰孲峕晎挰峕旜
屼嵳恄丗僯僊僴儎僸側偳丄堫攚泺柦丄戝屓婱柦
(http://1st.geocities.jp/huhito80/F-Jinja-kouhutyou.html)
幮揱偵傛傞偲丄揤楋擭娫乮嬨巐幍?嬨屲幍乯偵摉抧曽傪帯傔偨崑懓丒恑巵偑丄戝榓崙愇忋恄媨乮尰撧椙導揤棟巗乯偺暘楈傪丄揤偺斨慏偵柾偟偨恄梎偵埨抲偟偰姪惪慏恄幮偲徧偟偨偲偄偆丅偦偺屻丄塜屗朙憦帹柦傪崌釰偟丄墹巕尃尰偲恄幮柤傪夵傔偨丅柧帯榋擭乮1873乯偵峕旜恄幮偲夵徧偝傟丄戝惓廫堦擭乮1922乯偵嬤椬偺彫釱傪崌釰偟丄尰嵼抧偵堏偝傟丄幮柤傕峕旤恄幮偵夵傔偨丅
乽恄撧愳恄幮乿丗捁庢導擔栰孲峕晎挰晲屔925斣
屼嵳恄丗堫攚泺柦丄戝屓婱柦
(http://1st.geocities.jp/huhito80/F-Jinja-kouhutyou.html)
乽惞恄幮乿丗捁庢導擔栰孲擔栰挰崟斅1796斣
屼嵳恄丗崙嵃柦丄梍揷暿柦丄恄岟峜岪丄慺岬柭懜丄戝擔傔婱柦丄戝嶳媉柦丄墡揷旻柦丄帠戙庡柦丄鏴嬾撍抭柦丄巗媙搰昉柦丄堫攚泺柦丄戝擔傔柦丄宱捗庡柦
(http://1st.geocities.jp/huhito80/F-Jinja-hinotyou.html)
乽懡棦恄幮乿丗捁庢導擔栰孲擔撿挰怴壆俈侽斣
屼嵳恄丗憅堫嵃柦傎偐係俁拰
曐怘柦丄抰嶻楈柦丄悰尨摴恀丄戝嶳媉柦丄埳淨檉恄丄懍嬍抝柦丄帠夝抝柦丄堫攚泺柦丄墡揷旻柦丄昰巕柦丄媏棟昉柦丄戝屓婱柦丄揤曚擔柦丄揤捗帣壆崻柦丄抰擔彈柦丄嬥嶳旻柦丄榒晲柦丄梍揷暿柦丄垻嬾撍抭柦丄嫽搊嵃柦丄屲廫栆柦丄戝壆捗昉柦丄漇壆捗昉柦丄愹捗帠嵅壛抝柦丄戝擔傔柦丄戝擭柦丄崙忢棫柦丄崙嫹搚柦丄朙澪熧柦丄揇搚幭柦丄嵐搚幭柦丄戝屗摴柦丄戝撓曈柦丄柺懌柦丄湷崻柦丄埳淨戻柦丄揤徠戝恄丄擡曚帹柦丄帙帙媙懜丄旻壩乆弌尒柦丄塋憪晿晄崌柦丄揤抧壛棳旤摢昉柦丄鉙捗庡柦
(http://1st.geocities.jp/huhito80/F-Jinja-nitinantyou.html)
乽埳撧攚攇婒恄幮乿丗搰崻導弌塤巗(媽旚愳孲)戝幮挰嶋塝
屼嵳恄丗堫攚泺柦丄攝釰丗敀揺恄
(http://www.genbu.net/data/izumo/inasehagi_title.htm)
嵳恄偺鈐攚泺柦偼丄晲酨捚恄偲宱捗庡恄偑崙忳傝偺岎徛偺偨傔偵崀椪偟偨帪丄彅庤慏乮揤數慏乯偵偰丄戝崙庡恄偺巕丒帠戙庡恄傊偺巊偄傪偟偨恄丅傑偨丄揤徠戝恄偺巕丒揤曚擔柦偺屼巕恄偱丄傑偨偺柤傪揤埼捁柦偲偄偆丅
傑偢丄乽搚巘昐堜恄幮乿乽戝峕恄幮乿偵乽搚巘巵乿偑尒偊丄嵟屻偺搰崻偺乽埳撧攚攇婒恄幮乿偼俀侾擔偵堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨偲偙傠偵偁偭偨傛偆偵丄乽鈐攚泺柦乿偑乽揤埼捁柦乿偱偁傞傛偆側偺偱丄側傞傎偳丄偲丒丒丒摴恀偑墔楈偨傞強埲偼偙偙偵宷偑傞傛偆偱丅
乽彫栰恄幮乿嬤偔偱彫挰偺揱彸偑偁傞偁偨傝偼彫栰巵偑丄乽峕旤恄幮乿偱僯僊僴儎僸偑釰傜傟偰偄傞偁偨傝偼暔晹巵偑丄偦傟偧傟僥儕僩儕乕偵偟偰偄偨偙偲傪昞偟偰偄傞偲巚傢傟丄慡懱揑偵乽屆戙偐傜偺僱僢僩儚乕僋乿乽峴婎僾儘僕僃僋僩乿偺巵懓偑懙偭偰偄傞傛偆側姶偠偱丅
俀侾擔偵乽攲闼偺傕偆堦偮偺敀揺恄榖乿偐傜堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨乽偙偺抧堟偱梈崌偑峴傢傟偨偲憐憸偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅乿偺捠傝偱丄弶傔偵墶摴偵偦傟偨媑旛偺拞嶳偱偺乽拞嶳恄乿偼丄尦偼捁庢偺乽拞嶳恄幮乿偲摨偠屼嵳恄偑釰傜傟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟丄姪惪偝傟偨崰偵壗偐偑偁偭偨偺偱偼丅
巹偺憐憸偱偼晄斾摍偺忔偭庢傝岺嶌偑偁偭偨偺偱偼側偄偐偲巚偆偑丄偦傟傪撉傒庢傟傞帒椏偼傑偩尒偮偗傜傟側偔偰丒丒丒傑丄乽導將帞旤愮戙乿傪嵢偲偟偨偙偲偵傛偭偰丄摗尨巵偑媖巵堦栧偺巵恄乽攡媨戝幮乿偵忔傝崬傫偱偄傞偺偱丄彅孼偺枛遽偵偁偨傞偲偄偆乽摗撪巵乿偑婥偵側傝傑偡偹丅
(攡媨戝幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E5%AE%AE%E5%A4%A7%E7%A4%BE)
(乽傗側偄乿巵偺儖乕僣丗http://www.ne.jp/asahi/yanai/roots/body02.html)
偁丄愭擔偺専嶕偱尒偮偗偨丄崅抦導屷愳孲偄偺挰偺乽揤愇栧暿埨殸嬍庡揤恄幮乿偺嫬撪幮偵偁傞偲偄偆乽恄曣恄幮丒敀揺恄幮乿偑婥偵側偭偰傞偗偳丄傛偔傢偐傜側偔偰丒丒丒丅
(揤愇栧暿埨殸嬍庡揤恄幮丗http://www.genbu.net/data/tosa/iwatowake_title.htm)
乽楈柌乿偵傛傝涇偺忋偱乽搹嶥乿傪敪尒偟偨偲偄偆嶰恖偺恄庡偑丄乽擔壓巵乿乽幁晘巵乿乽彑夑悾巵乿偲偁傝丄乽幁晘巵乿偵偮偄偰偼傢偐傜側偄偑丄乽堃廆惄乿偺乽彑夑悾巵乿偼乽恅巵偺巕懛乿偲偺偙偲偱丄乽擔壓巵乿乽彑夑悾巵乿偼乽峴婎僾儘僕僃僋僩乿偺巵懓偐偲巚傢傟傞偑丄杮棃偺屼嵳恄偼塀偝傟偰偄傞傛偆偱丒丒丒丅
(堃廆巵丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%9F%E5%AE%97%E6%B0%8F)
偁偲丄恄撧旛偝傫偺乽幨恀宖帵斅乿偵丄孮攏導偺乽敀揺傪釰傞恄幮乿偑Up偝傟偰偄偰丄忋婰偺乽攲闼偺傕偆堦偮偺敀揺恄榖乿偵偁傞乽僆僆傾僫儉僠偲堫攚泺柦偲嶋偲敀揺乿傪釰傞恄幮偵宷偑傝偦偆丄偲偄偆偐丄曭嵵巵懓偺堏摦偑尒傜傟傞傛偆偱婥偵側傝傑偡偹丅
(幨恀宖帵斅丗http://6314.teacup.com/kamnavi/bbs/)
晽椩摪偝傫偺僽儘僌偑峏怴偝傟偰偄偰丄乽岦塤帥乿偺乽廫榋墹巕乿偵偮偄偰彂偐傟偰偍傝丄傆偲丄峴婎傪乽悈娫帥乿偺抧傊偲摫偄偨偲偝傟傞乽曎嵥揤廫榋摱巕乿傪巚偄弌偟丄2010.02.07暘偱偼乽搾旜摶乿偺乽摋釋偺恄條乿偐傜乽廫榋摱巕乿偵宷偑偭偨側偀丄偲丅
(曎嵥揤廫榋摱巕丗http://www.telemesse.ne.jp/daikakuji/00.html)
乽廫榋摱巕乿偼杮抧偑乽曥嶧乿側偺偱丄乽廫榋墹巕乿偲偺娭楢偼傛偔傢偐傜側偄偗偳丄壗偲側偔婥偵側偭偰丒丒丒丅
巐崙敧廫敧儢強楈応戞屲廫屲斣偺乽撿岝朧乿傕屼杮懜偑乽戝捠抭彑擛棃乿偱丄乽峲奀偺恄丄憤捔庣丒埳梊堦偺媨偺戝嶳媉恄幮偲怺偔偐偐傢傞楌巎傪桳偡傞丅乿偲偁傝丄
| 墢婲偵傛傞偲丄戝曮俁擭丄埳梊悈孯偺慶偲偄傢傟偨崙庡丒墇抭嬍悷岞偑丄暥晲揤峜乮嵼埵697乣707乯偺捄傪偆偗偰戝嶳愊柧恄傪戝嶰搰偵姪惪偟丄戝嶳媉恄幮傪寶偰偨嵺偵丄朄妝強偲偟偰俀係朧偺暿摉帥傪寶棫偟偨偙偲偑憂巒偲偄傢傟傞丅偙傟傜偺暿摉帥偼梻乆擭丄奀傪搉偭偰偺嶲攓偑晄曋側偙偲偐傜尰嵼偺崱帯巗偵堏偝傟偰偄傞偑丄榓摵尦擭乮708乯偵峴婎曥嶧偑俀係朧偺偆偪俉朧傪乽擔杮憤捔庣嶰搰偺屼慜乿偲徧偟偰曭嵳偟偨丅偝傜偵丄峅朄戝巘偑偙偺暿摉帥偱朄妝傪偁偘偰廋朄偝傟丄楈応偵掕傔傜傟偨丅 (http://www.88shikokuhenro.jp/ehime/55nankobo/) |
偲丄峴婎棈傒偱傕偁傞偍帥側偺偱丄宷偑傝傪姶偠傜傟傞傢偗偱丅
偁丒丒丒乽墇抭嬍悷乿乽朄妝強乿偱専嶕偟偰偨傜丄乽嬍悷偼丄柌偺拞偱嶳栰偺恄偐傜乽帺暘偺崤懏偱偁傝丄巊偄偱偁傞敀嶋偑旘傃棫偭偰宔偭偨偲偙傠偵丄昁偢怴偟偄壏愹偑偁傞乿偲偺恄堄傪庼偐傝丄偦偺抧傪扵偟偰丄崱偺摴屻壏愹傪敪尒偟偨偲偝傟偰偄傞丅乿偲偁傝丄乽嶋戝柧恄乿偼傗偼傝乽悾怐捗昉乿偐偲丅
(屆戙乽埳槵偺搾乿偲搾擵扟丗http://homepage1.nifty.com/kisetunokaze/s_history/s_history10.html)
乽暿媨戝嶳媉恄幮乿偵偮偄偰丄
| 埳梊崙堦媨偺戝嶳媉恄幮偺暿媨偲偟偰憂寶偝傟偨傕偺偱丄戝嶳愊戝恄傪釰傞丅椬愙偡傞巐崙敧廫敧売強俆俆斣嶥強丒撿岝朧偲偼丄偐偮偰偼堦懱偺傕偺偱偁偭偨丅 |
偲偺偙偲偱丄惓帯擭娫偐傜乽嶲攓晄曋乿側偺傪棟桼偲偟偰嶥強偑堏偭偨傛偆偩偑丄偙偪傜傪杮棃偺乽嶰搱棿恄乿偲偟偰偄偨偺偐傕丒丒丒丅
(暿媨戝嶳媉恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/ehime/imabari/betsumiya_ooyama/ooyamazumi.html)
(暿媨戝嶳媉恄幮丗http://www.geocities.jp/je5fbd/jinja02_1imabari.htm)
(暿媨戝嶳媉恄幮丗http://goshuin.ko-kon.net/shokoku_jinja/38_bekku-ooyamadumi_imabari.html)
| 仠2011.01.27(Thu.) |
偄傗乣丄傃偭偔傝偟傑偟偨傛丄嶐擔偼侾擔偐偗偰乽拞尨拞栫偲僟僟僀僘儉丄嫗搒帪戙乿偝傫偺僒僀僩傪攓尒偟偰偄偰丄傑偩敿暘傎偳偟偐撉傒廔偊偰側偄偗偳丄乽夑栁扵媶乿偝傫偺僒僀僩傪攓尒偟偰偐傜堦憌婥偵側偭偰偄偨乽嶰搰乿偐傜丄偐偮偰廧傫偱偄偨暯栰嬫偺乽婌楢乿傊丒丒丒丅
(拞尨拞栫偲僟僟僀僘儉丄嫗搒帪戙丗http://www.ten-f.com/index.html)
乽戝嶳愊柦乿乽帠戙庡柦乿傪釰傞乽嶰搰姏恄幮乿偵丄埳梊丒埳摛側偳偱乽戝嶳愊柦乿傪釰傞偒偭偐偗偑偁偭偨傛偆偵巚傢傟丄偦傟偑姍懌偺杮嫆抧偲偝傟偨乽嶰搰乿偲宷偑傞偺偱偼側偄偐偲専嶕偟偰偄偰丄姍懌偑側偤偦偺抧傪摼傞偙偲偑偱偒偨偺偐偵僂儔偑偁傞傛偆偵巚偭偨偺偩偑丄乽拞尨拞栫偲僟僟僀僘儉丄嫗搒帪戙乿偝傫偺僒僀僩偵傛傞偲丄乽慼変巵乿偑娭傢偭偰偄傞傛偆側丅
(嶰搰偺撲丄慼変巵偲宲懱揤峜斳丗http://www.ten-f.com/sogashi-to-keitai.htm)
乽慼変憅嶳揷愇愳杻楥乿偺孼掜偱晄斾摍偺鋘偺乽楢巕乿偑棈傫偱偄傞傛偆偱丄乽楢巕偺懛偵摉偨傞乽愇懌乿偐傜俁戙偵傢偨偭偰乽擭懌乿乽柤懌乿偲乽懌乿偺堦暥帤偑堷偒宲偑傟偰偄傞偺傕晄巚媍乿偲偝傟偰偍傝丄傑偨丄乽宲懱揤峜乿偺巕偺柤偑乽擔杮彂婭乿偵乽岡戝孼峜巕乿(埨娬揤峜)偲乽瀢嬿崅揷峜巕乿(愰壔揤峜)偲偁傝丄乽岡乿乽瀢嬿乿偑乽乽偁偺乿姍懌偺惗抧丒崅巗孲撪偵偁傞抧柤偱偁傞偙偲偼堦憌嫽枴傪偦偦傞晞崌乿偲偝傟偰偄傞偙偲側偳丄嬄傞捠傝偲巚偆丄偲偄偆偐丄偱偒偡偓偰偄傞側偲巚偊傞傎偳偱丅
(慼変楢巕丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%87%E6%88%91%E9%80%A3%E5%AD%90)
(愇愳愇懌丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9F%B3%E8%B6%B3)
(埨娬揤峜丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%96%91%E5%A4%A9%E7%9A%87)
(愰壔揤峜丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A3%E5%8C%96%E5%A4%A9%E7%9A%87)
乽姍懌乿偼乽姍巕乿偲柤忔偭偰偨帪婜傕偁傝丄乽僂傿僉儁僨傿傾乿偱乽嬙柧揤峜挬偱暔晹旜梎偲嫟偵攔暓傪偍偙側偭偨拞恇姍巕偲偼暿恖乿偲彂偐傟偰偄傞偑丄摉帪偼乽暿恖乿偱偁傞偙偲偑傛偔傢偐傜側偐偭偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞偙偲傗丄乽岡乿乽瀢嬿乿偺鎭偑乽擔杮彂婭乿偺傒偵偁傞偲偄偆偁偨傝偵丄晄斾摍偺栚榑尒偑昞傟偰偄傞傛偆偵巚偊丄乽慼変楢巕乿偵偮偄偰偺乽亀擔杮彂婭亁乽揤抭揤峜婭乿3擭5寧忦偵巰朣婰帠偑尒傜傟傞偺偑摨帪戙巎椏偵尒偊傞楢巕偺嵟弶偱嵟屻偺婰弎偱偁傞丅乿偲偄偆偺傕婥偵側傝傑偡偹丅
(拞恇姍巕丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%87%A3%E9%8E%8C%E5%AD%90)
乽慼変楢巕乿偲乽嶰搰乿偺宷偑傝偼傛偔傢偐傜側偄偑丄慭懛偺乽擭懌乿偺曟帍偑乽愛捗崙搱忋孲敀敮嫿乿(尰嵼偺崅捨巗恀忋挰)偱尒偮偐偭偰偍傝丄搱忋孲偺幃撪幮偲偟偰恅巵宯偺乽恄暈恄幮乿丄暔晹巵宯偺乽垻媣搧恄幮乿丄搚巘巵宯偺乽栰恎恄幮乿丄拞恇巵偺堦巟懓丠(拞恇巵偑懡巵傪忔偭庢偭偨丠)偺乽懢揷恄幮乿偲丄乽乽愛捗崙搱壓孲偺嶰搰姏恄幮乿偲婰偝傟偰偄傞偺偼搱忋孲偵埵抲偟偨嶰搰峕偺乽嶰搰姏恄幮乿偱偼側偔摉幮偺乽姏恄幮乿側偺偱偡丅乿偲偄偆姏巵偺乽姏恄幮乿側偳偑偁傝丄乽峴婎僾儘僕僃僋僩乿偺娭楢巵懓偺僥儕僩儕乕偵拞恇巵(摗尨巵)偑忔偭庢傝偺懌愓傪巆偟偰偄傞偺偑尒偊傞傛偆偱丅
(愇愳擭懌偺曟丗http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi/daiou/17.html)
(恄暈恄幮丗http://kamnavi.jp/en/settu/sinpuku.htm)
(垻媣搧恄幮丗http://kamnavi.jp/en/settu/akuto.htm)
(栰恎恄幮丗http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/hokusetu-nomi.html)
(懢揷恄幮丗http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/hokusetu-oota.html)
(姏恄幮丗http://kamojinja.web.fc2.com/kamojinja03.html)
忋婰倀俼俴偺乽嶰搰偺撲丄慼変巵偲宲懱揤峜斳乿偵丄宲懱揤峜偼恅巵摍偺巟墖偵傛偭偰慗搒偝傟偨偺偱偼側偄偐偲偝傟偰偄傞偙偲傗丄乽壨撪乮偺搉棃宯巵懓乯偲偺娭學傕擹枾偱偁偭偨偙偲傪塎傢偣傑偡乿偲彂偐傟偰偄傞偙偲偐傜乽婌楢乿偵宷偑偭偰偄偔傢偗偩偑丄乽懅挿巵偲乽壨撪乿偲宲懱掗偺偊偵偟乿偵偼丄妧尨偺乽廆変搒斾屆恄幮乿偺乽桼弿棯婰乿偵丄乽岶尦揤峜偺屼巕旻懢擡怣柦偺懛偵偁偨傞抾撪廻擧偺戞嶰巕愇愳廻擧偑慼変偺戝壠傪帓偭偰戝嶃壨撪偐傜堏傝廧傒丄惄傪慼変偲夵傔偨乿偲偁傞偦偆偱丄偐偮偰偼乽壨撪崙乿偩偭偨暯栰嬫乽婌楢乿偺乽弢尨恄幮乿偵偼丄乽晲屼棆抝偺巕懛偑崙偺柤傪乽戝乆瀈崙乿丄嫿偺柤傪乽戝乆瀈嫿乿偲柤偯偗偨偑丄恄晲掗偐傜戝乆瀈偺惄傪帓偭偨丅乿偙偲側偳偑彂偐傟偨乽壠婰乿偑偁傞傛偆偱丅
(懅挿巵偲乽壨撪乿偲宲懱掗偺偊偵偟丗http://www.ten-f.com/okinaga-to-keitai.htm)
(壨撪偺懅挿巵偲乽宲懱掗偺寣柆乿傪扵傞丗http://www.ten-f.com/kawachi-to-okinaga.htm)
(弢尨恄幮丗http://kamnavi.jp/ym/hiboko/tatehara.htm)

| 恄幮偺楌巎偼偒傢傔偰屆偔丄悞恄揤峜偺崰弶傔偰釰傜傟偨偲偄傢傟傞墑婌幃撪偺屆幮偱偁傝丄嵳恄偼僞働儈僇僤僠僲僆僆僇儈偲戝崙庡戝恄偱偁傞丅傑偨丄恄晲揤峜偑崙撪暯掕偵梡偄偨廫埇偺寱傪釰偭偨偲幮揱偵偁傞丅傕偲帤弢尨(尰嵼偺婌楢惣1)偵偁偭偨偑丄暫壩偵偁偄丄尰嵼偺抧偵堏偭偨丅 (暯栰嬫偆偋乣偔傜傝乣 僗僞儞僾挔傛傝) |

擛婅帥
| 悞弒揤峜尦擭(588)丄惞摽懢巕偺憂寶偲偟偰丄傕偲婌楢帥偲偄傢傟偨丅垻栱懮帥丒栱栌帥側偳丄巐曽偵憫尩側彅摪偑寶偰傜傟偨戝壘棔偱偁偭偨偑偦偺屻丄峅朄戝巘偵傛傝嵞寶丄擛婅帥偲夵傔傜傟偨丅杮懜惞娤悽壒曥嶧偼暯埨帪戙偺嶌偱丄戝嶃晎桳宍暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傞丅 (暯栰嬫偆偋乣偔傜傝乣 僗僞儞僾挔傛傝) |
偐偮偰抧壓揝扟挰慄乽挿媑弌屗乿傪嵟婑墂偲偡傞応強偵廧傫偱偄偰丄墂慜偺僗乕僷乕偑堚愓偺偁偭偨応強偩偭偨偙偲側偳丄堚愓偺懡偄抧偱偁傝丄侾偮戝嶃傛傝偺乽婌楢塟攋乿墂偺乽婌楢乿偼乽婈恖嫿乿偑鎍偭偨傕偺偲偝傟偰偄偰丄乽塟攋乿偺桼棃偼摴徍傗嬻奀偵傑偮傢傞揱彸偑偁偭偨傝丄乽塟乿偺嶻抧偩偭偨偙偲偵傛傞傕偺側偳偲偝傟偰偄偰丄乽婌楢塟攋乿墂偲偼媡偺椬偺乽挿尨乿墂嬤偔偱傕乽挿尨堚愓乿偑偁偭偨傝丄抧柤偺桼棃偲側偭偨乽挿峕廝捗旻柦(妺忛廝捗旻柦)乿傪釰傞乽巙婭挿媑恄幮乿偑偁偭偰丅
(挿尨堚愓丗http://inoues.net/ruins2/nagaharaiseki.html)
乽挿尨墂乿偺師偑廔揰偺乽敧旜撿乿墂偱丄嬤偔偺乽敧旜撿堚愓乿偐傜偼乽攔悈梡乿偺峚傪敽偭偨廧嫃愓傗旙丄乽棿乿傪昤偄偨奊夋搚婍側偳偑弌搚偟偰偍傝丄恅巵偺僥儕僩儕乕偩偭偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟丄乽敧旜乿偼暔晹巵偺僥儕僩儕乕偲偟偰傕抦傜傟偰偄傞応強偐偲丅
榖偑彮偟偦傟傑偟偨偑丄壨撪乽懅挿巵乿偺寣嬝偑乽宲懱揤峜乿偵丄偦偟偰乽旜挘巵乿偺寣嬝偑乽埨娬揤峜乿偵堷偒宲偑傟丄備偊偵2008.04.04暘偱偺乽崟昉嶳屆暛乿嬤偔偺乽淎殸恄幮乿偺傛偆偵乽憼墹尃尰乿偲摨堦帇偝傟丄2009.05.06暘偺乽彫悰嶳敧強尃尰乿偺乽嬥曱尃尰乿側偳丄乽悾怐捗昉乿偲廗崌偝傟傞偙偲偵側傞傛偆偱丅
乽拞尨拞栫偲僟僟僀僘儉丄嫗搒帪戙乿偝傫偺愢偱偼丄乽杮挬峜堺徯塣榐乿偱乽埨娬揤峜乿偺巕偲偝傟傞乽朙旻墹乿偑乽慼変堫栚乿偱偼側偄偐偲偝傟偰偄偰丄恅巵備偐傝偺乽戝鐒恄幮乿偵乽朙旻墹乿偲乽庣壆乿偑釰傜傟偰偄傞偲丄乽恄幮鍵榐乿側偳偵偁傞偦偆偱丅
(愰壔掗偺弌帺偲乽堫乿偵偮偄偰峫偊傞丗http://www.ten-f.com/senkatei-to-ine.html)
(彫愢丄慼変堫栚偑惓懱傪尒偣偨両丗http://www.ten-f.com/iname-no-syotai.htm)
(戝庰恄幮丗http://www.genbu.net/data/yamasiro/oosake_title.htm)
(淎殸恄幮丗http://www33.ocn.ne.jp/~hagizin/hirokuni/zaou.html)
2007.05.26暘側偳偱彂偄偨傛偆偵丄乽堿梲偺悽奅乿偲偄偆嶨帍偵傛傞偲晳掃巗偺乽梇搱乿偵釰傜傟傞乽榁恖搱柧恄乿偵偼偄傠傫側柤傪帩偭偰偄傞偲彂偐傟偰偄偰丄乽堦愢偵乽儂傾僇儕乿偲宲懱揤峜斳乽栚巕榊彈乿乿偲偝傟偰偄偨偙偲偐傜丄乽儂傾僇儕乿偲乽宲懱揤峜乿偺宷偑傝偲偲傕偵丄宲懱揤峜斳乽栚巕榊彈乿偲乽埨娬揤峜乿乽憼墹尃尰乿乽悾怐捗昉乿偺寣嬝偑宷偑傞偙偲傪昞偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞傢偗偱丅
乽朙旻墹乿偱専嶕偡傞偲乽嫄惃巵乿偑僸僢僩偟丄乽杮挬峜堺徯塣榐乿偵傛傞偲乽朙旻墹乿偺曣偼丄乽宲懱揤峜乿傪梚棫偟偨傂偲傝偲偝傟傞乽嫋惃抝恖乿偺柡乽崄乆桳昋乿偱丄摨偠偔埨娬揤峜偺斳乽幯庤昋乿偺枀偲側偭偰偄傞傛偆偩偑丄乽嫋惃抝恖乿偺懚嵼偑媈栤帇偡傞愢偑偁傞偲偐丒丒丒偨偩丄嫄惃巵傕峴婎傜偲偺宷偑傝偑偁傝丄嶄偵傕抾撪奨摴増偄偵僥儕僩儕乕偲巚傢傟傞乽嬥壀恄幮乿偑偁偭偰丄乽杮挬峜堺徯塣榐乿偑婥偵側傝傑偡偹丅
(嫄惃巵峫丗http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-37.html)
(嫄惃巵丗http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/01/012/01227.htm)
(嬥壀恄幮丗http://www.geocities.jp/engishiki01/settu/bun/st060107-01.html)
嶄巗撪偱傕乽拞恇巵乿(摗尨巵)偺忔偭庢傝傜偟偒懌愓偑丒丒丒丅
(彑庤恄幮丗http://www.geocities.jp/engisiki/settu/bun/st060107-02.html)
(恵柎抧慮崻恄幮丗http://kamnavi.jp/mn/osaka/sumutisone.htm)
(業揤恄幮丗http://fishaqua.gozaru.jp/osaka_tuyutenjin.htm)
乽擻場乿偺壧偵乽悾怐捗昉乿偑尒偊偰丄乽惣峴乿傗乽攎徳乿偨偪傕傑偨摨偠傛偆側巚偄偱塺傫偩偺偱偼丒丒丒偁丄擻場偼乽栰揷偺嬍愳乿偱傕塺傫偱偄傞偲偄偆偙偲偼丄乽嬍愳乿偵壗偐偁傞丠乽堜庤偺嬍愳乿偱偼摗尨弐惉偑乽嶳悂乿偲偲傕偵塺傫偱偄偰丅
(埳惃昉偲擻場朄巘丗http://www.city.takatsuki.osaka.jp/new/syoko/html/travel0007.html)
(偙偲偽偺婫愡丗http://www.ris.ac.jp/kokubun/kotoba/naka2.html)
(懡媑偺扠擔婰丗http://takiti.cocolog-nifty.com/tanuki/2006/10/post_2f1e.html)
(擔杮榋嬍愳丗http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/tama/know/property/12.htm)
(懡夑忛帒椏幨恀偲夝愢丗http://www.bashouan.com/piPhoto5.htm)
(堜庤偺嬍愳丗http://minami-lo.jp/member/sugiyama_6.html)
乽嬍愳乿偺桼棃偵偮偄偰丄忋婰倀俼俴偱乽嬍乿偺嶻抧偩偐傜偲偝傟偰偄傞応強傕偁偭偨偗偳丄乽嶳悂乿偐傜乽揝乿傪楢憐偟丄俀侾擔偵堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨乽彫摛乿偲屇偽傟傞乽嵒嬥傪壛岺偟偰嶌傞乿偲偄偆乽摛嬥乿傕乽嬍乿側偺偱偼側偄偐偲巚偭偨傝偟偰丄宷偑傝偑偁傝偦偆側姶偠偑丒丒丒丅
忋婰暘傪揮憲屻傕乽拞尨拞栫偲僟僟僀僘儉丄嫗搒帪戙乿偝傫偺僒僀僩傪攓尒偟偰偄傞偲丄崅捨偺乽妢怷恄幮乿偐傜戜搶嬫扟拞偵姪惪偝傟偨偲偄偆乽釋庣栻墹曥嶧乿偵偮偄偰彂偐傟偰偄偰丄懢揷摴燇偺傛偆偵乽醰釋彍偗乿偲偟偰娭惣偐傜姪惪偟偨恖偑偄偨傫偩側偀丄偲丅
(曭峴偵側偭偨塀枾丗http://www.ten-f.com/bugyo-to-onmitu.htm)
(妢怷恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%A0%E6%A3%AE%E7%A8%B2%E8%8D%B7)
(妢怷堫壸丗http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi/daiou/39.html)
姪惪偟偨偲偄偆乽擻栶幰乮墡妝乯偺壠嬝偩偭偨偲偝傟傞戝慜巵乿偵偮偄偰偼傛偔傢偐傜側偐偭偨偑丄乽擻栶幰乮墡妝乯偺壠嬝乿偱偁傟偽恅巵偲偺宷偑傝偑巉傢傟丄乽栻墹曥嶧乿偲偄偆偲2009.07.24暘偱偪傚偙偭偲彂偄偨乽朄棽帥乿嬥摪偺乽庍夀嶰懜憸乿偺榚帢偑乽栻墹曥嶧丒栻忋曥嶧乿偩偦偆偩偑丄2010.02.07暘偱偺乽搾旜摶乿偺乽摋釋偺恄條乿偼丄乽懛拕巕揱愢乿偱偼乽擛堄椫娤壒乿偺傛偆偱丄偦傟傪埨抲偟偨乽岝柧摱巕乿偼乽曎嵥揤廫榋摱巕乿偺乽慏幵摱巕乿偺傛偆偱丄杮抧偼乽栻忋曥嶧乿偲彂偄偰偰丄宷偑傝偑偁傞傛偆側偦偆偱側偄傛偆側丒丒丒丅
(懛拕巕揱愢丗http://www.geocities.jp/hokuriku1970/yunoo.html)
乽妢怷乿偵偮偄偰偼丄2010.04.10暘偱乽妢怷娤壒(愮梩)偲妢帥(柤屆壆)乿傪専徹偝傟偰偄傞僒僀僩傪攓尒偟偰偄偰丄偦偺嫟捠崁偺侾偮偵乽攎徳偑嬪傪塺傓乿偙偲偑嫇偘傜傟偰偄偰丄嶰搰峕偱塺傑傟偨傕偺偑偦傟偵偁偨傞偺側傜丄宷偑傝傪帵偡攎徳偐傜偺儊僢僙乕僕偐傕丄偲丅
偱丄崅捨偺乽妢怷恄幮乿偼乽抧尦偺崑懓丒妢巵偑抰晲旻柦偲姏暿柦傪釰偭偰憂愝偝傟偨偲揱偊傜傟傞丅乿偲偁傝丄乽妢巵乿偑乽媑旛巵乿偺棳傟傪媯傓偙偲偐傜乽抰晲旻柦乿偲偦偺巕偺乽姏暿柦乿偑釰傜傟偨傛偆偱丄乽妢巵乿偼2010.10.09暘偱怷巵偺挊彂偵彂偐傟偰偄偨乽妢昐巹報乿偐傜婥偵側偭偰偰丄偦偺帪偵彂偄偨傛偆偵乽悰乿乽揝乿偵娭偡傞巵懓偲巚傢傟丄乽醰釋乿傕娷傔偰乽悾怐捗昉乿乽僯僊僴儎僸乿偵宷偑傞偺偱偼丒丒丒丅
(抰晲旻柦丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%9A%E6%AD%A6%E5%BD%A6%E5%91%BD)
(媑旛丒妢丒夑梲丒忋摴丒擔曭晹丒榓婥丗http://homepage2.nifty.com/amanokuni/kibi.htm)
(妢怷娤壒(愮梩)偲妢帥(柤屆壆)丗http://rizardon.com/~nakai/kasamori.htm)
偆乕傫丄乽憼墹尃尰乿偲摨堦帇偝傟偰偄傞乽埨娬揤峜乿偑釰傜傟偰偄傞乽淎殸恄幮乿偺偁傞偁偨傝偼乽壨撪拻暔巘乿偺杮嫆抧偱丄乽拻暔乿乽堭乿乽醰釋乿偺宷偑傝偑尒傜傟傞丄偲偄偆偩偗偠傖丄愢柧晄懌偱偡傛偹丒丒丒丅
(撶媨戝柧恄丗http://www33.ocn.ne.jp/~hagizin/hirokuni/imoji.html)
捛婰(2011.01.29)丗
乽墇抭巵乿偲乽媑旛巵乿偑乽孼掜巵懓乿偲偁傝丄乽暔晹巵乿偲傕宷偑傞偲偄偆偙偲偵側傝偦偆偱偡偹丅
(墇抭巵峫丗http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-15.html)
| 仠2011.01.29(Sat.) |
尨場偼偙傟偐丒丒丒乽戝嶳嶎柦乿偲乽戝嶳愊恄乿(戝嶳媉柦丒榓懡巙戝恄)偑摨偠偱偁傞偐偺傛偆偵彂偐傟偰傞偗偳丄乽戝嶳嶎柦乿偼乽戝擭恄偲傾儊僲僠僇儖儈僤僸儊偺娫偺巕偱偁傞丅乿偲偁傝丄乽戝嶳愊恄乿偺偲偙傠偱乽僆儂儎儅僣儈恄偺柡偱偁傞恄戝巗斾攧恄偲偺娫偵戝擭恄偲憅堫嵃懜傪傕偆偗偰偄傞偲婰偟偰偄傞丅乿偲偁傞偐傜暿偺恄偭偰偙偲偱偟傚丅
(戝嶳嶎柦丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E5%92%8B%E7%A5%9E)
(僆僆儎儅僣儈丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E7%A9%8D%E7%A5%9E)
恅巵偲摗尨巵偑摨偠偲偝傟傞攚宨偲偟偰丄忋婰偺偙偲偑偁傞偩偗偱側偔丄懡巵偑摗尨巵(拞恇巵)偵忔偭庢傜傟偨偙偲偑彂偐傟偨暥專偑側偄偐傜丄恅巵偑夑栁巵傪忔偭庢偭偨傛偆偵夝庍偝傟偰偄傞傛偆偩偑丄嶰搰偺乽垻堊恄幮乿偼懡巵偵傛傞曭嵵偲巚傢傟丄偦傟傪忔偭庢偭偨摗尨巵(拞恇巵)偑丄懡巵偲偲傕偵廤棊傪宍惉偟偨巵懓傪巟攝偟偨偺偱偼丒丒丒悇應偱偼乽楢巕乿偵偡傝懼傢偭偨乽姍懌乿偵傛偭偰偱偼側偄偐丄偲丅
(垻堊恄幮丗http://kamnavi.jp/ym/osaka/ibaragiai.htm)
(垻堊恄幮丗http://www.h3.dion.ne.jp/~miyachan/aijinja.htm)
乽暭媣椙恄幮乿偵偮偄偰丄乽偁傞帪丄摉幮偺恄梎傪巕嵶偑偁偭偰晬嬤偺抮乮屼庤愻抮乯偵杽傔偨丅乿偲偁傞乽巕嵶乿偼丄摗尨巵(拞恇巵)偵忔偭庢傜傟偨偙偲傪昞偟丄乽悾怐捗昉乿偑塀偝傟偨傛偆偵巚傢傟傞偺偩偑丅
(垻堊恄幮(暭媣椙恄幮)丗http://bittercup.blog81.fc2.com/blog-entry-1892.html)
乽攄杹崙晽搚婰乿偵乽愄丄屶偺彑[僋儗僲僗僌儕]偑娯偺崙偐傜搉偭偰棃偰丄巒傔婭埳偺崙偺柤憪偺孲偺戝揷偺懞偵拝偄偨丅偦偺屻丄暘偐傟棃偰愛捗偺崙偺嶰搰偺夑旤[僇儈]偺孲偺戝揷偺懞偵堏偭偰棃偰丄偦傟偑傑偨桲曐偺孲偺戝揷偺懞偵堏廧偟偰棃偨丅偙傟偼傕偲偄偨婭埳偺崙偺戝揷傪偲偭偰棦偺柤偲偟偨偺偱偁傞丅乿偲偁傞偦偆偱丄摗尨巵(拞恇巵)偵傛傞懡巵偺忔偭庢傝偲偟偐巚傢傟側偄偺偼丄巹偑傾儞僠晄斾摍偩偐傜偲偄偆偩偗偱偼側偄偲巚偆丅
(戝揷丒懢揷偵偮偄偰丗http://kamnavi.jp/log/oota01.htm)
(攄杹晽搚婰丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%92%AD%E7%A3%A8%E5%9B%BD%E9%A2%A8%E5%9C%9F%E8%A8%98)
(攄杹晽搚婰偺悽奅丗http://www.himeji-utimati.jp/history/harimafudoki.htm)
(攄杹殸晽搚婰丗http://www.cam.hi-ho.ne.jp/sakura-komichi/kodaishi/harimatop.shtml)
偄偮傕偺擛偔墶摴偵偦傟偰偟傑偆偺偩偑丄乽攄杹殸晽搚婰乿傪彂偐傟偰偄傞僒僀僩偺乽僗僋僫僸僐僫偲椉柺廻橳偵偮偄偰偺僩儞僨儌乿偱偺丄僗僋僫僸僐僫偑僀儞僪恖偐傕丄偲偄偆愢偼嫽枴怺偄側丄偲丅
(僗僋僫僸僐僫偲椉柺廻橳偵偮偄偰偺僩儞僨儌丗http://www.cam.hi-ho.ne.jp/sakura-komichi/kodaishi/sukunahikona.shtml)
榖傪栠偟傑偡偑丄乽拞尨拞栫偲僟僟僀僘儉丄嫗搒帪戙乿偝傫偺僒僀僩偺乽恅巵偲摗尨巵丄偦偟偰乽嶰搰乿乿偵丄乽堬揷掔偺姰惉偵婑梌偟偨恅巵偑丄楈尡偁傜偨偐側帠傪徹柧偟偰尒偣偨戝嶳愊恄傪丄姏巵偲嶰搰巵偺椆夝偺壓偵釰偭偨偲峫偊傞偺偑帺慠偱偡丅乿偲偁偭偨偙偲偐傜偺専嶕偩偭偨傢偗偩偑丄乽俁悽婭偐傜係悽婭偵偐偗偰丄姏巵偺抧斦傪宲偖宍偱乽巣杻巵乿偑乽搱巵乿偵丄峏偵乽屼搱乿偐傜乽嶰搰巵乿偲側偭偰摑崌巟攝乿偟偨偲偄偆偺偼丄慼変巵傪憰偭偨乽姍懌乿偵傛偭偰愭廧偺巵懓偑晻偠崬傑傟丄偝傜偵乽姍懌乿偺巕偲偄偆棫応傪棙梡偟偨晄斾摍偑丄拞恇巵(摗尨巵)傕乽嶰搰楢崌偺堦堳乿偱偁傞偺偩偐傜偲丄嫤椡偝偣偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞傢偗偱丅
(姏恄幮丗http://kamojinja.web.fc2.com/tayori.html)
(恅巵偲摗尨巵丄偦偟偰乽嶰搰乿丗http://www.ten-f.com/hata-to-fujiwara-mishima.htm)
乽擔杮彂婭乿偵偁傞乽帠戙庡恄丄敧恞榢偵側偭偰嶰搱峚偔傂昉丄埥偄偼偄傢偔丄嬍孂昉偵捠偄媼偆丒丒丒乿傪怣偠傞側傜偽丄乽嶰搱峚偔傂昉乿偺偄傞抧偵乽帠戙庡恄乿偑傗偭偰偒偨偙偲偵側傝丄乽嶰搱峚嶎帹乿偼恅巵偐懡巵偺恄偲巚傢傟傞偺偱乽帠戙庡恄乿傪庴偗擖傟偨懁偱丄偦偙偵忔傝崬傫偱乽屼搱乿偐傜乽嶰搰巵乿偵偟偰摑崌巟攝偟偨偺偑乽姍懌乿偐偲丅
(乽儓僪乿偺廃曈丗http://www.dai3gen.net/yodo.htm)
(嬍孂昋丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E6%AB%9B%E5%AA%9B)
乽斨庤搈恄幮乿偺媨巌偝傫偑偍偭偟傖偭偰偄偨偲偄偆丄堬栘偺乽垻晲嶳乿偲崅捨偺乽埨枮嶳乿偲嶳嶈偺乽揤墹嶳乿偑丄乽偦傟偧傟戝奀偵晜偐傇嶰偮偺搱偺巔偵尒偊偨偐傜乽嶰搱乿偲柤偯偗傜傟偨乿偙偲偲丄乽巣杻巵乿丄乽屶偺彑乿偑偳偆宷偑傞偺偐偑晄柧偩偑丄崌釰偝傟偰偄傞乽塤曱恄幮乿偑乽栶彫妏偑曱摢敀塤偺棫搊傞傪尒偰乿釰偭偨偲偄偆乽憼墹尃尰乿偑丄乽埨娬揤峜乿乽棆恄乿偲廗崌偟偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄廧柉偺曽乆偑乽悾怐捗昉乿偱偁傞偙偲傪抦偭偰偺偙偲偱偼側偄偐偲巚傢傟偰丅
(埨娬揤峜偲慼変巵偦偟偰愇愳丗http://www.ten-f.com/ankan-kumomime.htm)
(斨庤搈恄幮丗http://kamnavi.jp/en/settu/iwate.htm)
(斨庤搈恄幮丗http://bittercup.blog81.fc2.com/blog-entry-945.html)
(峚嶎恄幮丗http://kamnavi.jp/en/settu/mizokui.htm)
(峚嶎恄幮丗http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/hokusetu-mizokui.html)
(峚嶎恄幮丗http://bittercup.blog81.fc2.com/blog-entry-396.html)
乽嶰搰姏恄幮乿偺幮揱偵乽暔晹偺娯崙楢偑嵳釰偵嫤椡偟偨偲偟偰偄傞乿偲偁傞偙偲傗丄晽椩摪偝傫偺僽儘僌偵偁偭偨埳梊偱乽戝嶳愊恄乿偑乽曽曋偺恄乿偲偟偰釰傜傟傞棳傟偐傜丄乽屶偺彑乿傗乽巣杻巵乿偑暔晹巵偲宷偑傞壜擻惈傕偁傝丄姍懌丒晄斾摍偵傛偭偰暔晹巵丒慼変巵偺懌愓偑徚偝傟偨偩偗偱側偔丄婰婭偵偼嵹偭偰側偄偲偄偆乽堫捾恄幮乿偺屼桼弿偵偁傞乽娯崙孯偺廝寕乿偱偼乽峳塇媉恄傪媡棙梡乿偝傟丄偝傜偵屼桼弿傪夵鈧偝傟偰偟傑偭偨偺偱偼丅
(嶰搰姏恄幮丗http://kamnavi.jp/en/settu/misimakamo.htm)
(嶰搰姏恄幮丗http://bittercup.blog81.fc2.com/blog-entry-1093.html)
(堫捾恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E7%88%AA%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(梊復婰丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%88%E7%AB%A0%E8%A8%98)
乽墔楈乿偑抋惗偡傞偺傕傢偐傞婥偑偡傞丅
乽戝嶳愊恄乿偵偮偄偰丄暿偺柤傪乽屷揷崙庡帠彑崙彑挿嫹柦乿偲偁傝乽戝嶳愊恄偺媅恄懱乿偲偝傟偰偄偨偺偱丄偳偆偄偆偙偲側傫偩傠偆偐偲専嶕偟偰偄傞偲丄
(戝嶳媉恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/ehime/imabari/ooyamazumi/ooyamazumi.html)
| 挿庡嶳乮側偑偸偟傗傑乯ゥ_戙偺愄丄屷揷偺挿壆偺崙庡帠彑崙彑挿嫹偲偄偆挿偄柤慜偺恄偑丄帺暘偺椞撪偺愨宨偱偁傞偲偄偆偲偙傠偑傜丄挿嫹偑庡嵣偡傞嶳偲偄偆堄枴偱丄偙偆屇傫偱偄偨偺偩偲偄偆偙偲偱偡丅 (奐暦偺愄榖丗http://kaimon.lolipop.jp/index.php?%E9%96%8B%E8%81%9E%E6%98%94%E8%A9%B1) |
偲偁傝丄傑偨丄乽廆憸戝曥嶧屼墢婲乿偵偁傞乽堥椙娵乿偺儌僨儖偑乽烼斾逋杻楥乿偱丄偦傟偑乽屷揷崙庡帠彑崙彑挿嫹乿丄偦偟偰乽柸捗尒乮儚僞僣儈儈乯乿亖乽屷揷崙庡乿丄乽奀恄崙亖帠彑崙側傫偩側丅偮傑傝岲屆搒崙丅乿偲彂偐傟偨僽儘僌偑偁偭偰丄偼偀丠偲丅
(壖徧儕傾僗幃丗http://gownagownaguinkujira.cocolog-nifty.com/blog/)
(堥椙娵丗http://www.k3.dion.ne.jp/~kodaira/xyz1107a.htm)
(岲屆搒崙(榘巙榒恖揱)丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%8F%E5%BF%97%E5%80%AD%E4%BA%BA%E4%BC%9D)
乽屷揷崙庡帠彑崙彑挿嫹乿偼乽擔杮彂婭乿偺戞俀偺堦彂偵弌偰偔傞乽恄晲乿偑弌夛偭偨偲偄偆恖暔偺傛偆偩偑丄乽墫搚榁墺乿乽墡揷旻乿乽晲撪廻擧乿偲傕偝傟偰偄傞傛偆偱丄乽垻懡乮嶧杸乯敼恖偺晲彨乿偲傕彂偐傟偰偄傞僒僀僩偑偁偭偰丅
(杸懡梾恄俀丗http://hwbb.gyao.ne.jp/akione-pg/Japanese/2_J.html)
壀嶈巗偺乽榋強恄幮乿偼丄乽徏暯巵乮摽愳巵乯敪徦偺抧偱偁傞徏暯嫿乮尰 朙揷巗徏暯挰乯偺榋強恄幮傛傝嵳恄偺姪惪傪庴偗偰憂寶乿偲偁傝丄乽徏暯嫿偺榋強恄幮偼丄阣鈣榋強柧恄乮阣鈣恄幮偺榋強媨偺恄乯傛傝姪惪傪庴偗偨傕偺乿偩偦偆偩偑丄乽壀嶈偺榋強恄幮偼偦偺偆偪墡揷旻柦丒墫搚榁墺柦丒帠彑崙彑挿嫹柦偺嶰恄偺暘釰傪庴偗偨丅乿偲偟偰丄庡嵳恄偑乽墡揷旻柦乿乽墫搚榁墺柦乿乽帠彑崙彑挿嫹柦乿偲側偭偰偄偰丄乽阣鈣榋強柧恄乿傕傛偔傢偐傜偢傑偨偟偰傕丄偼偀丠丄偲丅
(壀嶈巗丒榋強恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E6%89%80%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E5%B8%82))
(墫鈣恄幮丗http://5.pro.tok2.com/~tetsuyosie/miyagi/shiogamasi/shiogama_keidai/shiogama_keidai.html)
媨忛偺乽旲愡恄幮乿偵偼丄乽阣鈣幮墢婲乿偵傛傞偲乽阣鈣榋強柧恄乿偼乽墡揷旻柦丄帠彑崙彑柦丄墫搚榁墺丄婒恄丄嫽嬍柦丄懢揷柦偺摨懱堎柤偺俇嵗乿偲彂偐傟偰偄偨偑丒丒丒丅
(旲愡恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BC%BB%E7%AF%80%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
乽崅愮曚恄幮乿偱偼丄乽嫬撪幮乿偺乽堫壸幮乿偵乽帠彑崙彑挿嫹恄偲戝擭恄傪釰偭偰偄傞丅乿偲丒丒丒丅
(崅愮曚恄幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8D%83%E7%A9%82%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
帬夑偺乽懡夑戝幮乿偱偼丄愛幮乽層媨恄幮乿偵乽埳幾撨婒柦丒埳幾撨旤柦丒帠彑崙彑挿嫹乿偑釰傜傟偰偄偰丄乽懡夑幮偺撿曽2僉儘儊乕僩儖偵偁傞彫崅偄媢乮恄懱嶳乯偵捔嵗偡傞丅 庼巕丒庼嶻丄捔壩偺恄偲偟偰悞宧偝傟傞丅乿偲丒丒丒丅
(懡夑戝幮丗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E8%B3%80%E5%A4%A7%E7%A4%BE)
乽妢嵐楬扵朘乿偝傫偺僒僀僩偱丄杮棃偺恄乽嶰搰棿恄乿偲乽攐桪丒僆儈僒僉乿偲偼宷偑傞傛偆側姶偠偼偡傞偑丄曽曋偺恄乽戝嶳愊恄乿偲偼堎側傞傛偆偵巚偊偰丄晄斾摍偺栚榑尒偵僴儅偭偰偟傑偭偰偨偺偐丠巹丒丒丒丅
(揤恄偺暈懏丗http://www4.synapse.ne.jp/yatusiro/newpage17.html)
偦偆偄偊偽挿栰巗偺乽壛栁恄幮乿偼丄乽屆揱偱偼弶戙戝杮婅忋恖偑怣擹壓岦偺嵺丄擔崰怣嬄偟偰偄偨嫗搒夑栁屼慶恄幮乮壓姏幮乯偺屼恄楈傪曭帩偟釰偭偨乿偲揱偊傜傟偰偄傞偲偁傝丄乽慞岝帥乿偺弶戙戝杮婅忋恖乽懜岝忋恖乿偼乽惞摽懢巕斳丅峜嬌揤峜偺柦偵傛傝慼変攏巕偺柡偑弌壠乿偟偨偲偝傟偰偄傞偺偱丄偦偺慼変巵偑嶰搰偱恅巵丒夑栁巵偺僥儕僩儕乕傪忔偭庢傞僴僘偑側偄偲巚傢傟丄乽擭懌乿偺偍曟偟偐側偄偺傕柇偱丄側傜偽乽姍懌乿偑忔偭庢偭偨偲峫偊傞偺偑帺慠側偺偱偼丅
(壛栁恄幮丗http://www.zenkojikai.com/shinetsu/s-183.html)
(慞岝帥忋恖丗http://www.daihongan.or.jp/shounin/)
梋択丗栺懇帠丄偲偄偆偐丄寛傑傝傒偨偄側偺偑偁傞傫偱偟傚偆偐丒丒丒 偺夛幮偺乽俿搰乿偝傫偪偼杮壠偩偦偆偱丄暘壠偼乽俿搱乿偝傫傜偟偄丅偱丄乽俵搱乿偝傫偪偼暘壠偱丄杮壠偼乽俵搰乿偝傫偩偦偆偱丅
偺夛幮偺乽俿搰乿偝傫偪偼杮壠偩偦偆偱丄暘壠偼乽俿搱乿偝傫傜偟偄丅偱丄乽俵搱乿偝傫偪偼暘壠偱丄杮壠偼乽俵搰乿偝傫偩偦偆偱丅
幁搱巗偵偁傞乽幁搰恄媨乿傗丄嶰搰巗偺乽嶰搱戝幮乿側偳偵傕丄偦偆偄偆偺偑偁傞偺偐側偀丒丒丒丅
| 仠2011.01.31(Mon.) |
堦嶐擔撏偄偨俵俴乽惣峴帿揟乿偺戞159崋傪攓尒偟偰偰丄傆偲棅挬偲惣峴偺弌夛偄偑婥偵側偭偰専嶕偟偰傒偨丅
乽屷嵢嬀乿侾侾俉俇擭 乮暥帯俀擭丂暩屵乯偵丄
| 俉寧侾俆擔丂屓塏 擇昳掃壀媨偵屼嶲寃丅帶傞偵榁憁堦恖捁嫃偺曈偵減渏偡丅 偙傟傪夦偟傒丄宨婫傪埲偰 柤帤傪栤傢偟傔媼偆偺張丄嵅摗暫塹偺堁寷惔朄巘側傝丅崱惣峴偲崋偡偲丅 樄偭偰曭暭 埲屻丄怱惷偐偵墆尒傪悑偘丄榓壧偺帠傪択傞傋偒偺桼嬄偣尛傢偝傞丅 惣峴彸傞偺桼傪 怽偣偟傔丄媨帥傪夢傝朄巤傪曭傞丅擇昳斵偺恖傪彚偝傫偑堊憗懍娨屼偡丅 懃偪塩拞偵 彽堷偟屼朏択偵媦傇丅 偙偺娫壧摴暲傃偵媩攏偺帠偵廇偄偰丄瀶乆恞偹嬄偣傜傞傞帠桳傝丅 惣峴怽偟偰塢偔丄媩攏偺帠偼丄嵼懎偺摉弶丄側傑偠偄偵壠晽傪揱偆偲瀚傕丄曐墑 嶰擭敧寧撡悽偺帪丄 廏嫿挬恇埲棃嬨戙偺拕壠憡彸偺暫朄傪從幐偡丅 嵾嬈偺場偨傞偵埶偭偰丄偦偺帠慮偰埲偰怱掙偵巆傝棷傔偢丅奆朰媝偟傪偼傫偸丅 塺壧偼丄壴寧偵懳偟摦姶偺愜愡丄嬐偐偵嶰廫堦帤偽偐傝傪嶌傞側傝丅 慡偔墱巪傪抦傜偢丅慠傜偽惀斵曬偠怽偝傫偲梸偡傞強柍偟偲丅 慠傟偳傕壎栤摍娬側傜偞傞偺娫丄媩攏偺帠偵墬偄偰偼嬶偵埲偰偙傟傪怽偡丅 懄偪弐寭傪偟偰偦偺帉傪婰偟抲偐偟傔媼偆丅鉸廔栭偵愱傜偣傜傞偲丅 (http://www5a.biglobe.ne.jp/~micro-8/toshio/azuma/118608.html) |
偲偁傝丄傑偢擔晅偑婥偵側傝丄攎徳偑乽寧偵柤傪曪傒偐偹偰傗摋釋偺恄乿偲塺傫偩乽拞廐偺柤寧乿偺擔偵夛偄丄乽壧摴乿偵偮偄偰棅挬偑暦偄偨偲偄偆偙偲傗丄惣峴偑揱庼偟偨梻擭偐傜乽掃壀敧敠媨乿偱乽棳揕攏乿偑峴傢傟傞傛偆偵側偭偨偙偲側偳丄棅挬偑乽悾怐捗昉乿乽僯僊僴儎僸乿偵娭偡傞壗偐傪暦偒偨偑偭偰偄偨傛偆偵巚偊偰丅
乽惣峴乿偲乽帨墌乿乽柧宐乿摍偲偺娫偵傕乽悾怐捗昉乿偺懚嵼偑姶偠傜傟丄偦偆偟偨宷偑傝偑尒偊偨偺偱丄柌枍巵傕彂偐傟偨偺偱偼側偄偐偲巚偊偨傝丒丒丒丅
(柌枍嘌偺昤偔惣峴丗http://59155480.at.webry.info/200801/article_4.html)
(撲偺廻恄丗http://www.kuniomi.gr.jp/geki/wa/seireo02.html)
(傂偲丒棳峴丒榖戣丗http://book.asahi.com/clip/TKY200612190369.html)
(挬擔怴暦弌斉乽堦嶜偺杮乿丗http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=12225)
乽峴婎乿偲乽惣峴乿傪宷偖傛偆偵塺傫偩乽悽偺恖偺尒晅偸壴傗尙偺孖乿偵崬傔偨攎徳偺憐偄偲偼丒丒丒丅
(恵夑愳丗http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/okunohosomichi/okuno09.htm)
(偲偐偔偟偰墇偊峴偔傑傑偵丗http://www5f.biglobe.ne.jp/~mind/knowledge/japan/hosomichi006.html)
榖偼曄傢傞偑丄峴婎備偐傝偲偝傟傞乽挿崙帥乿偲丄偦偺乽挿崙帥乿傪嵞嫽偟偨偲偝傟傞乽崻捗恟暯乿丄偦偟偰偦偺嬤偔偵偁傞偲偄偆乽惣峴捤乿偵偮偄偰婥偵側傞傫偩偑丄偄傑偄偪傛偔傢偐傜側偔偰丒丒丒丅
(戝堜廻丗http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/douro/naka_douro3/nakasanndou6.html)
(戝堜廻丗http://okamoto.u.cnet-ta.ne.jp/naksendo/n10day.htm)
(恟暯嶁丗http://www.ja-higashimino.or.jp/hiroba/story/e/jinbei.html)
柪憱偼傑偩傑偩懕偒偦偆偱偡丒丒丒丅