 とんでもニャ~Mの推測3-7
とんでもニャ~Mの推測3-7※役にたたない推測ばかりの駄文です。(爆)
 とんでもニャ~Mの推測3-7
とんでもニャ~Mの推測3-7| ●2011.02.01(Tue.) |
「笠沙路探訪」さんの2011年 2月号「践祚大嘗祭の翌年、衣物を持って伊勢に行幸した持統女帝」を拝見した。
(http://www4.synapse.ne.jp/yatusiro/newpage45.html)
そうか・・・「事勝國勝長狭」が「皇孫」からの「織經(はたお)る少女」についての問いに、「大山祇神の女等、大(あね)を磐長姫と號(い)ふ。少を木花開耶姫と號ふ。亦の號は豐吾田津姫」と言った、ということから、「大山咋命」と「大山積神」が異名同神と思われているのかも。
「大山積神」の別名が「吾田国主事勝国勝長狭命」ならば、自分の子のことを「大山祇神の女等・・・」と説明することに違和感がある、というか、不比等らが無理やり「大山祇神」という神名を突っ込んだのでは、と。
で、「笠沙の岬の『布のまつり』」を拝見していると、2011.01.20分での折口氏の「幣束から旗さし物へ」に繋がるようで、そこから「御霊信仰」に発展したように思われ、やはり秦氏・物部氏などの「古代からのネットワーク」の氏族によって興ったのでは、と。
不比等らによって無理やり突っ込まれたとは言え、「大山祇神」が「隼人」との関連があることを示していると言えるわけで、「隼人」の一員と思われる「秦氏」が「太子」の時代にいち早く仏教を取り入れているのだから、「奈良天武政権の仏教国教化」に隼人も一役を担っているのではないかと思われ、要請により持統天皇は「僧侶を派遣」したのかもしれないな、と。
「過疎、限界集落、地域崩壊」までもたらしてしまっている、と書かれていることについても、「都」「旧都」から少し離れた場所で「市」が始まったのは、「商人」の足跡を辿ればある種「隼人」の知恵によるもののように思われて。
(海柘榴市:http://www5.kcn.ne.jp/~book-h/mm064.html)
(海柘榴市:http://bell.jp/pancho/travel/yamanobe/tubaiti.htm)
(海柘榴市:http://nire.main.jp/rouman/fudoki/34nara05.htm)
(市場の祭文:http://www.adachi.ne.jp/users/a.trm/newpage11.htm)
(市比賣神社:http://ichihime.net/)
(六斎市:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E6%96%8E%E6%97%A5)
(宇都宮・二荒山神社:http://usagiya.ti-da.net/e1495797.html)
(西宮神社:http://www.decca-japan.com/nishinomiya_ebisu/history.html)
うーん、「西宮神社」からの検索で「不思議空間「遠野」」さんのサイトに辿り着いたが、「オシラサマ」信仰と持統天皇の「伊勢に幸さむ。此の意(こころ)知りて、諸の衣物(きもの)を備ふべし」の詔が繋がるように感じ、そのことや「河童伝承」などと同様に、「御霊信仰」「市」なども「海人族の信仰」に当てはまるように思うのだが。
(河童と傀儡と瀬織津比咩:http://dostoev.exblog.jp/i216/)
やはり私には、「天武禍」というより「不比等禍」のように思えて・・・。
| ●2011.02.05(Sat.) |
体調がイマイチでつい寝転んでしまい、ゆっくりと拝見できてないんだけど、風琳堂さんのブログが更新されていて、「楠にまつわる伝説」に書かれていた「頭はこの島(鬼塚という)に、胴体は求菩提に埋められた。」ことと、「この島(鬼塚という)はその後、満潮には浮島となり、干潮には砂州となって水没することがなかった。」とあり、2011.01.21分での「浮島」と繋がりそうで改めて検索した。
(求菩提山・岩岳川の守護神──鬼の供養のために:http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2011/02/05)
熊本の「浮島熊野座神社」の御祭神はイザナギ・イザナギだが、そもそもは「浮島熊野大権現」のようで、摂社「井王神社」に創始者の「井王三郎」が「水神」として祀られ、「【いぼとり、頭痛、歯痛】など痛みをやわらげてくれる神様」で眷族は「河童」とあり、「瀬織津姫」に繋がりそうで「井王三郎」との繋がりが気になったものの、詳細はわからず・・・。
(浮島熊野座神社:http://mat01.p1.bindsite.jp/temp.html)
で、愛媛の「浮島神社」の御祭神「宇摩志阿斬訶備比古遅神」で検索していると、御祭神は異なるが小角が「浮島宮」を建てたという山形の「大沼浮島稲荷神社」も、「ここは、もとは田畑を人間に提供した「アシカビ」のような神の結界だったのでしょうが・・・」とあり、「宇摩志阿斬訶備比古遅神」と繋がるようで、「浮嶋明神の聖地は交易地となって、家屋が立ち並んで市がたつようになったと記しています。」と、「菅江真澄」の「月の出羽路」にあるとのことで、1日のことに繋がりそうで。
(第5柱 可美葦牙彦舅尊1:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=1171)
上記URLの続きに「これは今の刈和野(かりわの)の本宮浮嶋大明神(秋田県大仙市)のことで、市神を祀ります。」とあり、「刈和野」で検索していると、「長山氏の奉ずる氏神が市神」とされていて、2009.05.01分などで調べた「葛原親王」の末裔で、将門の一族が奉斎していた神は「瀬織津姫」のようで。
(刈和野大綱引の由緒沿革:http://www.city.daisen.akita.jp/content/nisisenboku/otuna/02_3/index.html)
つまりは「浮島」「市」が繋がり、「古代からのネットワーク」による祭祀・神事があるようで、2009.12.15で検索した「砥上ヶ原」も同様に繋がるのであれば、西行の「芝まとふ(えは惑ふ)葛のしげみに妻こめて砥上ヶ原に牡鹿鳴くな里」も何かありそうで、MLで3号続けて載せられていた「鹿」の歌が気になってきた。
(砥上ヶ原:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%A5%E4%B8%8A%E3%83%B6%E5%8E%9F)
「葦」「鹿」「鉄」・・・あ、「鹿葦津姫」か!ということで繋がるようですね、「瀬織津姫」に。
元は池之宮に祀られていたという「百済王神社」の境内社「浮島神社」は、秦氏らとの交流が見えるようですね。
(百済王神社:http://www12.plala.or.jp/HOUJI/jinja-1/newpage1205.htm)
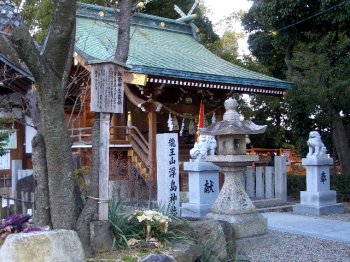

で、「足神社」も「宇麻志阿斯訶備比古遅神」に繋がりそうですね・・・とすると、「頭」や「腹」を祀った神社は何に繋がるのかが気になる・・・「腹」は「フイゴ」、「頭」は「たたら」かも?
(第5柱 可美葦牙彦舅尊5:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=1212)
| ●2011.02.06(Sun.) |
昨日拝見していた「ISIS本座 - 高橋秀元 バジラな神々」さんの「第7柱 国常立尊-10◎高賀山の「さるとらへび」と円空の結界」を拝見していたんだけど、2010.02.10分などでの妖怪さるとらへび退治の「藤原高光」と、2010.01.10分などでの「惟喬親王」が繋がるようなんだが・・・。
(第7柱 国常立尊-10:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=2498)
「藤原高光」のモデルとして「藤原広嗣」「藤原忠文」を挙げておられ、両者とも「怨霊」とされているあたりに何かありそうだが、「高賀山を朝廷のために守備した一族が後世に藤原氏の子孫を称したと推測」されているのなら、なぜ「怨霊」となったのかがよくわからなくて。
さらに、「藤原氏の子孫を称した」のが「美濃に入った木地師の一族」とされていて、さらにわからなくなって・・・。
将門の乱ともリンクしているとされているのは、背後に山岳修験者を含めた「古代からのネットワーク」が絡んでいるからのように思われ、「高賀山信仰」を知る「円空」が「瀬織津姫」を刻んでいるから、「怨霊」となった2人は「藤原氏」でありながら「古代からのネットワーク」に与したことを表しているのかもしれないが。
でも、そうすると、「広嗣の乱」が何を意味しているのかがわからなくなりそうで・・・「円空は天下動乱を予告してあらわれる妖魔を鎮める高賀山の神々を代表する男女神」を刻んだと解しておられるが、そのあたりの考え方が異なるのは、私の捉え方が間違っているのかと思えたり・・・。
で、2003.04.11分などでの「虚空蔵信仰」や、2011.01.20分などでの「金剛童子」(蔵王権現と同体)なども繋がるようで、「瀬織津姫」の信仰が形を変えていく流れが見えるようだが、まだ頭の中は混乱してまして・・・。
ただ、2011.01.29分での「鹽竈六所明神」が「猿田彦命、事勝国勝命、塩土老翁、岐神、興玉命、太田命の同体異名の6座」とあるのと、湯布院の「宇奈岐日女神社」の御祭神「国常立尊、国狭槌尊、彦火火出見尊、ヒコナギサタケウガヤフキアエズノミコト、神倭磐余彦尊、神渟名川耳尊」が繋がりそうで、2007.03.03分などで書いた行基ゆかりの「水間寺」を天台宗に改宗した「性空」もまた、「瀬織津姫」について知る人物だった、という確信ができたような。
(第7柱 国常立尊-11:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=2591)
(宇奈岐日女神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%A5%88%E5%B2%90%E6%97%A5%E5%A5%B3%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
| ●2011.02.07(Mon.) |
解せん・・・「ISIS本座 - 高橋秀元 バジラな神々」さんの「第2柱 高皇産霊神―4 ◎山城の壱岐氏・大和の対馬氏と亀卜の行方」で、「壱岐氏に祀らせた高皇産霊神の行方」を探すと、「『日本書紀』の大宝元年(701)の項目を眺めますと、「葛野郡月読神、樺井神、木嶋神、波都賀志神など、その神稲を、今より以後、中臣氏に給え」という記述がみられます。」とあり、「これらの神社によって結ばれた部族が祭祀を持続できないまでに衰えたので、国家政策によって中臣氏の支族に編入されたわけです。」とされていたが、それはちゃうやろ、と。
(第2柱 高皇産霊神―4:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=448)
(続日本紀 巻第二 四月三日:http://www1.kcn.ne.jp/~watblue7/tenpyo/shoku/shokunihongi02.html)
(木嶋坐天照御魂神社:http://www.geocities.jp/engisiki/yamashiro/html/020202-01.html)
(羽束師坐高産日神社:http://blogs.yahoo.co.jp/hiropi1700/folder/953154.html?m=lc)
(樺井月神社(水主神社境内社):http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/tuki-kabaituki.html)
(葛野坐月読神社:http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/kindex2.php?J_ID=11801)
「中臣氏・大中臣氏考」さんのところに書かれている、太田亮氏の「「勝海」のところで、旧来の中臣氏は滅び、新たな中臣氏がこれを継いだ。」という説が相当するのではないかと考えており、「新たな中臣氏」の経済力では秦氏等を凌ぐとは考えにくく、「祭祀を持続できないまでに衰えた」のではなく、三島などと同様に乗っ取られたようにしか思えないわけで、「勅」は不比等のしわざかと。
(中臣氏・大中臣氏考:http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-23.html)
それに対抗すべく、聖武天皇の時代には「勅」によって「国分寺・国分尼寺」や、行基たちによる寺院・神社が建てられたのでは。
「第4柱 津速産霊神―3◎『日本書記』と『新撰姓氏録』の間に」では、中臣氏の乗っ取りに関すると思われることも書かれているんだが・・・ま、鎌足や不比等が乗っ取った「中臣氏」の祖を祀らず、乗っ取った氏族の神を祀るのは、各地にいるその同族のテリトリーを、「勅」とする「祭祀権」をふりかざして乗っ取るためかと思われるが。
(第4柱 津速産霊神―3:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=1047)
「第4柱 津速産霊神―4」には、松原市の「屯倉神社」の境内社「酒屋神社」について、「王政権との関係を安定させるために中臣氏の系列に入」ったとされ、それにより「津速産霊神を祀った」のであろうとされていて、「不比等が復活した藤原氏、新たに設けられた大中臣氏」が祖神を「武甕槌命」に変更したにもかかわらず、「中臣酒屋連は津速産霊神を祀る酒屋神社を祖廟として結束をくずさなかった」のは、中臣氏による土師氏のテリトリーの乗っ取りと、不比等による系譜捏造を表しているのではないか、と。
11年前にお参りした際には、「酒屋神社」はひっそりと祀られていたと記憶しているが、「酒屋神社」の本来の御祭神は「瀬織津姫」だったのではないかと思われるわけで。「津速産霊神」は「方便の神」名ではないかと・・・。
(第4柱 津速産霊神―4:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=1079)
(屯倉神社:http://www.xhotzone.net/vh/vh09070401.php)
(酒屋神社:http://www.geocities.jp/engisiki/yamashiro/html/020710-01.html)
(酒屋神社:http://achikochitazusaete.web.fc2.com/sikinaisha/yamasiro/tuduki/tuduki.html)

| ●2011.02.09(Wed.) |
神奈備さんの掲示板「青草談話室」で、生田氏が「大きな袋とは牛(ウ=大、シ =風)の皮ではなかったかと思い始めました。」とあり、なるほど、と。
(青草談話室5876:http://ucgi.kamnavi.net/cgi-bin/aokbbs.cgi)
2010.08.31分などでの検索で、「アイヌ語のウス(ウシ)us=入り江、湾」とあったけど、他にも何かあるような気がしてて、「昭和新山では1944年の噴火で洞爺湖に巨大な渦巻きが発生。」というのは、「大風」が関連しているからではないかと思われ、それにより「牛」は「鍛冶」に繋がる言葉なのかも、と。
とすると、道真の背後には「鍛冶集団」との繋がりがあることや、2008.11.06分などの和歌山市小野町の「水門・吹上神社」の「牛祭り」での「牛の舌餅」なども「鍛冶集団」と繋がり、「瀬織津姫」に繋がるということではないかと思われるわけで・・・「牛頭天王」も、ですね。
生田氏が「また大黒様シリーズを始めようかなぁ~。」とされているように、「三面大黒天」とも繋がると思われ、「円空」作の伊勢の「中山寺」の「三面大黒天」が「瀬織津姫」と思われるので、ナットク。
(円空さんを訪ねる旅25:http://shigeru.kommy.com/enkuu25isetyusanji.htm)
| ●2011.02.10(Thu.) |
 本代より送料の方が高かったという童門冬二氏の「小説太田道灌」の古書を、体調を考えながら少しずつ読んで、やっと読み終えたんだが、3分の2を読んだあたりで道灌ゆかりの寺社が列挙されていて、関与の経緯はわからないので検索してみようかな、と。
本代より送料の方が高かったという童門冬二氏の「小説太田道灌」の古書を、体調を考えながら少しずつ読んで、やっと読み終えたんだが、3分の2を読んだあたりで道灌ゆかりの寺社が列挙されていて、関与の経緯はわからないので検索してみようかな、と。
| 太田道灌 室町時代の武将。武蔵国守護代。摂津源氏の流れを汲む太田氏。諱は資長。扇谷上杉家家宰太田資清(道真)の子で、家宰職を継いで享徳の乱、長尾景春の乱で活躍した。江戸城を築城した武将として有名である。 江戸築城 『永享記』には資長が霊夢の告げによって江戸の地に城を築いたとある。また、『関八州古戦録』には品川沖を航行していた資長の舟に九城(このしろ)という魚が踊り入り、これを吉兆と喜び江戸に城を築くことを思い立ったという話になっている。これらの霊異談は弱体化していた古族江戸氏を婉曲に退去させるための口実という説がある。江戸城が完成して品川から居館を遷したのは、長禄元年4月8日(1457年5月1日)であったと言い伝えられている。江戸城の守護として日枝神社をはじめ、築土神社や平河天満宮など今に残る多くの神社を江戸城周辺に勧請、造営した。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E9%81%93%E7%81%8C) (万里集九:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E9%87%8C%E9%9B%86%E4%B9%9D) (飛鳥井雅親(飛鳥井家):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E4%BA%95%E5%AE%B6) (道灌紀行は限りなく:http://blog.doukan.jp/category/703280-1.html) |
| 太田道真館(埼玉県入間郡越生町小杉641) 扇谷上杉氏の執事を務めていた太田道真は在地土豪の越生氏、毛呂氏らの威勢が侮りがたいことから、山深い龍ヶ谷の三枝庵に砦を築いて時勢を窺っていた。 (http://joe.ifdef.jp/001saitama/136doushin/doushin.html) 道真は河越城で著名な歌人宗祇と心敬を招いて連歌会を催し、これは「河越千句」として有名である。道真の連歌は宗祇が編纂した『新撰菟玖波集』に収められている。 (太田道真:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E6%B8%85) (川越城:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E8%B6%8A%E5%9F%8E) |
日枝神社(千代田区永田町二丁目)
主祭神:大山咋神、相殿:国常立神、伊弉冉神、足仲彦尊(仲哀天皇)
| 創建の年代は不詳である。文明10年(1478年)、太田道灌が江戸城築城にあたり、川越の無量寿寺(現在の喜多院)の鎮守である川越日枝神社を勧請したのに始まる。徳川家康が江戸に移封されたとき、城内の紅葉山に遷座し、江戸城の鎮守とした。 (http://www.hiejinja.net/jinja/hie/saijin/index.html) |
喜多院(埼玉県川越市)
御本尊:阿弥陀如来
| 良源(慈恵大師、元三大師とも)を祀り川越大師の別名で知られる。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%9C%E5%A4%9A%E9%99%A2) |
川越日枝神社(埼玉県川越市小仙波町1-4-1)
御祭神:大山咋神、大己貴命
| 円仁(慈覚大師)が喜多院を創建(天長7年・830年)したおりに、その鎮守として貞観2年(860年)に坂本の日吉大社を勧請したものであるといわれている。東京赤坂の日枝神社(旧官幣大社)は、文明10年(1478年)、太田道灌が江戸城築城の際に、この川越日枝神社から分祀したものである。 |
築土神社(千代田区九段北1-14-21)
主祭神:天津彦火邇々杵尊、配祀:平将門、菅原道真
| 天慶3年(940年)6月、江戸の津久戸村(現:千代田区大手町付近)に平将門の首を祀り、「津久戸明神」として創建された。 室町時代に太田道灌により田安郷(現:千代田区九段坂上)へ移転させられて以降は「田安明神」とも呼ばれ、日枝神社、神田明神とともに江戸三社の一つにも数えられることもあった(江戸三社のうち、日枝神社、神田明神以外は固定していない)。 元和2年(1616年)に江戸城外堀の拡張により筑土八幡神社隣地(現:新宿区筑土八幡町)へ移転し、「築土明神」と呼ばれた。 明治7年(1874年)天津彦火邇々杵尊を主祭神として「築土神社」へ改称する。 第二次世界大戦の戦災による焼失(1945年)まで300年以上の間、筑土八幡神社と並んで鎮座していたが、戦後、現在地へ移転した。 (http://www.tsukudo.jp/gaiyou-rekisi.html) (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%89%E5%9C%9F%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
築土八幡神社(新宿区筑土八幡町2-1)
主祭神:応神天皇・神功皇后・仲哀天皇
| 嵯峨天皇の時代(809年 - 823年)に、付近に住んでいた信仰心の厚かった老人の夢に現われた八幡神のお告げにより祀ったのが起源であるといわれている。その後、慈覚大師が東国へ来た際に祠を立て(850年前後)、伝教大師の作と言われた阿弥陀如来像をそこに安置したという。その後、文明年間(1469年 - 1487年)に当地を支配していた上杉朝興によって社殿が建てられ、この地の鎮守とした。上杉朝興の屋敷付近にあったという説もある。元和2年(1616年)にそれまで江戸城田安門付近にあった田安明神が筑土八幡神社の隣に移転し、津久戸明神社となった。 筑土の名は「その昔伝教大師が筑紫の宇佐の宮土を求めて社の礎とした」事に由来するとされていますが、津久戸村(現大手町)にあった平将門の首塚を祀った津久戸神社が江戸城拡張により、当地に移転していた事が本当の由来のようです。 (http://www.asahi-net.or.jp/~cn3h-kkc/shiro/tukudo.htm) (http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/18_shinjuku/18026.html) (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%9C%9F%E5%85%AB%E5%B9%A1%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
平河天満宮(千代田区平河町1-7-5)
御祭神:菅原道真公、誉田別命、徳川家康公
| 江戸平河城主太田道灌公が、菅原道真公の霊夢を見て、文明十年城内に天満宮を建立した。その後、徳川家康公が築城のため本社を平河門外に奉遷し、慶長十二年二代将軍秀忠公に依り、現在の地に奉遷され地名を本社に因み平河町と名付けられた。 (http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/01_chiyoda/1007.html) (http://www.tesshow.jp/chiyoda/shrine_hirakawa_tenman.html) |
川越氷川神社(埼玉県川越市宮下町2-11-3)
御祭神:脚摩乳命、手摩乳命、素盞鳴尊、奇稲田姫命、大己貴命(大国主命)
| 川越城主の総鎮守として知られる「川越氷川神社」は、540年の創建と伝えられる。縁結びの神さまを奉る神社として、多くの人の信仰を集めてきた。江戸城を築城した太田道灌が深く崇敬したことでも知られている。平成の御代替わりを奉祝するために建てられた大鳥居は、高さ15メートルと、木製としては日本最大級と言われ、中央の社号文字は、幕末の幕臣、勝海舟の筆によるものとなる。 (http://commonclub.jp/s-kawagoe/169) (http://www.hikawa.or.jp/jinja/index.html) |
青松寺(港区愛宕)
御本尊:釈迦牟尼仏
| 江戸府内の曹洞宗の寺院を統括した江戸三箇寺の1つで、太田道灌が雲岡舜徳を招聘して文明8年(1476年)に創建。当初は武蔵国貝塚(現在の千代田区麹町周辺の古地名)にあったが、徳川家康による江戸城拡張に際して現在地に移転した。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%9D%BE%E5%AF%BA) (http://www5.ocn.ne.jp/~seishoji/yurai.html) |
市谷亀岡八幡(新宿区市谷八幡町15)
御祭神:誉田別命(応神天皇)、気長足姫尊、与登比売神(応神天皇の姫神)
| 当神社は太田道灌が文明11年(1479年)、江戸城築城の際に西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を祀ったのが始まりである。「鶴岡」に対して亀岡八幡宮と称した。当時は市谷御門の中(現在の千代田区内)にあった。しかし、その後戦火にさらされ荒廃していったが、江戸時代に入り寛永13年頃(1636年頃)に江戸城の外堀が出来たのを機に現在地に移転。市谷亀岡八幡宮は三代将軍・徳川家光や桂昌院などの信仰を得て、神社が再興された。江戸時代には市谷八幡宮と称した。 (http://www.ichigayahachiman.or.jp/engi/index.html) (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E8%B0%B7%E4%BA%80%E5%B2%A1%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE) |
湯島天満宮文京区湯島三丁目)
主祭神:天之手力雄命、合祀:菅原道真
| 社伝によれば、雄略天皇2年(458年)1月、雄略天皇の勅命により創建されたと伝えられている。(文明10年(1478)十月に、太田道灌が再建) (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E5%B3%B6%E5%A4%A9%E7%A5%9E) (http://www.yushimatenjin.or.jp/pc/engi/f_engi.htm) |
妙義神社(豊島区駒込3-16-16)
御祭神:日本武尊、高皇産霊神
| 日本武尊が東征の折、陣営を構えた処と伝えられ豊島区最古の神社である。また、太田道灌が出陣に際し文明三年(1471年)同九年、十一年にも当社に戦勝を祈願し、その都度勝利を収めたことにより勝負の神として「勝守り」を授与している。 (http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/index.html) |
正蔵院(新宿区神楽坂6-54)
御本尊:薬師如来
| 通称 「草刈薬師」と言い、 その由来は略縁起によりますと、 太田左金吾道灌が今の宮城の基である江戸城を築こうとして、千代田の野辺に茂る草を刈らせている時、一人の僧が現れ一体の薬師如来を道灌に授け、「この尊像は後醍醐天皇に味方し奥州白河に流された北条高時が日夜護念していた伝教大師真作の薬師如来である。 このご利益は国家の安泰のみならず庶民の現世災厄を除き未来得脱の果報が得られる有難き尊像である。 今国家の乱れを鎮めようとして城を築こうとしているあなたに授けよう」 と言ったとあります。そして尊像を授けられた道灌が城内の平川梅林坂に正蔵院を建て、 圓觀上人を別当に補したとあります。 (http://www.tendaitokyo.jp/jiinmei/jinss/ss4shozo.asp) |
金剛寺(文京区春日→中野区上高田)
御本尊:不明
| 金剛寺は建長2年、波多野中務忠経が源実朝の菩提のため狐舟を開山として建立した曹洞宗のお寺です。文明年間太田道灌が中興し、のち荒廃したが徳川家康が用山元照に再興させその時臨済宗から曹洞宗に改宗し、更に昭和になって地下鉄丸の内線開通の為に文京区から現在地に移転しました。 (http://1st.geocities.jp/tekedadesu/kongozi.html) |
諏訪山吉祥寺(文京区本駒込3-19-17)
御本尊:釈迦如来
| 長禄2年(1458)太田道灌が江戸城築城の際、井戸の中から「吉祥」の金印が発見されたので、城内(現在の和田倉門内)に一宇を設け、「吉祥寺」と称したのがはじまりという。天正19年(1591)に現在の水道橋一帯に移った。現在の水道橋あたりに橋は吉祥寺橋と呼ばれた。明暦3年(1657)の大火(明暦の大火)で類焼し、現在地に七堂伽藍を建立し移転、大寺院となった。 (http://www.tesshow.jp/bunkyo/temple_honkoma_kichijoji.html) 室町時代1458年(長禄2年)に太田持資(太田道灌)の開基で江戸城内に青巌周陽を開山に招いて創建した。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%A5%A5%E5%AF%BA_(%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA)) |
法恩寺(墨田区太平町一丁目)
御本尊:十界曼荼羅
| 太田道灌が1458年(長禄2年)に江戸城を築くにあたり、城内鎮護の祈願所として武蔵国平河村(江戸城平川口)に建立開基。 開山は本住院日住上人で、当初は本住院と称した。 道灌の跡を継ぎ城主となった嫡子・法恩斎の年忌に際し、孫の太田資高が寺号を法恩寺と改めた。その後神田柳原、谷中清水町と移転した後、1695年(元禄8年)に現在地に移ったが、当時は塔頭20ヵ寺・末寺11ヵ寺を擁していた。 (http://www.tesshow.jp/sumida/temple_taihei_hoon.shtml) (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%81%A9%E5%AF%BA_(%E5%A2%A8%E7%94%B0%E5%8C%BA)) |
太田姫稲荷神社(千代田区神田駿河台1-2)
主祭神:倉稲魂神、菅原道真、徳川家康
| 社伝によると、室町時代中期に太田道灌の娘が天然痘(疱瘡)に罹って生死の境をさまよい、京都の一口稲荷神社(いもあらいいなり)が小野篁にまつわる縁起により天然痘に霊験があると聞いた道灌が一口稲荷神社に娘の回復を祈願したところ、天然痘が治癒したという。道灌はこのことに感謝し、長禄元年(1457年)に一口稲荷神社を勧請して旧江戸城内に稲荷神社を築いたとされる。後に城内鬼門に祀られた。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%A7%AB%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E7%A5%9E%E7%A4%BE) (http://www.daisuki-kanda.com/festival/ohtahime/) (麹町太田姫稲荷神社:http://www.tesshow.jp/chiyoda/shrine_kojimachi_otahime.html) |
柳森稲荷神社(千代田区神田須田町2-25-1)
御祭神:倉稲魂大神
| 柳森神社は、長禄2年(1457)、太田道灌公が江戸城の鬼門除けとして、多くの柳をこの地に植え、京都の伏見稲荷を勧請したことに由来します。 (http://www.tesshow.jp/chiyoda/shrine_suda_yanagimori.html) |
福徳神社(中央区日本橋室町)
御祭神:倉稲魂命
| 清和天皇の貞観年間(859~877)に既に鎮座していたようである。武蔵野の村落である福徳村の稲荷神社として祀られ、その地名をとって社名とされた。 (http://jinja-kikou.net/nihonbashi-kita.html#2) (http://www.fukutokujuku.jp/jinja.html) |
椙森神社(中央区日本橋堀留町)
御祭神:倉稲魂大神、素戔嗚大神、大市姫大神、大己貴大神、五十猛神、抓津姫神、大屋姫神、事八十神、相殿:恵比寿大神
| 承平元年(931)ころの創建。天慶3年(940)俵藤太秀郷(藤原秀郷)が当社に祈願して平将門を滅ぼし、その報賽として白銀の狐像を奉納。元文元年(1466)大田道灌が雨乞祈願をし霊験あり。大いに喜びて伏見稲荷山の大神を分霊して椙森稲荷伍社大明神を祭る。 (http://jinja-kikou.net/nihonbashi-kita.html#6) (http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/index.html) (http://www.tesshow.jp/chuo/shrine_horidome_sugimori.html) |
熊野神社(港区麻布台二丁目2-14)
御祭神:素戔嗚尊、伊弉諾尊、伊弉冉尊
相殿:塩竈大神(塩土老翁)、宇迦之御魂大神(三田稲荷神社)、火之加具都知大神(愛宕神社)、宇迦之御魂大神(太田稲荷神社)
| 古来、祝融の災に遭うことたびたびに及び、古記録・宝物が失われているため、由緒沿革等詳細は不明であるが、社伝によれば養老年間(717~724)芝の海岸に勧請され、その後、現社地に遷座したという。文明年間(1469~87)太田道灌により再興され、宝物が寄進されたと伝わる。江戸時代は武家から篤い崇敬を受け、仕官の際には当社に参拝し、牛王神符を拝受したという。 (http://goshuin.ko-kon.net/touto_jinja/03_kumano_iigura.html) (http://www.mikumano.net/ztokyo/minato1.html) (http://www.minato-ala.net/sightseeing/welcome/root07/r07.html) |
氷川神社(港区白金二丁目1-7)
御祭神:素戔嗚尊、日本武尊、櫛稲田姫尊
| 日本武尊が東征の折に大宮氷川神社を遥拝した当地に、白鳳時代に創建されたと伝えられている。 (http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/index.html) (http://www.tesshow.jp/minato/shrine_shirokane_hikawa.html) |
赤城神社(新宿区赤城元町1-10)
御祭神:岩筒雄命、相殿:赤城姫命
| 正安二年(1300)、上野国赤城山の麓から牛込に移住した大胡彦太郎重治が上野国赤城神社から勧請し、牛込早稲田村田島(今の早稲田鶴巻町)に鎮祭されたが、寛正元年(1460)に太田道灌、神威を尊び牛込台に遷し奉り、その後、弘治元年(1555)、太胡宮内少輔(牛込氏)の尊崇により現在の地に遷し奉ったものである。 (http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/18_shinjuku/18008.html) (http://www.akagi-jinja.jp/akagi/goyuisho/) (群馬・赤城神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%9F%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
小日向神社(文京区小日向二丁目16-6)
御祭神:誉田別皇命、建速須佐之男命
| 氷川神社と八幡神社を合祀し明治二年五月、現社名となる。 氷川神社は、天慶三年(940)平貞盛が、この地方を平定しその報賽として建立。 八幡神社は貞観三年(860)の創立で旧社名を田中八幡と称し文京区音羽に鎮座していた。 (http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/index.html) (http://ginjo.fc2web.com/201sinkei_kasanegafuti/sinkei_kasanegafuti.htm) |
波切不動堂(本伝寺?)(文京区大塚)
御本尊:不動明王?
| 日蓮宗の本伝寺は、大法山と号します。法仙院日影上人(正保4年1647寂)が当地に創建したといいます。 (http://www.tesshow.jp/bunkyo/temple_otsuka_honden.html) (http://yoyochichi.sakura.ne.jp/yochiyochi/2010/10/post-138.html) |
日輪寺(文京区小日向一丁目4-18)
御本尊:不詳
| 道灌が再建。 (http://jkhome2.blog74.fc2.com/blog-date-200609.html) (http://kawawalk.de-blog.jp/blog/2009/02/index.html) |
根津神社(根津権現)(文京区根津一丁目28-9)
御祭神:須佐之男命、大山咋命、誉田別命、相殿大国主命、菅原道真公
| 日本武尊が東制の途中、千駄木の地に須佐之男命を祀ったのに始まる古社で、文明年間に道灌公が社殿を再興した。 (太田道灌公の足跡:http://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-enmt/index1/oota.html) (http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/index.html) (http://www.nedujinja.or.jp/main/k4.html) (http://www.tesshow.jp/bunkyo/shrine_nedu_nedu.html) |
東漸院(台東区上野公園16-3)
御本尊:不明
| 「局沢十六ヶ寺」の1つ。「千駄木」は太田道灌が栴檀(せんだん)の木を植えた地であり、この栴檀木が転訛したとの説がある。 (千駄木:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E9%A7%84%E6%9C%A8) |
局沢十六ヶ寺
| 局沢とは、皇居の西部地区と北の丸の一帯をいう。道灌時代の江戸城は東御苑の一帯で局沢には16の寺が散在し、家康の江戸城拡張で城外へ立ち退きを命じられた。現在正確には判っていないが、日蓮宗5、禅宗5、貝塚の末寺3、真言宗2、天台宗1だったという。 16ヶ寺は、①法恩寺(神田柳原→谷中→亀戸)・②大法寺(小梅村)・③本妙寺(飯田町→湯島本郷→巣鴨5丁目・、④浄心寺(湯島本郷)・⑤本行寺(谷中6丁目)・⑥青雲寺(西日暮里3丁目)・⑦聖徳寺(松が谷)・⑧善徳寺・⑨東光院・⑩東漸寺・⑪地蔵院・⑫祝言寺(以上浅草)・⑬祥雲寺(小石川)・⑭浄土寺(赤坂4丁目)⑮多門院・⑯宝泉寺(以上牛込)という記録もあるが、この中で確実なのは法恩寺・本妙寺・浄心寺・青雲寺・地蔵院・多聞院・祝言寺くらい。世田谷の慶元寺、浅草の清水寺なども局沢にあったことは判っており、この先の研究が必要。 (局沢十六ヶ寺:http://www.geocities.jp/pccwm336/sub1..html) |
品川神社(品川区北品川三丁目7-15)
御祭神:天比理乃咩命(天太玉命の后神・洲ノ神)、素盞嗚尊、宇賀之売命
境内末社:阿那稲荷社、御嶽神社、清滝弁財天社、浅間神社、猿田彦神社
| 社伝によれば、後鳥羽天皇の文治3年(1185)に源頼朝が安房国州崎明神を勧請した。 (http://www.tesshow.jp/shinagawa/shrine_nshinagawa_shinagawa.html) (http://www8.plala.or.jp/bosatsu/sinagawa/sinagawa-jinjya.htm) (洲崎神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%B2%E5%B4%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |
品川寺(品川区南品川三丁目5-17)
御本尊:水月観音、正観音
| 寺伝によると、弘法大師空海を開山とし、大同年間(806-810年)に創建されたという。長禄元年(1457年)、江戸城を築いた太田道灌により伽藍が建立され、寺号を大円寺と称した。中興開山弘尊が承応元年(1652)に再興した。貞享3年7月太田摂津守資直はひそかに寺領100石を寄附した。本尊の正観音は太田道灌の持仏で、長禄年品川の館から江戸城に移った頃、武運の長久と城中及江戸鎮護の為、この本尊を堂内に安置して伽藍を建立した。 (http://www.tesshow.jp/shinagawa/temple_sshinagawa_hinsen.html) (http://honsenji.net/engi.html) (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%AF%BA) |
円福寺(板橋区西台3-32-26)
御本尊:不明
| 文明11年(1479)太田道灌が川越に創建し、慶長13年(1608)にこの地に移転したと伝えられる。ただし、永正10年(1513年)以前に創建したという説もある。道灌が茶室にかけたものと伝えられている青銅製の「雲版」がある。 (http://www.portaltokyo.com/guide_23/contents/c19053enpuku.htm) |
日曜寺(板橋区大和町42-1)
御本尊:愛染明王
| 正徳の頃(1711-1716)に宥慶比丘が小堂を営んだのに始まり、田安宗武(八代将軍吉宗の第2子)の帰依により寺院としての伽藍を整えました。 (http://www.tesshow.jp/itabashi/temple_yamatocho_nichiyo.html) |
西音寺(北区中十条3-27-10)
御本尊:不動明王
| 文明2(1470)年、太田道灌の帰依を受けて玄仲法印が創建したと伝えられている。 (http://news-tool.com/xoops/modules/diary/?cat=25&paged=2) |
静勝寺(北区赤羽西1-21-17)
御本尊:釈迦牟尼如来
| 曹洞宗の静勝寺は、自得山と号し、永正元年(1504年)太田道灌の禅の師匠雲綱が、彼の菩提を弔うため、太田道灌が築城した稲付城跡に道灌寺として創建しました。明暦元年(1655)に道灌の子孫太田資宗が堂舎を建立し、道灌(香月院殿春宛静勝大居士)とその父資清の法号に因んで寺号を自得山静勝寺と改めました。北豊島三十三ヶ所霊場4番札所。 (http://www.tesshow.jp/kita/temple_akabanew_seijo.html) (http://www.kitaku.info/area/akabane-area/ota-doukan.htm) |
王子神社(北区王子本町1-1-12)
御祭神:伊邪那美命、伊邪那岐命、天照大御神、相殿:速玉之男命、事解之男命、境内社:関神社
| 康平年間(1058-65)以前の平安時代に勧請され、当地名由来の神社です。源義家が奥州征伐(前9年の役)の際にはここで祈願をした他、豊島氏、後北条氏らからも崇敬を受け、徳川家康からは天正19年(1591)に社領200石の朱印を賜りました。 (http://www.tesshow.jp/kita/shrine_kita_oji.shtml) 曾て社殿は森深く昼なお暗い幽寂地であり、「太田道灌雨宿の椎」をはじめ、勝海舟の練胆話も伝えられている。 (http://www.genbu.net/data/musasi/ouji_title.htm) |
水神社・関屋天神(墨田区墨田一丁目)
御祭神:不明
| 関屋天神 もともとは関屋の里に祀られていたものがこの地に移されたもの。関屋の里って、源頼朝の命を受け、江戸太郎重長が奥州防備のため関所を設けたところ。が、いまひとつ場所が特定されていない。 (http://yoyochichi.sakura.ne.jp/yochiyochi/cat12/23/cat30/) |
櫻田神社(港区西麻布3-2-17)
御祭神:豊宇迦能賣大神
| 1180年頃に霞ヶ関の地に建立されたといわれ、文明年間(1461~86)太田道灌公は当社の縁起を伝え聞き、直ちに神殿を改修再興され、地領の守護神として崇敬された。また、当時道灌公は太刀甲冑等を寄進され永く当社の御神宝として伝えられたが、「青山火事」により焼失した。1624(寛永元)年に現在のところに遷宮。 (http://futennochun.cocolog-nifty.com/gungungunma/2010/01/2-72e0.html) (http://www.tesshow.jp/bunkyo/shrine_hongo_sakuragi.html) |
天祖神社(港区六本木7-7-7)
御祭神:天照大神、伊弉諾尊、伊弉冉尊
| 南北朝の後小松天皇の御代、至徳元年(西暦1386年)8月16日に、芝西久保、飯倉城山(現在のホテルオークラの南側付近)に、はじめて祀られたと伝えられています。竜土神明宮とは、創建当時、毎夜のように江戸湾から竜が灯明をあげに飛んで来たという伝説から、『竜灯』に由来するといわれています。太田道灌が方五丁の祭田を寄進し、神社の社殿を再建し信仰したことも伝えられています。 (http://futennochun.cocolog-nifty.com/gungungunma/2010/01/post-709f.html) |
久國神社(港区六本木2-1-16)
御祭神:倉稲魂命
| 元は千代田村紅葉山(現皇居内)に鎮守、長禄3年(1457)太田道灌が江戸城を築城の時、寛正6年(1465)溜池の地に遷座し、後に久國作の刀が寄進され、久國稲荷神社と呼ばれるようになりました。永禄3年(1560)境内が公用に属し、寛保元年(1741)に現在地に遷座しました。 (江戸城内由来:http://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-enmt/kami/kami.html) |
千代田稲荷神社(渋谷区道玄坂2-20-8)
御祭神:宇賀御魂神
| 長禄元年(1457)太田道灌が千代田城を築城のおり、千代田郷に古くから祀られていた千代田神社を城内に遍座し守護神としたのが始まりです。その後、家康公が慶長8年(1603)入城し、紅葉山に移して江戸城の鎮守とし、江戸城拡張に当たり、渋谷村宮益坂に遍宮し、神領を寄進したので、江戸城守護及び万民斉仰の神社として、広く参拝を集めました。 (江戸城内由来:http://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-enmt/kami/kami.html) (http://futennochun.cocolog-nifty.com/gungungunma/2010/01/post-709f.html) (http://www.powerspotdb.jp/node/258) (http://www.hyakkendana.jp/chiyoda-inari.html) |
千代田稲荷神社(八王子市裏高尾町957)
御祭神:宇賀御魂神
| 長禄元年(1457)太田道灌が千代田城を築城のおり、千代田郷に古くから祀られていた千代田神社を城内に遍座し守護神としたのが始まりです。その後、家康公が江戸開府の時、三方が原の合戦以後加護を得た白狐の遺骨を祭り、城内紅葉山に移し歴代の将軍家にも鎮護の神とした。幕末の動乱時に大奥に仕えこの稲荷を信仰してきた奥女中の一人がご神体は託され、江戸城を脱出したとされる。以来、大正12年の関東大震災までその子孫の屋敷に祭られていました。現在の地に昭和4年に遍座されました。 (江戸城内由来:http://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-enmt/kami/kami.html) (http://www.takaosan.info/uratakao.htm) |
諏方神社(荒川区西日暮里3-4-8)
御祭神:建御名方命、境内社:末廣稲荷神社、銭降稲荷神社、三宝荒神社、三峰神社
| 元久2年(1205)の創立で、豊島左衛門尉経泰が勧請。文安年間に道灌公が神領を寄進し、徳川時代に神領を賜わり、寛永12年社殿を現在の地に御遷座。 (太田道灌公の足跡:http://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-enmt/index1/oota.html) (http://www.tesshow.jp/arakawa/shrine_wnippori_suwa.shtml) |
荻窪八幡宮(杉並区上荻4-19-2)
御祭神:応神天皇、境内末社:稲荷神社(保食神)、祓戸神社(瀬織津姫神・速開津姫神)、須賀神社(須佐之男命)、琴平神社(大物主命)、御獄神社(太詔戸神)、猿田彦神社(猿田彦大神)、秋葉神社(火之迦具土神)
| 寛平年間(900年頃)の創祀。道灌公らが戦勝を祈願し、社殿の修復や献木(道灌公槇―現存)を行った。 (太田道灌公の足跡:http://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-enmt/index1/oota.html) (http://www.amy.hi-ho.ne.jp/ogikubo-hachiman/page004.html) |
西久保八幡神社(飯倉八幡宮)(港区虎ノ門5-10-14 )
御祭神:品陀和気命、息長帯比売命、帯中日子命、境内末社:宇迦之御魂神(稲荷社)、柿本人麻呂(人麿社)、猿田彦神(庚申社)
| 寛弘年中(1004~12)に、源頼信が、石清水八幡宮の神霊を請じて、霞ヶ関のあたりに創建したという。道灌公が江戸城を築いた時、現在地に遷された。慶長5年(1600)、関ヶ原の戦に、崇源院は戦勝と安全を祈願し、その報賽として寛永11年(1634)社殿を造営した。度々、火災に遭い、宝物・旧記等をことごとく失った。 (太田道灌公の足跡:http://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-enmt/index1/oota.html) (http://www.hachimanjinja.or.jp/main/?page_id=19) |
常盤稲荷神社(中央区日本橋本町1-8-11)
御祭神:倉稲魂命
| 長禄元年(1457)に太田道灌が江戸城を築城の際、京都伏見稲荷大神の御分霊をいただき、常盤稲荷と名付け、同城の守護神として勧請されました。その後江戸時代には、日本橋魚市場内に移り、市場の守護神水神大神(みずは象女神)を相殿に祀り鎮座されました。水神大神は、明治34年に神田神社境内に遷座し、現在に至っています。 (http://www.tesshow.jp/chuo/shrine_honmachi_tokiwa.html) |
いくつか検索では出なかった場所もあるんだが、道灌ゆかりの「静勝寺」や中野区に移ったのいう「金剛寺」などを検索していると、2011.01.21分の「赤羽」に出会い、「水神社」で「隅田川神社」がヒットして、上記の検索の「椙森神社」「日枝神社」「築土八幡神社」「品川神社」や、「市谷亀岡八幡」の「与登比売神」など、「瀬織津姫」が感じられたが・・・。
(赤羽から志村城跡へ:http://blog.goo.ne.jp/fland_2006/c/458cffac9f64a8e5842297aa277ef5a6)
(隅田川神社:http://www.asahi-net.or.jp/~vm3s-kwkm/zue/sumidagawa/index.html)
あと、ほとんどに絡んでくる徳川家だけでなく、菅原道真・頼朝・将門・柿本人麻呂などが御祭神で出てくるあたりや、道灌の父・道真がいたという「越生」には行基が「法恩寺」を建立した際に勧請した「鹿下越生神社」があり、親子で「歌」に通じているあたりなども気になる・・・というか、「古代からのネットワーク」と繋がっていたと想像し、「瀬織津姫」に繋がるのでは、と。
(東武越生線・越生駅:http://yoyochichi.sakura.ne.jp/mt/mt-search.cgi?blog_id=1&tag=%E5%A4%A7%E7%94%B0%E9%81%93%E7%81%8C&limit=20)
(江戸城の遺構:http://hya34.sakura.ne.jp/musasinannbu/edozyou/edoikou.html)
(川越街道:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E8%A1%97%E9%81%93)
(越生の歴史:http://www.town.ogose.saitama.jp/div_soumu/cyousei_youran/ogose-walking/histry.html)
追記(2011.02.11):道灌に興味を持つきっかけとなった「太田姫稲荷神社」ついて考えてみたんだが、「小野篁」が創建したという京都の「一口稲荷神社」は、当時は有名だったんだろうか、と。
(一ロの地名伝承:http://www2s.biglobe.ne.jp/~yamaday/newpage2.html)
「太田姫稲荷神社」について、そもそもは「大物主神」が祀られているところに「倉稲魂神」を勧請した、とあり、「疱瘡神」を祀ったというのは表向きの説明で、「ニギハヤヒ」が祀られていた和歌山の「藤白神社」に行基が「熊野坐大神」を勧請したのに似ているような気がして。
(太田姫稲荷神社:http://kotora888.art-studio.cc/ootahime_fr.html)
(藤白神社:http://www.iris.dti.ne.jp/~min30-3/magoichi/fujisiro.htm)
道灌に関連する神社の御祭神の多くが「怨霊」「疱瘡神」に繋がることや、「小野篁」が冥府と繋がる伝承があることなど、「古代からのネットワーク」が背後に見えるようで、「信玄」「海舟」らと同様に「交易」が経済力になっていることなども、それを示しているように思われて。
ちなみに、2004.08.30分で森氏の著書から検索して書いたように、「一口」という地名は「京都競馬場」の東で旧巨椋池の北岸にあたる地域で、秦氏のテリトリーかと。
ん?道灌と「十一面観音」で検索すると、「「本尊十一面観音は越泰澄(おちたいちょう)の作にして、道灌入道(太田道灌のこと)崇尊の霊像なり。」と記述がある。」と書かれたサイトがヒットし、これも「古代からのネットワーク」との繋がりを示しているのでは、と。
(赤羽界隈案内:http://www.ukima.info/meisho/kaiwai/inatuke/humondo.htm)
| ●2011.02.12(Sat.) |
道灌、信玄、海舟を繋ぐ1つとして「妙見信仰」が見受けられ、その背後には「古代からのネットワーク」が存在し、将門等にも繋がるように思われるのだが、ふと気になったのが「妙見信仰」で繋がるであろう2010.01.27分などでの山口の「大内氏」で、周防国多々良浜に着岸したという「琳聖太子」についてが気になって。
(大内氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%B0%8F)
(第1柱 天之御中主神―6:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=321)
「琳聖太子」は「百済の聖明王の第3王子」とされており、「聖徳太子」との面識があったとされること、「聖明王」からの仏像「善光寺如来」から「聖徳太子」への手紙があったこと、「四天王寺」の守護・鎮守として「聖徳太子」が祀ったという「天王寺七宮」の一宮「堀越神社」の「鎮宅霊符社」が「妙見信仰」に繋がるようであること、山口の「大内氏」や「妙見信仰」が「行基」と繋がるようで。
(善光寺如来と聖徳太子の往復書簡:http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaihou58/kai05806.html)
(善光寺式阿弥陀三尊像:http://www.zenkoji.jp/about/index2.html)
(堀越神社:http://www.horikoshijinja.or.jp/jinja/kamisama/chintaku-san/)
(宇部市・広福寺:http://www.ji-sha.com/teratabi/jisya/jisya_info.php?key_id=073535202000055066822&sub_key=000001)
(山口市・龍蔵寺:http://www.kannon.org/jiin/01/20/index.htm)
(光市・冠念寺:http://saha1702hitomi.web.fc2.com/20040428dainichiichi.html)
(能勢の妙見さん:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E7%B2%BE%E3%81%AE%E4%BB%A3%E5%8F%82)
(赤穂市・妙見寺:http://tabiseto.com/sakoshimyokenji.html)
(妙見と虚空蔵、北辰と明星、破軍星と太白星:http://www.susanowo.com/archives/1658)
(八代神社:http://hayato.com/jisya/myokengu.html)
(円泉寺妙見堂(全国の妙見菩薩):http://www.ensenji.or.jp/myouken.html)
「琳聖太子」で検索して気になったのが、対馬の「元嶋神社」と、河内長野の「建水分神社」に合祀されている「多々羅神社」で、「多々羅神社」(多々良宮跡)は「楠木氏が祀っていたもの」だそうだが、それ以外はよくわからず・・・「百済」の王子を調べてて「新羅」に繋がるあたり、行基の足跡を追っていた時と同じで。
(元嶋神社:http://www.genbu.net/data/tusima/motosima_title.htm)
(建水分神社:http://www.eonet.ne.jp/~kagariyamakanpo/index.files/takemikumari.htm)
(建水分神社:http://7kamado.net/takemikumari.html)
(多々良宮跡:http://kamnavi.jp/en/kawati/siraki.htm)
(河内の新羅神社4:http://www.shiga-miidera.or.jp/serialization/shinra/140.htm)
ただ、「建水分神社」には「瀬織津姫」が祀られているし、「妙見信仰」について「地域によっては水神、鉱物神・馬の神としても信仰されたました。」ということや、「羽黒山(羽黒彦命・玉依姫命・九頭竜王)-聖観音菩薩、軍荼利明王、妙見菩薩とする神仏習合関係を結ぶ。」とあることなど、「古代からのネットワーク」や「瀬織津姫」に繋がるようで。
(日本石仏協会談話室資料:http://www.ensenji.or.jp/img/pdf/09.pdf)
「湊川神社」の楠木正成墓碑の台が「亀」であること、2007.05.26分での小浜の「空印寺」にある「八百比丘尼縁起」で「道満」が「亀」に乗っていること、、「浦島太郎」伝説などの「亀」に関連する事柄には、「妙見信仰」が絡んでいると考えられそうで、「古代からのネットワーク」を示すものでもあるのでは、と・・・。
(湊川神社:http://www.minatogawajinja.or.jp/history/)
(浦島太郎:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E5%B3%B6%E5%A4%AA%E9%83%8E)

「明月記」を買うべきかどうか迷いつつ、懲りずに「古今伝授」で検索して「古代からの暗号」さんのサイトを拝見していると、「古今伝授の<呼子鳥>は日本書紀の雄略紀に載る<呼子の加唐島>で生まれた<百済の武寧王>を<嶋君(セマキシ)>と名付けられたと述べたが、武寧王の諡号が<斯麻王>であることも考えると、大山積神の<御嶋>とは<武寧王>を指す<みしま>の可能性があると思われる。」とあった。
(女郎花と鵲ー3:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/223e637ec527e6cb39e4093d445d3071)
(謎解き 呼子鳥:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/8ad9f110274b622c0ec7679d5febf8d3)
(女郎花と鵲ー2:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/a50bb949c2efcb786a6e87a0e8e29d3a)
「笠沙碕は<かささぎ>=<鵲>で<百済>を指している」とされていることや、「出雲系の人々にとって<サギ(百済・天神)>は恐ろしいもの。百済系の人々にとって<出雲(国神)>は祟りをなすもの。と考えられていたと思われる。」とあることなど、興味深いですよね、2011.01.19分の「鷺大明神」は「サギ」に、「稲背脛命」が「萩」に繋がると思われることから「怨霊」に繋がると思われるので。
しかし・・・「馬子」が「嶋大臣」で「武寧王」(嶋君・斯麻王)と関連が?で、「御嶋」と「馬子」と「武寧王」に関連が?・・・武寧王陵の棺材が日本にしか自生しない「コウヤマキ」だそうだが・・・武寧王の子が聖明王で・・・うーん。
(武寧王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AF%A7%E7%8E%8B)
(聖明王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E7%8E%8B)
そうした蘇我氏と三島の繋がりは、先日の鎌足が蘇我氏を語って摂津の三島を乗っ取ったという推測に繋がるように思われ、さらに不比等が伊豆の三島で賀茂氏のテリトリーを乗っ取り、「木綿」を納めさせ、「採物」として「隼人の俳優」を舞わせていたのかも、と。
(三島木綿:http://dic.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&p=%E4%B8%89%E5%B6%8B%E6%9C%A8&fr=dic&stype=prefix)
(まつりの俳優・隼人:http://www4.synapse.ne.jp/yatusiro/newpage4.html)
(アラセツ:http://www3.pref.kagoshima.jp/kankou/blog/picup/2008/08/post_33.html)
(アラセツ:http://www.town.tatsugo.lg.jp/ibennto/arasetu/kinensi.pdf)
「笠沙路探訪」さんが書かれていた「園韓神祭」と繋がるであろうとされている「今宮戎神社」も、「四天王寺」の鎮護として祀られた、とされているんですよね・・・太子を通しても、「妙見信仰」と「瀬織津姫」が繋がるように思われるわけで。
(今宮戎神社:http://www.imamiya-ebisu.net/htm/top.html)
そうそう、折口氏が興味深いことを書かれてますね、「過去の人及び神を中心として、種々の信仰網とも言ふべきものが、全国に敷かれて居」て、それは「巡游伶人」によるもので、それを「深く成就して行つた」のは「海部の民たち」で、「山の聖水によつてする禊ぎを勧める者が多く游行した様に思はれる。」と・・・つまりそれは「隼人」である「秦氏」ら「古代からのネットワーク」によって、信仰が各地に伝えられたということなのでは。
(折口信夫 唱導文学 ―序説として―:http://www.aozora.gr.jp/cards/000933/files/47188_35992.html)
追記(2011.02.13):去年の今頃検索した「朱蒙」が関連してくるのだろうか・・・2010.02.28分では「億うそ」さんのサイトで「朱蒙(鄒牟)」は「日月王」で「住吉大神」とされていたことを引用させていただいていて、2008.09.24分では「朱蒙」の子が百済「温祚王」とあるのを引用させていただいていて。
(百済氏考:http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-30.html)
上記サイトにもあるように、「朱蒙」の別名が「東明聖王」「東明王」「鄒牟」「衆解」「都慕王」で、「武寧王」の子「聖明王」に似た名もあり、「知られざる古代」という本には「東海の龍宮から来たという脱解王」と書かれていて、2010.02.28分の検索では「朱蒙の母・柳花は「河伯」の娘で、鴨緑江の河神」とあり、「瀬織津姫」との関連が気になるところで。
そして「聖明王」がもたらした「善光寺如来」との関連も・・・って、どう調べたらいいんだろうか。
(東明聖王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%98%8E%E8%81%96%E7%8E%8B)
(温祚王建国神話:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E7%A5%9A%E7%8E%8B#.E5.BB.BA.E5.9B.BD.E7.A5.9E.E8.A9.B1)
(河伯:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E4%BC%AF)
(洛嬪:http://myrmecoleon.sytes.net/iib/view/LPN001.html)
(檀君神話:http://homepage2.nifty.com/jiyudaigaku/kannkoku/sinnwa.htm)
(鄒牟(住)は日月の子とは?:http://www31.tok2.com/home2/okunouso/moksirok/timei.html)
そういえば、「赤羽」と「古代からのネットワーク」や「瀬織津姫」などの繋がりが見えたように思えるが、そもそも2011.01.19に「赤羽」を調べるきっかけとなったのが「三日月神社」でしたね・・・。
「三日月」というと2007.04.18分などでは「キリスト」絡みで、2009.04.29分では「摩利支天」絡みで調べたりもしてますね・・・。
で「億ウソ」さんの上記URLでは「朱蒙」(鄒牟王)は「スキタイに出自を持つ好太王」ともあって、なけなしの脳みそが蒸発しそう・・・。
(好太王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%BD%E5%A4%AA%E7%8E%8B)
| ●2011.02.19(Sat.) |
体調がイマイチで「朱蒙」(鄒牟王)や「武寧王」「聖明王」の考察がまだできていないが、「億ウソ」さんのサイトの今月号のところに「大山咋神」について書かれていて、「ジャムシのカミであったことになる。」とあった。
(日枝山を偽称して山王権現に収まった比叡山のウソ:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/10nen/1102hie.html)
(茶臼:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/0305cha.htm#tyawszin)
「ジャムシのカミ」とは「黒龍江省佳木斯」の神のようで、「億ウソ」さんのサイトについての私の解釈が間違ってなければ、「オボ(意富)(大日)」の神で「扶余」の「大日女」(大日霎貴)のことで、「妙見信仰」に繋がり、「瀬織津姫」に繋がると思われるわけで。
(地名黙示録:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/moksirok/timei.html)
ただ、かつて「暗号 山上憶良」さんのサイトで「斯鬼宮」が「雄略天皇」の宮か否かについて書かれていて、「稲荷山鉄剣」に天皇の宮に「鬼」という字を用いているのならば、「鬼道」にしても「大日」を「鬼」と読んだとしても、当時は今のような意味を持ってなかったのではないか、と。
(「斯鬼宮」を雄略天皇の宮としてよいだろうか:http://www.geocities.jp/yasuko8787/o-224.htm)
(金錯銘鉄剣:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E9%8C%AF%E9%8A%98%E9%89%84%E5%89%A3)
「日枝を「稗」にすり替えた」ように、藤原氏、というか、「不比等禍」なのでは。
(【鬼】は、本当に化け物なのか?:http://iwamikagura.web.fc2.com/oni1.html)
ひょっとしたら、のちにそれを逆手にとって「タタる神」としたのかもしれないが、2004.03.10分での「おかめ」のように、昔の「美人」が後世では逆の意味になっていることがあるし・・・って、自己弁護っぽい。(苦笑)
(おかめ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%82%81)
話を戻しますが、「ジャムシのカミ」について書かれている上に「山城」などの地名について書かれていて、秦氏がテリトリーで「ジャムシのカミ」を祀り、不比等による隠蔽工作の対抗手段を、「祟(タタリ)」など「意富比」からの転訛で見られるようですね。
そうそう、「億ウソ」さんのサイトによると、スキタイ王=鄒牟王=好太王=住吉大神のようで、「スミ」が鄒牟王の足跡ならば、「大隅隼人」は「勿吉」等との繋がりをもち、物部氏など「古代からのネットワーク」に繋がることになるのではないかと思われるわけで。
(地名黙示録:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/moksirok/timei.html)
「阿多隼人」も「阿多」が「中(アタる)」になるようで、「大隅隼人」同様「匈奴・フン族」に繋がるようで、「嶋」は「武寧王の斯麻(シマ・嶋)」に繋がり、「司馬氏」に繋がるような・・・。
(「あっち向いてホイ」にはめられた検定日本史のウソ:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/hun/0803hune.html)
(歴史の隠蔽を担った神々のウソ:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/new/04emisi.htm)
(「中央」という名のメタファ:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/0301.htm)
ということで、「藤原氏もまた解字的には「アタ(中)オミ(臣)」となる」ことについて、「どう理解したらよいのか。」とあるが、「ただのサルまねかもしれないが……」と書かれた通り、というか、「奈良の神鹿が鹿島神宮から来たってことは……」で「磐裂神」「鹿見塚神社」について書かれているのを拝見し、不比等らによってトーテム・御祭神ごと乗っ取られた証しと言えそうだな、と。
(アチオミとアタオミ(中臣)に差異はあるか?:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/identity/toppage.html)
(アテルイのルーツはスキタイか根裂(ねさく)か:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/moksirok/timei.html)
(鹿見塚の神鹿伝説:http://www.geocities.jp/gotos_room/_geo_contents_/shinroku.html)
で、「鄒牟王(4・5世紀)時代の記憶「日月」」が、「(坂上田村麻呂の)東北遠征の百済官吏によって当地に持ち込ちこまれた」のであれば、やはり実際には「蝦夷征伐」ではなかったように思われ、「百済ヤマト」は故意に「日本の歴史にモザイクを掛けてきた」のではなく、「行基プロジェクト」のように藤原氏らの「乗っ取り」から守るため、他の字をあてたのではないかと・・・。
(イルワル(日月)の隠蔽に腰割の字:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/hun/0705yohgoe.html)
(十一(東夷)観音に託した東一のnigui:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/hun/1007higci.html)
(「中央」という名のメタファ:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/0301.htm)
あ、「十一面観音」について書かれていたところに、石川県加賀市の「十一町」の南に「東横町」があることから思い出したが、「横」は「愛(宕)」「日(向)」と同じで「邑婁」とされていることは、「大山祇神社」の元宮「横殿宮」の「横殿」も「邑婁と勿吉の合体名」の可能性もあり、それを越智氏は言わんとしていたのかも・・・。
(なぜ日向の逆さ地名、向日があるのか:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/nimaru.htm)
(しんがり(殿)とは吉野ヶ里のことだ!:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/moksirok/timei.html)
追記(2011.02.20):「億ウソ」さんのサイトで、「扶余の夫がOTTOなら歴史は変る」という見出しがあり、「紀元前匈奴に染まったアマル族が存在したことになる。」とのことで、その逆の「アマル族に染まった匈奴」もいたのではないかと考えることもできるように思われ、そのどちらになるのかは何とも言えないが、秦氏など「行基プロジェクト」の氏族はそれにあたるのではないかと、「賀茂氏」との繋がりから思えるわけで。
(http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/hun/0808atta.html)
(蛇も蚊も:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/hun/0712kamkra.html)
「ヤクザとヤクス(薬師)は「茶臼」の裏表だ」という見出しのところに、「新井薬師」などの薬師堂について「ジャクズ(弱水・沃沮)隠しに他ならない。」とあり、こちらでも「神仏習合による新手の神隠し」と言われているように思えたが、それは藤原氏と他の氏族を同じように捉えておられることからではないかと・・・。
(http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/hun/0709yakza.html)
2011.01.27分で引用させていただいたように、伊豆で藤原氏(中臣氏)が「三島明神」の名をもって、「事代主神」を信奉する賀茂一族の領地を乗っ取ったと思われるふしがあり、朝廷からの御祭神の変更の際、もし越智氏が「横殿宮」を祀っていなければ、もし行基プロジェクトによる「南光坊」の奉祭がなければ、藤原氏にすっかり乗っ取られてしまっていたのではないかと・・・。
ただ、それを裏付ける文献はなく、今まで書いてきた中で感じたことだから、私の思い違いだと言われればそれまでなわけだが・・・。
だけど、全てを消してしまう、隠してしまうつもりだったのなら、秦氏の末裔が「風姿花伝」などで芸論に紛れ込ませて何かを伝えようとしたのは何故なのか、また、藤原定家が「百人一首」などにメッセージを含ませるようなことをしたり、「古今伝授」があったり、「万葉集」が編集されたであろう形跡が見えるのは何故なのか。
(万葉集が成立したのはいつか:http://www.geocities.jp/yasuko8787/kokindenzyu-10.htm)
「千葉市に多い大日もまた意富比でルーツは邪馬壱だ」という見出しのところには、「蘇我と邪馬壱は平和的に共存していたことを物語っている。」とあり、千葉には行基の足跡も多くみられ、蘇我氏以外にもそういう氏族があったかもしれないのではないかと思えるので、「行基プロジェクト」の足跡を再度見ていきたいですね。
(http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/hun/0801yabai.html)
たしか「秦氏の研究」で多氏と秦氏に繋がりがあることを書かれていたように思うので、まずは「秦氏の研究」を読み直してみようかと。
| ●2011.02.21(Mon.) |
まず、12日分の訂正をしなければ・・・「秦氏の研究」によると、「採物」として「三島木綿」を用いた「隼人の俳優」の舞いは、祭祀が始まったころからのならわしのようで、秦氏の童女もそれに関わっていて、その子たちを養育してたと思われるのが、多氏と同祖の「小子部氏」のようで。
(子部神社:http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/ou-kobe.html)
(子部神社:http://kamnavi.jp/as/taketi/kobe.htm)
だから不比等は乗っ取った人脈を利用していたようですね、神域を乗っ取ったことによってそのなわらしを、さも自分の力によって継続させてやっているのだからと、金品を納めさせていたんじゃないでしょうか、祭祀のすべてを中臣氏に明け渡さなかったからと。
そうして得た利益を元手に、さらに乗っ取りを拡大していったのでは。
そう考えると、独自の祀り方に変えていかなければ、「方便の神」の名をもってさらに乗っ取られ、財産をしぼりとられて祭祀もままならなくなっていくので、中国に対しての文化的水準の表明のみならず、独自の祭祀を広める方法として、仏教に一層力を入れることになったのかも・・・。
うーん、やはり私は間違っていたのか?と・・・。
「古代からの暗号」さんのブログで、「暗号 山上憶良」さんの解読された内容と、ご自身が「万葉集」巻八の山上憶良の「秋の七草」の暗号から解読された内容から、「出雲=鵜伽耶=倭=杉を祀る人々」すなわち「倭」を討ったのは秦氏、ということが導き出されたようで。
(字母歌に仕組まれた暗号 はじめに:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/849bd5f6bdaff92f729c88059d8dd0a7)
(字母歌に仕組まれた暗号 「いろは」3:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/952de63757ecedc827e3337f73e4db41)
西行や芭蕉が詠んだ「雁」は秦氏のことだったのだろうか・・・行基や関連する職能をもつ氏族たちの「行基プロジェクト」は、それをふまえた上での活動だったのだろうか・・・。
だけど、「<国つ神である出雲の大国主命を天つ神である天穂日命が祀っている>という矛盾は、<餅が白鳥に化した>という稲荷縁起と一体のものではないかと思われる。」とされていることから、戻らなかった「天穂日命」は、昨日書いてた「アマル族に染まった匈奴」のように思われ、秦氏もそれと同じだったのではないかと・・・「染まった」というか、信仰が元に戻ったということも考えられそうだが。
(伏見稲荷神符 餅と国譲り:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/c379ec621f05a3a54df2bd8cb6b85b7c)
また、<餅が白鳥に化した>という「稲荷縁起」には、何かしらの疑問があって・・・。
(狐と瀬織津比咩:http://dostoev.exblog.jp/i217/)
(稲荷神社と「ヨハネの黙示録」(その1):http://kojiki.imawamukashi.com/05kosatu2/05inari01.html)
(折上稲荷神社:http://kata.wablog.com/747.html)
それにしても、「古代からの暗号」さんってすごいですね、「秋の七草」と「古今伝授」の「三木三鳥」を解読されたのを一覧表にされていて・・・「宇佐も宮熊野も同じ神なれば伊勢住吉も同じ神々」(後奈良院御撰何曽)の頭文字で「うぐいす」が浮かび上がり、「百千鳥」が「隼人」のこととは・・・。
(暗号解読 一覧表:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/2a3c4005e3f7a7510d84d50502ee162b)
(謎解き 百千鳥(ももちどり):http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/3a613911960c581d55a402186d919a37)
「日本書紀」によると「応神天皇14年に弓月君(新撰姓氏録では融通王)が朝鮮半島の百済から百二十県の人を率いて帰化し秦氏の基となった。」とあるが、「日本書紀」に載ってない場合もあったと思われるので、「日本書紀」に載っている人々が、はるか昔に渡来していた同族と合流した可能性もあるのではないか、と。
(秦氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E6%B0%8F)
だとしたら、「紀元前匈奴に染まったアマル族が存在したことになる。」のではないかと思われ、それが東北方面にあったと思われる「扶桑国」だったのかも。
(扶桑:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E6%A1%91)
| ●2011.02.22(Tue.) |
うーん、秦氏は利用されてたんじゃないのかな、不比等に。御縁起にあるという「餅が白鳥に化した」件についても自ら書くようには思えず、「風土記」の著者による何かがあったように思われるのだが・・・たぶん、秦氏は恨みを買う立場に立たされたんじゃないかな、不比等のせいで。あるいは中臣氏と縁のある「吉田兼倶」によるものかも。
(山背國風土記逸文・伊奈利社:http://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/fuudo/itubun/itubun07.htm#yamasiro)
(卜部氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9C%E9%83%A8%E6%B0%8F)
かつて「伏見稲荷大社」にお参りした際、「深草 稲荷」という冊子を購入していて、それを昨夜読み返していたら、2011.01.07分で「賀茂探求」さんの「伊豆/三嶋大社」から引用させていただいた話と同じ内容のことが書かれていて、それで気になって検索してみた。
すると、「和銅年間(708~715年)(一説に和銅4年(711年)2月7日)に、伊侶巨秦公が勅命を受けて・・・」とあり、「トコロテン遷座」は秦氏の意志のみによるものではないようで、「松尾大社」もまた「勅命」による社殿造営で、不比等の指示によって費用の負担を強いられたのでは。
(伏見稲荷大社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E5%A4%A7%E7%A4%BE)
(藤森神社:http://kamnavi.jp/yamasiro/fujinomori.htm)
(松尾大社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B0%BE%E5%A4%A7%E7%A4%BE)
「松尾大社」の社殿を創建したとされる「秦忌寸都理」は「伊侶巨」の弟とされる説があり、「饒速日命之後也」とあるそうで「越智氏」と同じかと思われ、秦氏の中でも物部氏に繋がる人物に、不比等は乗っ取りの狙いを定めたのでは。
(伏見稲荷大社:http://www5e.biglobe.ne.jp/~hidesan/fushimiinari-taisya.htm)
(京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏:http://blog.livedoor.jp/susanowo/archives/50087709.html)
(『新撰姓氏録』氏族一覧2(第二帙/神別):http://homepage1.nifty.com/k-kitagawa/data/shoji02.html)
で、「伊侶巨秦公」について検索したところ、「『山城国風土記』逸文で秦中家忌寸の祖とされる人物」とあり、「中家忌寸」について吉野裕氏は「産鉄族を代表する一分派」とされているそうで、「ナ」とは「アルタイ語系の土地を表す言葉である」と「日本書紀」の補注にあるそうで。
(秦伊侶具:http://kotobank.jp/word/%E7%A7%A6%E4%BC%8A%E4%BE%B6%E5%85%B7)
(中家忌寸:http://blogs.yahoo.co.jp/sunekotanpako/30361623.html)
産鉄については「深草 稲荷」にも「刃物造りに適した地」であることが書かれており、特に「稲荷山周辺の粘土や赤土」が「焼き入れ」に適していたそうで、「伊侶巨」は先に渡来していた同族あるいは近い間柄の氏族のもとで、新しい技術をもって産鉄業を営んでいたのではないか、と。
ウラに藤原氏が絡んでいることについては、天長4年(827)に「大中臣雄良」が遣わされて「従五位下の神階が授けられた」とあるが、そのまま神祇官になって雄良の子・有本も神職についているのがその証しなのでは。
(稲荷社のあけぼの:http://inari.jp/b_shinko/b01c.html)
(大中臣有本:http://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B8%AD%E8%87%A3%E6%9C%89%E6%9C%AC)
で、「深草 稲荷」に俊成の「夕されば野辺の秋風身にしみてうずら鳴くなり深草の里」が載っていて、「古代からの暗号」さんのブログによると、「うずら」は「鶉鳥→鶉獲り→鵜づ羅獲り→鵜の羽を葺き草とした屋根を葺き終わらない意味の鵜伽耶(海人系伽耶)を獲る」とあり、不比等による隼人征圧をにおわせるような歌のようで。
(謎解き詠花鳥和歌 薄と鶉ー6:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/9fbfea2f543dcac4b215fde1eb9a6efd)
「深草 稲荷」に「稲荷神」の白狐の名が書かれていて、それがいつの頃からのものかは不明だが、「上の社」は「小薄」だそうで、その名も「伽耶」に繋がるのかも・・・。
そうそう、「伏見稲荷大社」で検索していると、「薩都神社(祟り神伝説)」と書かれてリンクがあり、拝見していたところ、こちらもまた藤原氏(中臣氏)による乗っ取りがあったのではないかと思われる内容だった。
(薩都神社(祟り神伝説):http://audience.studio-web.net/HDdiarypro/diary.cgi?no=116)
ML「西行辞典 第163号」が届き、その中に上賀茂神社の棚尾社に幣の奉納を取り次いでもらい、四国への旅立ちに際して詠まれた歌があり、それを読んでいてふと、西行は賀茂での祭祀が変えられてしまわぬように、見張りながら瀬織津姫への想いを詠んでいたのかも、と。
かつて「北面の武士」で身元がある程度知られていて、なおかつフリーの身でなければできないだろうし、かと言って警備員のようには張り付いていられないだろうから思いを歌に託した・・・鳥羽院と志を同じくし、歌の才ある人たちが選ばれて、そういう任務を与えられた、もしくは望んでその道を選んだのでは・・・というのは、考えすぎかな?
追記(2011.02.23):神奈備さんの掲示板「青草談話室」で、生田氏が「神社仏閣にたむろする男たちの日常業務は、昔日の医師団だった・・・・・が、浮上しました。」と書かれていた・・・西行もひょっとしたら・・・?
(青草談話室5904:http://ucgi.kamnavi.net/cgi-bin/aokbbs.cgi)
追記(2011.02.24):「秦伊侶具」が「鴨県主久治良」の子、「秦都理」が「鴨禰宜板持」と兄弟、という説もあるそうで。
(古代豪族・賀茂氏の氏神として知られる神社:http://bell.jp/pancho/travel/hata/preface.htm)
| ●2011.02.23(Wed.) |
今月の初めに拝見した「ISIS本座 - 高橋秀元 バジラな神々」さんの「第5柱 可美葦牙彦舅尊―4◎西播磨の蘇我氏・秦氏とアシカビ幻想」にあった、「宇麻志神社」が気になってまして。
(第5柱 可美葦牙彦舅尊―4:http://www.honza.jp/author/3/takahashi_hideharu?entry_id=1211)
(相生の伝説:http://www.aioi-city-lib.com/bunkazai/den_min/den_min/densetu/15.htm)
(相生の伝説:http://www.aioi-city-lib.com/bunkazai/den_min/den_min/densetu/18.htm)
(副島隆彦の学問道場:http://www.snsi.jp/tops/kouhou/1388)
「宇麻志阿斯訶備比古遅神」が祀られているが、幕末までは「蘇我馬子」を祀っていたそうで、その近辺では秦氏と蘇我氏の足跡が伺えるようで、「宇麻志神社」の社名についても、志阿斯訶備比古遅神の「宇麻」と、蘇我馬子の「馬」の「共音性から、両者が結びつけられて祭神となった」と社伝にあるらしい。
が、私はニギハヤヒの子「ウマシマジ」も浮かんでくるわけで、馬子のヨメが物部氏とされていることなどから蘇我氏と物部氏が無関係とは思われないので、神社近辺の物部氏の足跡の有無が気になるが、今のところ検索ではわかりかねていて。
「久富保」という地名からナガスネヒコが絡んでいそうで気になるし、定家もまた絡んでくるあたり、何かありそうなんだが、よくわからず・・・。
(矢野荘と藤原定家:http://www.aioi-city-lib.com/bunkazai/den_min/den_min/densetu/16.htm)
推測なんだけど、って、ここのお部屋はほとんど推測で書いてるので改めて書くのも何ですが、鎌足が摂津の三島に別邸があったことや、不比等が物部氏系の神域などを乗っ取ろうとしたきっかけとして、日本書紀で徹底的に悪役にした蘇我氏に何かがありそうで、それで相生のことが気になったわけで。
まだ一部しか拝見してませんが、「天璽瑞宝」さんのサイトの「物部氏所縁の史跡」を拝見していると、やはり中臣氏が入り込んでいるだけでなく、蘇我氏所縁の神社にも入り込んでいるので、ひょっとしたら、と思って。
宇佐同様、伊豆の「三嶋大社」にも神職に物部氏がいたようなので、賀茂氏・秦氏も関係していると考えられ、伊豆の「三嶋大社」の本来の御鎮座地とされるのが三宅島の「富賀神社」だそうなので、共通点がありそうな相生で何か見つかれば、とも思ったわけだが・・・。
(三嶋大社:http://www.mishimataisha.or.jp/)
(三嶋大社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B6%8B%E5%A4%A7%E7%A4%BE)
(三嶋大社:http://mononobe.nobody.jp/tabi/mishima/izu.html)
(三嶋大社:http://www.genbu.net/data/izu/misima_title.htm)
(矢田神社:http://mononobe.nobody.jp/tabi/yata/tango-yata2.html)
(矢田部氏:http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/north/s_3sima.html)
(若建命:http://mononobe.nobody.jp/jinbutu/mononobejinbutu3wagyou.html)
(富賀神社:http://www.miyakejima.com/toga/history.htm)
(富賀神社:http://www.genbu.net/data/izu/toga_title.htm)
あと、静岡県掛川市の「和田岡古墳群」のあたりに「旧和田岡村・曽我村」があったそうで、古墳の被葬者と思われる「素賀国造」は、「その始祖を神武朝に国造に任じられた美志印命とする伝承を持ちます」とあり、「美志印命」が「宇摩志麻治命が元になって作られたもの」ではないかと太田亮氏、谷川建一氏、原秀三郎氏らが考えておられるとあることや、実家近くの「池上・曽根遺跡」周辺に物部氏・秦氏らの足跡が見られることなどから、「ネットワーク」を形成していた痕跡がみられるようだが、な~んかひっかかることがあって気になったわけで。
(和田岡古墳群:http://mononobe.nobody.jp/tabi/soga-saya/wadaoka.html)
秦氏の末裔とされる「長宗我部氏」の名の中に、ナガスネヒコの「長」が、「宗我部」には蘇我氏(曽我氏等)が感じられ、物部氏の足跡の見える「曽」のつく地名にも「蘇我氏」が見えるように思えて、そのあたりを鎌足・不比等はターゲットにしたように思えて・・・。
とりあえず、今のところわかっている蘇我氏ゆかりの神社と、物部氏の神社に中臣氏が入り込んでいる形跡がみられる場所等を覚え書きしておこうかなと・・・ただ、今日の検索では蘇我氏・物部氏・秦氏らに関する新たな発見は期待薄な感じだったので、続きが書けるかどうか・・・。
| [ 蘇我氏ゆかりとされる神社 ] | ||
| 蘇我比咩神社 | : | http://www.geocities.jp/engisiki02/shimousa/bun/smf200202-01.html http://blogs.yahoo.co.jp/natuoba3/8927733.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%87%E6%88%91%E6%AF%94%E3%82%81%E7%A5%9E%E7%A4%BE |
| 宗我都比古神社・入鹿神社 | : | http://www.geocities.jp/rekisi_neko/soga.html |
| 蘇我神社 | : | http://tosareki.gozaru.jp/tosareki/aki/sogajinja.html |
| [ 「天璽瑞宝」さんのサイトの「物部氏所縁の史跡」で「中臣(藤原)氏」の名が出てくる神社 ] | ||
| 木嶋坐天照御魂神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/konosima/index.html |
| 枚岡神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/hira/hira.htm |
| 謁播神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/mikawa/atuwa.html |
| 乃伎多神社と物部古墳群 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/nogita/mononobe-kohun.html |
| 伊香具神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/ikago/index.html |
| 因佐神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/izumo-hutu/wakahutunusi.htm |
| [ 「天璽瑞宝」さんのサイトの「物部氏所縁の史跡」で気になった神社等 ] | ||
| 天田神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/morikohun/kaminari.htm |
| 福王神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/hodumi/hotumi.htm |
| 府八幡宮 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/irimi/irumi.html |
| 淡海国玉神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/tootoumi3/index.html |
| 山名神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/yamanashi/yamana.html |
| 七ツ森神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/kunube/kooribe.html |
| 那閇神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/nahe/nahe.htm |
| 浅間大社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/sengen/index.html |
| 物部天神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/irumnnb/kitano.htm |
| 信太の流れ海 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/sida/sida.htm |
| 多岐神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/tagi/tagi.htm |
| 小内神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/oti-s/woti.htm |
| 飯豊比売神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/iitoyo/index.html |
| 荒嶋神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/arasima/arasima.html |
| 麻気神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/maki/make.html |
| 神田神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/kamta/index.html |
| 物部神社(佐渡国雑太郡) | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/sd-mono/mononobe.html |
| 引田部神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/hikitabe-sd/index.html |
| 須波伎部神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/suhaki/suhakibe.htm |
| 物部神社(丹後国与謝郡) | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/tango-mono/mononobe.htm |
| 矢田神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/yata/tango-yata2.html |
| 物部神社(但馬国城埼郡) | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/tajima-mono/mononobe.html |
| 神門の首長墳 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/kando/index.html |
| 生石(おうしこ)神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/houden/oushiko.htm |
| 建布都神社・赤田神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/takehutu/hutu.htm |
| 布都神社 | : | http://mononobe.nobody.jp/tabi/hutu/hutu.htm |
| [ 鎌足の足跡 ] | ||
| やましなを歩く栗栖野周辺と中臣遺跡 | : | http://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000012080.html |
| 山階寺跡 | : | http://www.city.kyoto.jp/somu/rekishi/fm/ishibumi/html/ya093.html |
| 談山神社 | : | http://www.tanzan.or.jp/history.html |
| 談山神社他 | : | http://sakuraoffice.com/huziwaranokamatari.html |
| 大原の里 | : | http://bell.jp/pancho/travel/asuka-ji/ohara_no_sato.htm |
| 藤原鎌足の常陸出自説を追う | : | http://blogs.yahoo.co.jp/toyoura_denske/folder/950311.html |
| 大伴連咋子 | : | http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/kuiko.html |
| 藤原鎌足を考える | : | http://www2.plala.or.jp/cygnus/s5.html |
| ●2011.02.24(Thu.) |
12日に太子が祀ったとされる「天王寺七宮」のうちの「堀越神社」についてちらっと書いたが、「妙見信仰」との繋がりが見えるようでも、場所としては四天王寺の南西だから、方角は関係ないのかなと地図を見ていて「ん?」と。
そういえば「大江神社」は「乾(北西)の社」とあり、「大江神社」に合祀された「上之宮神社」は「北東の守りとされた」とされていて、地図で見ると軸が少しズレているようで。
(大江神社:http://www.ooejinja.net/yuisho.html)
(上之宮町会の紹介:http://www.ocec.ne.jp/es/gozyou-es/uenomiya.htm)
(蔵鷺庵:http://www.ueroku-wake.net/cgi-bin/shops/detail_60.php)
とすると、四天王寺の北にあたるのは「生国魂神社」のようだが、かつては大阪城近くだったのを秀吉が遷座させたので、そもそもは何があったのかを知りたかったが、検索では出てこなかった。
(生國魂神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%9C%8B%E9%AD%82%E7%A5%9E%E7%A4%BE)
(生國魂神社:http://www.genbu.net/data/settu/ikukuni_title.htm#osaka)
(生國魂神社:http://kamnavi.jp/ym/osaka/ikutama.htm)
ただ、四天王寺が今の場所に建てられる前の候補地(?)みたいなのが、豊里大橋近くや大阪城近くにあったという説もあり、「天王寺七宮」が太子によるものかどうかも疑問っちゃ疑問だが・・・。
(豊里大橋:http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000030580.html)
(四天王寺:http://www.bell.jp/pancho/travel/taisi-siseki/temple/sitenno_ji.htm)
| ●2011.02.25(Fri.) |
神奈備さんの「青草談話室」で書かれている生田氏の説、興味深い&お勉強になります。
(http://ucgi.kamnavi.net/cgi-bin/aokbbs.cgi)
ということで、少々引用させていただくと、「イナリとは、田んぼに水を入れることを中心とした概念から意転したものと見受けられます。」とのことで、伏見稲荷の御由緒のこじつけ感は否めないような。
「新羅神社」「白髯神社」等は、「台湾アミ語の tsilar(太陽)、沖縄のテダと同根。」とのことで、ヒボコやニギハヤヒが浮かんできますね。
「便宜上タジク人とよびますが」とあるのは、鎌足のことと思われるものの、「タジク人」がわからないので検索したところ、「タジキスタンを中心に、アフガニスタン北部、ウズベキスタン東部、中国領新疆ウイグル自治区の西部などに居住するペルシア系民族を指す近現代的民族区分。」とあり、なるほど、と。
(タジク人:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AF%E4%BA%BA)
で、中大兄皇子は「タジク系勢力の一つを(インド流の)バラモンに仕立て上げること」が課せられた天命とのことだが、このあたりはいまいちよくわからず・・・でも、「puja(尊敬、礼拝)、wara……意訳少々で、氏子。→ 藤原。」は興味深い。
鹿島も「タジク語」からのものとされてますが、私としては鹿島と鎌足が本当に繋がるのかどうか、と・・・。
「薬師」について、「 iya(弥々)*kus(健康、シヤワセ) i(神)」に分解できるそうで、「弱水(佳木斯)」も実はそこからのネームングなのかも?なーんて思ったりして。
「ジャムス市は黒竜江省東北部、アムール川、ウスリー江、松花江が合流する三江平原に位置する。」とあり、「三江平原」がちょっと気になった。
(佳木斯:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%A0%E3%82%B9%E5%B8%82)
(黒竜江省ホーム:http://www.ne.jp/asahi/overland/japan/heilongjianghome.htm)
そうそう、「南無三」についてちらっと書かれていて、ふと「三宝」の「仏・法・僧」が気になった・・・というか、果たしてそうなのか?というか、ウラの意味がありそうな・・・「三光神社」の「日・月・星」あたりじゃないかと・・・三位一体となると「明星」?
(南無:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%84%A1)
(三宝:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%AE%9D)
2003.04.11分では、「金星」からの検索でヒンドゥー教の暁の神「アルナ」に行きつき、「アルナ」と「蛭子」がだぶって見える気がして、と書いているが、「アルナ」について書かれているのを拝見していると、当時は知らなかった「瀬織津姫」が今は見えるようで。
(ヒンドゥー教:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BC%E6%95%99)
(アルナの星:http://business4.plala.or.jp/kodomo/kodai5.htm)
| ●2011.02.26(Sat.) |
昨夜、コナンのDVDを見ながらソリティアしていると、「京都」「七夕」で思い出すのはというコナンの問いに対して平次が答えた1つが「御手洗祭」で「北野天満宮」と言ってて、「下鴨神社」だけじゃないんだなぁと思って検索すると、「菅原道真の神前へ、神宝松風の硯と梶の葉を供え、御手水を献じる。」とあった。
(御手洗祭:http://kotobank.jp/word/%E5%BE%A1%E6%89%8B%E6%B4%97%E7%A5%AD)
(北野天満宮ニュース:http://www.kitanotenmangu.or.jp/news/10.html)
(北野天満宮の七夕祭:http://www.geocities.jp/seijiishizawa/NewFiles/tanabata100-2.html)
(七夕:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%A4%95)
「松風の硯」は道真遺愛の品だそうだが、「梶の葉7枚」というのが気になりますね、2011.01.19分での「梶大明神」や2010.12.08分での「梶の葉は甕が三つつながった形」など、どう繋がるのか・・・。
「七夕の と渡るふねの 梶の葉に 幾秋かきつ 露のたまづさ」・・・「梶」は天の川を渡る橋?「舵」のこと?それとも「依代」?
(http://home.cilas.net/~jikan314/shinkokinwakashu/kanbetu/04/0320.html)
「白栲=梶の木」とあることや、「神功皇后が新羅征伐のとき、諏訪・住吉の二神が、梶葉松枝の旗を掲げて先陣に進んだ」とあるというのも気になる・・・。
(梶の木:http://www.hana300.com/kajino.html)
(梶紋:http://www.harimaya.com/kamon/column/kazi.html)
| ●2011.02.28(Mon.) |
「梶」について検索していたところ、「梶紙」というのがあり、「梶は楮の別名で、正倉院文書にも加地紙などの名称がある。梶と楮の植物学上の違いは指摘されてはいるが、現在の名称では混乱しており、区別は困難である。」とあった。
(和紙用語解説:http://www.washi.biz/index.php?%E5%92%8C%E7%B4%99%E7%94%A8%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC)
2008.11.17分で「穀とは楮の事で、木綿はこの穀の皮を細く裂いたものですが、これを織ると栲布となり、これは紙の原料にもなり、この功績により天日鷲命が紙祖神になったと思われます。」と、「野白神社」から引用させていただいていたが、現在はそのサイトがないようで検索では見つからなかった。
だが、「豊後風土記」に「常に栲の皮を取りて 木綿(ゆふ)をつくる。」とあるようで、「木綿を肩や腕に懸ける万葉歌がある。」と「神事」について用いられることを引用されていて、それは「縄文石以来のスタイルであって、鳥の羽に見立てたテープ状の布を腕や腰に垂らして鳥に変身するための方法が簡略化され変貌した姿なのだ。」(山口博著「縄文発掘」(小学館))と。
(万葉集その二百八十七(木綿:ゆふ):http://manyuraku.exblog.jp/14137771/)
つまり、「園韓神祭」で「三島木綿」が用いられるのは「鳥に変身するため」で、その木綿を作る神である「天日鷲命」と繋がり、「諏訪」の神もまた「天日鷲命」で、「七夕」は本来「天日鷲命」に「手芸・裁縫の上達を祈る」ことだが、祖神が「天日鷲命」に繋がるであろう道真についても、「七夕」に同じ神器を用いての神事が行われるようになった、ということなのではないかと。
| 乞巧奠 陰暦7月7日の行事。女子が手芸・裁縫などの上達を祈ったもの。もと中国の行事で、日本でも奈良時代、宮中の節会としてとり入れられ、在来の棚機女の伝説や祓えの行事と結びつき、民間にも普及して現在の七夕行事となった。 (http://kotobank.jp/word/%E4%B9%9E%E5%B7%A7%E5%A5%A0) |
ということは、やはり「天日鷲命」「道真」「瀬織津姫」が繋がる、ということのようで、さらに「伝説では、宅野(託農)という地名は、五十猛命が栲の木の種を朝鮮半島からもってきて植え育てたのを、抓津姫命が、その拷の木の皮を使って、機織りを教え、織物を作ったことによるともされています。」とのことから「五十猛命」そして「スサノヲ」にも繋がり、「抓津姫命」は「瀬織津姫」かと。
(大田市観光ガイド:http://www.tokusen.info/kankou/30.html)
上記の「大田市観光ガイド」さんに、「もしかしたら、同一神かもしれません。」と書かれているが、「拷幟千々姫命」「抓津姫命」「瀬織津姫」そして物部氏は繋がるように思われるわけで。
ちょっと気になったのが、「享保2年(1717年)に松江藩の地誌として、黒澤長尚が編さんした地方紙」という「雲陽誌」に、上三所の「白山権現」に「伊弉諾尊」が、原口・下横田・大馬木などで「大歳明神(大歳神社)」に「スサノヲ」が祀られていることと、「鬼神伊我武大明神と称えられた」という「五十猛命」を祀る仁多郡の「伊賀多気神社」「伊賀武神社」。
(奥出雲ごこち:http://www.okuizumogokochi.jp/468?okuizumo=85d7c19035682e2e5a2974c5e1dd59f4)
(伊賀多気神社:http://kamnavi.jp/it/izumo/igatake.htm)
(伊賀武神社:http://kamnavi.jp/it/izumo/igatake.htm)
(文献は語る:http://inoues.net/yamahonpen9.html)
(鬼神神社:http://kamnavi.jp/it/izumo/onikami.htm)
比企郡嵐山町に「鬼鎮神社」があるようで、「鬼神社」「鬼神明神社」だったのが「鬼鎮神社」に変わったようだが、「鬼神伊我武大明神」と御祭神の衝立船戸神、八街比古命との関連や、比企郡吉見町長谷の「長谷八幡神社」の境内にあるという「七鬼神」という「石宮」も気になるところで、「蘇民将来」に似ているような。
(鬼鎮神社:http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/7644/)
(鬼鎮神社:http://tencoo.fc2web.com/jinja/xkijin.htm)
(長谷八幡神社と七鬼神:http://blogs.yahoo.co.jp/sunekotanpako/33876890.html)
(七鬼神:http://blogs.yahoo.co.jp/sunekotanpako/34029044.html)
あと、通称「妙見神社」とされる「八束水臣津野命」を祀る出雲市の「長浜神社」と、「奥出雲ごこち」さんのところで、久比須の「三妙見」に「アマテラス・月弓尊・スサノヲ」が祀られる、とあることも気になりますね。
(長浜神社:http://kamnavi.jp/it/izumo/nagahama.htm)
で、「長浜神社」に「国引き神話」が書かれていて、「記紀」では出雲の命名を「スサノヲ」としているが、「国引き神話」では「八束水臣津野命」とされていて、それについて「出雲の真の建国者は八束水臣津野命だと言っているが、なぜ「出雲大社」では赤衾伊努意保須美比古佐倭気能を祭神にしないのだろう。」とされているサイトがあって。
(八束水臣津野命:http://kotobank.jp/word/%E5%85%AB%E6%9D%9F%E6%B0%B4%E8%87%A3%E6%B4%A5%E9%87%8E%E5%91%BD)
(出雲族と物部氏:http://members3.jcom.home.ne.jp/sadabe/oni-megami/oni-megami-2-3.htm)
(出雲風土記:http://1st.geocities.jp/huhito80/F-B2-izumohudoki-B.html)
「赤衾伊努意保須美比古佐倭気能」について検索すると、「出雲族と物部氏」さんと同様に「アジスキタカヒコ」ではないかとされており、出雲郡伊努郷では「八束水臣津野命」の子とあることから「八束水臣津野命」は「大国主(職名)の一人」かも、とあり、「赤衾伊努意保須美比古佐倭気能」を解読すると「「(アカの神族の後裔?)、隼人、大隅出身の彦、佐伯部族の長」ではなかろうか。」とのことで。
(赤衾伊農意保須美比古佐倭気命:http://www.dai3gen.net/akafsma.htm)
「アカ族」について、「モン・クメール族に近いアカ族に、ニニギと同様に「真床追衾」で降臨したとの神話があるとの御教示を頂いた。」とあり、「早くからクメール族、モン族はインド文化の、ベトナム族は中国文化の花を咲かせ、この地域の文明化に寄与した。」とのことで、「モン族」とは「ミャオ族」(苗族)のことで「タイのミャオ族は中国文化に影響を受けた精霊崇拝を行っている。さらにシャーマンによる儀礼を持つ。」とあり、
(アカ族:http://wee.kir.jp/thailand/tai_akha.html)
(アカ族の基礎知識:http://column.chaocnx.com/?eid=179172)
(アカ族と日本との不思議な共通点:http://www.cromagnon.net/blog/2004/07/post_85.php)
(モン・クメール系諸語の分布:http://www.aoikuma.com/mas/map_kml.htm)
| 天界には、人間を助けるヨーム・スアという精霊がいるとされている。この精霊はミャオの洪水神話や、初めての結婚などの神話に登場する。また雨をつかさどる龍や虹もいるとされるが、在所は海の下もしくは湖の下の宮殿であるとされている。その他にも太陽の精霊、月の精霊、雷神などが知られている。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%82%AA%E6%97%8F) |
とあることなどは、記紀の神話にも繋がるように思われ、「アカ族」の「犬信仰」は秋鹿郡の伊農郷の条で「赤衾伊農意保須美比古佐和気能命の后、天のミカツ姫が此の地をイヌと名付けた。」とされることや、隼人の「俳優」と繋がるようで、「出雲族と物部氏」さんでは「「天のミカツ姫」の話が「出雲・尾張・美濃」に登場するのは、物部氏が「尾張国造、参河国造、三野後国造」だったことに関連していると推察する。」とあることからも物部氏との繋がりも見えそうで。
ということで「梶」から遠ざかってしまったが、物部氏などによって織られた「梶(楮)」の「木綿」が神事で用いられるのは、「鳥に変身」するためであり、「梶(楮)」の「木綿」である「真床追衾」に包まれて降臨したのがニニギ、ということになるような。
そうした経緯から「鷲」は「コウノトリ」として「赤ん坊を運んでくる」という伝承が生まれたのだろうか。
(コウノトリ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%A6%E3%83%8E%E3%83%88%E3%83%AA)
「コウノトリ」は「鵠」と書き、「鶴」や「鷺」は「形態類似種」とされており、「古代からの暗号」さんのところには「しろとり(古名・鵠・くぐひ)は記紀で・・・(中略)・・・白鳥は出雲と縁の深い鳥であった。」とのことで、「新羅」を表す鳥のようで。
(謎解き 稲負鳥:http://blog.goo.ne.jp/kotodama2009/e/b75f644b9cd6faaf469648d1b2134040)
「謎解き 稲負鳥」で、「稲負鳥」を「稲荷鳥」と書き、そこから伏見稲荷の「稲荷社の由来の白鳥」を導き出しておられ、「稲荷神」と「新羅」との繋がりから「庶民が出雲大社(杵築明神)の姿を稲荷明神として伝え続けてきたのではないか?と思った。」ことの答えとされていることから、やはり秦氏も出雲に絡んでいると見ることができそうな。
「国引き神話」に見られる「意宇郷」は、「億ウソ」さんのサイトからも「意富」そして「新羅」に繋がることが見られ、「赤衾伊農意保須美比古佐倭気命」で拝見したページにあった「「スミ」が共通している点」も、「鮮卑を表す呼称」として「熊襲」とも繋がるようで、「稲荷」の語源が「諏訪」(トルファン)で「須賀」「蘇我」「宗我」「曾我」等にも変化したようだが、「アカ族」「鮮卑」「トルファン」(集安・通化)がどう繋がるのかは、私にはよくわからなくて・・・。
(新羅王の昔脱解はオボ系鮮卑だ:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/hun/0701tatal.htm)
(諏訪と須賀と稲荷のウソ:http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaya2002/new/07inarisuga.html)
それにしても、「赤衾伊農意保須美比古佐倭気命」を祀る「伊努神社」と「出雲大社」の繋がり、そして「伊努神社」に合祀されている「日妻大明神」と称されていたという「神魂伊豆乃賣神社」が気になりますね、あと土佐清水市の「伊豆田神社」に祀られている「伊豆那姫命」も。
(伊努神社:http://www.genbu.net/data/izumo/inu_title.htm)
(伊努神社:http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1288410790705/html/common/4ccce5a9024.htm)
(伊豆の国奇譚:http://protecs.web.infoseek.co.jp/izunokuni_kitan_izugogen.htm)
(伊豆田神社:http://homepage3.nifty.com/izuizu/izuta/shrine.html)
(伊豆田神社:http://www.genbu.net/data/tosa/iduta_title.htm)
(ルーツを探して。。。:http://ameblo.jp/ginka999/entry-10797388781.html)
それと、飯石郡を開拓したとされる「天穂日命」の御子神「伊毘志都幣命」の別名が、「天夷鳥命、武夷鳥命、天熊大人、大背飯三熊大人、武三熊大人、稲背脛命、武日照命など」とあることや、「伊毘志都幣命」が「事代主」とされていること、「タケミナカタ」のこともさらに気になった。
(飯石神社:http://www.genbu.net/data/izumo/iisi_title.htm)
(月読命をたずねて:http://homepage1.nifty.com/fumio-y/tuki11.htm)
(大国主は「ムコ殿」であった説:http://cocorofeel.blog119.fc2.com/blog-entry-6811.html)